白岩 玄さん『プリテンド・ファーザー』

子どもに対してやったことが家族を作るんだという思いに辿り着きました
現代男性の生きづらさや価値観の変化を小説やエッセイで綴ってきた白岩玄さん。新作『プリテンド・ファーザー』でもまた、二人のシングルファーザーの姿を通して、今の時代に私たちが考えなければならない諸問題を丁寧に浮き上がらせていく。そのなかで著者自身が気づいたこととは?
対照的な二人のシングルファーザー
二〇一八年に刊行した『たてがみを捨てたライオンたち』では、世間の〝男らしさ〟のイメージに縛られた男性たちの苦悩と成長を描いた白岩玄さん。久々の新作『プリテンド・ファーザー』では、共同生活を送ることとなった二人のシングルファーザーの姿が描かれていく。
「『たてがみを捨てたライオンたち』を書いてすぐに、もう一回男性の問題をテーマに書きたいと思ったんです。それまで毎回違うテーマの小説を書こうとしてきたので、そんなふうに思ったのははじめてでした。というのも、このテーマに、自分が幼少期から大人になるまでのこれまでの人生で考えてきた何かが埋まっている気がしたんです。次はどういう切り口にするか考えたり試し書きしたりしていくなかで、たまたま〝いい父親の振りをしている〟という言葉が出てきて、なぜかすごく惹かれたんですね。自分は今二児の父親で、当たり前に育児しているつもりでしたがその言葉にひっかかりを感じ、ここを掘り下げていくことにしたのが一年ほど前でした」
山崎ナオコーラさんと子育てについて考察した交換エッセイ『ミルクとコロナ』などから、白岩さんは子育てに積極的に参加しているイメージがある。
「誰に見せても大丈夫なくらい問題なく育児をしている自分と、そうでもない自分がいます。妻が仕事で朝から晩まで家にいなくても、子ども二人の面倒を見て過ごせる自分もいれば、妻から子どものことで何か相談された時に、〝ようわからんから任せるわ〟と言ってしまう自分もいる。両方の自分を拡大していって二人の人物を作り、対話させるような感じで作ったのがこの小説です」
三十六歳の恭平は妻を亡くし、四歳の娘・志乃を一人で育てている。大手飲料メーカーの営業部にいたが人事部に異動し、早く帰宅できるようになったものの育児に苦戦中。そんな折に再会したのが、高校の同級生だった章吾だ。フリーランスのベビーシッターの彼は、現在妻が海外赴任中で、一人で一歳半の息子、耕太を育てているという。恭平がシッターとしての章吾を雇う形で、彼らは章吾の妻が帰国するまでの期間限定で同居生活を始めることに。物語は恭平の視点、章吾の視点を交互にして進んでいく。
「周囲に頼れる女性のいない状態ということで、シングルファーザーという設定を考えました。男性一人で子どもの面倒を見ざるをえなくなった時、どんな感情がわきおこるのかを書いてみたかった。僕は恭平のように会社でキャリアを積んだ経験はないですし、章吾のように専門職のベビーシッターとして子どもの面倒を見たこともない。想像したり、ある程度人から話を聞いたりして作っていきました。でもたとえば冒頭にある、恭平が絵本を読むのが苦手だというのは自分と一緒です(笑)」
家庭内でのケア問題、職場でのジェンダー問題
それぞれの日常が丁寧に綴られていく。「子育ては日常の集積でしかないと感じるし、そこは大事に書きたかった」と白岩さん。一緒に暮らしているものの、二人の育児スタイルはまったく違う。元保育士・現シッターの章吾から見れば、恭平の育児はぞんざいに見えて閉口する部分もあるが、口出しはしない。
「男同士って、あまりお互いの家庭の問題点を指摘しあわない感じがしていたんです。当たり障りのない話ならするけれど、プライベートに踏み込んだことはあまりしないイメージが僕にはありました」
そんな章吾は、保育士を目指したものの父親に反対された過去がある。男らしさを求める環境のなかで、ずっと違和感を抱いてきた人間だ。
「僕も大人になるまでの間に、男の子にありがちなエロとバカの大縄跳びに入れなかった感覚はあります。僕は無理やり入って跳んだりもしましたが、章吾のように本当に入れなかったのなら、それは辛かっただろうと思います」
父親は今、母親が自宅で介護しており、章吾は二週間に一度実家に戻って手伝っている。
「今回意識していたのは〝男性のケア問題〟です。これまでは、たとえば結婚したら親の面倒は奥さんとか嫁とか呼ばれている人が見る、という価値観でしたよね。でも今は女の人も当たり前に仕事しているし、これからは男性も育児や介護を担うはず。ただ、今回は介護がテーマではなかったので深く書き切れなくて。自分にとっては現在進行形の問題だと思っています」
一方、恭平は内心、営業部の仕事に未練がある。育児についても、志乃が泣きわめいていると内心うんざりしたり、世話を面倒に思うこともある様子。
「僕も意外だったんですが、恭平に共感したという女性が多いんです。〝自分も家庭と仕事の板挟みになっています〟とか〝私も子どもに早く寝ろ、と思ってしまいます〟とか、〝章吾のように丁寧に子どもの面倒は見られません〟とか。僕は男の人の話を書いたつもりでしたが、逆に女の人の話でもあったと気づかされました」
恭平の職場の日常も描かれる。営業部の元後輩からは、長期の育児休業をとりたいが、申請すれば上司から文句を言われる、と相談が。
「実際、男性が育休をとるにしても、一週間かそれ未満の人がほとんどです。夫婦二人で新しい環境を作っていく認識を持っている人は少数派。でも、出産後は母親の体力も回復しませんから、一週間では短いと思うんです」
一方、「男に育児は無理だ」と断言する同僚も。昭和の世代は、男は外で働くのが当たり前だと育てられてきたから、いきなり子どもの面倒を見るなんてできない、という主張である。
「実際、十年くらい前までイクメンなんて言葉は聞かなかったし、小学生の頃は将来の夢に〝お嫁さん〟と書いている女の子だっていた。僕も、将来男は働くしかないんだって、子どもながらに思っていました」
そんななか、恭平の営業部の元後輩、井口という女性がじつに魅力的。社内男性や取引先のパワハラやセクハラについて愚痴をこぼし、バサバサと切っていくのだが、どれもリアリティのあるエピソードばかり。
「読んでくれた人のなかで、井口のファンがすごく多いんです(笑)。僕は井口から教えられたことが沢山ありました。というのも、彼女については担当編集の女性から〝男性はこういうところが見えていないですよ〟〝女性はこういうことに怒りますよ〟とすごく指摘してもらったんです。僕一人ではリアリティをもって書けなかったキャラクターです。たとえば、恭平が井口に、志乃の下着を買ってきてもらおうとして顰蹙を買いますよね。僕もこういう頼みごとには違和感がありましたが、編集者とのやりとりのなかで、なぜこれがおかしいのか、言語化できました。すごくありがたかったです」
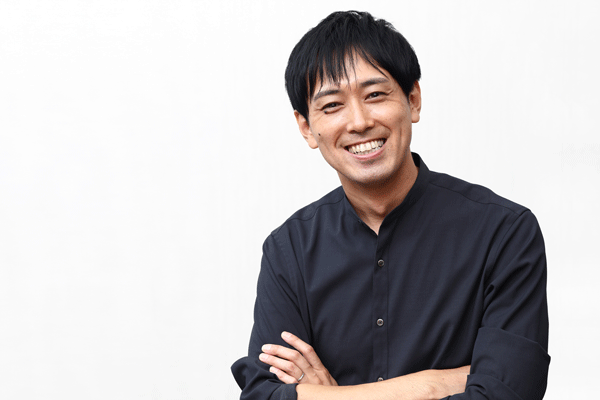
やがて恭平は、男女格差に無頓着だった自分に気づいていく。
「家庭のなかでいい父親になることはできても、社会で娘に恥ずかしくない父親でいられるかどうかはまた違う。でも、自分が今作っている社会は、娘が将来出ていく社会なんですよね」
次作もまた現代男性がテーマ
インタビュー中、何度も「噓がないように書きたかった」と言う白岩さん。二人の子どもたちの言動や、じつはとある事情を抱える章吾と妻の関係なども、リアリティを大事にして考えた。また、期間限定という条件つきで同居を始めたことに関しても、
「期限がない場合、友人同士でもない男同士が一緒に住むだろうか、という疑問がありました。それで、期間限定で、お金を介しているなら一緒にいられると考えていったんです。じゃあ期限が近づいたら彼らの関係性はどうなるのか、そこはどうしたらリアリティを持たせられるか悩みました」
という。悩むなかで、家族というものについても改めて考えた。
「書いていくうちに、家族って、血の繫がりや〝父親〟〝母親〟という肩書によって作られるわけではなくて、子どもにしたことの集積で作られるんだなと思って。〝父親〟や〝母親〟なんていう肩書は、他人に説明する時に便利なだけ。それよりも、働くことや、ご飯を作ることも含め、子どもに対してやったことが家族を作るんだという思いに辿り着きました。でも本の帯を見た時、〝拡張家族〟という言葉にびっくりしたんです。自分が書いたものはそうだったのか、とそこではじめて気づきました」
前作と今作で、現代の男性の問題という、同じテーマの小説を続けて書いた白岩さん。では次作は?
「このテーマで三部作にしたいと思っています。じつは今回の小説を書く前に別の話を書いていたんです。それがうまく進まないうちに、〝いい父親の振りをしている〟という言葉が出てきて、『プリテンド・ファーザー』を先に書くことになりました。次は、それを書こうと思っています。〝男性〟の成り立ちの話になりますね。子育てをしていると、たとえば、おもちゃからして男の子向け、女の子向けに分けられている。社会が男性を男性に、女性を女性に醸成していくんだなと感じるんです。男の子は何を経て男性性を持った男性になっていくのか。それを書くことで、自分のなかでひとつきりがつくなという気がしています」
白岩 玄(しらいわ・げん)
1983年京都府京都市生まれ。2004年『野ブタ。をプロデュース』で第41回文藝賞を受賞しデビュー。同作は芥川賞候補作となり、テレビドラマ化。他の著書に『空に唄う』『愛について』『R30の欲望スイッチ──欲しがらない若者の、本当の欲望』『未婚30』『ヒーロー!』『たてがみを捨てたライオンたち』、共著に『ミルクとコロナ』。
(文・取材/瀧井朝世 撮影/浅野 剛)
〈「WEBきらら」2022年11月号掲載〉


