医師と作家の二刀流 夏川草介おすすめ4選

医師不足と僻地医療問題を抱えながらも奮闘する若手医師の姿を描いた『神様のカルテ』で知られる医師で作家の夏川草介。最近では、コロナ禍における医療の現状を伝える小説が話題になっています。そんな著者のおすすめ作品4選を紹介します。
『レッドゾーン』コロナ患者の受け入れに葛藤する医師の本音とは
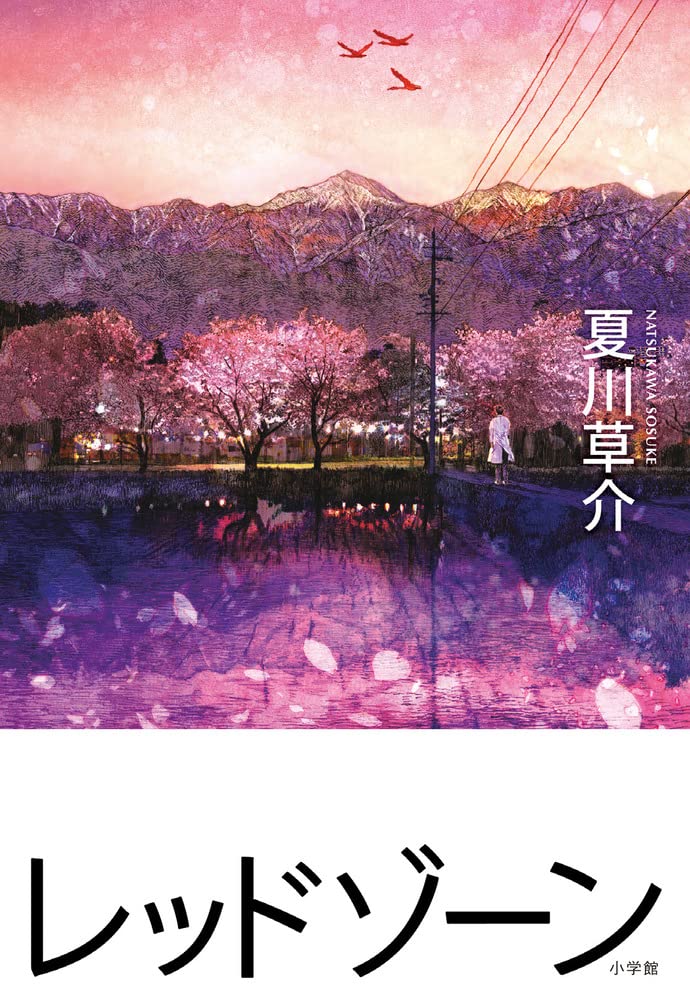
https://www.amazon.co.jp/dp/4093866473
横浜港に到着したクルーズ船で新型コロナ患者が発生した、2020年2月。横浜近郊の病院は、受け入れ病床が満床となり、国から全国の感染症指定医療機関に受け入れ要請が出され、長野県の公立病院・
当病院に勤務する内科医・日進は、設備が不十分で専門医もいない田舎の病院へ患者を受け入れることには断固反対です。
日進は仕事に対する情熱とはあまり縁がない。患者のために命懸けで働くというような状況は、最初から想定していない。想定していないことを恥ずかしいとも思っていない。
ところが、使命感の強い内科部長の三笠は、「病める人がいるのなら、我々は断るべきではない」と、自分が主治医になってでも患者を受け入れると言います。
この人は、本気で死地に踏み込むつもりだ。日進はほとんど絶句していた。このタイプの人間は、映画かドラマの中にしかいないと思っていた。表面上は英雄的な振る舞いをする人物も、本音をさぐれば打算や駆け引きがあり、自らの安全はきっちりと確保しているものだというのが、日進の人間観である。その俗な人間観に、三笠という人物はどうしても合致しそうになかった。
周囲の大半の病院がコロナ患者の受け入れを拒否するなか、信濃山病院には患者が搬送されます。このことは地域住民には極秘にされていたはずが、いつのまにか噂が広がり、日進の家族は、彼が患者を診察することに猛反対します。医師とて人間だし家族もいる、と。
いつも冷静沈着で、高潔な若手の医師・
「リウー(『ペスト』に出てくる医師)は特別な力をもった人物ではありません。平凡な市井の一内科医です。しかし彼は治療法がないにもかかわらず、そして命の危険があるにもかかわらず、ペストにかかった患者のもとに、淡々と足を運びます。病気で苦しむ人がいたとき、我々が手を差し伸べるのは、医師だからではありません。人間だからです。もちろん医師であればできることは多いでしょう。けれども治療法のない感染症が相手となれば、医学は役に立ちません。だからこそリウーは言ったのです。『これは誠実さの問題なのだ』と」
日進は、死地(レッドゾーン)に踏み込むのでしょうか。
『臨床の砦 』コロナでひっ迫する医療を、医師の立場から克明に描く

https://www.amazon.co.jp/dp/4094071520/
コロナが流行して1年後の2021年冬。多くの病院がコロナ患者の受け入れを拒否するなか、感染症指定医療機関に選ばれた地方の公立病院・信濃山病院で、患者を受け入れる医師たちの奮闘を描きます。
コロナ患者の受け入れ数が急増して一般診療に差し支え、まともに休みが取れていない状況に、現場の医師たちは悲鳴を上げます。
以下は、患者の受け入れを継続したいと考える三笠内科部長と、医師たちによる会議での緊迫感あふれるやり取りです。
「ここは、いくらでも代わりの病院のある大都市とは違うのです。当院が拒否すれば、患者に行き場はありません。それでも我々は拒否すべきだと?」
「皆さんは立派なお医者さんですからね。まだまだ自己犠牲の精神にのっとって頑張れるのかもしれませんが、僕のような凡庸な小市民は、そろそろ退場を願い出たいくらいです」
「この状況はまだまだ続きます。国はおそらく、経済を守るためには、ある程度医療の側にも犠牲が出るのはやむを得ないと判断しているのでしょう」
「言いたいことがあるなら言った方がよいですよ。三笠先生とともに玉砕 することに浪漫 を見出しているなら別ですが」
「この問題に正解はないのでしょう。ただ正解がないから逃げ出すというのは違う気がしています」
「三笠先生の方針が正しいと確信しているわけではありません。しかし、ほかに理想的な代案も持っていません。代案もないのに投げ出すというのは大人の態度ではないと思っています」
現場には、誰もが満足する正解は存在しない。ゆえに、個人的な信念や本音をぶつけ合うような議論の仕方は、問題を解決しない。医療は青春ドラマではないし、ここに集まった医師たちは信頼と友情でつながったクラスメートではない。感情を抑え、微妙な駆け引きの中からぎりぎりの妥協点を探していく。
そんな中、第3波が押し寄せ、病院近隣の高齢者施設でクラスターが発生します。医師たちはどのような「妥協点」のもと、いかなる対応をするのでしょうか。
マスメディアは、舞台上で声を張り上げる人にスポットライトを当てることは得意だが、市井の沈黙を拾い上げる機能を持っていない。うつむいたまま地面を見つめ、歯を食いしばっている人の存在には気づいていない。苦しい毎日に静かに向き合い、黙々と日々を積み上げている。
という一節がありますが、本書は、その「市井の沈黙」を丁寧に掬い上げた一冊でもあります。なお、本作は、高橋源一郎・斎藤美奈子著『この30年の小説、ぜんぶ 読んでしゃべって社会が見えた』で、現代人が読むべき1冊として取り上げられています。
『勿忘 草 の咲く町で ~安曇野診療記~』老人は早く死ね、という考えの老獪 な先輩医師に、研修医が挑む

https://www.amazon.co.jp/dp/4041123461/
桂正太郎は、長野県にある小規模な病院の内科へ研修医としてやって来たばかり。自分の頭の寝ぐせは気にしないのに、看護師の飾った花に、「白と青の配色は、葬式を連想させるからやめた方がいい」と意見し、つかみどころのない変人と目されます。
けれど、桂の研修を受け持つ医師たちも、彼に輪をかけた曲者ぞろい。例えば、循環器内科の谷崎。看護師は、このように噂します。
「80歳を越えた患者は、全身状態にかかわらず、みんな看取りにもっていくって、有名な先生なのよ。もともと高齢の心不全患者さんが多いから、できることがあんまりないっていうのは本当だけど、それにしても点滴とか酸素でさえ最低限しか使わないで。どんどん看取っていくの。ついた
綽名 は『死神の谷崎』」
谷崎自身、そのように悪評が立っていることは承知のうえで、それでも自分の方針を曲げようとはしません。
「私は死神ですよ。そんなにがんばって助けてどうするんですか。我々はもう、溢れかえった高齢者たちを支えきれなくなっている。人的にも経済的にもね。20年前と同じことを続けていれば、医療という大樹は、やがて根腐れを起こして倒れてしまうでしょう。倒れた大樹の下敷きになるのは、今懸命に高齢者を支えている若者たちです。彼ら次の世代の医療を守るためにも、枝葉を切り捨てていかなければいけない時代だ」
想像もしなかった言葉に、桂は呆然として指導医に目を向けた。
「すごく……危険なことを言っているように思います」
「そうですね。こういう余計なことを話してしまうから、研修医を引き受けるのは嫌だったんですよ」
この病院に高齢者が溢れ、介護施設と化していることは事実なのですが、谷崎は、心機能が低下した82歳の認知症患者を、これ以上生かしておいても仕方ないと、積極的な治療はせず、「家族には細かいことを説明する必要はない。一般的な治療は行ったが、効果がなかった」とだけ言え、と厳命します。けれど、正義感にあふれた桂はこれが不服で谷崎にぶつかります。
新米医師の目を通して見た、命の尊厳をめぐる医療青春小説です。
『始まりの木』社会で役に立たないと言われる、大学の人文系の学科はなくしてしまってよいのか

https://www.amazon.co.jp/dp/4093865914/
千佳は、柳田國男『遠野物語』を読んだことがきっかけで民俗学に興味を持ち、現在、国立大学大学院に籍を置く、修士課程1年目。指導教員は、皮肉屋で知られる民俗学者・古屋准教授です。
ある学会で、若手の研究者が最新のソフトを用いて、特定の山林の植生を統計処理した発表を行ったとき、にわかに立ち上がって、ひとこと、
「君はその山を歩いたのかね?」
と古屋は問いかけた。
「行ったことも見たこともない土地の情報を、単純に数値化して数式に放りこむだけなら統計屋にまかせておけばいい。いやしくも民俗学者のはしくれなら、自分の足で土を踏んでくるべきではないかね」
民俗学の方法論としては重要である。しかし、重要な事柄を述べる者が必ずしも好かれるとは限らない。
だがいかに偏屈であっても、千佳はこの変人学者が嫌いではなかった。人に対しては、愛想も社交辞令も見せないが、学問に対してはどこまでも真摯であるのが古屋という人間である。性格はどうあれ、古屋は口先だけの学者ではない。必要とあれば、日本中どこにでも出かけていく。どれほど足が悪くとも、階段を登るのにさえ苦労をする身であっても、彼は書斎の学者ではなく、歩く学者であった。
そんな古屋のお供をして、千佳は各地をフィールドワークで回ります。初老の男性教師と若い女子学生は、たとえ研究のため旅館に投宿しても、絶対に不倫カップルに見られる心配だけはない、という間柄。古屋は千佳に、「頭は空っぽだけど、鞄持ちとしては使える」と嫌味を言いますが、その実まんざらでもない様子。
古屋はある日、学部生から、「そもそも民俗学とは何か? 昔話や珍しい風習を調べて、社会の役に立っているのか」という悪意のない素朴な質問を受けます。それに対し、他の教員が「役に立つことを学ぶだけが学問ではない」とお茶を濁そうとすると、反対に怒り、「そういう中身のない返事をしているから、民俗学は曖昧さを解決できないまま迷走している」と言う古屋。そんな折、就職へ結びつきにくい人文系の民俗学研究室は廃止するという噂が流れます。学内政治に疎い古屋は、研究室を守ることができるでしょうか。
医療小説を多く手掛ける著者にとっては、異色の作品ですが、人文系の学問を学んでいる人にとって、何のために学ぶかということを再考させてくれる1冊です。
おわりに
現役の臨床医でしか書けない、コロナ禍の最前線を伝える記録文学から、それとは正反対の人文系の研究者の小説まで、文系理系の垣根を越えた作風が魅力の夏川草介。幅広い知識に基づくこれらの作品は、読者の教養を豊かにしてくれるでしょう。
初出:P+D MAGAZINE(2022/11/02)

