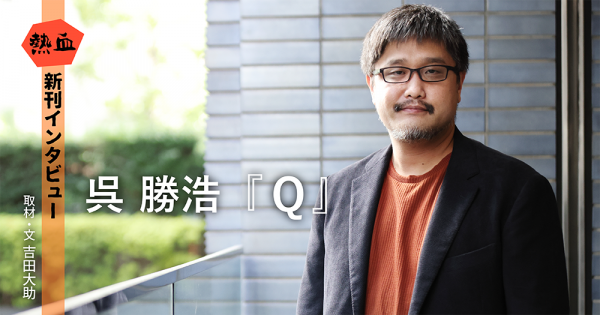呉 勝浩『Q』◆熱血新刊インタビュー◆
快感と日常の狭間で
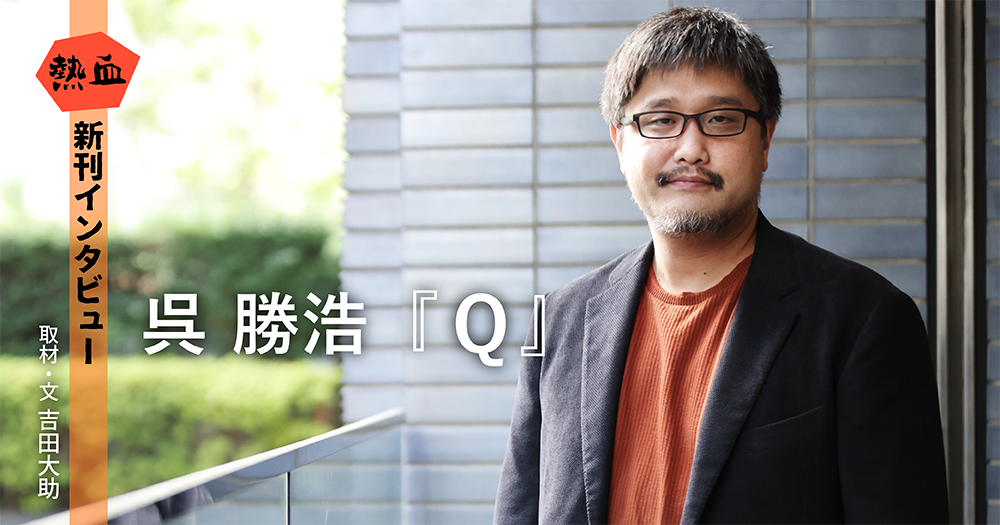
連続爆弾事件の犯人と警察サイドの攻防を描いた代表作『爆弾』の発表後、呉勝浩は次回作となる長編についてこんなコメントを出していた。「(代表作ができると)どうしても似たようなテイストのものが求められると思うのですが、僕は飽きっぽいので同じものを続けて書くのは苦手なんです。だから、次は恋愛小説を書こうと思っているんです」(『このミステリーがすごい!2023年版』より)。それが、『爆弾』以来1年半ぶりとなる長編『Q』だ。
「僕はいつもプロットを作らず、とにかく冒頭から書き出すんです。今回であれば、主人公が車で走るシーンがなんとなく書きたかったんですよね」
それが次の文章になる。
〈夜と夜明けのあいだ、県道は青白いというよりどす黒い〉
〈反吐が出るのを我慢する〉
〈わたしの首根っこをつかんで放さないのは食い扶持だった〉
書いてみて呉は思った。「あれ、これは恋愛小説にはならないぞと確信しました(笑)」
語り手の「わたし」こと町谷亜八(ハチ)は、千葉県富津市の清掃会社に勤めている。過去に傷害事件を起こし執行猶予の身である24歳の現在は、職場の同僚のパワハラをかわしながら、父が放置していた家で静かに一人暮らしを営んでいた。愛車のアウディを駆って夜の東京へ繰り出そうとしたところ、ロクという人物からスマホにメッセージが届く。「キュウのことで話がある」「返事をして、ハチ」。長姉のロク、次女のハチ、末っ子の男の子・キュウ──3人は腹違いのきょうだいだった。7年前のある事件がきっかけで3人は距離を置くことになっていたはずなのに、ロクが突然連絡をしてきた理由は、19歳になった弟が芸能活動存続の窮地に陥っていたからだった。「天才よ、あの子は」。キュウは見る者全てを魅了する、ダンスの才能の持ち主だったのだ。再会したハチもまた魅了され、キュウのために自分ができることはないかと暗躍を始める……。
「プロットを立てないとはいえ、これまでの長編では必ず、何かしらの謎は用意していたんです。お話の冒頭にその謎を出して、書きながら答えを探していくやり方が基本だったんです。でも今回は、長編では初めてメインとなる謎が存在しません。冒頭を何度も書き直しながら主要登場人物たちの設定をある程度作った後は、彼らがどういう方向へ人生を進めていくのか、関係性をどう変化させていくのか。とにかくじっと考え続けていく書き方をしてみたかった」
謎によって牽引されるストーリーではなく、登場人物たちの関係性、そこで起こる感情の交歓を重視する書き方は、ある意味で恋愛小説的だったのかもしれない。
「全く新しい書き方だったことは間違いないですね。よく言えば週刊連載マンガのノリ、悪く言えば行き当たりばったり、だから650ページも書いてしまったんです(苦笑)」
しかし、この長さには意味がある。
一番大きかった転換点はコロナを出したことです
第一部だけ見れば、東野圭吾の『白夜行』を連想する人もいるかもしれない。ハチはかつてキュウのために犯罪に手を染めた過去があり、今回もまた手段を選ばず動こうとしているのだから。ところが、第一部の終わりでガラッとムードが変わる。7年前の事件にまつわる暗雲は変わらず立ち込めているものの、キュウの芸能活動に大きな転機が訪れるとともに、その才能を支持する人々が集まり始める。
「その辺りは、本庄健幹という裏主人公的な存在を出したことが大きかったです。あの人は一番まともだったはずが、キュウと出会って才能に惚れ込んでしまったことで、おかしくなってしまった(笑)。彼がキュウを支える裏方に回ったことで、そうか、キュウのサクセスストーリーを書いていけばいいんだと道が開けたんです」
キュウはダンスが圧巻であることはもちろんのこと、常識や慣習をぶち破る無邪気な言動もまた多くの人を惹きつける。キュウという人物の魅力が、この物語にとって何よりの吸引力となっている。
「僕がやったら一発で〝おまえ、なんやねん〟と言われて社会からはじかれてしまうような振る舞いが、彼であれば成立する。僕の中の憧れを膨らませて作っていったキャラクターですね。ちなみに、ダンスの部分、芸能の部分で参考にしたのはBTSです。エンターテインメントのトップアーティストはどんな感じなんだろうと、資料のつもりで『ON』という曲のMVを初めて観たら一発でハマったんですよ。ダンスに全く詳しくない自分が『ON』を観て一発で〝めちゃくちゃすごい!〟となった感動を、キュウのダンスに閉じ込めたつもりです」
ガラッと変わった物語のムードは、第三部でまたしても更改される。
「僕自身にとって一番大きかった転換点を挙げるならば、第一部の終わりで新型コロナウイルスを出して、時間軸を明確化したことです。それ以降、物語はコロナ後の世界に突入していくんですね。その瞬間から、コロナ禍で僕なりに感じていたことや考えたこと、世間の空気が作品の中になだれ込んでくる感覚がありました。例えば第二部の冒頭で、緊急事態宣言で飲食店をクビになった佐野勇志という青年が、〝なんでおれたちは、暴動をしないんだろう?〟と疑問を覚えます。それを書いた時、〝確かに〟と僕も思ったんですよ。結果的に、そのモノローグが第三部の展開に繋がっていったんです」
かくして本作は、ハリウッド級エンターテインメントに社会派のテーマを接続する、呉勝浩らしい色を帯びていくこととなった。
平穏な日常を守るために異様な情熱が絶対に必要
声を上げるな。集まるな。言うことを聞け。コロナ禍真っ只中の時期、政府は国民に対してそんな要求を突き付けてきた。相互監視の空気も絡み合い、息苦しい世界になったと多くの人々が感じていたはずだ。それを、いかに晴らすか。登場人物が一堂に集結するクライマックスでは、コロナ禍で人々の胸に巣くった鬱屈を吹き飛ばすような祝祭空間が出現する。スケールといい法の逸脱っぷりといい、現実では決してお目にかかれないもの。映像化もまず不可能だ。小説だからこそ、これを表現することができた。
「小説の後半で、異様な情熱、というキーワードを出しました。人は、情熱を持ったがゆえに行動を起こす。その行動に対して、作品の中では善悪をつけないようにしています。ただ、作品から離れた僕自身の感覚として言うならば、情熱は人生にとって絶対に必要だと思っているんですよね。むしろ平穏な日常を守るためにこそ、それは必要な気がします」
異様な情熱とは、恋愛がまさにそうではないか? 恋愛にはポジティブな側面もたくさんあるが、恋愛なんてしない方が、平穏な日常を送るうえではラクだしストレスも生じない、かもしれない。しかし……。
「快感なんてないほうが穏やかに暮らしていける、みたいな話と一緒ですよね。でも、やっぱり我々は快感を求める生き物でしょう、みたいな意見も否定できないところがある。快感を求めている人間に、何も求めていない人間は勝てるのかなと僕は思っちゃうんですよ。コロナ以降は特にそう感じていて……僕の知人で、コロナ禍で陰謀論に嵌った人がいました。地頭の良い人なのですが、傍から見ると突飛なロジックで〈世界の真相〉を語っていて、よくよく話を聞いていくと最終的に『楽しいんだよ』と。まぁ勝ち負けの話は置いておいて(笑)、結論としては、人は快感と日常の狭間で生きていくしかないんですよね」
実はこの作品の中で亜八ほど、日常を守ろうと努力している人はいない。そんな人物が、キュウとの再会によって芽吹いた異様な情熱とどう折り合いをつけるのか。あるいは、つけられないのか。
「この結末にしたかったから亜八を作ったわけではなくて、亜八という人が主人公だったからこそこの結末になった。書き終えた時、こういう小説になるんだってびっくりしましたけど、僕は今これが書きたかったんだとも思ったんです」
千葉県富津市の清掃会社に勤める町谷亜八(ハチ)は、過去に傷害事件を起こし執行猶予中の身。ようやく手に入れた「まっとうな暮らし」からはみ出さぬよう生きている。ある日、血の繋がらない姉・ロクから数年ぶりに連絡が入る。二人の弟、キュウを脅す人物が現れたというのだ。キュウにはダンスの天賦の才があった。彼の輝かしい未来を守るため、ハチとロクは、かつて、ある罪を犯していた。華々しくデビューし、注目を集めつつある今、それが明るみに出れば、スキャンダルは避けられない。キュウのため、ハチは守り続けた平穏な日々から一歩を踏み出す。
呉 勝浩(ご・かつひろ)
1981年青森県八戸市生まれ。大阪芸術大学映像学科卒業。2015年『道徳の時間』で第61回江戸川乱歩賞を受賞しデビュー。18年『白い衝動』で第20回大藪春彦賞受賞、20年『スワン』で第41回吉川英治文学新人賞、第73回日本推理作家協会賞(長編および連作短編集部門)受賞、第162回直木賞候補。21年『おれたちの歌をうたえ』で第165回直木賞候補。22年『爆弾』で第167回直木賞候補。