源流の人 第10回 ◇ 小島武仁 (経済学者/東京大学教授)
ワクチン配分、待機児童、就活社会の抱える疑問を解決するため「マッチング理論」を携え帰国した若き頭脳が切り拓く日本の明日
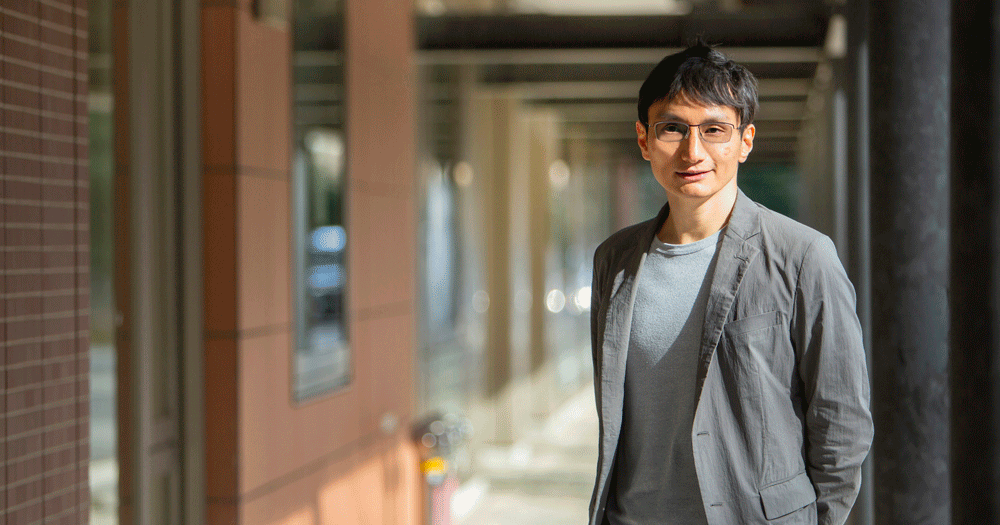
ハーバード、イェール、スタンフォードで、世界でも最先端の経済理論を研究し、恩師、同僚はノーベル経済学賞を受賞。世界が注目する経済学者の目にはいま何が映っているのか。
二〇二〇年、年の瀬のある日。アメリカ西海岸を飛び立った国際線が、疫禍で静まり返った東京国際空港に着陸し、一人の若き経済学者が故国に降り立った。
小島武仁。東京大学を卒業後、ハーバード、イェール、スタンフォードと、世界の英知が集結する最高学府に在籍し、現代社会に横たわる数々の問題解決の糸口を導き出す、経済学の最前線を走ってきた。このたび彼は、約十七年間に及ぶ海外生活にいったん終止符を打ち、東京大学に新設された「東京大学マーケットデザインセンター(UTMD)」センター長に就任した。まだ、引っ越しの荷物がすべて片付いていない研究室を訪問すると、屈託のない笑顔で声を弾ませ、出迎えてくれた。
「(感染症対策で)二週間の隔離生活を経て、晴れて、本格スタートを切ることができました」
UTMDは、東大付属の研究所という位置づけで、二〇二〇年九月に東京・本郷のキャンパス内に設立された。小島は初代の所長である。設立当初の数か月間、リモートワークで米国からディスカッションに加わっていた彼をはじめ、ここには学内外の研究者約三十人が在籍している。
小島の専門分野は、人と人、モノ、サービスの間をAIとアルゴリズムを駆使し、「適材適所」で引き合わせる方策を練っていく「マッチング理論」と呼ばれる学問領域だ。この「マッチング理論」を応用し、社会制度の設計や実装につなげていくのが、UTMDが今後、知見を深めていこうとしている「マーケットデザイン」だ。たとえば保育園の待機児童や、研修医の偏在など、実社会で起こっている問題の解決法を探っていくことになる。小島は抱負について、こう語る。
「米国では多様な分野で採り入れられている『マッチング理論』ですが、日本ではまだ浸透していません。これは非常にもったいないことです。研究の成果を社会に実装させていくことを、研究自体と共に大きなミッションとして掲げています」
新型コロナワクチン接種問題への活用
そもそも「マッチング理論」とは何だろう。「適材適所で引き合わせる」などと聞けば、まず想起してしまうのが、交際相手を探す「マッチングアプリ」だろう。彼は笑って説明してくれた。
「たしかに、すぐに思いつくのはアプリかもしれませんね。世の中を私たちの眼鏡で見てみると、実はいろんなことが『マッチング』問題になっているんです」
たとえば、就職活動。これは学生と企業のマッチング。受験。これは学生と学校のマッチング。子どもを保育園に入れるための保活は、保育園と子ども。人事異動は、従業員とオフィスのマッチングだ。本人の希望、能力、環境、あらゆるデータを集積し、分析し、「適材適所」の最善の答えを、しかも瞬時に導き出していく。とりわけ喫緊で取り組まなければならない課題がある。
「急務なのはコロナワクチンの問題です。いかに必要な人たちから接種をマッチさせていくか。センターでは今、急ピッチで研究を進めているところです」
たとえば、接種の順番においては医療従事者、高齢者の次に優先すべき、とされながらも現状把握が遅れている「基礎疾患のある人」。現状では共通のデータベースがないため、彼らをどう把握するのかが大きな課題となっている。そんなトピックも含めつつ、いかに迅速に、効果的に投与作戦を進めていくか。小島は、米国時代に指導した後輩である野田俊也(現ブリティッシュコロンビア大学助教授)にも協力を仰ぎ、ワクチンを配る際の論点の整理を進めている。すでに自治体などからの問い合わせを受け、対策を進めている最中だ。
希望の叶わない子どもが六割減った
「マッチング理論」による「マーケットデザイン」先進国とされる米国では、あらゆる分野で実践が進んでいる。たとえばニューヨーク市では二〇〇三年度から、公立高校選択に「マッチング理論」を採用している。約九万人の新・高校生を、どうやって市内の約五百校ある高校に進学させるのか。市の担当セクションが「マッチングサイト」を作成し、どの学校に進学したいかを聞き取る。情報をもとに計算し、「では、あなたはこの学校に」と指し示していく。実は、このシステム構築に中心的な役割を果たした研究者アルヴィン・ロスのもとで、小島はハーバード大の大学院生活を送っていた。小島は振り返る。
「ロス教授や、ボストンカレッジのタイフン・ソンメツ、ウトゥク・ウンヴァーなどの研究者が腎臓移植のドナー交換のシステムなども構築したことで、その理論を実社会で応用する試みが急速に広まったんです」

机上の空論で学問を語っている場合じゃない。もっと、実社会で役立たなければ。小島は、恩師の背中を見て、そうした確固たる思いを培った。
とりわけ小島が関心を寄せていたのは、日本の保育園の「待機児童」問題だ。同じく研究者である妻(高木悠貴・東京大学大学院経済学研究科講師)との間には、二人の子どもがいる。二〇一六年には「保育園落ちた日本死ね!!!」というタイトルのブログをきっかけに、認可保育所に入れない全国約二万三千人もの「待機児童」の問題に人々が声を上げた。自治体によって「待機児童」の定義が異なっているうえ、保護者が子どもを通わせたい保育園を記入して自治体に提出する「希望票」をもとに選考する方法が、自治体によってまちまちであることなどが明るみに出た。
小島はこの点に着目し、解決策として、さまざまな要素を点数化したデータをもとに選考する案を提唱。希望通りになる人数をいかに増やすかを追求し、問題点の整理と改善策を論文にまとめた。現在、いくつかの自治体と連携し、研究を続けている。
「改善策は、公平で、なおかつ、なるべく無駄が出ない方法を探っています。アルゴリズムの小手先といえば小手先に聞こえるかもしれません。でも、見方を変えるだけで改善できる点は多々あると考えています」
少子化が今後さらに急速に進むなか、リスクを考慮した方策を講じることも重要だ。ある県庁所在地の自治体と連携した研究では、園の数や定員枠を増やすなどの追加投資をしなくても、希望の叶わない子どもが約六割減った、という結果が出た。工夫すれば、支出を変えなくても、笑顔の人々を現状より増やせる。
さらに小島は、全国的に偏在する研修医の現状についても問題視し、マッチングの論文を発表している。ただ、解決策を提示したとしても、各省庁や、関係部署間の連携をとって提案通りに実行していくのは、この国では簡単なことではない。それでも、どの問題も切迫している。研究者個人ではなく、「東大の付属研究所からの提案」という「楯」を手にしたことは、小島にとってはさらに大きな強みとなった。
正直な希望を出せる人事配置へ
そんな小島の下に依頼が殺到している案件がある。それは「企業内の人事配置」についてのものだ。あの部署に行きたいけれど、希望者がたくさんいる。行きたくない部署に配属されてしまう。古今東西、オフィスで働く人たちに付きまとう悩みだ。人事担当者たちも同様に、頭を悩ませている。
「企業内の人事配置は難しく、皆さん、苦労されています。具体的にソリューションの提供をいくつかの会社と始めています」
第一希望、第二希望の部署は人気だから両方落ちてしまう可能性がある。それならば安全策をとって第三希望を本命として書く、というのは誰しも経験があるだろう。ともすればそんな「神経戦」が繰り広げられがちだ。
「でも、そんな変なプレッシャーを感じることのないよう、公平な制度をつくっていきたい。『正直に希望を出してくれれば、あとは私たちのほうで処理するから』って」
その「希望通り」をどこまで追求できるか、が、小島の腕の見せ所だ。希望の通らない人をいかに減らすか。小島のシミュレーションは進んでいる。命を預かる新型コロナワクチンから、会社人生の行く末を担う人事異動まで、小島が挑むべき山は数限りない。
「日本でこれから取り掛かりたい分野はいっぱいあります。今、すごくやりがいがある仕事です」
挫折で運命が変わっていく
小島は、一九七九年、東京都立川市で生まれた。
「父が農学の研究者で、肥料の研究をしていました」
三重県の農家に生まれ育った父親は、米などをつくる祖母の背中を見て育ち、農学の道に進んだ。いっぽう、小島の母親は教員を務めていた。その影響もあって、小島は子どもの頃から学者という職業に興味を持っていた。小島は笑って振り返る。
「言葉もおぼつかない頃、やたら『けんきゅうじょ』という言葉を連発していたみたい。親も覚えていて、そのことはよく言われます」
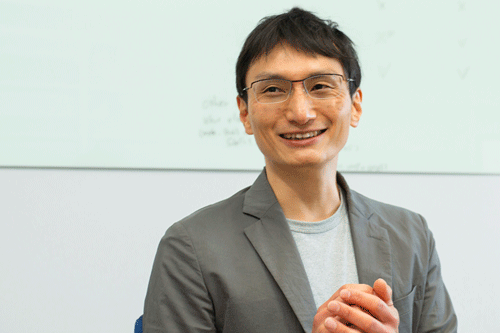
高校入学を控えた小島が読みあさったのは新書シリーズ「ブルーバックス」(講談社)だ。生物学の本に出合い「生物学、最高!」と閃き、筑波大学附属駒場高校では生物部に入ったという。ところが、手先を器用に動かす才能がまるでないことに、小島は気付いたという。
「同級生の部員がカエルの実験をするなかで、僕はカエルにひたすら餌をあげる係でした」
数学者になりたいと夢想したこともある。エヴァリスト・ガロアという十九世紀のフランスの学者にのめり込んだ。恋人をめぐって決闘して死ぬ直前、彼が友人に理論を書いた紙を託したという伝説に、惚れ込んだ。それに、答えを導くことだけが正解である数学の世界なら、偉い人への「忖度」が一切ない。サッパリしている。
東京大学の理科一類に現役合格。「理一」では、思う存分、数学に没頭できる。意気揚々と踏み込んだ駒場キャンパスで、小島は、こっぱみじんに打ちのめされた。
聞いたこともない複素数を書いてきて、いきなり解析学を始める者、英語の本をすらすら読む者。頭の回転が皆、とにかく速い。同じ年齢とは思えない。天才、神童だらけだった。それに比べて自分は、東京の都心から離れた多摩地域の野山で遊ぶ子ども時代を送り、のんびりと育ってきてしまった。小島は落胆した。
三年次以降の学部を選択する時には単位が足りず、小島は留年が決まる。人生の階段を転がり落ちた自分を変えようと思った。まずはバンドをやろうとボイストレーニングの教室へ。しかし GLAY や Bon Jovi の曲のサビ部分が高音過ぎて歌えず、ヴォーカルの道も挫折した。迷走を極めた小島はインラインスケートのサークルに駆け込んだ。
まさかここが運命の転換点になるとは思わなかった。経済学部に在籍するサークルの友達が貸してくれた一冊の経済書にのめり込んだ。小島は言う。
「松井彰彦先生という東大経済学部の先生の著作で、ゲーム理論の本でした。めちゃくちゃハマりました。『経済学をやろう!』。すぐに経済学への転向を決めました」
プレイヤーがどんな行動をとるか、互いを読み合うのが「ゲーム理論」。社会の様々な行動が当てはまる。勝ち負けという狭義的な「ゲーム」ではなく、ここで言うのは人間の行動だ。うまくプレーすれば、お互いのためになるゲームもある。まさに小島が現在心血を注ぐ「マッチング理論」の根底に流れる理念だ。経済学部に移った小島は、松井教授の門下生になった。するとすぐに頭角を現し、卒業時には経済学部の総代となった。
そしてハーバード大学へ留学した。小島は当時を振り返る。
「東大の卒論は松井先生の理論を発展させたものでした。しかし松井先生からは『アメリカでは自分で面白い問題を見つけるように』と諭されました。『僕は何を見つけられるのか』。悩みを抱えたまま、大学院に進みました」

恩師、アルヴィン・ロス教授の下で「マッチング理論」に出合い、そしてそれを実社会に活かすべく、早朝から深夜まで研究に打ち込む日々を送った。昨年末に東京に戻ってくるまで、彼が在籍していたスタンフォード大では、二〇一二年にハーバード大から移籍したロス教授が同年の、また、同僚だったロバート・ウィルソン、ポール・ミルグロム両教授がともに二〇二〇年のノーベル経済学賞を受賞。「ゲーム理論」がその受賞対象となった。まさに小島たちは今、経済学のトレンドの中心にいる。
帰国を決めたもう一つの理由
東京に戻ることを小島が決めた理由には、自身の研究を拡大し、実践に活かせるプラットフォームが整いつつあることと、もう一つ、大きな理由があった。
「妻も同時に、東大からオファーをいただいたんです」
妻・高木悠貴氏もオファーを受け、小島の研究室と同じ、本郷の経済学の研究棟で働き始めることとなった。こうした夫婦ともに同じ職場に移籍するというケースは、日本において実は極めて稀有だという。小島は言う。
「私の聞いた範囲では、東大では僕たちが最初の例なのだそうです。これまでは、男性の仕事を優先し、女性は仕事を辞めてしまったり、再就職に苦労したりすることが、まかり通っていました。ひじょうに良くないことです。そんな折、東大は力になってくれました」
日本に戻ってきた小島が痛感すること。それは、学生たちの「経済事情の厳しさ」だ。生活費のため大学院に通いながらアルバイト漬けになる学生は多い。しかし同時に研究する時間は減ってしまう。
「米国の有力大学では、基本的に生活は完全保証です。古巣のスタンフォードでは、大学院生には給料が出ています。日本にはそういった保証が十分ありません。UTMDで僕たちの仕事を手伝ってもらう学生には(ギャランティを)支払っていますが、今後もそういった仕組みを充実させていく必要が現実問題としてあると思っています」
後進の研究環境の整備も気遣いながら、小島はこの国の将来を見据え、種をまき育てていく。彼が今後、さまざまな分野において指し示す提案は、硬直した私たち日本社会の躯体を解きほぐし、新しい普遍へと導くヒントを与えてくれるかもしれない。本郷キャンパスの赤門や、冬木立を眺めながら、久々に希望のにおいを嗅いだ気がした。

〈写真下〉数式やアイデアは今も手書きで。紙のノートの代わりにE InkのタブレットやiPadを愛用している
小島武仁(こじま・ふひと)
1979年、東京都生まれ。2003年、東京大学経済学部卒業(経済学部総代)。2008年、米国ハーバード大学経済学部博士。イェール大学(博士研究員)、スタンフォード大学(助教授、准教授、教授)。2012年に同大学でテニュア(終身在職権)を獲得。2020年9月より東京大学経済学部教授、東京大学マーケットデザインセンター(UTMD)・センター長に就任。
(インタビュー/加賀直樹 写真/松田麻樹)
〈「本の窓」2021年3・4月号掲載〉

