源流の人 第38回 ◇ 藤原辰史(京都大学人文科学研究所准教授)

歴史学から見つめる子どもの「食」の明日
藤原が『給食の歴史』(岩波新書)を出版したのは、コロナ禍前、2018年のことだ。日本や世界の給食の歴史について振り返りながら、給食が、単なる教育の一環としてだけでなく、貧困や災害、社会運動、さらには国際情勢とも密接に繋がることを探っていく名著だ。現在までに8刷を重ね、支持が拡がっている。紅葉の色づくキャンパスにある研究室で、藤原は柔和な表情で迎え入れてくれた。

「給食費の無償化が、各自治体でちょうどブームになってきていて、給食をめぐる議論が高まっています。その背景にはコロナがあります。学校給食が、どれだけ貧困家庭や、社会的に弱い立場にある人の子どもたちを救ってきたのか、それに皆気づいたと思うんです」
給食の価値が、もう一度見直されつつある。経済状況が低迷し、生活が苦しい家庭が増えてきた中、給食の無償化に向けた動きも起きている。藤原の専門は歴史学、とりわけ農業史と環境史だ。20世紀の「食」と「農」の歴史や思想について深く見つめ、戦争、技術、飢餓、ナチズムなどについて、数々の研究・著書を発表してきた。
そんな藤原が分析概念としているものが、2つある。1つは「分解」。つまり、ものを壊して、属性をはぎとり、別の構成要素に変えていくこと。もう1つは、「縁食」。つまり「孤食」ほどは孤立しておらず、「共食」ほど強い結びつきのない食の形態のことだ。これらを用いて藤原は、自然界と人間界とを同時に叙述する歴史の方法を考えている。
調理現場を身近に感じてもらうことが大切
『給食の歴史』を発表してから、藤原のもとには講演依頼が全国から相次いでいる。依頼者たちは、給食を運営する側の栄養士、栄養教諭、そして調理師たちだ。藤原は語る。
「給食の激動の時代の中、簡単に給食を『センター方式』に持っていかれないように、『自校式』にしたい、という声が高まっています。歴史や他地域の実践を学び、理想の給食を目指したい人も増えていると思います。講演後、『自分の仕事にやりがいを見いだせた』という声を聞いた時には、私も励みになりました」

「自校式」「給食センター方式」。2つの長・短所は、それぞれ長い間議論され続けてきた。最近の潮流はどうなっているのか。
「日本の大きな流れとしては、明らかに『センター方式』に傾いています。理由は、お金がかからない、ということが指摘されます。1か所に大きな調理場を作って、大量購入・大量調理すれば、コストが抑えられる。いっぽう『自校式』にすると、各小学校・中学校にそれぞれの調理場ができるため、働く人を各校に置かなければいけない。時間と人件費がかかる。だから『センター方式』が自治体には好まれる」
彼は、自身の主張を続ける。
「でも私は、『センター方式』は教育の質が求められる時代に逆行していると感じます。『センター方式』にした場合、そこから各小・中学校に運ぶのに時間がかかります。午前10時半ごろには調理を終え、食缶の中に入れて(各校に)持っていかなければいけない。作っている人たちからよく聞くのは、『もう一手間、二手間かけたら、もっと美味しくなるのに』っていう言葉です」
さらに「センター方式」で導入されている、食材を切る際の裁断機の使用についても、藤原はこう語る。
「栄養士や調理師の方の多くが、人の手(包丁)で切った方が美味しいといいます。手を使えば使うほど美味しくなる。もちろん『センター方式』でもさまざまな工夫がなされていますが。ただ『自校式』の方が、子どもたちと距離が近いし、働く人が子どもたちの反応を直接聞ける。これって励みになるんですね」

たしかに、「自校式」だった小学校時代を思い起こすと、4時間目、給食室から流れてくる料理のおいしそうなにおいの虜になって、授業に集中できなくなった。献立がカレーだった日には、尚更たいへんだった。授業の終わる瞬間を待ちわびていた。においの記憶は強烈だ。ところが、「給食センター方式」に変わった中学時代、まず調理室から漂ってくるにおいが失われた。どういう人が作っているのか、その姿を見ることができなくなった。
大阪府の保育園の給食調理を担当する職員から、藤原がヒアリングした記録がある。
「料理を作っていると、午前11時ごろ、子どもたちが調理場の窓に集まるそうです。『なに、つくってんの?』。『今日はカレーだよ』『うわー!』。調理している場面を子どもが見て、そこで鼻をくんくんさせて、『やった!』と実感を得るプロセスが生まれるというのです」
その保育園では、建物の設計を相談するさいに、調理員も加わった。その結果、調理室が建物の中央に置かれ、調理過程が、園児だけではなく、保育士たちの目に入りやすくなった。これまでは端の目立たないところで作られていたが、新築校舎では料理が保育の中心的な位置づけを与えられる。運営者の意図通りになったそうだ。
「あなたたちに料理を作っていますよ」
「美味しいものを食べてほしいんですよ」
「あなたはここにいていいんですよ」
「ここでただ食べるだけでいいんですよ」
こんなメッセージがこもっている。ひいては、「命をいただく」ことに対する畏敬の念を、子どもたちの心に培うことにもなるだろう。
学校給食では救えなくなった子どもの貧困
ただ、最近は深刻なニュースも相次いでいる。
物価や人件費の高騰で、学校に給食を提供する業者が苦境にあえいでいるのだ。2023年9月には、全国約150か所で給食を請け負う広島の業者が、事業の一部を取り止め、問題となった。帝国データバンク調査によると、2022年10月時点で7864品目もの食品の価格が上昇した。給食事業者374社のうち約3割が赤字になっているのだという。藤原は語る。
「民間業者ではどうしてもコストを最優先し、丁寧に作られた質の良いものを子どもたちに食べさせたいという親の気持ちとなかなか連動しない。給食は本来、利益を増やすためのものではありません。自治体が安定的にやるべきものです。『破綻する』というのは、『給食の原則』から遠のいてしまっているということです」
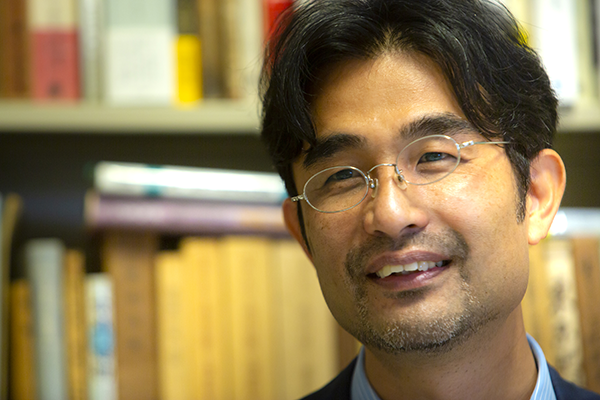
「給食の原則」──藤原は、こんなふうに捉えている。
「どんなことがあろうとも、とりわけ経済的に苦しい状況、不況、自然災害で大変な時にこそ、役立つものであること」
「財政がうまくいかないから給食も破綻、ではなく、ピンチの時こそ私たちの税金で安定的に供給されるものであること」
本来はそれが原則であるはずなのに、と藤原は嘆息する。
このところ「子どもの貧困」が、特に深刻であるとの報道を目にする。
もちろん、昔から貧困はあった。ではなぜ今なのか。昔から存在していたものが、最近、可視化されただけなのか。それとも、社会情勢がより酷くなっているのか。藤原はこう答える。
「私は、両方だと思っています。私たちの世代では、高度経済成長期が終わりかけ、急激な経済成長が止まった1973年のオイルショックから、緩やかに上りつつ、『バブル崩壊』でドーンと落ちました。その後、さらにリーマン・ショックが追い打ちをかけ、結果、貧困家庭が増えてきています。特に小泉純一郎が首相になった頃から、格差が広がって、リッチな人はよりリッチに、貧しい人はどんどん貧しくなっています。」
こうした事態を救う手立ての一環として、「学校給食」は目立たない貧困対策となりえる。経済的に恵まれた子も、貧しい子も、等しく同じものを食べる。貧しい子が恥ずかしい思いをしなくて済む。藤原によると、そこが大きなポイントなのだと栄養学者の佐伯矩は述べ、1930年代初頭に東北地方が凶作で苦しんだとき、国に全員給食の実施を勧めた。
「これによって、貧しい子がひもじい思いをしなくても良かったのです。おかげで貧困が隠されてきました。ところが最近は、給食が破綻することで、子どもの貧困が更に可視化されてしまったのです」

2008年、ショッキングな本が出版された。
経済学者・社会政策学者の阿部彩・現東京都立大教授が、『子どもの貧困 日本の不公平を考える』(岩波新書)。「格差」だけでなく、この国には「貧困」が存在することが広く知られた。高度経済成長を経て「日本は貧困を克服した」と思っていたのは、実は大きな誤解であり、「子どもの6人に1人は貧困だ」と阿部は著書で記した。そのことは世に驚愕を持って受け止められ、国会で取り上げられもした。藤原は振り返る。
「このあたりから、実態が明らかになってきました。朝、お腹ペコペコでやってくる子どもたち。夏休み明け、ガリガリに痩せている子どもたち」
藤原が『給食の歴史』の筆を執るきっかけになった、社会を取り巻く事態は、阿部の記した15年前よりも、更に悪化の一途をたどっている。
「子ども食堂」が作り出す「縁食」の場
「子ども食堂」が全国に広がっていったのは、ちょうどこの頃と時を同じくする。
地域の大人が子どもたちに無料、あるいは低額で食事を提供する場で、2012年、東京都大田区でできたのが始まりとされる。社会福祉法人やNPO組織が全国各地で立ち上がり、運営を担う「子ども食堂」。本来ならばこれは、国や行政が調えるべき対策ではないか、そんな声も多く出ている。しかしながら藤原は、「『子ども食堂』には、むしろ可能性を感じています」と話す。
「たしかに子どもの暮らしは国や行政が支えるべきことで、子ども食堂が増えることは、日本の、子どもの福祉に対する政策の穴、日本政府が子どもたちのケアができてない証です。でも驚いたのは、コロナ禍になっても『子ども食堂』が増え続けていることです。私は、(感染が)危ないから減ると思ったんですよ。ところがコロナ禍になり、ひとり親世帯や非正規雇用の経済状況はますます悪くなった。せめて子どもに美味しいご飯を食べさせたい、って一所懸命頑張る人たちがたくさんいたんです」
彼らのおかげで、地域にコミュニティーが生まれたケースもある。鳥取県では、こんな事例があった。
ある福祉事業体のトップが各戸に、子ども食堂を開くという「お知らせ」を配った。お年寄りには無料であることを告げた。
ところが大人はあまりやって来なかった。そこで、彼は文言を変えた。
「子どもが困っているので、あなたたちの力がほしい。ぜひ『子ども食堂』で手伝ってください」
すると、高齢者がどんどん集まってくれた。もう一度、誰かのためになれる場所。その場所が「子ども食堂」で叶ったのだ。藤原は言う。
「鳥取だけじゃなく、『子ども食堂』を運営される方たちは皆、そうです。自分たちも一緒にケアされている。料理を通じ子どもたちをケアし、同時に自分の生きる場所を与えられている。そういう意味で、可能性は大きい」

しかも、家庭以外の人が入ってくる。学校給食の現場では、担任しか大人がいない。ところが「子ども食堂」の場合、親以外の大人がいっぱい関わってくる。近所の農家のお兄さんが、曲がって売り物にならないキュウリやピーマンを持ってきて「ほら使って!」──。人類学では、親以外の大人と子どものゆるやかな関係を「ジョーキング・リレーションシップ」と呼ぶのだそうだ。冗談を言い合えるという関係。親関係や、先生と児童という関係だけでは決して得られない、面白い大人たちと触れ合うことで、子どもの関係が多面的に広がっていく。「子ども食堂」が持つポテンシャルとは、地域で子どもたちを見守り育てていくことだ。
「親の負担が軽減するとまでは言えずといえども、じわーんと横に広がっていく感覚。こういうのを見せてくれた意味で、未来を感じています」
さらに、藤原自身の提唱する「縁食」という概念とも関わっていく。「孤食」でも「共食」でもない「縁食」。その概念がいかに大切なものであるかは、著書『縁食論』(ミシマ社)に詳しく記されている。
その『縁食論』では、「縁」という概念について、藤原はこう記している。
「縁とは、人間と人間の深くて重いつながり、という意味ではなく、単に、めぐりあわせ、という意味である。じつはとってもあっさりした言葉だ。めぐりあわせであるから、明日はもう会えないかもしれない」
(『縁食論』P27より抜粋)
読み進めていくと、日本では、いかに社会や政治の問題が、「家庭」にばかり押しつけられてきたのかがわかってくる。2022年に安倍元首相が暗殺されてから国内では「旧統一教会」の問題が大きく取り上げられた。彼らが声高に唱えてきたような「家庭こそが善」「家庭こそ目指すもの」との概念が、日本ではあまりにも強調され、押しつけられ過ぎるきらいがあると藤原は主張する。
「家族は大事、ということにはもちろん同意します。でも、『何かあったら、家庭で全部解決してください』というように、家庭が『利用されている』ことが問題だと思います。家族で社会の矛盾を解消しろとの圧しつけが、重なってしまっている。『自己家族責任』といったような事態です」
家庭から、アウトソーシングできる場所があればあるほど、家族は楽になっていく。ところが、「子どものことは、母親のこと」という考え方は、日本では今なお強い。「給食ではなく、母親の愛情弁当を」などという、化石のような言葉を吐く人々も、ずいぶんと減ったとはいえ、今でもたまに聞くという。その価値観の根源にはいったい何があるのだろうか。
「根源には、過剰な競争社会があって、競争するためには中断できない。本来は権利なのに、育児休暇を取っちゃいけない。女性たちも働く上では男になれ、と言われているようなものです。男女平等は現代の日本では、『男になって働け』というシステムだと思うんですよね。今も格差は広がったままですから」

形だけ男女の雇用機会を均等化させようとしながら、実態はそれとは合致しない。だから二重に苦しむことになり、とりわけ女性に皺寄せがくる。
たとえば先に記した「子ども食堂」などは、「たまたまその場で子どもがご飯を食べている」という、藤原の唱える「縁食」の絶好の形態ともいえる。そして、その場所にやってきただけでも、「ようこそ来たね!」といった声が誰かしらから掛けられる。タテでもヨコでもない、緩やかな連帯がそこに生まれる。藤原は、広島の「子ども食堂」で起きた、ある事例について語ってくれた。
「コロナ禍による一時閉鎖を経て『こども食堂』が再開した日、ワンオペのお母さんが子ども2人を連れてそこに行ったんです。『子ども食堂』の女将さんが『ようこそ!』と迎えると、下の、3、4歳のお子さんが、ワーッて女将さんのところに駆け寄って、女将さんに抱きかかえられました。すると、上の男の子が、お母さんの膝が空いていることを発見し、お母さんの膝にちょこんと座ったのです」
親でも先生でもない、女将さんという「誰かしらの大人」が入ることで、子どもにとってゆとりが生まれ、しなやかなスペースが確保されていく。藤原はこう続ける。
「たぶんずっと、上の息子さんは我慢していたと思うんですよ。コロナ禍で、家庭では下の子にお母さんは付きっ切りになりますから。だけど、『子ども食堂』ではお母さんが自由になるんです」
そんな「ゆとり」がどれだけ大切か、痛感するいっぽうで、藤原は現在、学校現場で続く「あるルール」に対して覚える違和感を隠さない。
「『黙食』です。皆の憩いの時間が、今もなお、奪われているんです。驚くべきことです」
給食時間に会話を一切せず、無言で食事しろという「黙食」。実は、防止策のひとつとして全国で採用された。厚生労働省は当初、「飲食はなるべく少人数で黙食を基本とする」と発表していたが、2022年11月25日にはこの部分が削除されている。藤原は嘆く。
「政府が『もういい』って言っているのに、今も『ご飯の時にしゃべっては駄目です』っていうのが各校で続いているんです」
藤原によると、じつは「黙食」の取り組みはコロナ禍以前から始まっていた。子どもたちには黙ってスピーディーに給食を食べてもらい、昼休みには校庭で遊ばせる。その昼休み時間を使って、教員は山積するカリキュラムの準備に充てていたのだという。

「これは先生のせいじゃなくて、政府のせい。競争社会でカリキュラムを詰め込み過ぎているのが問題だと思うんですよ。僕は特別にノーベル賞が偉いとは思わないけれど、こんなことをしていたら、間違いなく日本からノーベル賞は出なくなります。ゆとりのある思考ができなくなるばかりですから。一見無駄なことをやって楽しめることがあってこそ、世界をあっと驚かせるアイディアが浮かぶはずです。それこそ、ご飯を食べながら、コーヒーを飲みながら、発想が豊かになるんです」
地産地消給食で農業の復活を
藤原の関心が「農」や「食」に収斂されていったのは、自身の育った環境と関係が深い。
藤原は北海道生まれ、島根県育ちだ。父親は中国山地の山奥にある島根県横田町(現在の奥出雲町)の農家の長男として生まれた。地元の大学を卒業後、もう少し農業を深く学ぼうと、北海道・旭川にある「上川農業試験場」に勤め、土壌や肥料の研究に明け暮れた。その旭川で生まれ育った母親と彼は出会い結婚。藤原が生まれた。
「おふくろと結婚して、僕が生まれて、島根に戻ってくるんです。僕が2歳の終わり頃でした」
島根県の農業試験場(当時)があった出雲市で小学校卒業までを過ごし、中・高校生時代は、父親の実家へ。いつも彼のそばには農業があったという。藤原は振り返る。
「パッカーと呼ぶ、藁とか牛糞を積む三輪車の荷台に乗ることが好きでした。おじいちゃんから『とうきび(トウモロコシ)食うか?』って。とうきびを網であぶったのをパッカーで食べたのを思い出します」

ただ、地域に書店は1軒だけ。映画館はない。寂しく感じていたこともたしかだった。そして、いわゆる家族主義の強い場所に育つなか、「日本の農業がいかに蔑ろにされているか」を感じていた、と藤原は言う。たとえば、「減反」。
「目の前に田んぼがあるのに作れないわけですよ。もちろん補助金が来るわけですけど、働かないでお金が来るのを、農家の人も疑問に思っていた。日本近代の矛盾が凝縮していました」
それから、当時通っていた中学校の給食が美味しくないことにも衝撃を受けた。
「近くにはこんなに素晴らしい食材が溢れているのに、なんで……?」
その苦い思い出は、数十年間、彼の脳裏に焼き付いていた。京都大学に進み、人文科学研究所助手、東京大学講師を経て、2013年から京都大学人文研准教授を務める藤原には、「食」と「農」を掘り下げながら、改めて、当時の給食の苦い思い出が蘇った瞬間があった。それは同時に、新たなプランが閃いた瞬間でもあった。韓国の最近の学校給食の事例を知った時のことだ。
「各校で、オーガニック給食がかなり普及しているんですよね。給食でオーガニックが普及すれば、オーガニック野菜を作る農家が増えていく。だから、農家を育てられる。今、注目しているのは、『給食が農業を育てる』ということです」
「給食」を、農の産業育成の契機として捉える。大量の野菜を買うことがあらかじめ決まっているのだから、輸入食材で賄うのではなく、地域で担う。たとえば東京なら、茨城や千葉などの大農業地帯に隣接しているのだから、連携を深めていく。有機野菜を使うようにし、農業分野に若い人が就くような仕掛けが作れれば、農業を復活に向かわせられるはずだ。
京都府伊根町、ある日の小学校の給食の献立。
「調理員の自宅で穫れたサツマイモのご飯」
・サツマイモは細かくサイコロ状に刻んで少し揚げて甘みをつけてある。
・サツマイモの芋づるを細かく刻み、ご飯に混ぜてある。
「地元産コシヒカリ」
「牛乳」
「地元漁港のサワラに味噌をつけて焼いたもの」
「地元産のじゃこで出汁をとったスープに玉子を溶いたもの」
「ピーマンとニンジンのゆかり和え」
「カボチャ・ニンジン・ちくわ・ゴボウ・こんにゃくの炊き合わせ」
――著書『給食の歴史』で挙げた伊根町では、このような献立で既に100%地元産の給食を実現している。取材に訪れた時の思い出を、藤原は快活な表情で振り返る。
「むちゃくちゃ美味しかったんですよ! そのためにものすごく苦労した栄養士さんがおられるんです。漁港に通って、農家に通って、子どものために、って。誇りを持っていらっしゃる。その後を継いだ栄養士さんと話したのですが、食べている様子を見て、子どもたちの健康状態までわかっちゃうそうです。すごい仕事ですよね」
ナチスの悲劇を二度と繰り返してはならない
「子ども」と「食」についての発信が多い印象の藤原だが、それ以外の分野でも精力的に発言を続けている。
「もういっぱいあります。全方位的に戦わされている状態(笑)。たとえば東京・明治神宮外苑再開発は、ただ開発のためだけに、長く育ててきた樹木が伐採されるというのは、私が『分解の哲学』(青土社)で主張したような、修繕して修理し、愛着を持って使っていくというあり方を否定していると思うんですよね。これからは、古いものを修繕しながら、作っていけば良いはずです」
そして何よりも、2023年11月の現時点で、彼が強く憤っていることがある。
「イスラエルによるパレスチナ自治区への猛烈な攻撃です。ハマスのやった、10月のイスラエルの奇襲攻撃はたしかに衝撃的でしたが、でもその根源は、2007年からのイスラエルによるガザ地区の軍事封鎖です。軍事封鎖はつまり、武力で住民たちの移動を制限し、食料や水を行き渡らせなくすること。そして、今回の攻撃で、完全封鎖になり、電気も水もストップした。今、ガザの人々の飢えは極限に達しています」
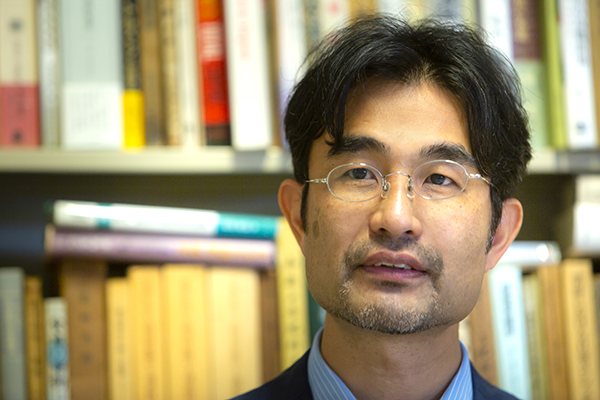
藤原自身の研究であるナチス・ドイツとも深く関わっている。京大の学部生の時に資料に読みふけるうちに、ナチスの問題に出合った。「健康ではない」という理由で、他民族や障害者を殺したナチスに、強い嫌悪感を抱いた藤原は、そのナチスが食料の自給自足をめざし、有機農業を進めようとしていたことを知ってから、「ナチス」と「農」「食」を連携させて研究の道を歩み始めた。
「僕は、ナチスを生んだ原因の一つは、『飢え』だと思っています。第一次世界大戦の時、イギリスがドイツを海上封鎖し、ドイツ国内の農業政策も失敗して、76万人の餓死者が出ています。世界第2位の科学大国かつ工業国で、子ども38万人を含め死んでいる。『飢え』だけで、です。この傷跡は大きかった」
封鎖で人を殺した。兵器による戦争ではなく、「Food War」だった。藤原は続ける。
「食料こそが武器だ、ということを考えたのがナチスでした。これは僕の研究のメインでもあるのですが、『食料を子どもたちに食べさせない国は国ではない』というナチスのメッセージがある」
農民を国家の中心に据え、農民こそが国の主人公だ。そう唱えて農民の票を得て、ナチスは支持を獲得していった。世界恐慌で農民たちが借金苦に陥っている時、一気に票を伸ばした。
「ナチスは食料について考えたんです。プロパガンダで農民たちの気持ちを最初だけはつかまえた。ただし、ナチスが酷いところは、その恩恵を被るのはアーリア人であるドイツ人だけ、という点です。私が一番許せないのは、身体の不自由な人たちや、ユダヤ人やスラブ人たちは劣っているので飢えてもらう。私たちドイツ人だけは飢えさせない。そんなふうに人種主義に転換してしまったことです」
子どもを飢えさせない、という問題提起自体に間違いはなくとも、ナチスはそれを人種問題に巧妙に転換しすり替えた結果、悲劇が起こった。そんな悲劇を、もう二度と繰り返してはいけない。そう藤原は訴える。
「こうした歴史を考えると、今のパレスチナで起こっている、飢えさせる作戦、上から爆撃し、生活基盤自体を破壊していく攻撃に、欧米諸国はあまりにも批判が弱い。どちらも許されるべきことではない」
パンデミックを経た世界が連帯へ舵を切るどころか、ウクライナで、パレスチナで、逆走の一途をたどる現在。「給食」「子ども食堂」について視座を得るうち、話は地球規模に拡がっていった。すべては食で繋がっている。

藤原辰史(ふじはら・たつし)
1976年、北海道旭川市生まれ、島根県横田町(現奥出雲町)出身。京都大学総合人間学部卒業。2002年、京都大学人間・環境学研究科中途退学、同年、京都大学人文科学研究所助手。その後、東京大学農学生命科学研究科講師を経て、現在は京都大学人文科学研究所准教授。博士(人間・環境学)。19年、第15回日本学術振興会賞受賞。著書では13年、『ナチスのキッチン』(共和国)で河合隼雄学芸賞、19年、『分解の哲学』(青土社)でサントリー学芸賞を受賞。他の著書に『給食の歴史』(岩波新書)、『縁食論』(ミシマ社)、『農の原理の史的研究』(創元社)など多数ある。







