著者の窓 第26回 ◈ 小佐野 彈『ビギナーズ家族』

新進気鋭の歌人として活躍する一方、小説家としても評価を得ている小佐野彈さんが、最新作『ビギナーズ家族』(小学館)を発表しました。会社経営者でエッセイストの秋と、特別支援学校の体育教員の哲大。都内で暮らす同性カップルが、ひょんなことから秋の亡父が三番目の妻との間に遺した子・蓮を養子として迎えることになり……。さまざまな困難を乗り越え、超難関私立小学校受験に挑む親子三人の姿を通じ、〝家族になること〟を描いたエンターテインメント長編について、小佐野さんにうかがいました。
兄一家を救いたくて書き始めた物語
──小佐野さんは歌人として活躍するかたわら、二〇一九年刊の『車軸』以来、小説も執筆されています。文芸誌にも純文学作品を発表されていますが、小説と短歌では創作スタンスにどんな違いがありますか。
短歌はもともと告白性の強い文芸ですから、ノンフィクション的になりますよね。以前とある編集者さんに「彈君もそろそろ人に知られたくない自分を書くべきだ」と言われたんですが、それはおそらく小説に対する評価であって、短歌ではずっと恥ずかしい部分をさらけ出してきた気がします。メンヘラな自分も、虚勢をはって必死に生きているビビリな自分も、嘘偽りなく歌にしてきました。対して小説はフィクションですから、自伝的に見えても私性からは自由になれます。その中間にあるのがエッセイで、あれは実話七割、盛りが三割という感じかな(笑)。虚実の比率が違う三つのジャンルを書くことで、うまくバランスが取れているような気がします。

──三十一文字で完結する短歌と、それなりの長さが必要な小説では、苦労する点も異なりますよね。
そうですね。短歌はそもそも作るっていう感じがしない。息をするように勝手に出てきてしまう。明日までに連作五十首作ってきてと言われてもできると思います。なんならスキー場のリフトの上でも詠める(笑)。小説はまだ息をするようにとはいきません。構築性が必要なジャンルですし、多少は身構えてしまうところがあります。なんとなくコツがわかってきたのは去年くらいから。『ビギナーズ家族』はまだ一作しか小説を発表していなかった三年半前に初稿を書いた作品なので、気負わずに書けていると思います。改稿作業しながら下手くそだなあと思いつつ、でも今の自分ではこんなにピュアに書けないな、と微笑ましくも感じましたね。
──『ビギナーズ家族』はひょんなことから亡き父親の遺児・蓮を引き取ることになった会社経営者でエッセイストの秋と恋人の哲大が、わが子の幼稚園入園、難関私立小学校受験などのライフイベントを通して〝家族になるまで〟を描く長編です。構想のきっかけは?
正直に答えるべきかどうか迷うんですが……、答えないとインタビューにならないのでお話しすると、この小説を書き出す少し前に、兄の子が私立小学校を受験して、失敗してしまったんです。周囲から大丈夫だろうと言われていただけに、兄一家はショックを受けたんです。でも残念な結果に終わったのは甥っ子のせいじゃないし、兄夫婦のせいでもない。たかが小学校受験くらいで家庭内が暗くなったり、アイデンティティクライシスに陥ったりすることはないんじゃないか、という思いからこの小説を書き始めました。出発点は兄一家を物語の中で救いたいという、ごく個人的動機なんです。
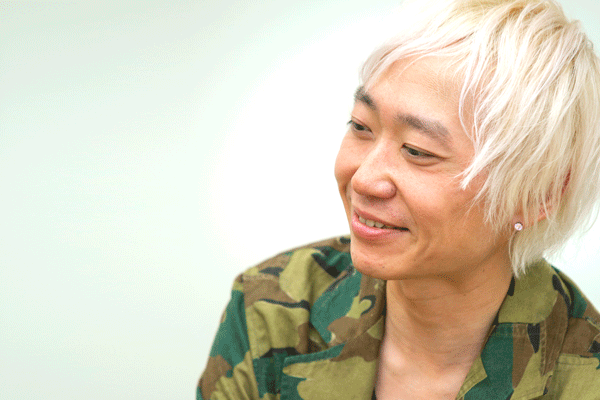
──そんな背景があったのですね。てっきり同性カップルが養子を迎える、という部分から着想されたのかと思っていました。
それはまったく違います。今回は僕がたまたまゲイだからこういう設定ですけど、主人公が同性愛者だろうが異性愛者だろうが、そこはどっちでもよかったんです。過度に社会批評的なニュアンスで同性カップルを取り上げたくはないし、そこは「養子を迎えたカップルがたまたま同性でした」くらいで受け止めてもらえれば。
もちろん日本にはまだまだ同性愛者への制度上の差別や社会的偏見がいっぱいあるわけですけど、それに対する怒りを小説で訴えようとは思いません。小説をマニフェストにしたくない。秋と哲大が直面している悩みや苦しみも、同性カップルじゃなかったとしても、誰にでも起こりうることなんですよ。家族を作っていくということの大変さという、普遍的な悩みを描いているつもりです。
世の中に〝他人事〟なんてひとつもない
──秋は中堅ゼネコングループの創業者の孫で、いわゆるセレブ家庭の出身です。小佐野さんご自身を連想させるプロフィールですね。
さっきお話ししたような事情があったので、僕の生まれ育ってきた環境をある程度モデルにする必要があったんです。でもあくまでフィクションですから、秋イコール僕ではありませんし、大田川家は小佐野家ではありません。家族構成も微妙に違いますしね。いっぽう哲大には一応モデルがいます。僕の最近の小説にはよくノリのいい関西人が出てくるんですが、あれは僕のパートナーをベースにしています。非常に書きやすいキャラですし、人物配置的にも使いやすいので、つい登場させてしまいますね。

──そんな秋と哲大の生活が、蓮という養子を迎えたことでがらりと変わります。煙草をやめ、高熱を出して嘔吐する蓮を看病する。秋が〈親〉としての自覚を得ていく姿が、印象的に描かれています。
僕もずっと子ども嫌いだと思っていたんですけど、実は好きかもしれない、という事実に気づいてしまったんですよね。僕はこんな見た目なので、大人は警戒して近寄ってこないんですが、なぜか小さい子はよく寄ってくるんですよ。それがまんざら嫌でもなかったりして……(笑)。でも煙草をやめる覚悟はつかないし、秋みたいにはなれないと思います。
──秋の母親、知香は国際的に活躍するデザイナー。夫と別れた後、ひとりで秋と姉・春を育てあげた彼女は、今も家族に強い影響力を持っていて、孫たちの進路にも積極的に関わろうとします。
ここで描かれている葛藤や苦労は、どこのご家庭にもあることだと思うんですよ。富裕層だから自分たちと全然違う世界に生きてるんですよね、と考える人がいたら、それは違うと言いたい。僕は他人事という言葉が嫌いなんです。経済学的に考えれば、世界のあらゆる財は繋がり合っているはずで、今手にしているこのコーヒーだって地球の裏側で働く人たちの賃金や暮らしとの関わりで値段が決まっていく。世の中に他人事なんてひとつもないんですよね。
それなのにみんなすぐ一線を引きたがるじゃないですか。あの人は金持ちだから、ゲイだから世界が違うって。そう言われるとがっくりしてしまう。自分とは関わりのない世界に見えても、実はそれほど変わらない、同じようなことで悩んだり、苦しんだりしているんだということを知ってほしいと思っています。

──蓮を区立幼稚園に通わせはじめた秋は、親しくなった保護者の翔子から「秋さんのお母さんは毒親だと思う」「秋さんはお母さんを嫌いになる自由を奪われている」と言われ、知香との距離を見つめ直すことになります。この翔子の台詞には、はっとさせられました。
僕もこの台詞を書いていて、自分自身救われたところがあります。日本人って血縁関係を特別なものだと信じ込まされていて、家族だから愛さないと、家族だから面倒を見ないと、って思い詰めがちですよね。最近になって毒親という言葉が出てきて、ようやく風通しがよくなりましたが、それでも「親が嫌いだ」と翔子ちゃんみたいに公言するのは、勇気がいることだと思います。
うちの母親も知香さんみたいにパワフルな人なので、僕もかなり息苦しい思いをしましたが、それでも抜きがたい愛情がある。母親は母親で必死だったと思うんですよね。女手ひとつで子どもたちを育てないといけないというプレッシャーがあり、離婚した父への対抗心もあって、僕たちに過剰な思いをぶつけていた。書いていてそんな僕と母の関係も、あらためて考えるきっかけになりました。
手に汗握る名門小学校受験の舞台裏
──やがて蓮は私立幼稚園に転園、そこで超難関私立の小学校受験に挑戦することになります。そこで秋たちを待ち受けていたのは、保護者同士のマウンティングに、金品が飛び交う入試対策など。セレブな世界の静かな戦いから目が離せません。
今回はエンターテインメント小説なので、読者に思いっきり感動したり、ハラハラドキドキしてもらいたい。やっぱりみんな知りたいじゃないですか、名門私立小学校のお受験って。果たしてどこまで書いていいのか迷いましたが、僕はサービス精神が旺盛なので、つい深いところまで書いてしまう(笑)。ただもちろん誇張したり、フィクションを混ぜたりしている部分もあります。そもそも蓮の目指す慶心学院が、僕の母校の慶應義塾や、立地やミッション系である点が似ている青山学院だとは一言も書いていないですからね。東京にある他の私立がモデルかもしれない。虚実のあわいを楽しんでもらえたらと思います。

──しかし熾烈な小学校受験によって、秋と哲大の間にすれ違いが生じてしまう。そんな時、哲大が怒りとともに秋に投げかける言葉が胸を打ちます。
哲大が感情を爆発させるシーンですね。あそこは僕も好きです。それまで完璧過ぎた哲大が、ちゃんと不完全で感情のある生き物なんだということを書けたし、物語にもカタルシスが生まれました。結局、この小説に出てくる人たちはみんな家族ビギナーなんですよ。玄人なんて一人もいない。だからこそ愛おしいですね。これまでの経験上、登場人物に愛着の持てない小説は成功しないんですが、今回はめちゃくちゃ愛おしい。秋たちを陥れようとしてくるあの人も含めて、みんな大好きです。
──家族のビギナーだった秋たちは、小学校受験という一大イベントを経て、どんな風景に出会うのか。爽やかなラストシーンには、家族のあり方についてのひとつの答えが示されているように思いました。
答えというと大げさですけど、こういう家族っていいんじゃない、というひとつの姿を描けたかなとは思います。親が子の人生に全責任を負う必要もないし、子が親の望みを叶えるために必死になることもない。つい血が繋がっていると、自分の理想を押しつけたくなりますが、それぞれ別人格なんですから、もっと自由であっていい。憎しみ合っても、罵り合ってもいいんですよ。家族との関係で悩んでいる人たちがこの小説を読んで、家族ってこういうもんだよねと〝わかりみ〟を感じて、少しでも楽になってくれたら嬉しいです。

──確かに、多くの読者にとって〝わかりみ〟のある物語だと思います。
短歌にしても小説にしても、文学がなすべき仕事ってそれだと思うんですよ。わかりやすい共感や理解ではなくて、なんとなく腑に落ちる〝わかりみ〟を与えること。読者にとって秋の暮らしは縁遠いものかもしれませんし、知香みたいな強烈な母親もなかなかいないと思いますが、登場人物それぞれの生き方にはどこか〝わかりみ〟があるはずです。どうか楽しんでください。
小佐野 彈(おさの・だん)
1983年東京都生まれ。慶應義塾大学経済学部卒業。台湾台北市在住。2017年「無垢な日本で」で第60回短歌研究新人賞受賞。18年、第一歌集『メタリック』刊行。19年、第63回現代歌人協会賞、第12回「(池田晶子記念)わたくし、つまり Nobody 賞」受賞。小説作品に『車軸』『僕は失くした恋しか歌えない』がある。
(インタビュー/朝宮運河 写真/松田麻樹)
〈「本の窓」2023年6月号掲載〉





