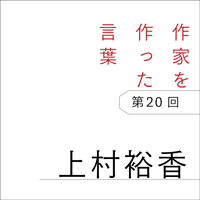「推してけ! 推してけ!」第56回 ◆『ほくほくおいも党』(上村裕香・著)

評者=窪 美澄
(作家)
傷がそこにあると書くこと
『救われてんじゃねえよ』で鮮烈なデビューを飾った上村裕香さんの二作目『ほくほくおいも党』は、活動家二世たちの生活と現実を綴った連作短編集だ。とまるで知っているように書いてしまったけれど、私はこの作品を拝読するまで、「活動家二世」という言葉を知らなかった。
親や家族が特定の宗教を信仰している家庭で育ち、本人の意志とは関係なく、その信仰の影響を強く受けている子どもたちのことを指す「宗教二世」という言葉は、ある程度、認知度が高まっているといえるが、活動家二世については、まだまだ知られていないのではないか。
本作から引用すれば「親が左翼政党の専従者や組合職員である、息子や娘のことを、活動家二世と呼ぶみたいです。」となる。共政党という左翼政党に属する父。そして、活動家二世である高校生の千秋。父はどんなときも選挙と党のことしか考えておらず、頻繁に選挙に出馬するようになってから、千秋の家は経済的にも苦しい。母は子ども二人を置いて出ていってしまった。千秋はなんとか現実世界に属して生きてはいるが、その兄は引きこもりで部屋からは出てこない。
物語のはじまり、ベランダで父が千秋の髪を切る、という美しいシーンでスタートするのだが、もうすぐ自分の誕生日なのだ、と告げる千秋に父はこんなふうに言葉を返す。
「参院選も投票できるってことやね」
「十八歳選挙権はね、共政党が戦前から主張してきたとよ。党創立直後の綱領草案のときから。共政党は戦前の、女性が選挙権を持っとらん時代から男女平等の十八歳選挙権を目指して闘って……」
えーい、黙れ! という言葉がずらずらと続く。
そんな父のブログのコメント欄を「しろたん@ほくほくおいも党」というアカウントが荒らすようになる。ほくほくおいも党とは、「ほくほくしたおいものにおいが好きな人ならだれでも歓迎する政治団体で、活動家二世の自助サークルみたいなもの」。千秋はこのしろたんが自分の兄なのではないかと思い……、というところから物語が転がっていく。連作短編なので、どれも千秋が主人公というわけではないのだが、どの登場人物も人生のどこかで共政党に抵触した経験を持つ。
物語のなかで何度もくり返されるのは、「……言葉をもたないわたしは、父とうまく会話ができない」という千秋の台詞に代表されるような、人と人との間で交わされる言葉の不在とディスコミュニケーションだ。千秋の父は饒舌なようでいて自分の言葉をもたない。政治の、共政党の言葉を鵜吞みにしているだけで、彼自身の体験から絞り出されたものではない(ここで自分の立ち位置を書き記さないとずるいような気がする。私は左翼寄りの人間なので、千秋の父、豊田正が候補者にいたら一票を投じてしまうだろう)。なまじ父の言葉が正しいだけに子どもの千秋は反論ができない。だが、この物語は、千秋が自分自身の言葉を獲得していくまでの成長譚でもあるといえる。最終話で、千秋は、父にも母にも、『ほんとう』の言葉で話してほしい、と迫る。
「……お母さんから見たら小さい傷かもしれないけど、痛そうに見えないかもしれないけど、それは、それはさ……痛くないってことではないよ」
そうだ。これを読んで思い出した。上村裕香、という書き手はこういう書き手だった、と。彼女の小説を初めて読んだ日のことを思い出した。傷がそこにあると書くこと、それを読んだ人が傷のありかを自覚することで、傷が治癒していくこと。一人の人間が長い時間をかけて知ることを、なぜ若い書き手である彼女がすでに知っているのか。彼女の小説を読んだあの日の驚きを、この『ほくほくおいも党』でも体験することができたのが、私はものすごくうれしい。
そして、共政党が、共政党の親世代が間違っている、という安易な結着に持っていかないところに、この作者の胆力を感じる。第2話の佐和子が語るように、
「……とにかくその『異和』を言語化したいからほくほくおいも党にいることと、わたしの理想がリベラルであることは矛盾しない」
この台詞は上村裕香という小説家の宣誓でもあると思った。
物語の上っ面だけを撫でて、悲しい物語かと思われてしまうのはあまりに惜しい。悲劇のなかにくすっと笑える要素を入れ込んでいく様はこの小説でも健在だ。だって、『ほくほくおいも党』だもの。活きのいい、次世代を担う小説はどこにあるのか、という方におすすめします。ここに、あります。
窪 美澄(くぼ・みすみ)
1965年東京生まれ。2009年「ミクマリ」で「女による女のためのR−18文学賞」大賞受賞。11年『ふがいない僕は空を見た』で山本周五郎賞、12年『晴天の迷いクジラ』で山田風太郎賞、19年『トリニティ』で織田作之助賞、22年『夜に星を放つ』で直木三十五賞を受賞。近著に『ルミネッセンス』『ぼくは青くて透明で』『給水塔から見た虹は』など。