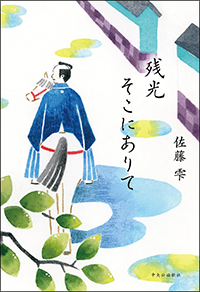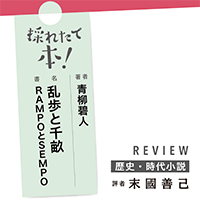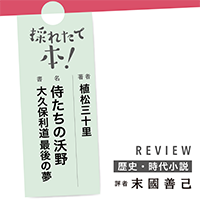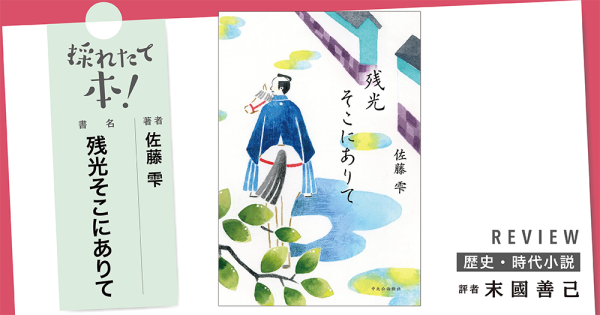採れたて本!【歴史・時代小説#32】
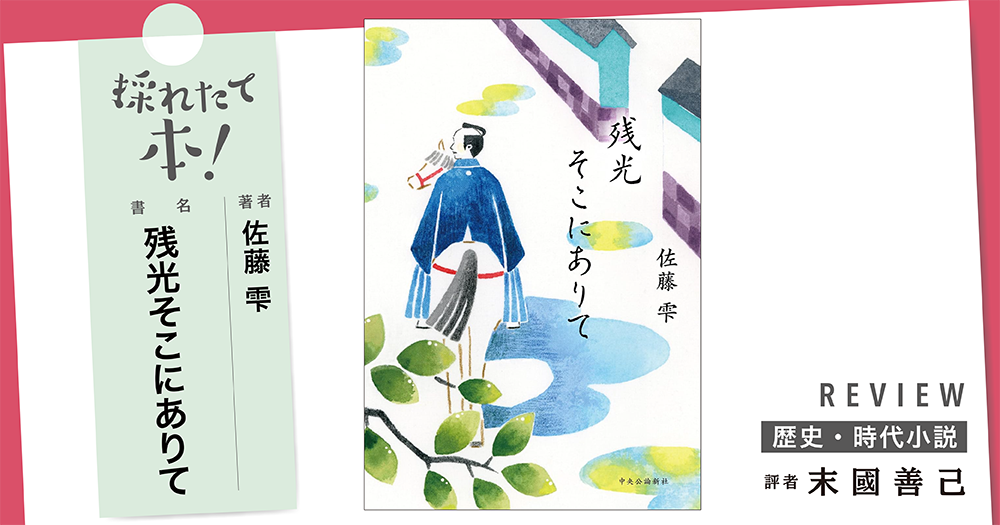
今年3月、2027年のNHK大河ドラマが、幕末の幕臣・小栗上野介忠順を主人公にした『逆賊の幕臣』になると発表された。執筆時期を考えると偶然だろうが、佐藤雫の新作も忠順を描いている。
大身旗本の小栗家に生まれた忠順は、33歳の時、日米修好通商条約の批准書を交換する幕府遣米使節団の目付として渡米する。その直前に大老の井伊直弼に呼び出された忠順は、条約によりメキシコ銀貨1枚と一分銀3枚の交換比率になったことで、一分銀が小判に両替されて金の国外流出が続いており、これを改めるために金小判とアメリカ金貨の金含有量を比較して欲しいとの密命を受ける。
アメリカで最新の科学技術に触れた忠順は、日本に造船所を造るという夢を抱くようになる。パナマ運河が天候不順で使えず喜望峰廻りで地球を1周して帰国した忠順は、外国奉行、勘定奉行などを歴任し外交と財政に辣腕を振るっていく。
海外から最新の技術を学ぶべきと考える開国派と外国人を排斥する攘夷派に国論が二分し、幕府の財政再建のため生糸の専売、フランスとの独占的な取り引きを考えるも他の国から保護主義的と批判され、諸外国と為替レートや関税率などの難しい交渉をしなければならなかった幕末の状況は、経済のグローバル化の波にさらされ、トランプ関税に振り回されている現代の日本に近い。攘夷派が殺傷した外国人の賠償金を幕府が肩代わりしたため、幕府の財政悪化を加速させ、外交交渉で不利な条件を吞まざるを得ない状況を作ったなど、意外な史実が掘り起こされているのも興味深く、いつの時代も外交は一筋縄ではいかないこと、その中で孤軍奮闘した忠順の偉大さがよく分かる。
忠順の宿敵(と書くと少し大袈裟だが)として登場するのが、勝麟太郎(海舟)である。譜代の旗本だった忠順に対し、株を買って武士になった小身の旗本の家に生まれ実力で出世した勝は、生まれた家で将来が決まる現体制を嫌い能力があれば世に認められる新しい社会を求めている。忠順と勝の考え方の違いは、古い組織を改善の繰り返しで再生するのが正しいのか、壊して新しく作り直すのが正しいのかを問い掛けており、アクチュアルなテーマは考えさせられる。
大政奉還後、徹底抗戦を唱えた忠順は守旧派の代表とされてきたが、著者は独自の解釈で晩年の忠順に新たな光を当てている。巨大な船が完成したら誰も目を向けないネジに自身を投影した忠順は、幕府が倒れても、自分が汚名にまみれても、日本の未来を照らす何かを残そうとする。この忠順の精神は、自己顕示欲と利己的精神が広がる現代日本への痛烈なカウンターになっているように思えてならない。
評者=末國善己