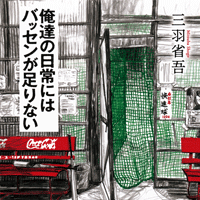今月のイチオシ本【エンタメ小説】

芳朗と蕗子の碇谷夫妻が、友人でミステリー小説家の野呂晴夫と、東京から離島に移住してくるところから、物語は始まる。芳朗、蕗子、野呂、三人はそれぞれに〝秘密〟を隠していて、その〝秘密〟は、物語が進むにつれ、薄皮が一枚ずつ剥がれていくように、ゆっくりと明らかになっていく、というのが本書の大枠だ。
冒頭、芳朗のパートで明かされるのは、七十歳になった蕗子の手が、まだ十分に美しいこと、そしてその手は殺人者の手であること、だ。妻が殺人者? そんな疑問符が頭の中に浮かんでしまったら、読者はもうこの物語から離れられない。そして、最後の一行まで、一気に読んでしまう。
けれど、それは作者の企みの一つにしかすぎない。ミステリアスな仕掛けや、幾重にも絡まり合った細部の精緻さはもちろんなのだけど、井上さんの物語を読む醍醐味は、そこではない。少なくとも、私にとっては。
私が我知らず井上さんの物語にからめとられてしまうのは、例えばこんな箇所である。蕗子が芳朗の不実な過去を回想するシーンだ。
けれども蕗子は応じてしまった。理由のひとつには、「芳朗さんもいらっしゃいます」と女が言ったことがあった。芳朗も来る。女と夫をふたりきりにしたくない、と思ったわけではなかった。女と蕗子、ふたり揃った前で、夫がどんな顔をし、何を言うのか知りたかったのだった。
この文章だけで、蕗子という女の輪郭が鮮やかに浮かび上がってくる。彼女の心にある、名状しがたく、そして自分自身でさえ御し難い、残酷でほの昏いもの。それが読んでいる側に、するりと入り込んでくるのだ。こういった、言葉の、そして、文章の巧みさを味わうこと。それが私にとって井上さんの物語を読む醍醐味であり、喜びでもある。
三者三様の〝秘密〟が明らかになった後、野呂の言葉──人生というものを、誰もがもれなく持っているのだ──が、じわじわと効いてくる。