『ムーンナイト・ダイバー』
【ポスト・ブック・レビュー 著者に訊け!】
3・11から5年
鎮魂と生への祈りをこめた
著者渾身の長編
『ムーンナイト・ダイバー』
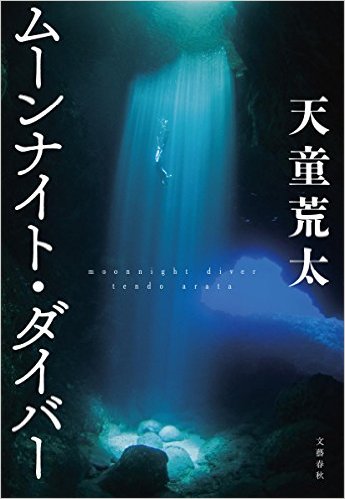
文藝春秋 1500円+税
装丁/関口聖司
写真/岡本隆史
天童荒太

●てんどう・あらた 1960年愛媛県生まれ。明治大学文学部演劇学科卒。86年「白の家族」で野性時代新人文学賞を受賞後、林海象監督『ZIPANG』等の脚本を手がけ、執筆を再開。93年『孤独の歌声』で日本推理サスペンス大賞優秀作、96年『家族狩り』で山本周五郎賞、00年『永遠の仔』で日本推理作家協会賞、09年『悼む人』で直木賞、13年『歓喜の仔』で毎日出版文化賞。坂本龍一氏との対談集や荒井良二氏との絵本『どーしたどーした』も。182㌢、68㌔、A型。
あれは自分かもと考える繊細さを失えば
つらい時に思いをかけられる機会も失う
『永遠の仔』、『包帯クラブ』、『悼む人』等々、天童荒太作品は「媒体」を思わせる。
単に部数や映像化の問題ではない。小説そのものが同じ境遇や傷を持つ人々の社会的受け皿と化し、作家自身、刊行後もその痛みと向き合ってきた。「なぜそこまで……」と思うほどに。
そんな天童氏が、東日本大震災から約5年が経つ今、『ムーンナイト・ダイバー』を上梓したことは、どこか得心がゆく出来事ではある。主人公〈瀬奈舟作〉が潜るのは、〈あれ〉から5年目の東北の海。彼や地元の漁師〈文平〉が〈光のエリア〉と呼ぶ、福島第一原発らしき建物が見える沖に、満月や立待月の月夜を選んで漕ぎ出し、海底に沈む誰かの宝物を誰かのために探す。それは舟作と文平、発案者の〈珠井〉と会員だけが知る秘密の仕事だった。
〈なぜ潜る〉〈禁を侵せば、罰せられるかもしれないのに〉〈だからこそ潜るのだ。誰も潜らないから、誰かが潜らなければいけない〉
*
本書では舟作が潜る海も、さらに北にある故郷の港町も、あえて特定されない。
「理由は2つあって、地名を特定して住民の方が傷つくのは避けたかったこと。今1つは生存者の罪悪感は、サバイバーズギルトの問題にしろ、被災地に限らない普遍的な問題だからです」
当初は震災を小説に書くつもりはなかったという。
「僕は小説家を常々不遜な存在だと思ってますから。
ただ我々は震災直後こそ、経済効率を優先した社会の在り方を見つめ直し、人と人が繋がる契機ともした。しかし1年も経たずにそうした意識は失われ、むしろ以前にも増した他者排斥の競争格差社会に進んでいる気がしてならないんですね。
そんな風潮を見るにつけ、これこそがモラルなき競争や偽装に人々を駆り立てる見えない震災被害だと思うに至った。つまり、時と共に忘れられていく被災地の姿や、忘れようとする自分自身に、『つらい立場にある人間は結局、忘れられる』と強迫観念を覚えた結果、目先の損得や自分を守ることに躍起になる社会の象徴として、あの大震災を捉え直そうと思ったんです」
目に見えないものを形にできるのが小説の強みだとも氏は言う。地上の目に見える復興ではなく、海に沈んだ人々の生活の痕跡を月夜に探す舟作の造形もそこから着想され、まずは自身、ダイビングを習い始めた。
「以前、『悼む人』を書いた時に自分でも各地を悼んで歩いてみて、その人を知れば知るほど早くは歩けなくなる感じとか、皮膚感覚の大事さを痛感したので」
幼い頃、舟作は兄〈大亮〉や友達と〈化石〉を探して遊んだ。今から4億年前のサンゴの化石が付近の山で出土したと聞いて宝探しに行くのだが、舟作は昔から山と海の匂いを嗅ぎ分けるのがうまかった。しかしなぜ海の化石が山にあるのだろうか。
〈大昔ここは海で、地震で山になったんだ、だったらまた海にもどることもあるのかな、と誰かが口にした〉〈自分たちが生きているあいだにそれが起きるとは思っていなかった〉―。
見ることと耳を
澄ますことが愛
5年前のあの日、大亮と両親は港で津波に呑まれ、腰を痛めて家にいた舟作は生き延びた。妻〈満恵〉や子供たちも無事だったが、彼は自分を責め、漁師をやめて親友が営む東京隣県のダイビング店で働き始める。その町でアパートを借り、満恵もパートで働きながら、自宅のローンを返す日々。そんな時、父の旧友の文平から珠井を紹介されたのだ。
〈行政側の限界が理解できる〉と言う公務員の珠井は、今も行方不明の妻と娘の死亡届を出し、当初はその保険金を原資に自宅のある帰還困難区域に海から入ることを考えたらしい。
現在会員は12名。1度潜る度に舟作と文平に各50万円が支払われる約束だ。ただし捕まっても会は関知せず、会員との直接交渉も禁じられている。しかし、その規則を破った女がいた。夫が帰省中に消息を絶った東京在住の宝飾デザイナー〈眞部透子〉だ。帰りに待ち伏せされ、〈夫がしていた指輪を、探さないでほしい〉と頼まれた舟作は、何より彼女に欲情していた。兄を身代わりに失って以来戻らなかった〈性の感覚〉が、〈あの海に潜って、変わった〉。
「彼が無性に肉が食いたくなったり透子に性的刺激を覚えるのも、死と向き合うことで生存本能が亢進されるから。2人がただ話しているビジネスホテルの一室に漂うエロティックで濃密で剥き出しな空気は、書き甲斐がありました。
最近は10代の胸キュンか、不倫の愛かというくらいに恋愛表現が幼く窮屈になっていて、性は性で別売りされているからか、愛のあるセックスなんて言うと逆にいやらしく聞こえる。でも本当は結婚したり歳を取ってから性的に成熟する方が重要で、透子がこのまま独りで生きるのか、〈まだ子供も産めるのに〉と迷う感じなんて、もっと正直に語られていいはずなんです」
死者の時間は止まるが、生者の時間はなおも続く。まして帰らない人の帰りを待つ間にも時は刻々と進み、そのズレは哀しく、残酷だ。愛する者の死を受け入れるのはそれほど簡単ではなく、頭ではわかることと身体が拒むことの狭間で葛藤する舟作に、天童氏はこう言わせている。〈なぜあれが起きた? どうしておれが残った?〉〈あっちやそっちの人に、どうしてその心が伝わらない? どうしてこんな不公平なことが起きていながら、人間はそれを我慢して、こらえて、生きていかなきゃならない?〉
「これは僕自身の問いでもあります。例えばシリアで起きていることに関して、あれは自分かもしれないと考える繊細さが今は失われ、それはつまり自分がつらい時に思いをかけられる機会をも失うことなんですね。
例えばテレビに映る元気な被災者の見えない痛みに心を馳せ、本人が折り合いをつけられるまで待つのが大人のわきまえで、見ることと耳を澄ますことが愛なんです。見て、聞いて、『どうかした?』と声をかけられれば実は十分で、その『どうした?』が出なくなった今、いきなりシリアは無理でも身近な友人や同僚や家族に声をかけることが、第一歩だと僕は思います」
喪失感や罪悪感に苦しむ彼らは愛が豊かだから自分を責めるのであって、人はその愛を大切に抱えて生きてもいけるのだと氏は言う。単に忘れるのとも諦めるのとも違うその再生の過程を描く本書は、なるほど震災小説ではないのかもしれない。
□●構成/橋本紀子
●撮影/国府田利光
(週刊ポスト2016年3・4号より)
初出:P+D MAGAZINE(2016/02/28)

