ミステリーを始めよう! 入門編・きほんの「き」

ジャンルも書き手も膨大なミステリー小説の世界。興味はあるけれど、どれから手をつけていいか わからない……。そんなあなたに、「ミステリー」の代表的な 5つのジャンル「探偵」、「密室」、「倒叙ミステリ」、「日常の謎」、「あやかし」から、入門編としてオススメの5冊を紹介します。実力派の気鋭作家たちによる、サービス精神たっぷりの極上ミステリーで、謎解きの快感を味わってみて下さい。
1.ハードボイルドな雰囲気あふれる探偵小説系:若竹七海「葉村晶シリーズ」
ユーモラスな中に、 ドキリとするような人間の「闇」を潜ませ、得も言われぬ読後感を残す若竹七海作品。 ジャンルは多岐にわたり、多くのファンを獲得している作品の中で、とりわけ 熱い視線を注がれるキャラクターが探偵・
わたしは葉村晶という。国籍日本、性別女、三十七歳。(中略)俗にいう探偵。あらゆる意味で独り身である。(中略)誰ともつながっていないし、ペットも飼ってない。自由といえばこのうえなく自由であり、無味乾燥な人生と言われればそのとおりだ。
(暗い越流)
アラフォー・独身の女探偵、葉村晶。1996年刊行の初登場作『プレゼント』 ではまだ20代だったことから、作者の若竹氏も「これほど長く葉村晶シリーズを書き続けられるとは思わなかった」と、シリーズ最新作『錆びた滑車』刊行記念のインタビューでコメントしています 。
作品点数は決して多くなく、どちらかというとやや「通好み」の作品群だともいえます。
それが、2016年の「アメトーーク!」の「読書芸人」企画で メイプル超合金のカズレーザーが『静かな炎天』を「今読んでもらいたい本」として挙げ、「読書芸人大賞 」を受賞したことで大きな話題となり、突如、書店で平積みとなった葉村シリーズに従来からのファンの方が驚いた、というエピソードも。
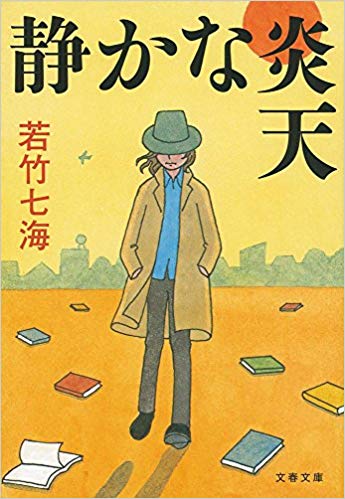
https://www.amazon.co.jp/dp/4167906740
現在、あまたの人気ミステリー小説の中で、主人公の本職 が探偵であることは逆に珍しいかもしれません。
多くは警察がその役目を果たしていたり、「日常に潜む謎系」 では全く別の職業につく主人公が卓越した推理力によって探偵役を務めます。
そんな中にあって葉村晶は、正真正銘の探偵です。世話になった事務所が解散となった後も、つてのある大手事務所の嘱託となったり、ついには自身の個人探偵事務所を立ち上げるまでになり、一貫して「探偵」という職業にこだわっています。
葉村の生き方・考え方は徹底してハードボイルド。そんな彼女が探偵として活躍する本シリーズの魅力を、カズレーザーも推した連作短編集『静かな炎天』から考察していきましょう。
・とにかく不運な探偵、葉村晶
探偵・葉村晶を表す言葉として、頻繁に使われるのが“不運”というキーワードです。望むと望まないとに関わらず、かなりの頻度で事件に巻き込まれてしまうのが彼女の特徴です。『静かな炎天』に収録されている作品を例に取ると、通勤途中に交通事故&バス炎上に遭遇し(『青い影』)、昔の同僚の人質事件に巻き込まれ(『副島さんは言っている』)、身勝手な上司のせいで面倒な「おつかい」を押しつけられ、クリスマスの東京を縦断するはめに……。(『聖夜プラス1』)と、不運話は枚挙にいとまがありません。
時には悪態をつきながら、それでも頼まれれば決して無下にできず、有象無象のトラブルメーカーからの依頼を引き受けてしまう葉村晶。そして、ひとたび“事件のにおい”に気づいた途端、職業意識がむくむくと頭をもたげ、自ら、事件の渦中へと飛び込んでいきます。その瞬間、彼女にとって、気の進まなかった頼まれごとではなく、自ら選び取った選択となるのです。それからの彼女は、決して誰かのせいにすることはありません。依頼人がもういい、というのを振り切って、真相のために一人で調査を続行してしまうこともしばしば。世にひそむ悪意や不穏さに気づいたが最後、なかったことには出来ずに、ひたむきに真実を求めてしまう彼女のスタイルは、まさにハードボイルドな探偵そのものです。
・探偵としての、清々しいまでにストイックな生き方
葉村晶の生活は、およそ女性らしさとは無縁です。衣・食・住、どれもシンプルで、最低限の生活が確保できれば御の字。異性との関わりも求めない。しかし彼女は、人生のどんな場面においても、自分が決定権を持ち、選択することを求めます。探偵という仕事を通し、人間心理に精通してゆくことで、彼女のドライさ、皮肉屋ぶりは際だっていきます。けれどそこには、苦しむ人を 放っておけない優しさ も感じられます。本当に無味乾燥な人生を送りたければ、生身の人間と関わらない道だっていくらでもあるはずです。それでも探偵として、ひとの思い、罪というものにふれずにはいられない。それは誰にでもできる仕事ではなく、徹底したストイックさがなければ立ち向かえない現実です。
どんなに大変でも、やはりわたしには探偵仕事が天職なんだろうと思う。
(静かな炎天)
打算やかけひき、ないものねだり。息苦しい 現実にもがく心の底で、いっそ誰にもよりかからず、自分ひとりを頼みに生きて行けたらどんなに良いだろうか――そんな思いを誰もが抱えているのかもしれません。本書に登場する大小様々な謎の最後にあらわれる、恐ろしいまでの人間の心の「闇」に、彼女自身も傷つき、やるせない思いを 抱えます。それでも、誰かが引き受けなければならない仕事を、「天職」としてまっとうする芯の強さと甘えのなさ。当の本人は、他人から認めてもらうことなど露ほども期待していません。本書を手に取れば、探偵・葉村晶のストイックな生き方に惹かれ、煩雑で鬱屈した日常をしばし忘れる謎解きの快感がやみつきになってしまうこと間違いなしです。
2.密室殺人系:倉知淳『星降り山荘の殺人』
「密室殺人」は、ミステリー小説には欠かせない人気要素のひとつです。「第1回本格ミステリ大賞(小説部門)」を受賞した実力派の人気作家・倉知淳にも、多くの密室殺人を扱った作品が存在します。 中でも『星降り山荘の殺人』は、刊行から20年が経過した今も、密室ものの決定版としてミステリフェアなどに選書されるなど、人気の衰えない作品です。 「本格」ミステリーにはファン、作家の間でいくつかの“評価ポイント”があるそうで、本作のあとがきで貫井徳郎が言及しているように「フェアであるかどうか」もそのひとつ。 作中の人物だけが知っている情報が事件解決のカギだったりすると、読者には本当の「謎解き」は無理となってしまいます。本格ミステリーにおけるフェアさとは、すべての情報が読者にもあらかじめ開示されている状態であり、読者自身が謎解きに挑戦できる設定であるということです。この本は「作者のフェア精神」が高らかに謳われており、同業のミステリ作家達からも評価が高い作品といわれています。
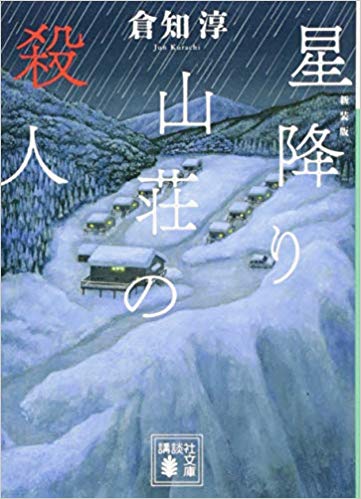
https://www.amazon.co.jp/dp/4062937018
和夫は早速新しい仕事に出かける
そこで本編の探偵役が登場する
探偵役が事件に介入するのはむろん偶然であり
事件の犯人では有り得ない論証は終盤を迎え
提示された条件に基づいて
いよいよ星園による犯人の限定が始まる
作中には随時、このような「作者からのメッセージ」が差し挟まれ、状況を俯瞰するとともに丁寧なヒントが示されます。こうして、主人公と同じ視点で謎解きに挑み、絶対にだまされないぞ―― と興奮しつつ高をくくっていても、ラストにはほぼ全ての読者が驚愕し、「そうだったのか……!」と、あわててページをめくって見直してしまうはずです。 予想に反した展開への敗北感 には、心地よささえ感じるでしょう。登場人物も皆魅力的で、物語としての重厚性がありながら飽きさせないユーモアがちりばめられており時代を経ても変わらない普遍性が入門編としてぴったりの作品です。クライマックスでは、ひょいとハシゴを掛け替えるような意表をつく驚きが待っています。生粋のエンターテイナーであるともいえる倉知淳の作品の魅力に、本作をきっかけにはまってしまうこと請け合いです。
3.倒叙ミステリ系:大倉崇裕「福家警部補シリーズ」
“倒叙ミステリ”とは、冒頭に犯行シーンが登場し、あらかじめ犯人が分かっている状態から始まる作品を指します。『刑事コロンボ』や『古畑任三郎』も倒叙ミステリの代表作です。作家の大倉崇裕は、『刑事コロンボ』の大ファンであることを公表していて、『刑事コロンボ』に関する同人誌も発行しているほど。彼の生み出した キャラクター「福家警部補」は、初対面の人からは 決まって警察の人間だと信じてもらえない、小柄で童顔、おっちょこちょいの女性。どこか風変わりで心許なく相手を油断させてしまう――そんな「倒叙ものの主人公」の系譜を踏襲しながら、シリーズを追うごとに増していく彼女の魅力、凄惨な殺人が行われながらもどこか愛を感じさせるストーリー展開が、独自の世界を紡ぎ出しています。

https://www.amazon.co.jp/dp/4488470025
「福家君、一つきいてもいいかな」
「何でしょう?」
「私の思いこみかもしれないが、君は最初から私を疑っていたようだった。そう……まるで私が妻を殺したことを知っていたかのように。君はいつ気づいたのかね?」
「五年前、シンポジウムで初めてお会いしたときです」
「何だって?」
「私が壇上にいるとき、会場に失踪者である女性が入ってきました。でも、あなたは前を向いたままでした。その後、女性の顔を確認に行こうともしなかった。そのとき確信したんです。あなたは、妻が帰ってくる可能性のないことを知っている」
柳田は目を閉じ、天を仰いだ。両足がかすかに震えている。
「そうか、あのときに……」
(福家警部補の挨拶)
登場する犯人たちは、どこかエリート的な匂いがします。実際に有能であり、そんな自分に自信を持っており、だからこそ「完全犯罪」に手を染めてしまうのです。本シリーズの犯人たちは、見た目や行動が「いかにも悪」、という人間ではありません。むしろ、世間からは高潔な人物だと思われていることが多いのです。そんな彼らだからこそ、世に蔓延する不公平さや倫理の欠如が許せず犯行に及んでしまいます。しかし福家は決して追撃の手を緩めず、彼らを断罪していきます。
どんな理由があったとしても、人が個人的な理由で人を裁けはしない。傲慢になった時点で罪である――警察官としての彼女は、冷徹にそう訴えます。
そんな彼女も、犯人逮捕の現場に際し、理性では割り切ることのできない、胸の内の苦しさを漏らすことがあります。ほんのささいな針の揺れで、進路を誤ってしまった犯人たち。人間として、彼らの犯した選択を彼ら以上に悔やむといった福家の描写が、善と悪だけでは割り切れないヒロインの魅力を際立たせ、このシリーズに深みを与えています。記念すべき第1作目、『福家警部補の挨拶』では、テンポのよい謎解きとともに、人間の闇やその先の希望といった深遠なものに思いを馳せさせてくれるでしょう。
4.日常に潜む謎系:北村薫『中野のお父さん』
主人公は出版社で文芸編集を担当する、20代の田川美希。体育会系の彼女は明るく前向きで、たまに落ち込みつつも、編集という仕事に深い愛着を持っています。彼女の日常に起こる、「謎」と呼ぶにはあまりにもささやかな出来事たち。それを、定年が近い高校の国語教師である父親が、実家に顔を出した娘とのほほえましい会話の中で鮮やかに解き明かしていきます。
今では多数ある「日常に潜む謎」系ミステリーですが、北村薫は『円紫さんと私』シリーズ、『覆面作家』シリーズなどで、このジャンルの先駆けともいえる存在です。新シリーズである本作はよりユーモラスに、同時代的に、謎解きを通して主人公をはじめとする登場人物たちの魅力と、人の世にあふれる優しさを描きます。
新人賞を取った作家の担当ができることになり、はやる心を抑えられずに受賞の電話をかけたら「私は応募していません」――等、いきなりの「つかみ」が秀逸な謎を、丁寧な描写でじらしながら次第に物語に引き込んでいきます。「謎」が解ければ、なんだ、そんなことか、と思わず脱力しそうな些末さの中に、思いも寄らなかった深い思いがあるのです 。

https://www.amazon.co.jp/dp/4163903259
「あの、おかしなこと、いい出すとお思いでしょうけど――わたしには、父がいるんです。
定年間際のお腹の出たおじさんで、家にいるのを見ると、そりゃあもう、パンダみたいにごろごろしている、ただの《オヤジ》なんですけど(中略)謎をレンジに入れてボタンを押したら、たちまち答えが出たみたいで、本当にびっくりしたんです。
お願いです。このこと――父にだけ、話してみてもいいでしょうか」
娘の一挙手一投足におろおろすることもある、ごくごくふつうの「お父さん」が、千里眼もかくやという洞察力で気負いなく謎解きしてしまう爽快さ。ストーリーを追うごとに見えてくる、家族の絆。ふとしたエピソードや情景によせて、言葉にはならない絆や思いの美しさを描き出していきます。
サッシ窓の向こうは、黒い紙を貼ったように暗くなっていた。そのとき、門の方で車の音がした。
「お母さんが帰ってきたぞ」
父は顔を上げ、嬉しそうにいった。
「――ミコと三人で、新しい年が迎えられる。まあ、お父さんには、これが何よりのプレゼントだな」
探偵役はあくまで父親で、アラサーの主人公・美希については等身大の悩みが瑞々しく描かれることで、ミステリーに疎い人にも共感する要素がたっぷりです。仲良し親子の会話にクスリと笑ったり応援したくなったりするうちに、北村薫作品特有の爽やかな読後感にひたり、続刊が待ちきれなくなることでしょう。
5.怪奇あやかし系:青柳碧人 『朧月市役所 妖怪課 河童コロッケ』
作者はライトミステリー・青春ミステリーの名手です。数多い人気作の中から、現代ファンタジーである「朧月市役所妖怪課シリーズ」第1作目、『河童コロッケ』をご紹介します。
「あやかしもの」ジャンルの人気はとどまるところを知らず、数々の出版社からひきもきらず刊行されている現在。本書の魅力は、緻密な取材に基づいて、妖怪の伝説や生態がとても生き生きと描かれているところです。日常×妖怪という、消化不良のファンタジーに陥ってしまいがちな題材が、本に“妖怪を封じ込めた”市町村・

https://www.amazon.co.jp/dp/4041012759
宵原秀也は、公務員という仕事に対して夢を抱く、真面目で気骨ある青年。念願叶って自治体アシスタントとして採用されますが、配属先はなんと、妖怪と共存する政府公認の秘密の町・朧月市の「妖怪課」!?
想像もしなかった妖怪達の存在を知り、自らと同僚達の特異な能力に戸惑い悩みながらも、秀也は、どちらかといえば惰性におちいりやすい役所という職場の“体質”に、若さも手伝っての直情と熱意で立ち向かっていきます。今は亡き父の遺した「公務員とは、住民に率先して夢を見る仕事だ」という言葉を大切に思い、仕事に真摯に立ち向かおうとする彼の姿勢は、物語の冒頭の、ある市民とのこんなやりとりにも表れています。
「どうも」
挨拶をすると、彼女は皺くちゃの笑顔のまま近づいてきた。
「お兄さん、こんな田舎に越してきたのかい?」
「ええ」
(中略)
「アメ、食べなさいね」
(中略)
老婆は秀也の手を取ると、無理やりその飴玉を握らせた。
「あ、ああ、ありがとうございます」
戸惑いながらも飴玉を受け取る。住民との初のふれあいだ。
公務員としての一歩を快く踏み出せた気がして、どこか気恥ずかしくも、嬉しくもあった。
(朧月市役所妖怪課 河童コロッケ)
そんな秀也の熱意が、役所の体質を、そして妖怪達との関係までをも変えていく展開は爽快です 。また、当初は妖怪たちの存在に右往左往していた新人の秀也が、しだいに彼らとの関わりを深め、不思議な絆を育てていく過程が丁寧に描かれているところも魅力。人間と妖怪との「友情」ともいえる絆やエピソードの紹介が、作品に不思議なリアリティを与えています。
秀也には他の妖怪を呼び寄せてしまう不思議な力があり、「長屋歪」という家の間取りを勝手に自由自在に変えてしまう妖怪がアパートに住み着いてしまいます。最初は邪険に扱っていた秀也ですが、しだいに彼に妖怪の扱いについて尋ねたり、情報共有をするようになり、いつのまにか友人のように身の上話や悩み相談までする関係になります。秀也の生来の素直な性格がもたらす、妖怪を含めた仲間との触れあいやその中での秀也自身の成長も、読みどころのひとつです。
「われわれ妖怪からするとね、(中略)人間の世界ってのは、窮屈なものなんですよ」
長屋歪 はまた笑った。
「ちらっと見させていただいた公務員ってのは、周りに住んでいる見ず知らずの他人のために一生懸命働くっていう仕事なんでしょう?それだけですでに大変なのに、『住民に率先して夢を見る仕事』だなんてもう……妖怪の立場から言わせてもらえば、面倒くさいの一言に尽きますよ」
(朧月市役所妖怪課 河童コロッケ)
妖怪退治というファンタジー要素が「公務」であるがゆえに、住人たちと一定の線引きをしなくてはならないもどかしさや、組織での煩雑な手続きなど、「役所あるある」ともいえる現実とファンタジー要素が組み合わさる面白さに膝を打ち、気づけばページをめくる手がとまりません。主人公の奥手な恋の行方にも注目。いわゆる「怪奇あやかし」系が苦手な人も、個性的な妖怪達の特性を活かした謎解きの面白さや、秀也と周囲の仲間達が仕事を通して成長してゆく姿に、気づけばのめり込んでしまうでしょう。
おわりに
ミステリーとひと口にいっても、そこに描かれているのは謎解きばかりではありません。むしろ事件、謎、解決といった分かりやすい切り口を通して、人間の心の機微や成長を描いているからこそ、老若男女を問わず多くの読者に求められているのがミステリー小説だと言えるでしょう。紹介した5つの作品はどれも、純粋なエンタテイメント小説としても読み応えたっぷり。ぜひ、謎解きやキャラクターの魅力に唸りつつ、作者が繊細にちりばめた伏線を楽しみながらご一読ください。きっと手元に置いて何度も再読したくなる、お気に入りの1冊になることでしょう。
初出:P+D MAGAZINE(2019/03/06)

