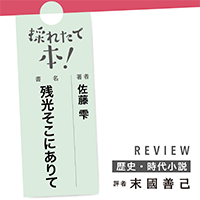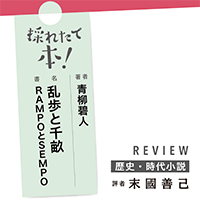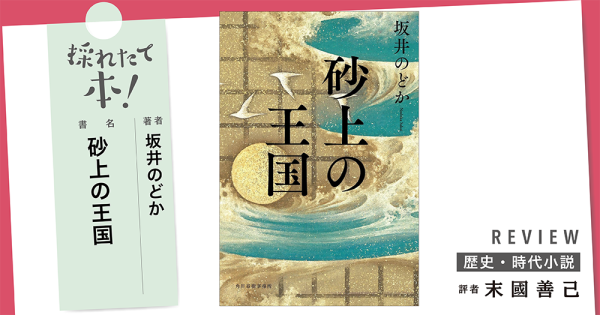採れたて本!【歴史・時代小説#36】

井上靖、司馬遼太郎、陳舜臣ら西域に魅せられた作家は少なくない。高昌国の興亡を追った『砂上の王国』で第17回角川春樹小説賞を受賞した坂井のどかも、この系譜に連なる作家といえる。
7世紀。シルクロードの交易で栄える高昌国は西突厥と結び、旧道を復活させて高昌国を通らなくても唐へ行けるルートを作ろうとした焉耆国を攻める。諸国との共存を重んじる太子の麴智盛と軍事の才能に秀でた異母弟の麴史含は、交渉で和睦に持ち込むが、待機しているはずの西突厥の援軍が来襲する。高昌国が援軍を頼んだのはイルビ・テュルクだったが、やってきたのはなぜかイルク・イシュバラ・ヤブク(アシナ・ボグド)だった。麴兄弟と勢力を拡大していくボグドの因縁は、物語を牽引する鍵になる。
高昌国の王・麴文泰は漢人で、遊牧民が作った唐よりも漢人が治める高昌国の方が偉大だと考え、伊吾国を唐の支配から解放するとして攻撃した。怒った唐が高昌国を攻めると考える智盛だが、唐を侮っている文泰は防備を固めようとしない。智盛は、史含、口は悪いが頭脳明晰な同母の末弟・麴智湛と力を合わせ、密かに唐の攻撃に対抗する準備を進める。
政治的にも軍事的にも大国の唐と、平然と略奪を行い援軍を頼めば多額な報酬も必要なので危険でもある軍事大国の西突厥に挟まれている高昌国は、やはり超大国に囲まれている現代の日本に近い。先の大戦を仕掛けた日本と同じく自衛を名目に伊吾国を攻め高昌国が孤立した現状を分析した智盛は、自国の利益を追求するのではなく周辺諸国が共に生きる道を模索すべきだと考える。これは自国第一主義を掲げる国が増えている現代社会への批判であり、今後の日本が平和のうちに繁栄するためにはどのような道を選択すべきかを突き付けてきているように思えた。
唐が大軍を派遣したとの情報を摑んだ三兄弟は、高昌城を放棄し狭く防御に向いた交河城に1万の兵で籠城し、西突厥の援軍が来るまで持ちこたえようとする。約10倍の唐軍との戦いが前半のクライマックスで、攻城戦のスペクタクルにも、史含と敵将との一騎打にも圧倒的な迫力があり引き込まれてしまうだろう。
智盛は、漢人の父とソグド人の母を持つ史含こそ、多くの民族が往来する西域を象徴すると考えていたが、唐との戦いの後に誤解から決別してしまう。様々な民族が暮らし、交易網によって人、物、情報、文化が流通し相互に影響を与え合っていた当時の西域は、グローバル社会だったといえる。その中にあった高昌国で生まれ育った智盛が、国家とは何か、国民とは何か、多文化共生とは何かを考えていく後半は、現代人も答えを見つけなければならないような問い掛けになっていた。
評者=末國善己