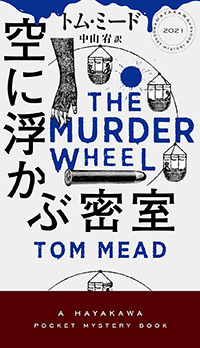採れたて本!【海外ミステリ#36】
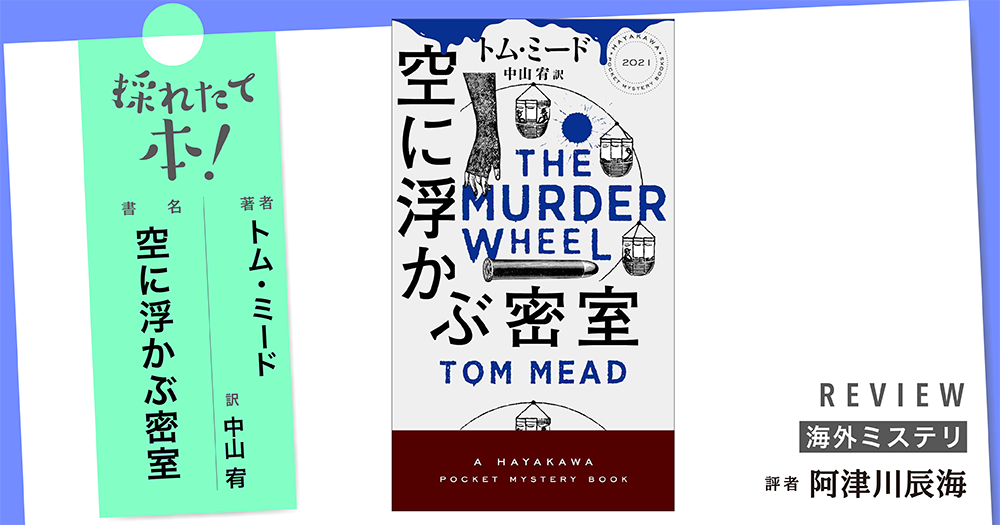
あなたの好きなものと同じものが私も好きだ。だからどんどん書いてほしい。ただただそう思わされて、鼓舞したくなる作品というものがある。イギリスの推理作家、トム・ミードの『空に浮かぶ密室』はまさにそんな作品だ。
著者の長編が邦訳紹介されるのは二作目である(短編はミステリマガジン二〇二三年十一月号に「インディアン・ロープ・トリックの謎」が紹介されている)。一作目は『死と奇術師』という作品で、巻末が袋綴じになっている。六十数年ぶりに早川書房から袋綴じのミステリーが刊行されたということで話題となった(前例はビル・S・バリンジャー『消された時間』)。名探偵を買って出るのは、奇術師、ジョセフ・スぺクター。一九三〇年代が舞台であり、密室殺人が起き、さらに「幕間 読者よ、心されたし」において読者への挑戦を投げかける……などなど、英米黄金時代の本格ミステリーを思わせる要素がてんこ盛りだった。
さて、二作目『空に浮かぶ密室』もまた、奇術師ジョセフ・スペクターものであり、読者への挑戦を試みている(二作ともに「亡き巨匠」に捧げられている、という共通点もある。一作目の献辞では、ジョン・ディクスン・カーと明記されていた)。魅力的なタイトルは、観覧車のゴンドラを指しているとひとまず言っていいだろう。
舞台は一九三八年のロンドン。銀行支配人のドミニク・ディーンが観覧車のゴンドラ内で射殺され、同席していた妻のカーラが疑われる──これが「第一の密室」だ。
続く第二幕では、奇術ショーの舞台上で事件が起こる。演目の最中に箱の中から死体が忽然と現れ、その被害者は例の観覧車事件と密接なかかわりを持っていた。密室、また密室の大盤振る舞いである。
前作に引き続き、どこに伏線があったのか謎解きの要所要所でページ数を示す手掛かり索引の趣向も健在であり、もちろんトリックや道具立ても好ましい。『幻術の奥義書』という奇術本をめぐる趣向や、ステージマジックの演出の部分に、黄金時代の作家の中でもとりわけクレイトン・ロースンの影響を強く感じる。特に舞台上の殺人の謎解きは入魂の出来栄えだ。登場人物たちの行動の意味が少しずつ浮かび上がっていく謎解きがスリリングである。
だがそれ以上に、今回は語り手である若い弁護士、エドムンド・イブズの魅力にやられた。いわば巻き込まれる形で事件の渦中に吞み込まれていく彼の等身大の語りが読者を牽引している。おまけに事件のウラには犯罪組織が見え隠れし、そいつらとの追いつ追われつがあり、アクションシーンまで完備している。前作よりもエンタメ要素の強い語りなのだ。密室トリックや謎解きの捌き方よりも、むしろ、この生粋のストーリーテラーっぷりに、ジョン・ディクスン・カーへの憧れを嗅ぎ取ってしまうのである。面白さのためにどんなものでも盛り込んでしまう、エンターテイナーとしてのカー。
私もカーのそういうところが好きだった。だから、トム・ミードにはいつまでも溌溂と書いて欲しい。そんな風に顔がほころぶような本格ミステリーなのである。
評者=阿津川辰海