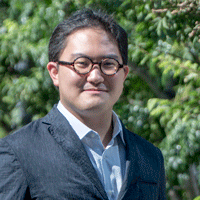「推してけ! 推してけ!」第45回 ◆『帝国妖人伝』(伊吹亜門・著)

評者=千街晶之
(ミステリ評論家)
〝探偵役〟を推理する歴史ミステリ
「次はどんな謎解きを楽しませてくれるか」だけではなく「次はどんな個性的な探偵役を登場させるか」という期待を読者に抱かせる作家、それが伊吹亜門だ。デビュー作にして第十九回本格ミステリ大賞を受賞した『刀と傘』は、幕末~明治の京都を舞台に、実在の佐賀藩士で明治政府の初代司法卿となる江藤新平と、架空の尾張藩士・鹿野師光が怪事件を解明してゆく連作だが、両者の関係は通常の名探偵とワトソン役に収まらない、一筋縄ではいかないものである。戦前の満洲が舞台の『幻月と探偵』の主人公・月寒三四郎は比較的オーソドックスな私立探偵だが、大正時代が舞台の『焔と雪 京都探偵物語』の元警官の探偵・鯉城と伯爵家の庶子・露木の関係には、連作を通しての大きな秘密が隠されている。著者にとって、長篇よりも連作短篇集という舞台でこそ、常道から逸脱した探偵役を活躍させやすいのかも知れない。
さて、新刊の『帝国妖人伝』は、歴史ミステリを得意としてきた著者の作品中、最も扱われている時期が長い。明治から昭和前期に至るこの連作の語り手は、尾崎紅葉に師事した探偵小説家の那珂川二坊。日露戦争前夜の東京を舞台にした第一話「長くなだらかな坂」では、当時「万朝報」の記者だった彼が馴染みの一膳飯屋で、居合わせた清吉という青年から、前の夜に起きた事件の顛末を聞くことになる。生き別れの母が徳川公爵家の使用人になっていると聞いた清吉は、故郷から上京して公爵邸を訪れるが、あいにく母は留守だった。その後、公爵邸の塀から侵入しようとしていた賊を見かけた清吉は、相手と諍いになったが、その際、賊は梯子から転落したのが原因で死んでしまった……というのだ。ところが、店に居合わせた男が「いやァ、そりゃ違いますやろ」と口を挟んできた。書家だというその男――福田房次郎は、事件の真相を推理しはじめるのだった。
こう内容を紹介すると、連作を通して那珂川がワトソン役、房次郎が名探偵の役割を務めるのかと予想するかも知れない。ところが、房次郎の出番は第一話で終わりであり、第二話「法螺吹峠の殺人」では、他殺死体の第一発見者となり危うく犯人に仕立て上げられそうになった那珂川を、別の人物が救うのである。このパターンは、第三話、第四話……と続いてゆく。
つまり本書は、ワトソン役だけが一緒で、一話ごとに名探偵だけが交代するという異色の連作なのだ。しかし、連作としての本書を貫く趣向はそれだけではない。
既に記したように第一話の探偵役は書家の福田房次郎だが、実はこの人物は別の名前で後世に知られている。第二話に登場する雲水も然り、第三話「攻撃!」に登場する「大尉」もまた然り。本書の五つのエピソードで活躍する探偵役は、いずれも歴史上実在の有名人なのだ。彼らの名前は各話のラストで明かされるが、読者はそこに至るまでに、事件の真相にとどまらず、探偵役が誰なのかを推理するという楽しみも味わうわけである。
那珂川は歳を重ねても売れっ子作家になれず、細々と物書き稼業を続けている。そんな彼は太平洋戦争の時期に入っても、お国の勝利に貢献するという考え方を捨てることはないが(といっても格別に国粋主義的というほどではなく、愛国心は恐らく当時の日本人の平均程度だと思われる)、第四話「春帆飯店事件」で描かれた事件で大きな衝撃を受ける。そして、第五話「列外へ」で絶望に打ちひしがれた那珂川が巡りあうことになる実在の人物の選択が絶妙で、このエピソードに相応しいのは彼しかないと思わせる(意外にも、この人物が歴史ミステリに登場した前例はないのではないか。他の四人と異なり、亡くなったのが今世紀で記憶がまだ生々しい人物だからかも知れない)。
一人の作家の挫折と再生の物語に明治以降の日本の歩みを重ね合わせた本書は、著者の本領発揮作と呼ぶに相応しい完成度を示している。
千街晶之(せんがい・あきゆき)
ミステリ評論家。日本推理作家協会会員。多数の推理小説に巻末解説を寄せている。主な著書に『怪奇幻想ミステリ150選』『水面の星座 水底の宝石』『幻視者のリアル』、共著に『21世紀本格ミステリ映像大全』がある。