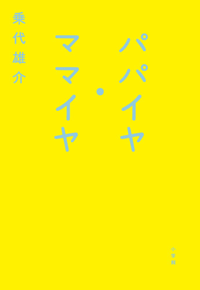- ホーム
- 特集
- STORY BOX 特別企画
- 『パパイヤ・ ママイヤ』刊行記念SPECIALレビュー
『パパイヤ・ ママイヤ』刊行記念SPECIALレビュー

息が詰まるような美しさと悲しみ
生きているといろんなことを見聞きし、その都度、いろんなことを感じ、また思うものであるが、そしてそれは嬉しかったり悲しかったりするが、人間というのは因果なもので、その際、これを自分の胸の内、腹の内に留めて自分だけのものとすることができず、これを他に露呈して、他と分かち合いたくなる。
その際、分かち合うための見えない通路のようなものが各人の間に通っており、その通路には細いものがあり、太いものがあり、また、長いものがあり、短いものがある。これらに自在にアクセスし、思いや感じの内容に応じて使い分けることができる、或いはもっと言うと、その見えない通路の長さや幅に合わせて、思うことや感じることを、うまく梱包したり、サイズを調節したりすることができる者が、謂うところの「大人」である。
その際、思いを届け合うことは既にして盆暮れの贈答のようになっていて、やり取りすることにこそ意味があるのである。
じゃあ子供はどうなのかというと、子供の場合、そうしたことができないのは、感受性が発達の途上にあるため、思うことや感じることがなになのか見極めが付かぬまま、それを恥ずかしいと感じる、それを言うと自分は破滅すると信じるなどするのと、それに加えて、通路が家族や同級生に限られて、太いけど短かったり、数は多いが細かったりするためである。
しかしその分、見聞きする範囲も限られているので、うまくバランスして、次第に大人に移行していく。
ところがいろんな条件が重なり、その通路がない、という状態の子供もいることが考えられる。そうなると、最初に言うように、人間は本来的にそれ、というのは、さまざまの思いが身の内に溢れたままにしておくこと、ができないから実に苦しい状態となる。これを別の言い方で言うと、孤絶した状態、ということができる。
この小説に登場する、二人の十七歳の少女は、まさにそのように孤絶したふたつの魂である。おかれた状況や環境が大きく異なり、それぞれの「パパイヤ」「ママイヤ」というハンドルネーム(ふたりはSNSを通じて知り合ったようである)が示すとおり、対極にある部分が少なくないふたりは、お互いを傷つけないように配慮しながらも、ときには衝突も恐れずに、二人の間の通路を掘削していく。
それは恰も、貝やヒトデ、イソギンチャクといった海辺の生き物が触手を伸ばすようでもある。
海辺と言えば、この小説の主な場所、ふたつの孤絶した魂が出会う海辺の場所はきわめて象徴的である。
そこは人の来ない孤絶した場所であり、自然と人工物があい混じる世界である。そこへ至る道は笹や葦に覆われ、混凝土の廃墟が草に埋もれている。動きのない海面には多くのゴミと死骸の如き流木が寄り、対岸には遠く工場群が霞んでいる。
親や学校という通路を断たれ、行き場をなくした思いを抱えた者が、まるでゴミが寄るようにこの海辺に寄るのである。
しかし、そこは干潟でもある。死滅して腐敗したような景色の裏側、動きのない砂の下には、地獄のような毒を持つエイやグロテスクなゴカイやカニや貝といった様々な訳のわからない生命が横溢している。
時に関係が壊れること、その通路が閉じてしまうことを恐れながらも、互いの思いを届け続けて、ある設定を二人の間に設け、時にふざけてありふれた言葉で呼びながらも、かすかなそれを信じることによって、自分が真に他に届けたいと思っていた、自分のなかにあるものを見つけ、と同時に相手のそれを見るにいたる道筋が海岸に沿って続いていた。
最後の最後、その夏の道中の果てに、十七歳の生命の中にあった思いが、「美しくて汚くて寂しくて優しい」その場所に、夢のような踊りとして顕れたその様は、息が詰まるような美しさと悲しみを湛えていて、私はたまらない気持ちになった。
町田 康(まちだ・こう)
1962年大阪府生まれ。作家。97年『くっすん大黒』で野間文芸新人賞、2000年『きれぎれ』で芥川賞、05年『告白』で谷崎潤一郎賞、08年『宿屋めぐり』で野間文芸賞など受賞多数。他著書に『夫婦茶碗』『湖畔の愛』『しらふで生きる 大酒飲みの決断』など。
孤独な魂が見た一夏の干潟の叙景
『パパイヤ・ママイヤ』は、SNSで知り合った一七歳の少女二人が共鳴し、実際に出会い、交流をする一夏の物語である。二人が会う「小櫃川河口干潟」は、木更津市に実在する。「人ひとりがやっと通れるほどのまっすぐな砂利道。左は笹がびっしり生い茂り、右は背の高い草木に覆われて薄暗い」と描かれる道を抜けた先の干潟で二人は初めて会う。
「パパイヤ」「ママイヤ」は、SNS上のハンドルネームで、対面した後もこの名前で呼び合う。「ママがイヤだからママイヤ、パパがイヤだからパパイヤ」なのである。以前からこの干潟に来ていたママイヤが、パパイヤを呼び寄せたのだ。
この小説を読み終えたあと、「東海の小島の磯の白砂に/われ泣きぬれて/蟹とたはむる」
という石川啄木の短歌が胸に浮上してきた。ままならない人生を嘆き、砂浜でひたすら涙を流す男が、蟹とたわむれている。三行目で突然現れる蟹。どうやってたわむれるのだろう。意表を突く形で現れるこの蟹の存在によって、この短歌は人々の心に強い印象を残したのだと思う。
「足元を小さな黒い影が左右に散っていくのに気付いて、パパイヤは足を止めた。影は藪の底にまぎれてなおカサカサと枯れ葉を踏む音を立てている。進むたびに、小さな影が視線の先で道を空ける」。初めて干潟に足を踏み入れたパパイヤが出会うこの不穏な何かが、そこに棲息する「無数のカニの群れ」である。人によってはここで気持ち悪くなって引き返すところだが、それが蟹であることに気づいたパパイヤは、「正体が知れればもう怖くはない」として「カニを散らしながら、ふいに飛び立つサギの羽ばたきやしきりに鳴くセッカの声を聞きながら、小径をどんどん進んでいった」のである。生き物の濃密な気配に引き込まれつつ、果敢に進んでいくパパイヤという人物にも強く引かれていった。蟹は、異世界への入り口への案内者のようである。
多くの人が居住する街のすぐそばにも、このような、滅多に人が来ない原始的な場所はある。SNSという現代のツールを通じて知り合った二人だが、社会と断絶されたようなこの場所が、安らぎになる。二人とも家族らによって傷つけられ、孤独感や淋しさ、無力感を抱いているが、この世の美しいものを見出そうとする気高さがある。干潟には、流木や、人間の排出したたくさんのゴミが流れ着く。ある種の不可抗力のように、二人もこの場所に辿りついたのだと思う。干潟で出会う少年やホームレスにも共通のものを感じる。あてどなくさまよう魂が寄り添うように。
一〇〇年以上前にこの世を去った啄木は、孤独を噛みしめるために一人で砂浜に来た。東京湾の工場が見える殺伐とした現代の干潟には、二人の少女が孤独を持ち寄るようにやって来た。啄木はひどく感傷的だが、彼女たちは、もっと冷めていて客観的である。
「わたしはこの日々が大事な思い出になるともう知っている。それは日増しに眩しくなって直視できないぐらいで、何もかも忘れられなくなっている」「探すとかじゃなくてさ、忘れちゃダメなんだと思うよ。自分が自分だってこと」「どこにいたって、さみしい時はさみしい」
彼女たちが折節に思ったり、考えたり、話したりする言葉は箴言めいていて、心に刺さる。終わることが分かっている時間の中で、彼女たちは真摯に考え続けている。その思索の背後に広がる情景描写が美しい。『最高の任務』や『旅する練習』など、これまでの乗代作品では、旅の途上での心の通い合いと、それぞれの土地が孕む学識的な側面とが拮抗していた印象があるが、この小説では学識的な側面は描かれず、あくまでも一七歳の少女たちの目で見た叙景として描かれている。ゴミだらけの風景が、やけにきれいに見える。ホームレスの老人が拾い集めた「きいれえもん」(黄色い物)も、希有な風景の一つなのだ。
東 直子(ひがし・なおこ)
歌人・作家。1996年歌壇賞受賞。2016年に『いとの森の家』で第31回坪田譲治文学賞を受賞。歌集に『春原さんのリコーダー』『青卵』など。小説に『さようなら窓』『とりつくしま』、エッセイ集『千年ごはん』『愛のうた』など著書多数。
ある特別な相手との特別な時間
大人になってから、激しく心を病んだ時期があった。自分のやることなすこと、自信がもてず、その自信のなさから間違った行動ばかりとってしまう。わかっているのにやめることができない。心療内科に行ってもみたけれど、心が落ち着く薬が出されただけで、それでは根本からの解決は難しそうだと感じた。そんな時に、たまたまSNSを通じて知り合った漫画家の先生とやりとりをし始めた。その先生の作品が好きで、少し心を病んだ主人公に自分を重ねていたからか、ある時期によく読み返していたのだ。先生は、メンタルヘルスの知識を豊富に持っていて、それはご自身の経験に裏付けされた血肉の通ったものだった。私は自分が楽になりたい一心で、寂しさや得体の知れない不安が襲ってきた時、昼夜を問わず先生にオンラインで話しかけた。私の気が済むまで文字でのやり取りが続けられ、心が落ち着いたところで途切れる。多い時では1日に何度も、つきっきりの対応を先生にしてもらっていたのだ。それも、いわゆるカウンセラーの資格を持っているわけではないからできたことだ。そんな風に応え続けることは、依存を招く。それでも、とにかくどんな時でも対応してもらう。もはや一種の依存状態ではあったけれど、先生曰く、こうしてどんな時にも話を聞いてもらった、向き合ってもらった、という経験が必要な人はいるのです、とのことだった。思えば、私にとってそんなことをしてくれる相手と出会ったのは初めてのことだった。母親にしてもらえなかったことを求めていたのだと、今となってはわかる。とことん向き合ってもらったあの時期を経なければ、私は今頃どうなっていたかわからない。自分の心が快方に向かっていくにつれ、先生に話しかけることは減っていき、もうここ数年は先生と連絡をとっていない。
主人公であるパパイヤとママイヤも、家庭環境が複雑な二人である。でも、そこに焦点は当たらない。この物語は、ひたすら彼女たちが解放に向かう輝きが、一夏の眩しさと共に描かれている。インターネットで偶然知り合った門限のない二人は、海辺で待ち合わせをして出会い、それからは一緒に過ごすようになる。二人の嫌がっているパパとママのエピソードは語られるが、本人たちが出てくることはなく、二人だけの狭くも柔らかい世界がある。これを読んで、私は先生とのあの時間を思い出したのだ。ひたすら誰かに向き合ってもらった経験が、自分を変えた。この人が味方でいてくれるから私は大丈夫、そう思うことができて、やっと暗い場所から飛び出すことができた。一人で立てるようになるには、自分を取り戻すことが必要であり、それには誰かの力が必要なのだ。
特別な相手というのは、一生でそう何人も出てくるわけではない。まして自分の人生に影響を与える人間は多くはない。彼女たちはまだ若く、目の前の海のように無限で、まだまだ想像もつかない未来が待っている。だからこそ踏み出すのは恐ろしい。けれどお互いの力を借りて、その一歩がすぐそこにもう見えている。ママイヤがパパイヤに出会って、少しだけ優しくなれたと言うように、人は人によって変わることができる。そしてこんなに一緒に過ごしている二人でも、数ヶ月後は離れ離れになっている可能性もある。どんな人とでもそうなのだ。人は、自分は変わるから、どんな相手とも永遠に一緒にいられるわけではない。家族でも、恋人でも、友達でも。それがわかっているから、彼女は写真を撮る。この瞬間を忘れないように、お守りのようにいつでも思い出せるように。
「この夏、奇跡みたいなことばっかり起こって、ずっと夢みたいだったから」
彼女たちは、ここからどこへでも行くことができる。二人で過ごした宝物のような時間が、先に進む背中を押してくれるのだから。
植本一子(うえもと・いちこ)
1984年広島県生まれ。2003年にキヤノン写真新世紀で荒木経惟氏より優秀賞を受賞。広告、雑誌、CDジャケット、PV等広く活躍中。著書に『働けECD〜わたしの育児混沌記』『かなわない』『家族最後の日』などがある。
〈「STORY BOX」2022年6月号掲載〉
関連記事
もっと光を! 小説の舞台である小櫃川河口干潟は、木更津駅から十分ほどバスに乗り、そこから徒歩で三十分という場所にある。足を運びやすい場所ではないが気に入って、手帳によると二十回行ったらしい。潮の満ち引きが見たくて朝から出向き、風景を書きとめ、蟹と戯れ、ゴミを漁り、飲み食いし、浜で遊び、昼寝して、夕焼けを見て帰る。一日い