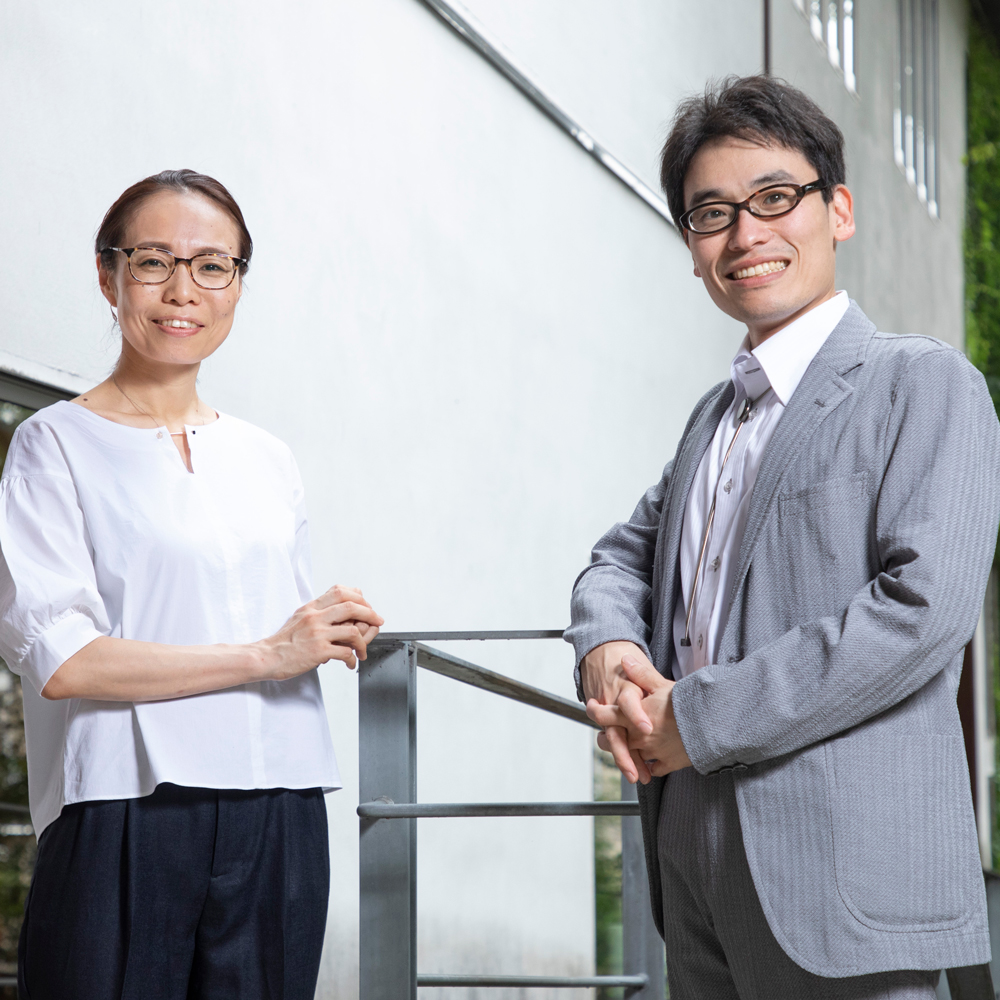長月天音『ほどなく、お別れです 思い出の箱』

変わるものと、変わらないもの
東京の外れに暮らす私は、時々無性に東京スカイツリーが恋しくなる。いてもたってもいられなくなり、つい足を運んでしまう。展望デッキまで上ることもあれば、下から見上げて満足するだけのこともある。
スカイツリー周辺が舞台の『ほどなく、お別れです』の執筆中は、近隣を歩き回って作中の人物の気持ちを想像する。と、言えばいっぱしの作家のようだが、単なる下町散歩で、老舗の銘菓をチェックすることも忘れない。
かつて墨田区民だった私は、スカイツリー開業当時、すぐ間近でその盛況ぶりを見守っていた。テレビで展望デッキへのエレベーターに延々と並ぶ人々を眺め、のんきに「すごいなぁ」と感心していた。「いつか、もう少し落ち着いたら行こうね」と隅田川のほとりを並んで歩く夫と約束をした。近所に住んでいるのだから急ぐことはない。いつでも行けると信じて疑わなかった。
しかし、二人でスカイツリーの展望デッキを訪れることはなかった。
私が初めてスカイツリーに上ったのは、夫の葬儀を終えた数日後である。
快晴だった。はるか遠くまで眺望がきき、ひしめき合うような建物の間に、私たちの住まいも確認できた。様々な思いが溢れ、私は泣いた。一緒に訪れた母はじっと待っていてくれた。
スカイツリーを訪れるたび、かつて暮らした土地での懐かしい思い出を辿り、あの時の空気のにおいを必死に探す。そんなことをしているうちに、新しい物語が浮かんでくる。
『ほどなく、お別れです』は、葬儀場の物語だ。どうしても残された人々が登場する。
どのように大切な人を失ったのか、事故死か病死か、はたまた焼死はどうかと、何やら物騒なことをあれこれ考えているうちに、「私、ちゃんと生きているんだな」と苦笑する。寂しさはあの頃のままだが、時間が流れることで、変わった感情も確かにあるのだ。
ここ数年、コロナ禍を経験し、葬儀の在り方や家族との最後の別れについて考える機会も多かったように思う。
物語はそれ以前の設定だが、作中で主人公は葬儀の在り方について議論を交わす。葬祭ディレクターを目指す彼女は、悩み、考え、時に憧れの相手に心をときめかせる。そう、それが生きているということなのだ。
読んでくださった方が、当たり前の日常や隣にいる家族を、いつもより少しでも愛おしく感じていただければ、私にとってこれ以上の喜びはない。
スカイツリーへの愛情もめいっぱい詰め込んだ本作、ぜひよろしくお願いいたします。
長月天音(ながつき・あまね)
1977年、新潟県生まれ。大正大学文学部日本語・日本文学科卒業。「ほどなく、お別れです」で第十九回小学館文庫小説賞を受賞しデビュー。他の著作に『ほどなく、お別れです それぞれの灯火』『明日の私の見つけ方』『ただいま、お酒は出ません』がある。