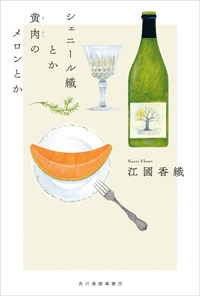吉川トリコ「じぶんごととする」 10. 若者言葉と中年小説家の危機
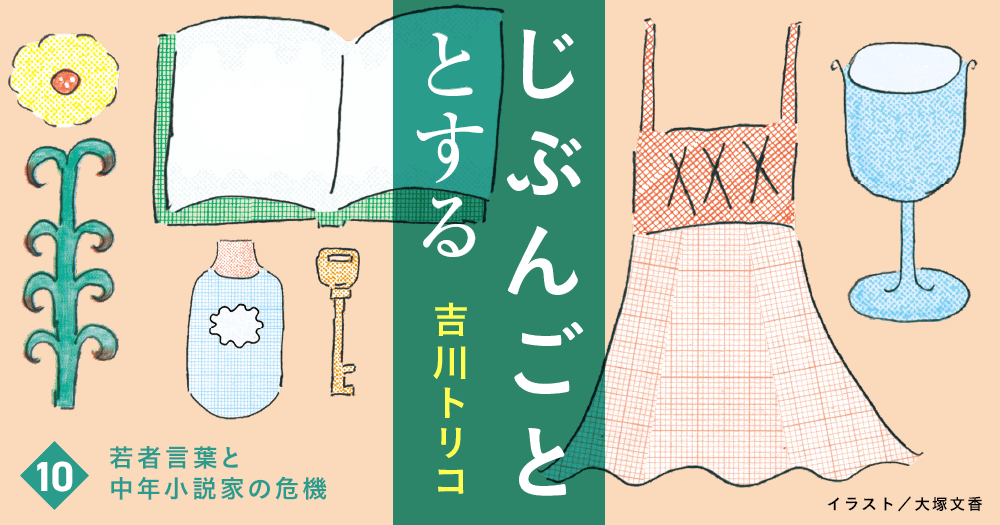
二冊目は江國香織さんの『シェニール織とか黄肉のメロンとか』。大学時代、「三人娘」と呼ばれていた五十代の民子と理枝と早希、それからその周辺人物——八十歳になる民子の母親、理枝の甥や民子の友人の娘といった若い世代の視点から語られる群像劇だ。
若い時代をともにすごした相手と再会すると、おたがいにどれだけ年を取っていても瞬時にそのころのような気分に戻ってしまうものだけれど、この小説にはまさにその気分が描かれている。年を取って忘れっぽくなり、体もあちこちがたがきて長時間ヒールを履いているのもつらい。それでも気分だけは若いままで、約束もしてないのにいきなり友だちの家に押しかけちゃうし、いい年して「全力で夢見がち」なことばかり言い、まだまだ「男性とめくるめく気」でいる。
それでも「寄る年波」がにゅっと顔を出す瞬間というのがあって、若い人から「古い」と指摘されてきょとんとする理枝、恋愛がオワコン化したと知って愕然とする小説家の民子、腕時計のフェイスをいまも手首の内側にしている早希、それからタイトルにもなっているシェニール織やカンタロープメロンについてのくだりなど、いちいち身につまされながら、同じ時代を生きることのかけがえのなさをしみじみと感じもした。この感覚はおそらく若い人とは共有できないだろう。古い時代を知っている、それなりに年を取った者だけの特権だ。
なにより江國香織といえば、私にとっては恋愛小説の極北、とっきんとっきんに尖りまくっていて息を詰めるように読んでいた作家であり、「みずみずしい感性」の代表格である。その江國さんが、こんなふうにゆるやかに元気いっぱい年を取っていく人たちの小説を書くなんてという驚きと喜びは、自分が古いものになっていくのではないかと恐れる気持ちを軽く吹き飛ばしてくれるようだった。
少し前に Twitter(←このようにかたくなに「Twitter」呼称にこだわるのもおばんしぐさなのかもしれない)で「おばさん構文」というのがやや嘲笑的に話題になったとき、井上荒野さんがやはり Twitter で「年代によって文体は違うだろう。(略)なんで若い方に合わせなきゃならないのだ」とツイートされていた。
いやもうほんとうにそのとおりで、若い人や新しいもののほうが正しく、若い人や新しいもののほうが優れていて、若い人や新しいもののほうが格好いいだなんて、エイジズムそのものの考えかたである。古いものにだって素晴らしいものはたくさんあるのに、私としたことが、なにをおもねったり卑屈になったりしていたんだろう。
近年、「現実にこんなしゃべりかたをする女はいない」とジェンダー的な観点から批判されがちな女言葉ではあるが、『照子と瑠衣』や『シェニール織とか黄肉のメロンとか』で使われているのを見ると、やっぱりいいものだなと思わずにいられなかった。彼女たちがしゃべるのに、あれ以上ふさわしい言葉はない。前述の『マリー・アントワネットの日記』でも、現代語を使いはするけれどあくまで十八世紀ヨーロッパのプリンセスという「言い訳」があったから、思うぞんぶんおきゃんな女言葉を使えて楽しかったおぼえがある。
女言葉そのものを好ましく思っているのか、失われていくものに対する郷愁なのかは自分でもわからないのだが、年を取るにつれ、なんとなく自然と女言葉が口をついて出てくるようになるのもたしかだ。とくに、おせっかいなおばさんしぐさをするときなんかに用いがち。中村桃子さんの『「自分らしさ」と日本語』に、「私たちは、ことばを工夫して使うことで、何とか表現したいアイデンティティを創造しようとしている」とあったが、要するに「古い女」をパフォーマンスするために女言葉を使っているのだろう。近頃、推しグループの若い男の子たちが語尾に「〜のよ」とつけてしゃべっているのもよく耳にする。これからどんどんジェンダーやそれにまつわる意味づけを攪乱し、越境するためのパフォーマンスとして女言葉が使われていったら、女言葉の延命が図れるのではないかと期待せずにいられない。
かつて私が若かったころ、若者を主人公にした小説を書くときには、女言葉などほとんど使わず、ストリートで実際に使われている言葉に極力近づけるようにしてきた。「登場人物のしゃべりかたが汚い」とか「下品」だとか「日本語の乱れ」だとかを嘆く声を数えきれないほどネットで目にしたが、そういえば「無理して若者言葉を使ってる」「痛い」「古い」などといった感想は当時は見かけなかった。『「自分らしさ」と日本語』によると、明治のころから「よくってよ」などといった女性の言葉の乱れについて苦言を呈するおっさんはいたみたいだし、どんな言葉で小説を書いたところでなにかしら言ってくる人はいるのだろう。じゃあもう知らん、好きにすればいいじゃんってことになって、晴れて中年小説家の危機にグッバイよ。
- 1
- 2