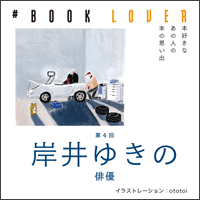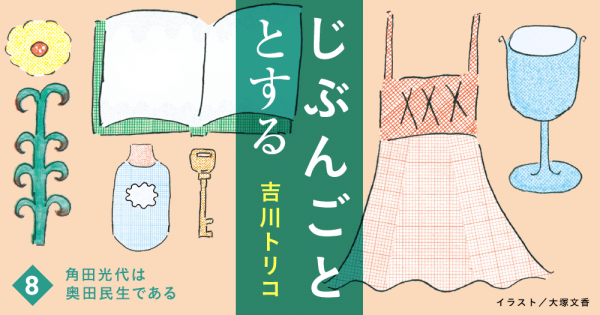吉川トリコ「じぶんごととする」 8. 角田光代は奥田民生である
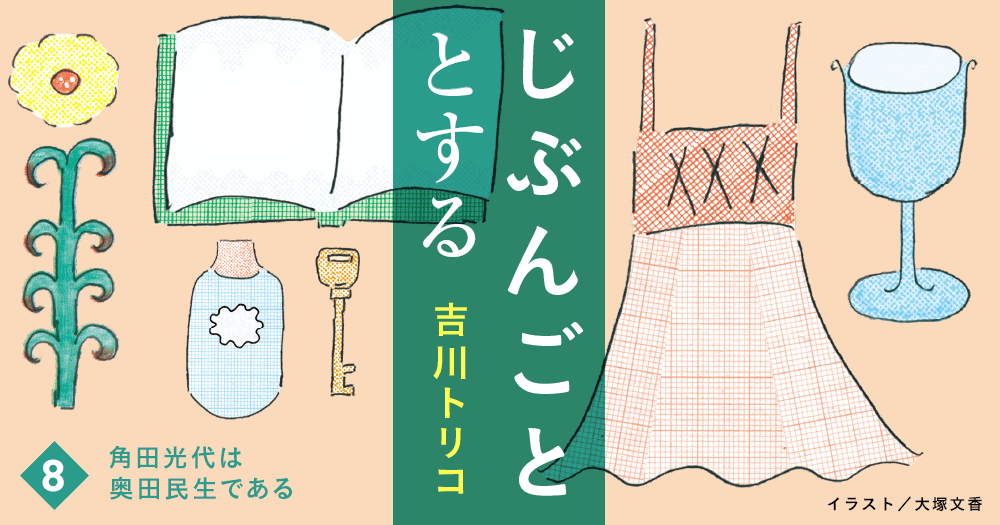
作家・吉川トリコさんが自身の座標を定めてきた、あるいはこれから定めようとするために読んだ本を紹介するエッセイです。
最初にことわっておくが、この文章は角田光代と奥田民生に類似性を見出し論じるものではない。あくまで私にとっての角田光代が私にとっての奥田民生みたいなものだというだけの話である。したがって「奥田民生ではなくどちらかというとブルーハーツなのでは?」「いややはり清志郎では?」などといった異論を寄せられたところで、どうぞご自由にそれぞれ自分にとっての角田光代をなにがしかにたとえてくださいとお答えするしかない。
ユニコーンの「命果てるまで」のМVをテレビで観たのは中学一年のときだった。当時アイドル歌手(光GENJI や浅香唯)のCDぐらいしか買ったことのなかった私は雷に撃たれたような衝撃をおぼえ、日本のロックシーンを熱心に追いかけるようになった。中でも奥田民生は特別な存在だった。
若い人からすればただのおじさんにしか見えないだろうが、当時の民生は日本のロックミュージシャンの中でもひときわアイドル的な人気があり、ファニーなかわいらしい顔で女の子たちをキャーキャー言わせていたのである。当代一の少女マンガ家・いくえみ綾の描く男の子が奥田民生に酷似していたり、ニット帽にエアマックス、ヴィンテージっぽく色落ちしただぶだぶのデニムを穿いた「奥田民生になりたいボーイ」たちがストリートにあふれたり、一時期の奥田民生の影響力たるや凄まじかったのである。そのゆるさ、ラフさ、かっこつけずにありのままの姿をさらすことが、たまらなくかっこよく見えた時代があったのである。
十代のころのように熱心に活動を追いかけることはなくなってしまったけれど、私の中で民生は「まちがいなくいいもの」の箱に入れられている。テレビに出ていれば見入ってしまうほどには関心を持っているし、町を歩いているときなんかにどこからともなくあの声が聞こえてくるとホームにいるような安心感をおぼえる。それが私にとっての奥田民生である。
一方、はじめて角田光代の本を読んだのは十九歳のとき、文芸創作のゼミで『学校の青空』が課題になったことがきっかけだった。
前回書いたとおり、それまで私は文学というものはなにやらいかつくハードな題材を扱ってこそという固定観念を持っており、十代の少年たちが日々感じていることや見ているもの、ごく狭い範囲の人間関係をスケッチしたような角田さんの小説にやっぱり雷に撃たれたような衝撃をおぼえた。え、これでいいんだ、こんなふうに書いていいんだ、と目からうろこが落ちるような思いがしたものだ。そこには私がいた。あいつやあの子やあの人もいた。もちろんそれまでにも主人公に共感し、「これは私だ」と感じるような読書をしたことはあったけれど、角田さんの小説はそこに一ミリの誤差もなく、ぴったりと正確に私たちだった。そんな読書体験ははじめてだった。
以来、書店で角田光代の本を見かけると手に取るようになった。自分で稼いだ金で小説の単行本を買ったのは、『カップリング・ノー・チューニング』がはじめてだと思う。それまで小説に出てくる音楽といえば、ジャズとかクラシックとか、ロックでもストーンズやビートルズといったような上の世代が聴いているものばかりだったけれど、角田さんの小説にはペイヴメントやスマ・パンやジョン・スぺやウィーザーなど、そのとき私たちがリアルタイムで聴いていたものが登場し、やっぱり私たちの小説だと思った。
角田さんの小説のなにがそんなに好きかといったら、文章がとにかくほんとうにべらぼうに凄まじくて真似したいのにとても真似できないと思う。何度も真似しようとして失敗してきたし、同じように同世代の「角田光代になりたいガール」たちの失敗も見てきたからこそ、その凄さがよくわかる。コバルト時代のデビュー作「お子様ランチ・ロックソース」(彩河杏名義)の時点ですでに完成されているんだから、もうなんかほんといやんなってしまう。
ひたすらに気持ちのいいリズムで、ドライなのにときどきエモく疾走するモノローグ、あざやかな飛躍、そのしびれるような緩急。日々の生活のなかで、ぼんやりしていたら見落としてしまいそうなほんの一瞬の心の揺れを、シャッター速度のはやいカメラでぱしゃぱしゃとらえていくような心理描写。特別な言葉やモチーフをいっさい用いず、だれが読んでもわかるような平易な言葉で書かれているのにほかのだれにも書けないひらめくような比喩。どこの家庭の冷蔵庫にもあるありふれた素材で一流シェフが腕をふるう(←我ながらあわれになるほど凡庸な比喩)とこうなるのだというような驚きが角田さんの文章にはある。
角田さんの小説は呼吸するのと同じようにいまでもいつでも読んでいるのだが(『薄闇シルエット』とかたぶんもう七回ぐらい読んでる)、一作だけもう二度と読み返したくないと封印していた作品がある。『愛がなんだ』である。
- 1
- 2