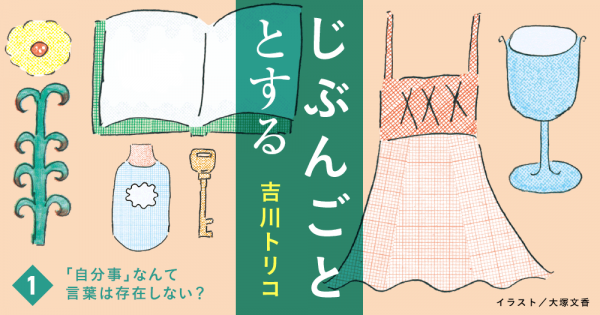吉川トリコ「じぶんごととする」 1.「自分事」なんて言葉は存在しない?
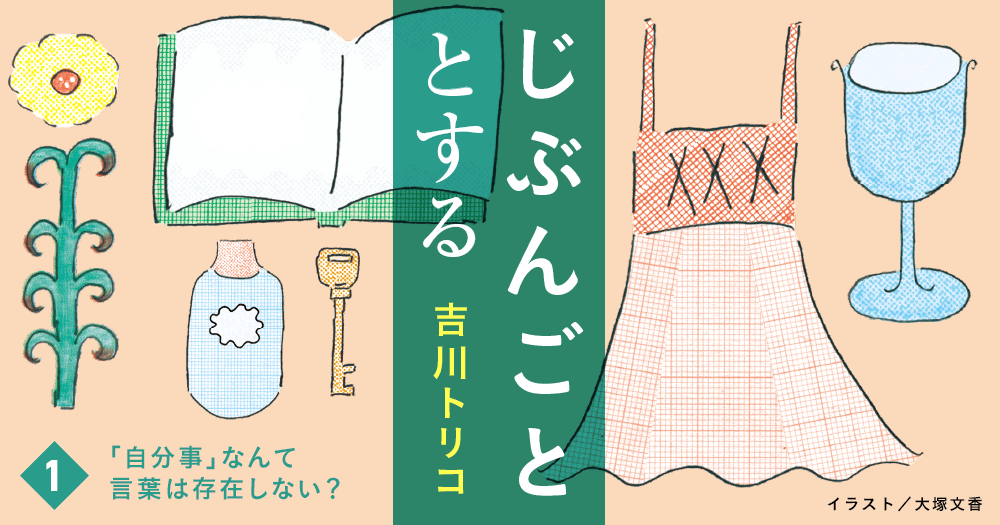
エッセイの連載をはじめようとしているくせにこんなことを書くのは気が引けるが(でも書くのだが)、昔から圧倒的にだんぜんフィクションが好きで、いまもエッセイは年に一冊読むか読まないかぐらいの頻度でしか手に取ることがない。エッセイの名手といわれた向田邦子は大好きな作家の一人だけれど、読みかえしているのは小説ばかりだ。
なぜなんだろうと改めて考えてみた。一編一編が「短い」というのがまずあって、それゆえどうしても印象が軽くなるのかなと思った。もちろん短くてもキレキレのエッセイなんてごまんとあるわけだけれど、どうせ読むなら栄養がたっぷりあってどっしり腹にたまるものをとつい思ってしまう。本というものをむやみに信望し、善きものであると疑わずにきた人間の考えそうなことである。
筆者の顔が見えすぎ、声が聞こえすぎてしまうのがいやなのかとも思ったが、むしろエッセイとして読むなら、内臓をさらけだすようなもののほうが好きかもしれない。かといって露悪的であればいいというわけでもないし、「わたしってすごいでしょ?」「わたしって変わってるでしょ?」「わたしっておちゃめでしょ?」といったかんじの自意識が過剰なものはうっとなってしまうので塩梅が難しい。小説の登場人物のことは好きになれなくても読み進めることができるけど、エッセイの場合は最初の数ページで著者を好きになれないともう読む気がしない。なんとわがままな読者なのだろう。小説よりエッセイを酷評されるほうが自分自身をけなされたように感じて傷つくのはそのせいかもしれない。
だれか一人、好きなエッセイストを挙げろといわれたらそんなの雨宮まみさんに決まっている。もう殿堂入りだ。エッセイを好きこのんで読まない私が、まみさんの本だけは出たらすぐに買っていた。とりわけ『女子をこじらせて』は何度も読みかえし、ことあるごとに人にプレゼントしてまわった特別な一冊である。
後にも先にも、あんなエッセイを読んだことはない。今回読みかえしてみてやっぱりそう思った。暗黒の学生時代から上京後ライターとして活動するようになるまで——「女」として生まれ、「女」をこじらせ、「女」を受け入れるまでに経験したさまざまなことを綴った、ずしりと重たい大河エッセイ。
まみさんは決して自分の欲望から目をそらさない。愚かさから、ずるさから逃げない。ことさらに自己卑下し、自己批判してみせることの欺瞞も許さない。そこまでしてくれなくていいのにとぎょっとしてしまうほど正直に、その欲望が、その迷走が、その混乱がどこからくるものであるのか、まぐろの解体ショーの要領でみずから解体して見せる。おかしみと哀愁。知性と熱狂。冷静と情熱のぐちゃぐちゃ。読後感はいっそすがすがしく、それまであたりまえだと思っていた世界ががらりと様相を変えていた。これこそが文学じゃないかと興奮とともに思った。
「男に欲望される女でありたい」といつのころからかごくごく自然に私は思わされてきた。胸やお尻の突き出た曲線的な体つきのほうがエロくて男ウケがよく、当然デブはだめだし、そうかといってガリもだめ。おばさんになったらおしまいだし、ブスは生きる価値なし。女の子は性欲なんてありませんという顔をしていないと淫乱だとみなされるから、ベッドの中では男に主導権をあずけ恥じらいをもってふるまわなければならないが、引かれない程度に床上手にはなりたい! 男に選ばれない女は憐れで不幸だし、いくつになっても女を捨てたらいけない、いつまでもきれいで愛される女でいなくっちゃ、セックスレスなんて絶対悪!!!
物心ついたころからテレビや雑誌、さまざまな広告やマンガや小説などから「学習」し、そう刷り込まれてきた。まさかそれが、自分の内側から出てくる欲望ではなく、他者からのお仕着せだったなんて、『女子をこじらせて』を読むまで考えもしなかった。まさに「ユリイカ!」と叫びたくなるほどの衝撃だった。
男目線を内面化し、男中心の社会で醸成されたこの価値観や性幻想はいまも私の中に根深く残っていて、ときどきふっと顔を出す。そのたびに苦々しい思いにはなるけれど、それすらまるごと自分のものであると最近は思えるようになった。いまでもやっぱりできることなら痩せたいしモテたいしきれいになりたい。セックスは正直もうめんどうだから積極的にしたいと思わないが、恋のようなものはいつだってしていたい♡ 大切なのはその欲望がどこからくるものであるのか、ちゃんと自分で見極めた上で、欲望を制御したり、制御しきれずに振りまわされたりすることなんじゃないだろうか(このようにして中年女のもてあました性欲が「推し」に向かってどっと注がれるのでしょうか……)。