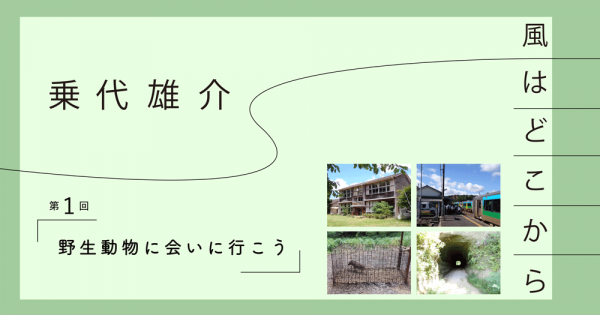乗代雄介〈風はどこから〉第1回

第1回
「野生動物に会いに行こう」
7月末の平日の朝、JR木更津駅から1時間に1本のJR久留里線に乗りこむ。窓を縁取るような青と緑に黄色いドアのカラフルな車両。いわゆるローカル線で日中は1両編成の時さえあるが、朝は通学のために車両が増え、この時は3両編成だった。もう夏休みのはずなのに学生が多い。部活にしてはみんなスクールバッグ一つだし、それぞれ制服も違う。車窓は住宅地から田園へと移り森林が目立ってくる中、清々しい青空だけが変わらない。学生が少しずつ乗車してくる。
久留里駅に着くと、有人改札に長い列ができた。久留里線はJRで東京駅に最も近いIC未対応路線なのである。ぜんぜん列が動かないところを見ると、ICで入場して木更津駅で乗り換えたはいいが、そのまま出られず現金精算している学生が多いのだろう。買った切符を渡すだけの私は列を離れて眺めながら、乗り降りに不慣れな学生だらけという妙な状況について頭を働かせる。近くの学校をネット検索し、年間行事予定表を見る。はたしてこの日は、このあたりに唯一ある高校の学校説明会であった。彼らの半分ぐらいは、定期券を買ってこの駅に通うようになるのかしらん。しみじみしているうちに列が短くなって、私も駅を出た。

中学生たちと反対の方へ進み、ここから養老渓谷を目指す。養老渓谷といえば房総半島屈指の観光名所であり、これまたローカル線の小湊鐵道の駅名でもある。養老渓谷を見る時間はないと思うが、その駅まで歩いて電車で帰ろうという計画だ。寄り道しなければ15キロといったところか。
まずは、そこかしこに自噴井戸がある久留里の町を歩く。観光地といえば久留里城址だが、朝早くで天守閣も資料館もやっていないのでまた今度。この連載に観光地の紹介を期待してもらっても困るけれど、観光名所ぐらいの景色や歴史は、滅多に人の通らない道にもあるものだという気持ちが少しでも共有できれば嬉しい。
例えば、城址の近くにある久留里神社は創建千年の歴史を持つ。しかしこの時、拝殿が丸ごとなかった。本殿に参拝用の口が開いている。令和元年房総半島台風の際に木が倒れ、拝殿がつぶれてしまったのだという。倒壊した写真を添えた立て看板には、義援金を募って再建を目指しているとあった。「○○年に再建された」とでも後に書かれる現在進行形を目の当たりにしているわけだ。それが叶うよういつもより多く賽銭を入れた。
国道410号線から離れるように南東へ進めば、もう家を数えて歩けるほどの長閑な風景が広がる。君津市の怒田という地域だが、すでにグーグルストリートビューは途切れている(2022年10月4日現在)。最後の人家から100メートルほどで、林道に入るらしい。
林道手前、道の脇の上方に鳥居を発見。危ない斜面を登り、ぎりぎりのスペースに立った鳥居から続く石段の先には庚申塔が一つ。蛇をのせた頭、額にある第三の目、怒った顔、印なのか合掌なのかわからない六臂のうちの一対、ムズい中央部分を完全にあきらめた法輪など、青面金剛の姿である。ただ、少し頭をもたげた蛇へのこだわりや、交差したようにも見える手元など、軍荼利明王の影響も感じる。なんでもこのあたりには大蛇伝説が残るそうであるし、近くの鹿野山神野寺の本尊の一つが軍荼利明王なのでその影響かもしれない。頭の蛇は寺宝の白蛇の彫像によく似ている。
私はこういう石仏が好きだ。曖昧な知識や技術の限界、土地の伝承、不思議な創作意欲が絡み合って出来上がったものだが、有名な寺の宝物館で国宝級の仏像を見るのとは異なる感動がある。それが今もここにあるという信仰は篤く深くというより、失礼な言い方をすればだらだら信じられてきたものかもしれないが、だからこそだ。あるからには放っておけないからずっとある。こういうものが宿している強さを、現代社会が再現するのは難しいだろう。それは、現代人からこの種の強さが失われるのと同じである。
いよいよ怒田福野線という林道に入る。林道とは、森林の整備・保全を目的として森林地帯に設けられる道路のこと。作業用の車が入る関係で舗装されている場合もあり、ここも鬱蒼とした森の中までほぼ全て舗装路だった。最高峰でも408メートルの千葉県だから高低差もほとんどない。途中の北向地蔵尊でお参りして、帳面に名前を書いた。こう書くと気楽なコースに思われるが、地蔵尊から先はとんでもなかった。
早速、高さのあるコンクリ擁壁の上からニホンジカが飛び出して、数メートル前を横切った。シカには何度もお目にかかってきたが、生身で目前を駆け抜けられたのは初めてで、先が思いやられる。少し行けば、箱ワナと呼ばれる檻がそこかしこに置いてある。エサとして撒かれた(たぶん)米ぬかがぐちゃぐちゃで牛糞のような臭いが漂い、と思ったら普通に子供のシカが捕まっている。じっくり見ていたらブルブル震えだし、逃げようと檻の内から体当たりをくり返し、あっという間に鼻と口が血まみれになってしまった。このあとどうなるか知りつつ勝手なものだが、かわいそうだからと先を急ぐ。

急に広い草っ原に出れば、その中を泳ぐように何頭もシカが散り、背後に飛び出たキョンが道を逆に駆ける。ドキドキしながら上っていくと〈素掘りトンネル〉があった。このあたりは御腹川の源流にあたるが、房総では浸食で形成された低い段丘を迂回せず、手薄なところを掘ってぶち抜く。もろい砂岩だからこそできる芸当だ。
トンネル内に溜まった砂は、往来する動物の足跡だらけだ。抜けた先にも箱ワナがあり、今度はウリ坊が捕まっている。経験の浅いのがかかりやすいとは聞くが、こうして現地でくり返し目にすると納得する。と同時に、この状況は子を失ったばかりの母親がそう遠くない場所にいることを示しており、急に恐くなった。シカは鉢合わせても驚くだけで済むが、イノシシは危ない。

人はいないし電波も微妙。なめて熊鈴を持って来なかったことを後悔しつつ、iPod をスマホにつないで、目一杯の音量でフレディ・マーキュリーの「Living On My Own」を鳴らしながら先を急いだ。動物にプレッシャーを与えられそうな音だし、歌詞のようにかなりロンリーな気持ちだったからである。歩いている時はあまり聴かないので忘れていたが、この連載では旅の中で3曲を紹介することになっているので、これを1曲目とする。
とはいえ、思ったほどには音も響かず、2回目のサビで「モンキービジネス」がどうのと歌っている時にサルの群れが道の遠くをザザザザッと横切った時にはびびりつつも笑ってしまった。その後も動物たちは生い茂った夏の草を鳴らしては消え、時に現れ、そのたびに、すわイノシシかと身を硬くした。北向地蔵尊から福野の集落に出るまでの3キロほどの道で私が遭遇した動物を、捕らわれも含めて列挙する。ニホンジカ8頭、キョン2頭、イノシシ1頭、ニホンザル10頭以上(群れなので正確な数は不明)、アナグマ1匹、ヤマカガシ2匹、アオダイショウ1匹。
気の休まる暇も動物にカメラを向ける余裕もなかったこの道で、私は野生動物の領分というのを思い知った。それは人里からの距離でも高低差でも舗装の有無でもない。剥き出しの山道であろうと土日に何十人でも人が登るならそこは人間の領分で、動物たちは音や匂いでそれをわかって近寄らない。ここは違う。クマもいないところで、人間からニンゲンという動物になってしまうとは思わなかった。やわなものである。
やっと林道を抜け、廃校になっている旧福野小の前に出た。番犬に盛んに吠えられて逆に安心する。ランダム再生にした iPod から、吉田拓郎の「川の流れの如く」。この曲が収録されているアルバムのタイトルだが、『人間なんて』という気分である。川の流れと同じく、自分もまた作り作られてここに立っていると拓郎は軽快に歌う。なるほど、人は何かに身を委ねつつも、行きたい方へ手で穴を掘るぐらいはできるはずだ。

白鳥神社を参拝し、梅ヶ瀬渓谷に下りて倒木の多い荒れ気味の沢を、流れに絡むツタのようにジグザグに下っていく。養老川の支流の一つで、明治時代、日高誠実という人が陸軍省を辞して、私財を投じてここに理想郷を作ろうとしたという。渓谷の最奥部に邸宅を建て、梅や橙を植樹して養魚場を作り、梅ヶ瀬書堂という塾まで開いたそうだが、水害のたびに荒れて流され、当人が亡くなって夢は潰えた。邸宅跡地のモミジだけがその名残だという。私はこの日、そこまで行かなかった。紅葉を期待して植えたであろう日高誠実のため、いつかの秋に再訪しようと思いつつ歩く。上手いもので、佐野元春 & THE COYOTE BAND の「新天地」が流れた。新しい場所を目指して歩いたところが誰かの夢の跡だったりするのは、世界の広さを思い知るようでうれしい。
道路に戻ってまた歩く。説明は何もないが故タイガー立石のアトリエだった古民家のそばを通って宝衛橋を渡ると、養老渓谷駅だ。まだ日は高いが、ちょうど来た五井行きに乗って旅も終わる。途中、どこの駅か覚えていないが、小さなホームが人や物で埋め尽くされていた。野球のユニフォーム姿が見えたが全く乗る気配もなく、ベンチでは傍らにバットケースを置いた少年が目をつむり、マスクをした女性から盛んに霧吹きで水をかけられている。どうやら映画か何かの撮影らしい。人間は色んなとこで色んなことをやるものだ。朝の中学生たちはもう家に帰っただろうか。シカとイノシシの子供は、まだ狭い檻の中をうろついているだろうか。
写真/著者撮影
乗代雄介(のりしろ・ゆうすけ)
1986年北海道生まれ。2015年「十七八より」で第58回群像新人文学賞を受賞しデビュー。18年『本物の読書家』で第40回野間文芸新人賞を受賞。21年『旅する練習』で第34回三島由紀夫賞を受賞。ほか著書に『最高の任務』『ミック・エイヴォリーのアンダーパンツ』『パパイヤ・ママイヤ』などがある。
〈「STORY BOX」2023年3月号掲載〉