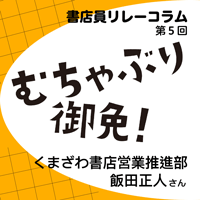「拾う人」森絵都

「そうですね。ただ、気にしてたのは親戚じゃなくて、坊さんの目だったみたいです」
「ああ、そっち?」
「国産車どころかスクーターで来てました」
「ふうん。じゃ、そういうの気にしない人なんじゃないの」
「俺もそう思いました」
どうやらベンツのことで恨まれてはいないようだ。ひとまず安心したものの、親戚づきあいをあからさまに避けている相手なだけに、一緒にいるとどうにも落ちつかない。夕子おばさんだって一人でジャフを待ちたいのではないか。そんなことを考えながら引きあげるタイミングを見計らっていると、
「そういえば、お母さんから聞いたけど、あんたたちには世話になったんだってね」
夕子おばさんが自分から話をふってきたので驚いた。
「お父さん、なんでもかんでも拾ってくるようになっちゃったんでしょ」
「はい」
俺はうなずき、一瞬迷ってから言った。
「このベンチもそうです」
「え」
夕子おばさんの瞳がすとんと落ちる。つかのま眉間に浮かんだしわは、しかし、意外とすぐ消えた。
「そっか、こんなのせっせと拾ってたんだ。ま、お父さんらしいっちゃ、らしいかも。お父さん、鉄の斧の人だったから」
「テツノオノ?」
「『金の斧銀の斧』って話、知ってる?」
「はあ」
話の飛躍にとまどいながらもうなずいた。
ある日、きこりが鉄の斧を泉に落とすと、金の斧を手にした泉の妖精が現れ、これはあなたの斧かと聞く。きこりが違うと答えると、今度は銀の斧を見せて同じ問いをする。きこりはまたも否定する。その正直さにほだされた妖精の計らいによって、きこりは金、銀、鉄とすべての斧を手に入れる。それを見ていたよくばりがきこりを真似るも、魂胆を見抜かれ、自分の斧を失って終わる――。たしかそんな話だ。
「私が子供のころ、お父さんがあの話にぶつぶつ文句言ってたの憶えてるんだ。きこりが鉄の斧を選んだのは、正直だからじゃなくて、木を切りたいからだって」
「へ」
「金や銀は柔らかすぎて斧としては使いものにならないんだって」
「はあ」
「ま、そういう人だったんだよね。私、小さいころはいやだったんだ、お父さんのそういうところ。金の斧は売ればお金になるのにとか思ってたし。よく反発したなあ」
夕子おばさんがふっと唇を笑ませた。笑顔を見たのは初めてかもしれない。笑うとなんだかじいちゃんに似ている。
「でも、お父さんが拾ったベンチは、べつにいやじゃないな」
「そうですか」
「うん。お父さん、なんか充実してたんだろうね。晩年のゴミ拾い」
高そうな指輪の光る手でベンチの木肌をそっとなで、夕子おばさんはゆっくり立ちあがった。
「じゃ、私、行くわ。もうジャフも来るころだし」
「あ……はい」
「ところであんた、尚行?」
「武です」
「そっか。お父さんによくしてくれてありがとう」
片方の手をひらひらふりながら門の方へ向かう。きょうだいと群れているのを見たことがないその孤高な後ろ姿は、やっぱりどこかじいちゃんを彷彿とさせる。もしかしたら彼女が一番じいちゃんの血を継いでいるんじゃないか。ふとそんなことを思う。
頭の中ではさっき夕子おばさんが口にした一言が余韻を広げていた。
――お父さん、なんか充実してたんだろうね。晩年のゴミ拾い。
たしかに、昔からじっとしていられない人だったじいちゃんは、仕事場であった田んぼを手放したのち、ゴミ拾いという妙な使命を己に課すことで、誰にもわからない自分だけの人生を生ききったのかもしれない。
最晩年の一時期かかわっただけの俺に断じられることは何もないけれど、七回忌で夕子おばさんと会ったときには、当時のじいちゃんがどんなふうだったのか教えてあげたいと思った。
毎月一週目の土曜に孫三人でじいちゃんちのゴミを片づけ、一泊する。一風変わったそのミッションは半年ほど続いた。一人の老人が一ヶ月で集めた量を中年三人で撤去するのはさほどの労ではなく、運び出しにもじきに手慣れて要領がよくなった。田舎の景色には心が和むし、労働後に供されるばあちゃんの手料理は懐かしい味だし、いとこ同士で飲み交わす酒もうまいし――率直に言って、俺は月頭の週末を楽しみにさえしていた。
そもそも昔から尚行と亜純は馬の合う者同士だった。競争心の強いいとこたちの覇権争いをよそに、いつも集団の片隅で心地よく寛ぎ、バカ話をして笑い合っていたのが俺たち三人だった。その基本スタイルは今も変わらず、じいちゃんとばあちゃんが寝たあとも続く酒盛りには仕事のグチとか、上司の悪口とか、株がどうのこうのとか、そうした酒をまずくする要素は決して入りこまず、もちろん男と女の厄介な色恋的要素もなく、俺たちはただ昔どおりにバカを言い合って笑っていればよかった。その気楽さがこの年になればこそ得難くも感じられた。
そんな俺の胸中はおのずと態度に滲んでいたのか、互いに干渉し合わなくなって久しい妻からめずらしく異議が出た。
「毎月毎月、茨城までゴミの始末に行くって、なんかおかしくない? べつに行くのは勝手だけど、でもさ、その前になんでおじいさんを止めようとしないの?」
「なんでって……」
なぜそんなことを聞くんだろうととっさに思ったものの、よく考えてみればそれは真っ当な質問だった。俺だって初めてゴミの山を見たときは思った。なんでばあちゃんは止めないのか、と。
「いや、それはあの……たぶん、じいちゃんにはじいちゃんなりの理由があるからだよ」
「どんな理由?」
「それはじいちゃんにしかわからない」
「なにそれ、意味わかんない。結局、あんたたちみんな、現実から逃げてるだけなんじゃないの。うちの親戚だったらとっくにおじいさんを病院へ連れてってるよ」
「俺はなんでもかんでも医者が解決してくれるとは思わない」
結局いつもの言い合いとなり、夫婦の断絶を一層深めて終わったのだが、実のところ、この問題に関しては妻の言い分にも一理あるのを俺は本音じゃ認めていた。
病院へ連れていく。おそらくそれが世間一般的な対処法なのだろう。じいちゃんが際限なく拾い集めてくるゴミを再び捨てにいく。こんなことをいくら続けても抜本的な解決には至らない。が、しかしそれを重々承知した上で、それでも尚且つ、当時のじいちゃんには「やめろ」と言うに言えない妙な迫力があったのもまた事実だった。
まるで田を耕すようにじいちゃんは日々こつこつとゴミを拾った。真夏の炎天下でも、真冬の突風の中でも。ばあちゃん曰く、よほどの大降りでもないかぎり雨の日も合羽をはおって長いことほっつき歩いていたそうだ。月いちで顔を合わせていた俺たちにもその重労働の断片は垣間見られた。
土曜の夕方、俺たちが処理場からもどってひと息ついているころに、じいちゃんはまた新たなゴミを運んでくる。収穫が多い日も少ない日も、それらはまず一階の風呂場へ運ばれ、たわしでごしごし洗われる。つぎに庭で乾かされ、必要とあらば磨かれ、ようやく広間に収容される。
汚れを落としたゴミの中にはまだ十分使えそうなものもあり、すっかり顔見知りになった処理場の職員から「こりゃ捨てるに忍びないよ」と近場のリサイクルショップを紹介してもらって以来、俺たちは見込みのありそうなゴミを売りに行くことも覚えた。いくらにもならないとはいえ、ばあちゃんのちょっとした小遣いにはなるし、なによりその循環によってじいちゃんの労働に生産性が付与されることが俺には嬉しかった。
じいちゃん自身はあいかわらず拾ったゴミがどうなろうとまるで頓着しなかった。自らの手で清めた時点で仕事は終わっていたようだ。三人の孫が訪れるたびに家のゴミが減る、その因果関係に気づかなかったわけもないのに、それについて俺たちは何も言われたことがない。
依然として俺たちにはじいちゃんの頭の中がさっぱり理解できず、ただじいちゃんが懲りずに拾いつづけるから、俺たちも懲りずに捨てつづけた。
一つたしかに言えるのは、じいちゃんのゴミ拾いが誰のことも不幸にしていなかった、ということ。三ヶ月に一度でもいいゴミの処分に俺たちが月いちで通っていたのに鑑みると、誰にも迷惑すらかけていなかった。
もしもゴミ拾いの犠牲者がいたとするならば、それはじいちゃん本人だ。
米寿をすぎた高齢者の体に連日の流浪は相当な苦役であったはずで、さすがのじいちゃんも季節が移ろうほどに疲弊の色を隠せなくなった。痩せた頰がさらに削げ落ち、少ない口数がますます減って、夜もしんどそうにはやばやと寝てしまう。それでも瞳にこもった執念の光は衰えず、朝が来れば必ず布団から這いだし、重たい足どりで荷車を引いていく。俺たちがゴミ拾いを止められなかったのは、結局のところ、その鬼気迫るど根性に負けたせいかもしれない。
忘れられないシーンがある。
背景は白だった。その冬初めての雪が降ったその日、俺たちはゴミの運び出しを早々に断念し、じいちゃんの家でじりじりとした時をすごしていた。普段どおりに朝から出かけていたじいちゃんがなかなかゴミ拾いを断念しなかったからだ。
正午をまわり、地面が隈なく雪で覆われても、じいちゃんは帰ってこなかった。午後二時をまわり、立木の枝が積雪でしなっても、まだ帰ってこなかった。四時をまわり、横殴りの風が強まってくるに至って、俺たちはとうとう手分けしてじいちゃんを捜しはじめた。
俺はスタッドレスタイヤをつけた車のナビを頼りに、じいちゃんの足でたどりつけそうな道を片っぱしからヘッドライトで照らしてまわった。歩く人の影もなければ走る車の影もない、陰気で暗い午後だった。となり駅に近いバス通り――個人商店や民家の建ち並ぶ道の先に異様な孤影が浮かびあがったのは、闇雲な捜索が小一時間も続いたころだった。
雪まみれのじいちゃんがそこにいた。荷車に積まれたタンスとおぼしき物体も白一色で、まるで四角い雪のかたまりを運んでいるようだった。その重みと闘うように、じいちゃんは眼光鋭く前を見据え、雪に埋もれた長靴の足を前へ、前へと押しだしていく。遅々として進まないのに立ち止まろうともしない。
なんだか俺はものすごい景色を見てるみたいだ、と肌が粟立った。わけもなく涙が出そうだった。
「じいちゃん!」
荷車は明日回収すると約束し、この日ばかりは強引にじいちゃんを車に乗せた。
帰り道、暖房をがんがん効かせた車の助手席で、じいちゃんはずっと小刻みに震えていた。
「なんでそこまでするの」
聞くともなしに俺がつぶやくと、答えるともなしにじいちゃんもつぶやきかえした。
「あぎらめだら、無駄死にだ」
その夜は酒を飲む気にもなれず、早々に解散して床についた。雪の中を全身全霊で駆けまわっていたという尚行も同じ部屋の布団でのびていた。屋根に積もった雪の防音効果か、世界は完璧に静まり返り、呼吸一つでもやけに鼓膜を刺激するような夜だった。
眠りたいのに眠れない。
「尚行、起きてる?」
冷たい足先をこすりあわせながら、隣で寝ている背中に呼びかけると、「おう」と声が返ってきた。
「ちょっと話していい?」
「おう」
「あのさ、俺、前からなんとなく思ってたんだけど……」
それまで誰にも言わなかったことを俺は初めて口にした。
「じいちゃんのゴミ拾い……あれって、戦争が関係してるんじゃないのかな」
「あ?」
「いや……どこがどうとは言えないんだけど。ただの勘だけど、なんか、どっかでじいちゃんの戦争体験と繫がってる気がして」
本当に、どこがどうとはいまだに言えない。けれど、いつからか俺はゴミを拾っているじいちゃんの姿に、骨を拾っている人の像を重ねるようになっていた。ゴミ拾いにかけるじいちゃんの執念を見るほどにその像は生々しさを増した。この日、雪の中で見たじいちゃんの形相も、とてもただのゴミを運んでいる人間のそれとは思えなかったのだ。
「戦争かあ」
俺につむじを向けたまま尚行は無言で息をつめ、数十秒後にごろんと寝返った。
「なるほど。戦争かあ」
それからまた数十秒ほど黙って天井を仰いだのち、彼は突然告白したのだった。
「俺さ、じつは、じいちゃんの秘密を知ってるんだよね」
「秘密?」
「じいちゃんが教えてくれた。俺が小六のとき。ほら、俺、しばらくこの家に住んでたことあるだろ」
「ああ……」
憶えていた。尚行は小六の一時期になぜか不登校になり、どんな経緯でそうなったのかは知らないが、何ヶ月間かじいちゃんちに預けられていたのだった。
「あのころ、じいちゃんが教えてくれたんだ。誰にも言ってないって秘密を、俺にだけ。それで俺、命を救われた」
命を救われた。物々しい表現に秘密の重みが匂う。
森 絵都(もり・えと)
1968年生まれ。90年、『リズム』で第31回講談社児童文学新人賞を受賞しデビュー。95年『宇宙のみなしご』で野間児童文芸新人賞、産経児童出版文化賞ニッポン放送賞、98年『アーモンド入りチョコレートのワルツ』で第20回路傍の石文学賞、『つきのふね』で第36回野間児童文芸賞、99年『カラフル』で第46回産経児童出版文化賞、2003年『DIVE!!』で第52回小学館児童出版文化賞、06年『風に舞いあがるビニールシート』で第135回直木賞、17年『みかづき』で第12回中央公論文芸賞を受賞と、数多くの文学賞を受賞している。他の著書に『いつかパラソルの下で』『クラスメイツ』『出会いなおし』『カザアナ』『できない相談』など多数。
関連記事