武塙麻衣子「一角通り商店街のこと」6. 立ち飲みジョン
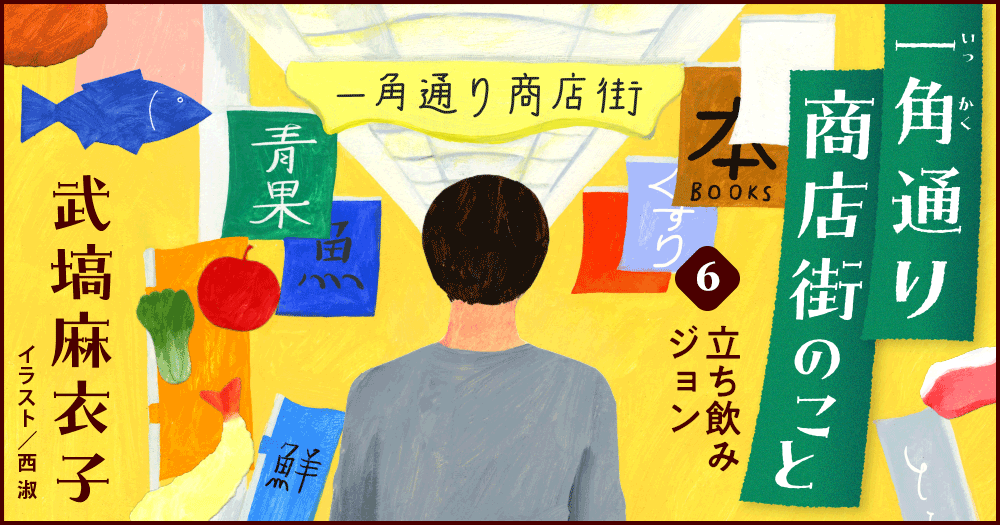
六時過ぎ、雄士は少し緊張しながら立ち飲みジョンの前に立った。ガラス戸越しに中を覗くと、奥に細長く続く狭い店内の真ん中にはどっしりしたコの字型のカウンターがあった。コの字の両サイドにはすでに多くの客が並び、わいわい飲んでいるのが見える。
雄士の母も祖母も酒飲みだ。遅い時間に仕事から帰ってきて台所に直行し、冷蔵庫から取りだした缶ビールを立ったまま美味しそうに喉を鳴らして飲む母(雄士が目をこすりながら起きていくと、おばあちゃんには内緒ね! と子どものような顔で釘をさされた)、気に入っている日本酒を毎日少しずつ飲んで「酒は百薬の長よねえ」と目を細めて言う祖母(中学生になるまで雄士は長を腸だと思いこんでいたのでそれを聞く度にうっすらと気味が悪かった)と一緒に暮らしてきたので、大人が酒を飲むこと自体は特にめずらしくもなかったけれど、こういう場所で何人も集まって談笑しつつジョッキやグラスを空にしていく様子は、映画や小説の中の出来事のようだった。自分など戸を開けた瞬間に百年早いと叩き出されてしまうのではないだろうか。
その時、数人が並んでいるカウンターの左奥からひょいと滝山さんが顔を覗かせた。片手でジョッキを持ち上げ、もう片方の手をこちらに向かってぱたぱたと振っている。
『入っておいでー』
口パクでそう言って、また大きく手を振るので、店内の客たちの目が自然と入口に立っている雄士に向けられ、緊張のあまり唾を飲む。入口に一番近い、コの字の縦線にあたるところで飲んでいた女性が腕を伸ばし、ガラス戸をからからと開けてくれた。
「どうぞどうぞ! いらっしゃいませ。なーんてあたしの店じゃないけども」
店内にどっと笑いが起きる。
「ありがとうございます」
雄士は頭をさげて、彼女の横を通り過ぎた。アルコールと香水の混じった匂いをさせながら、赤ら顔でにこにこ笑っている。母と同じくらいの年齢だろうか。
「失礼します」
声をかけながら何人かの客の後ろを通り、やっと滝山さんの隣の一人分だけ空いたスペースに体を滑り込ませた。店内に流れている音楽は、雄士が生まれるずっと前から活動しているアイドルグループのものだ。
「すみません、お待たせしました」
雄士の言葉に、滝山さんが首を振る。
「ううん、僕もう飲んでたし」
滝山さんのジョッキはほとんど空だ。
「さて、何を飲みますか」
カウンター上にたてかけてあったメニュー表を取って雄士の前に置く。ビール、ハイボール、酎ハイ、カクテル、梅酒、日本酒、焼酎、マッコリ。ざっと見たところ安心して飲めそうなのは梅酒だろうか。でもせっかくの機会だから飲んだことがないものにチャレンジしてみたい。
「あの、ハイボールってなんですか」
「ウィスキーのソーダ割り。さっぱりしていて美味しいよ」
そう言ったあと、滝山さんは、あ、という顔をした。
「これはどう? ジンジャーハイボール。ジンジャーエールでウィスキーを割っているから飲みやすいと思うけど」
「じゃあそれにしてみます」
ほっとした顔で雄士が頷くと、滝山さんが片手をあげた。
「ご注文お決まりですか」
奥の厨房から現れたのはピアスを両耳にびっしり、鼻と口元にもひとつずつつけた金髪の女性だった。もしやこの人がジョン? Tシャツの袖から覗く細い両腕には色鮮やかなタトゥーが入っている。
「ハイボールとジンジャーハイボールをください」
女性店員は頷いてほんの少し微笑むと、滝山さんの空いたジョッキを手にさっと厨房に戻っていった。
「お腹はどう?」
緊張していたため自分が空腹かどうか一瞬わからなかったけれど、壁にびっしり貼られた短冊には綺麗な字で書かれた料理名が並んでいて、その整った字を見ていたら急にお腹が空いてきた。
「空いてます」
「よかった。じゃ、好きなものを頼んでください。僕は板わさ」
「じゃあ、とうもろこしのかき揚げとささみの梅しそ和えをいいですか」
夏っぽいなあと滝山さんが言い、そのタイミングでちょうど運ばれてきたグラスを二人は受け取った。
「お誕生日おめでとう」
「ありがとうございます」
かちんと小さく乾杯すると、入口のドアを開けてくれた女性客とその連れがジョッキを持ち上げた。
「お兄さん、誕生日なの?」
「おめでとう!」
「ありがとうございます。二十歳になりました」
雄士の言葉に店内の客たちが一斉にほおっと声をあげた。
「若いねぇ」
「これからだね!」
「めでたいね!」
皆、好き勝手に親しげな調子で口々に祝いの言葉を述べるとまたそれぞれの会話に戻っていく。
「こういうのもなかなかいいでしょ」
呆気にとられている雄士の肩を、滝山さんがぽんと叩いた。
「それで、久しぶりの実家はどうだった?」
かまぼこにちょいちょいとわさびを載せている滝山さんに訊かれ、雄士は一瞬言葉に詰まり、二杯めのジンジャーハイボールに口をつけた。四ヶ月ぶりに帰る実家をもしかしてものすごく懐かしく感じるのではないかと思っていたけれど、実際はそんなことはちっともなく、暮らしていた頃は狭く思えた玄関や洗面所を妙にだだっ広く、それから少しよそよそしく思った程度だった。
「お兄ちゃんのものが場所とってたんだよ」
ねえおばあちゃん、と胡桃がこともなげに言う。
「だってお兄ちゃんの靴って大きくて汚かったもん」
汚いは一言余計だと思いながら、雄士が取りだしたお土産のクッキーは品川駅限定で発売されているもので、どうしても食べたいから買ってきてと胡桃に念を押されていた。富山には品川からではなく東京駅から帰るのだと説明しても「え、でも同じ東京でしょ? 寄ってくれればいいじゃない」とけろりと言われてしまい、兄としては東京を謳歌しているんだぞと見栄を張りたい気持ちもちょっとあり、じゃあ買っていくと言ってしまったのだ。それを聞くと滝山さんは、おかしそうに、はははと笑った。
「妹さん、喜んだでしょう」
「そうですね。どうかな? たぶん」
首を傾げながら雄士が自分の近くにあった醤油の小瓶を渡そうとすると、滝山さんは、大丈夫と首を振った。
「ジョンのかまぼこはすごく美味しくてね。醤油なしでわさびだけで食べるのが好きなんです」
まあ、ジョンのっていうかここの商店街の笹本かまぼこ店のなんだけどね、と付け加えて一口でぱくりとかまぼこを食べた。
「君もどうぞ」
滝山さんに言われ、割り箸を手に取る。
「あの、そういえば」
かまぼこに箸をのばしながら、雄士はなるべく自然に聞こえるよう、今、たまたま思いついたかのように切り出した。
「滝山さんて、なんのお仕事をされているんですか」
ちょうどとうもろこしのかき揚げの皿を運んできたピアスの店員が驚いた顔で雄士を見た。
「お兄さん、知らないの?」
「え?」
隣の滝山さんを振り返ると、なんともいえない顔をしている。
「え?」
訊いてはいけないことだったのかと不安になってもう一度店員を見ると、
「この人は何百人も殺してますよ」
小声でそれだけ言って彼女はさっと別の客の方へ行ってしまった。
「え、お医者さんですか」
咄嗟の雄士の言葉に、滝山さんが目を丸くする。
「いやいや、医者が何百人も殺してちゃまずいでしょう」
それじゃ一体なんなんだ。
「僕、ミステリー小説を書いてるんですよ」
ネムノキのママさん、僕のこと何も言ってなかった? と笑いながら訊かれ、頷くと滝山さんは更におかしそうに笑った。
「良かったら今度ネムノキに新刊を持っていくので読んでみてください」
それから片手をあげ、厨房に向かってこう言った。
「マスター、ジョンください」
ジョン、ください?
もしかすると僕はかなり酔っぱらっているのかもしれない。
「はいよ!」
マスターがジョンなわけではなく、注文すると出てくるのがジョン。
「水ももらおうか」
滝山さんはすっかり上機嫌だ。ぽかんとした顔の雄士の肩をぽんぽんと叩いて、
「ジョンは美味しいよ」
と言った。気付くと店内の客はあらかた入れ替わっていた。さっきまで向かい側にいた男性客たちの場所にはいつの間にか女性が三人。入口で雄士のために戸を開けてくれた女性ももういない。音楽は、と耳をすませてみると、それは変わらずさっきと同じアイドルグループのものだった。季節外れな冬の恋の歌が明るく頭上から降ってくる。なんだか頭がふわふわしてきた。
「先日は、本当にごちそうさまでした」
いつもと同じ時間にやってきて、いつもと同じミニグラタンのセットを注文した滝山さんのテーブルに水のグラスを置いて、雄士は頭をさげた。
「うん、楽しかったね」
滝山さんはにこにこしながら、
「あ、これ」
と一冊の本を取りだした。
「もし良かったら読んでみてください。僕の本です」
「ありがとうございます!」
立ち飲みジョンのマスターは、ジョンという名前ではなくこ松本さんだった。その松本さんが作ってくれたジョンというのは、薄切りにした肉を小麦粉と卵につけて焼いた韓国料理のことで、松本さん曰く、子供の頃に初めて自分で作った料理がジョンだったから店の名前もジョンとのこと。とても美味しかった。
「ジョン、美味しかったですね」
雄士がそう言うと、滝山さんが深々と頷いた。
「また今度行きましょう」
はい、ぜひと返事をしながら、いつか朝九時のジョンで滝山さんと飲んでみたいと雄士は思った。
1980年神奈川県生まれ。『諸般の事情』『驟雨とビール』などのZINEを発表後、2024年『酒場の君』(書肆侃侃房)で商業出版デビュー。
Xアカウント@MaikoTakehana
- 1
- 2






