武塙麻衣子「一角通り商店街のこと」6. 立ち飲みジョン
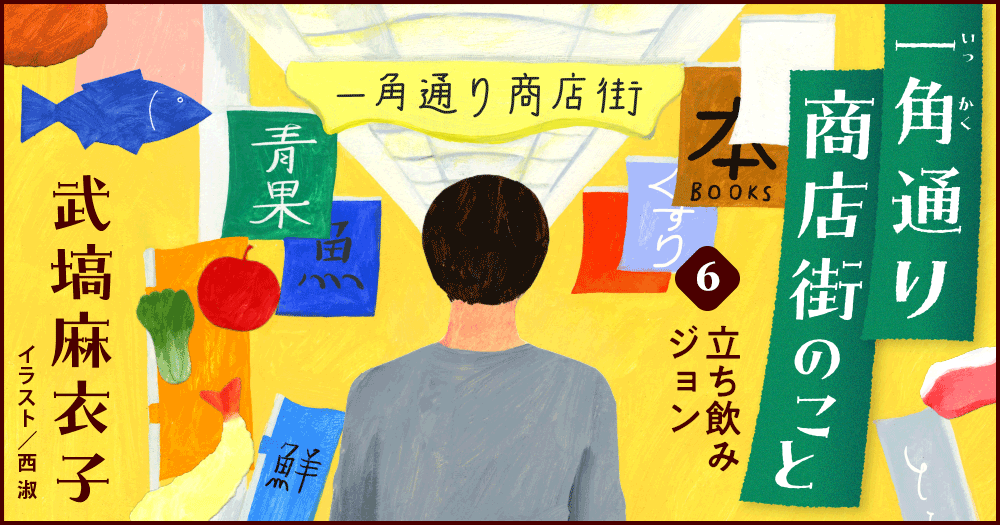
〜大学生の雄士とごはんの話〜
6. 立ち飲みジョン
モーニングを食べに来ていた客の波がすっと引き、次に忙しくなるランチタイムまでにポテトサラダを作ろうとした葉子さんが、冷蔵庫を開けて一言「ない!」と叫んだため、雄士は一角通り商店街の青果店フレッシュカジイまで、きゅうりを買いに出た。商店街に並ぶ様々な店にもだいぶ慣れてきたけれど、まだ入ったことのない店というのがいくつかあって、そのひとつがたとえばちょうどさっき通り過ぎた立ち飲みジョンだ。店の前を通る度にジョンて誰なんだと思う。ガラス張りの店なのでじっくり見れば店内の様子はわかりそうだが、いつでも客がいるのでそのまた向こうで立ち働いているであろうジョンとおぼしき店員の姿はよく見えない。おもてに出ている看板によれば立ち飲みジョンは朝九時から営業している。一体どんな人が午前中から酒など飲むのだろうと最初は不思議に思ったけれど、やって来るのは夜勤明けの人かもしれないし、久しぶりの休日で朝からとにかく飲みたいという人だっているだろう。アルバイトを始めてからそういうことの想像が少しできるようになったと思う。何にせよ需要があり、ジョンが朝九時から営業しているのは確かなのだ。いつか勇気を出して行ってみよう。先週、富山に帰省していた間に、雄士は二十歳になったのである。
きゅうりのついでにマスターに頼まれたトマトを買うと、フレッシュカジイの店主がレモンをひとつぽんとくれた。
「これ、ちょっと傷がついちゃって売り物にはならないけど無農薬で皮まで食べられるやつだから雄ちゃんにあげるよ」
「わあ、ありがとうございます」
お礼を言い、雄士は来た道を早足で戻った。途中ですれ違った数人の子供たちはとてもよく日焼けしていてビニールバッグを手に足取りも軽く、この夏休みたっぷり遊んだことが一目でわかる。気の早い子は、首からゴーグルをさげてきゃっきゃと笑っていた。きっとあの短パンの下には全員もう水着を穿いているに違いない。
「プール、今年は行ってないな」
四日間の帰省以外、雄士はこの一ヶ月ほとんど喫茶ネムノキでバイトしていた。来月大学が始まってからも続けさせてもらう予定だが、さすがに夏休み中と同じペースでシフトを入れるわけにはいかない。そのことを残念に思うほど、雄士は喫茶ネムノキでの仕事が気に入っていた。働き始めてすぐの頃は、入れ替わり立ち替わりくるくるやって来る商店街や近所に住む老人たちの見分けがまったくつかずに苦労した。雄士には、彼らは本当に驚くほど似て見えたのだ。髪型とか背の高さとか持ち物なんかもすべて。けれど、葉子さんもマスターも店にくる人たちのことを「こんにちは、守下さん」とか「いらっしゃいませ、千香子さん」というふうに必ず名前で呼ぶので、雄士はそれを聞き逃さないようにして、エプロンのポケットに入れたノートに後からいちいちメモをとった。彼らが次に来店した時に雄士が名前で呼びかけると、みんな最初は驚き、それからくしゃくしゃっと笑顔になる。名前を呼ぶと親しみが湧いて彼らにまた会うことがこちらも楽しみになるのだった。なんだか突然たくさん親戚が増えたみたいで、お正月ともなればみんながお年玉をくれそうな勢いだ。
そんな常連客たちの中で、滝山さんは初めから目立っていた。週に二、三度、忙しいランチタイムが過ぎた頃にふらりとやって来て必ずミニグラタンとバゲットのアイスティーセットを注文。背が高く痩せていていつもにこにこしている。どんなに暑い日でも長袖のシャツを着て、必ず本を一冊持ってきて食後に三十分ほど本を読む。読書の邪魔になってはいけないと最初はあまり話しかけなかったけれど、その独特な雰囲気が雄士には好もしく感じた。滝山さんの年齢不詳な感じも面白かった。もしも四十代ですよと言われれば、そうですかと思うだろうし、実は五十代なんだと教えられたらなるほどそういうものかと納得してしまいそうだ。しばらく会話らしい会話はなかったけれど、ある時、滝山さんが持ってきた本が気になって雄士が声をかけた。
「それ、文庫版があるんですね」
滝山さんが顔を上げた。雄士に話しかけられたことが心底意外だったのかきょとんとしている。
「これ読んだことあるの?」
滝山さんが読んでいたのは森崎和江『能登早春紀行』だ。雄士は頷いた。
「僕の祖母が石川の出身なんです。祖母の愛読書です。僕も好きで」
滝山さんはへえと言い、それから、指先でとんとんと本の表紙に触れた。
「冬に鳴る雷、僕も聞いてみたいなあ。金沢に行ってみようかな」
のんびりそう言ってミルクをたっぷりいれたアイスティーを飲む滝山さんをなんだか変わった大人だなと雄士は思った。
買ってきたきゅうりとトマトを厨房に届けてからのランチタイムは大忙しだった。なぜか、ナポリタンを注文する人がひっきりなしに現れたのだ。滝山さんは例によって店が少しすく二時すぎにやって来ていつもと同じミニグラタンをのんびりと食べ、また本を読んでいた。とても分厚かったので、どんな本だろうとちらりと表紙を見ると『人喰い』と大きく書いてあった。
「今日読んでいらっしゃったのはどんな本ですか」
お会計の時に聞いてみると、滝山さんは雄士が興味を持ったことが嬉しかったのか、いつになく饒舌に答えてくれた。
「アメリカのロックフェラー家って知ってますか? その一族の当時まだ二十三歳だった御曹司がニューギニアで失踪してね。それでまあいろいろあるんだけど、カニバリズムというのは一見センセーショナルだけど実は文化としてなかなか興味深いんだよ」
「カニバリズムですか」
よくはわからなかったけれど、説明してくれる滝山さんの目がキラキラしているので、あとでノートにメモしておこう。
「二十三歳で失踪か……。あ、そういえば僕、先週二十歳になったんですよ」
「そうなの?」
何かとてもめずらしいものを見つけたかのように目を丸くすると、じゃあお祝いに一杯ご馳走するよ、と滝山さんが言った。
「僕は六時頃、仕事が終わると思うんだけど、そのあとでも良ければ商店街の店でも行きますか? 立ち飲みジョンて知ってる?」
それから、はたと気がついたように、
「ああ、でもお酒は飲める口?」
と続けたので、雄士は慌てて頷いた。飲めるといっても、まだレモンサワーと梅酒しか飲んだことはないけれど。でも、これでついにあの立ち飲みジョンに行くことができる。
「今日、滝山さんと飲みに行くことになりました」
一息ついてアイスコーヒーを飲んでいる葉子さんにそう伝えると、
「あら、いいじゃない!」
と、葉子さんは笑顔になった。
「滝山さんてぱっと見、素敵よね。喋るとほわーんとしててゆるキャラみたいだけど」
確かにほわーんとはしている。でもあんなにひょろ長いゆるキャラっているだろうか。
「そういえば滝山さんてお仕事は何をしている方なんですか」
葉子さんが急に真顔に戻ってきっぱりと言った。
「詳しいことは本人に訊いてちょうだい」
ほわーんとしているけれど、滝山さんは謎めいている人だ。
- 1
- 2






