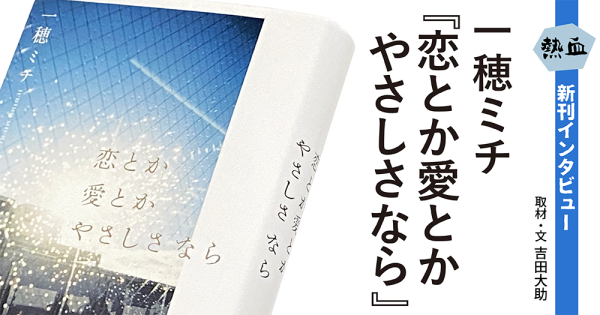一穂ミチ『恋とか愛とかやさしさなら』◆熱血新刊インタビュー◆
他者を諦めない
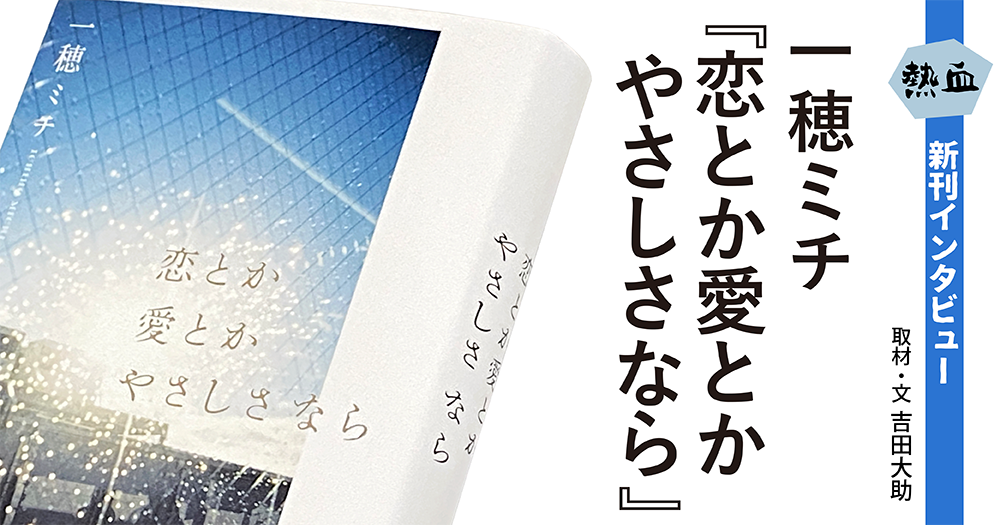
出発点はシンプルだった。
「恋愛小説で短編を、というご依頼をいただいたんです」
恋愛というテーマをどう扱うか、考えあぐねていたそうだ。すると、意外なところから突破口が開かれた。
「たまたま辻村深月さんの『噓つきジェンガ』という短編集を読んでいたら、息子の中学受験で裏口入学の誘いに乗ってしまって悩む母の話があったんです(「五年目の受験詐欺」)。親としては息子の頑張りを信じて受験に送り出すのが一番いいのはもちろんなんだけれども、受験に落ちたらこの子はどんなに悲しむだろうか、と。お母さんがぐるぐる葛藤した結果、思いがけない展開を迎えるんですが……物語としての面白さと共に親心の機微がとても繊細に描かれていて、とてもせつない話でした。あまりに心を動かされたので、辻村さんに感想の手紙を書こうと思ったんですね。その手紙を書いている中でふっと思いがけずに出てきたのが、〝なぜ信じるということは、こんなにも純度を求められなくてはいけないのか〟という言葉でした」
好きという感情であれば、「少し好き」や「少し嫌い」という使い方も許容される。けれど、信じるということに関してはそれが許されない。
「例えば、人が半信半疑という言葉を使うのは、本当は疑っている時ですよね。そもそも、〝半分信じている〟って状態は存在しないと思うんです。ほんの少しでも疑いがあったなら、あなたのその信じるという思いは本物ではないですよねとジャッジされてしまう。信じるということだけに求められる純度や潔癖さをテーマに、恋愛小説を書いてみたいと思ったんです」
恋愛のシチュエーションとしては最悪なところから始めてみたい
物語の幕開けは、カメラマンの関口新夏が恋人の神尾啓久にプロポーズされ、「はい」と即答する場面だ。〈啓久となら、何があっても人生を楽しめる気がする〉。その翌朝、啓久の母親から電話がかかってくる。啓久が盗撮で警察に捕まったのだという。初犯であり罪を素直に認めていることから、逮捕はされず、被害者との示談の話し合いへとフェーズは移っていったのだが……。〈そりゃ、お母さんは嬉しいよね。わたし、何で嬉しくないんだろ。(中略)じゃあどうするの、別れる?/もし、啓久のほうから「別れよう」って言ってきたら?〉。なにせ5年も付き合い、結婚を約束した仲なのだ。終わりのない自問自答を繰り返す日々が始まる。
「恋愛のシチュエーションとしては最悪なところから始めてみたいと思った時に、この設定に辿り着きました。もしも結婚していたり子どもがいたりしたら、一緒に頭を下げに行くとか、別れるのとは違う方向に進むかもしれないなと思うんです。でも、婚約者という立場は本当に微妙で、家族という意味では〝非正規雇用〟状態。自分の気持ちひとつで、別れるかどうかを決められるんですよね」
盗撮は衝動的な行動だったと反省や言い訳を口にする啓久はもちろん、彼の両親は、別れないでほしいという願望を隠さない。その反対に、啓久の姉・真帆子は、弟がやったことは性加害であると本人に突きつけ、新夏に対しては「まさか、別れないなんて言わないよね」という圧をかけてくる。新夏の親友の葵の意見は、ドライだ。「……正直、『こんなことで』って感じしない?」「愛情って、総合的な判断のことでしょ」。
新夏自身も決して完璧な人間ではない、という描写が要所要所で入り込んでくる点がフェアだ。他者のさまざまな価値観に触れることで起こる、新夏の内面の振幅を小説は追いかけていく。
「新夏を書く時に決めていたことは、最終的な判断を他者に委ねないということでした。自分で答えを出したいからこそ、〝あの人の言うことは分かる〟というふうに思いながらも、悩んで悩んで悩み抜く。一方で、啓久を許したら、女という自分が属する大きなコミュニティに背を向けてしまうんじゃないか、という心細さも彼女の中にはあるんです」
どこかのタイミングで、この物語の出発点となった「信じる」という行為についての思弁が現れる──そのことだけは決まっていたが、新夏が最終的にどんな決断をするかは分からないまま書き続けていったそうだ。
「何をどう選んでも、幸せとは言いがたい結末になるんだろうなとはうすうす分かっていました(苦笑)。もやもやした読後感になっていると思うんですが、答えの出ないことを答えの出ないまま書くということを、一度やってみたかったんです」
分かりやすい救いが描かれていないからこそ、読んでいる間はもちろん、読み終えた後も強烈なフィードバックが読者に巻き起こる。もしも自分が同じような状況に陥ったらどうか、身近な人間が当事者となったら自分はどう振る舞うだろうか……という想像が尽きないのだ。その感触をさらに高めてくるのが、2編目の存在だ。実は、本作は2本の中編で構成されており、2編目では啓久が主人公=視点人物となっている。
「恋愛小説というテーマを私にくださった編集さんから、次は自由なお題で短編をとお声がけいただいた時に、啓久のことを掘り下げてみたいと思いました。時間が経つごとに、犯した過ちの意味が重くなっていくものではないかと思ったんです。示談になってラッキーで済ませている人もいるかもしれないんですけど、彼は根が悪い人ではないからこそ、ずっとそのことを考えずにはいられない。そういう人だったからこそ、新夏もあんなに悩んだんですよね。やったことは取り返しがつかない、なんとか折り合って生きていかなければいけない。そんな中でも小さな光があれば……と、祈るように書き進めていきました」
〝あっ、分かる!〟と瞬発的に思うものは果たして共感なのか
「より的確な言葉を探して、まだ違うんじゃないか、この言葉ではないんじゃないかと、個々のエピソードの解像度を上げていく作業に時間をかけました。中編2本という構成も初めてでしたし、分からないことを分からないまま書くというやり方も初めてで、どう受け入れられるかという怖さもあるんです。でも、きっと5年後、10年後に振り返ってみたら、自分という書き手の一つのマイルストーンというか、この作品が大きなポイントになったと感じると思います」
作中でフォーカスされている、ある言葉が印象に残った。「生理的に無理」。〈「大嫌い」を上回る最上級の拒絶表現〉という解説には、膝を打った。
「思考停止の言葉ですよね。生理的に無理と言われてしまったら、言われたほうも納得しなければいけないというか、相手に理解してもらうことを諦めなければいけない。でも、自分と通じ合えるものって本当にひとつもないですかってより分けていく作業の中で、共感って生まれるんじゃないかなと思うんです」
この作家にとって共感の一語は、一般的にイメージされる共感とは違う。
「最近、特にエンタメ小説においては、評価軸の一番太いところに共感がきていると思うんです。共感自体を否定するつもりは全くないんですけれども、共感できる・できないという言葉が印籠のように使われることには違和感があります。自分の中にストレスなくスルッと入ってきて、〝あっ、分かる!〟と瞬発的に思うようなものだけが共感なのかしらと私は思ってしまうんですよね。初めから自分の側にあるもので反応するのではなく、すんなりとは飲み込めないものを、なんとか嚙み砕いて消化したいって思うところから共感は始まるんじゃないでしょうか」
あえて共感しづらい題材にチャレンジしてみたい、という気持ちもあったのだという。
「分かり得ない人の中にも〝自分と同じこの時代に生きて息をしている人なんだな〟と思うところって、目を凝らして探せば絶対に見つかるはず。その気づかれにくい小さなものを見つめることのほうが、小説の役割としては大きいんじゃないかなという気がします」
その意味での共感を、本作は──いや、一穂ミチという作家は書き続けている、これからも書き続けようとしているのだ。
「共感って、他者を諦めないっていうことなんですね、私の中で。他者を諦めないっていう行為は、自分が傷つくことも多いんですよ。あぁ、あの人の嫌いな部分と自分が繫がっているところを見つけちゃった、みたいなことでもあるわけですから。でも、自分が他者を諦めなければ、自分のことも誰かは諦めないでいてくれるんじゃないかと思えるようになる。それは家族や友達や恋人がいるいないに関係なく、孤独ではないってことになるんじゃないかと私は思うんです」
プロポーズの翌日、恋人が盗撮で捕まった。カメラマンの新夏は啓久と交際5年。東京駅の前でプロポーズしてくれた翌日、啓久が通勤中に女子高生を盗撮したことで、ふたりの関係は一変する。「二度としない」と誓う啓久とやり直せるか、葛藤する新夏。啓久が〝出来心〟で犯した罪は周囲の人々を巻き込み、思わぬ波紋を巻き起こしていく。信じるとは、許すとは、愛するとは。男と女の欲望のブラックボックスに迫る、著者新境地となる恋愛小説。
一穂ミチ(いちほ・みち)
2007年『雪よ林檎の香のごとく』でデビュー。『イエスかノーか半分か』などの人気シリーズを手がける。21年刊行の『スモールワールズ』が本屋大賞第3位。同作で吉川英治文学新人賞を受賞し、直木賞候補になる。22年刊行の『光のとこにいてね』は本屋大賞第3位、キノベス第2位。同作で直木賞候補になり、島清恋愛文学賞を受賞。24年『ツミデミック』で第171回直木賞を受賞。他の著書に『パラソルでパラシュート』『うたかたモザイク』など。