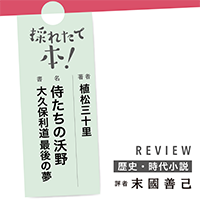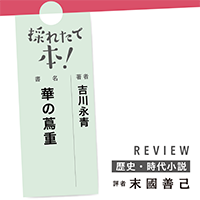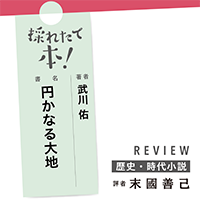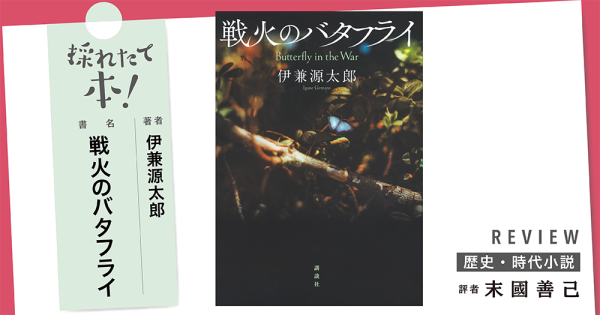採れたて本!【歴史・時代小説#29】
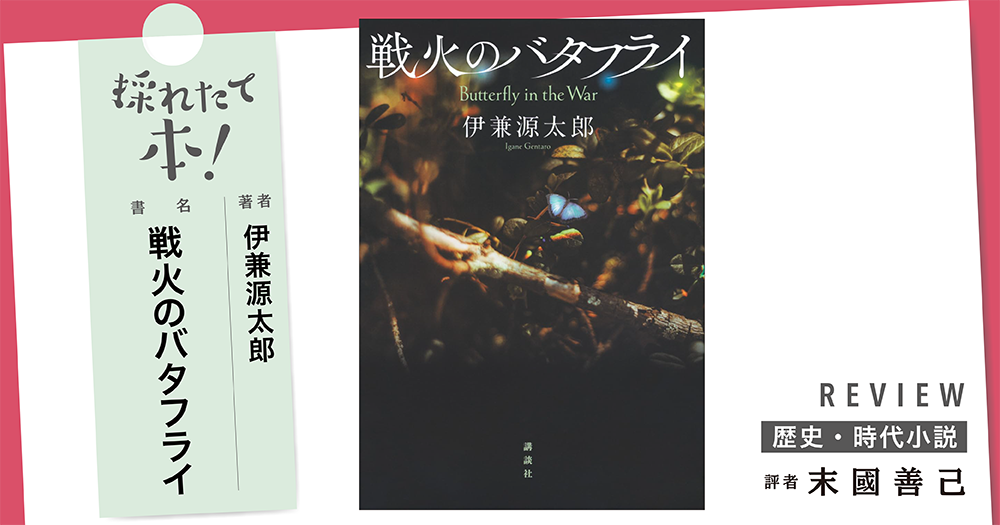
昭和が続いていたら100年、敗戦80年の節目となる2025年に刊行された『戦火のバタフライ』は、先の大戦と日本の戦後とは何かを問い掛けている。
1945年。医薬品が底をついた南方戦線で懸命に傷病兵の治療を続ける小曽根軍医の下で衛生兵をしていた尾崎は、多くの戦友を亡くしたが小曽根から託された切り札を使って生き残る。
小曽根の妹さくらは、3月10日の東京大空襲で、双子の妹の一人である雅、担任教師で兄の実質的な婚約者のつる、幼馴染みの勝男ら多くの家族、友人を亡くした。
復員した尾崎は、小曽根の遺品をさくらたちに渡し、京都帝大時代の同郷の先輩の誘いで第一復員省に入り、それから一貫して戦後補償を担当することになる。日本の占領統治が終わりに近付くと、軍人恩給復活の機運が高まる。民間の戦争被害者も補償すべきと考える尾崎は、同じ志の鏑木と相談し、軍人嫌いの有力議員・直江の協力を取り付けるが、医学界を動かそうとしていた鏑木が急死。政府の強い意向もあり民間補償は見送られた。
民間補償の実現を目指す尾崎は、誰かに監視され脅迫状も届く。自分を狙う勢力と、鏑木が殺された疑惑を追う尾崎が戦後史の闇を浮かび上がらせる展開は、優れた社会派推理小説になっており、周到な伏線が回収される終盤は本格ミステリとしても面白く、意外すぎる黒幕の正体には衝撃を受けるのではないか。
さくらは、名古屋で民間人戦争被害への補償を求める署名運動を始めた女性に共感し、東京で同じ活動を行い、その輪は徐々に大きくなる。やはり民間人への補償を諦めていない尾崎は、直江の地盤を継いで議員になった元秘書の則松やさくらとも連携を取りながら民間人への補償を実現させようとする。だが、補償金を増やしたくない政府、旧軍の出身者が多い官僚組織、旧軍人が票田になっている議員、社会の無関心などが壁になり、何度もはね返されてしまう。
戦争で亡くなった人たちの遺志を受け継ぐ尾崎とさくらが民間人の戦災補償を求める物語は、いまだに旧軍人だけを補償し、民間人には戦時中と同じ忍耐を強いている現状を明らかにし、戦後がまだ終わっていないことを教えてくれる。
政府与党の方針に逆らって全戦争被害者への補償を求める正論を主張する尾崎は、理性や合理性よりも精神論、根性論を重んじ、長いものに巻かれる体質で当初は反対していても決まったら逆らわない戦後の日本人が、戦争に突き進んだ戦前と同じメンタリティだと思っている。日本人が自分の頭で考えるようになって欲しい尾崎は、どれだけ不利になっても掲げた旗を降ろさないが、現代社会に尾崎ほどの信念を持って活動している日本人は少ない。自立した個人が増えるのが真の戦後であるなら、その意味でも日本人はいまだに戦前を生きているのかもしれない。
評者=末國善己