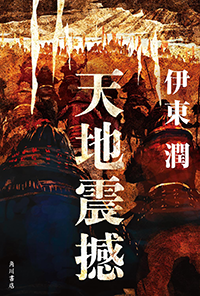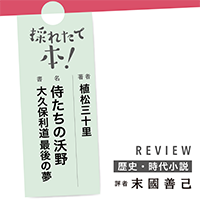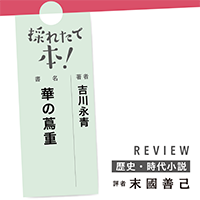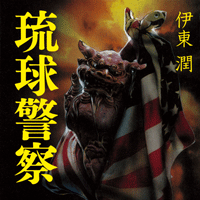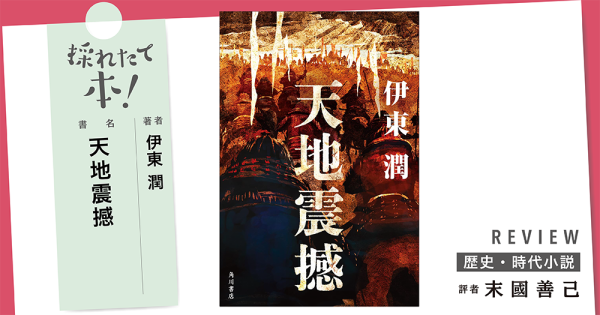採れたて本!【歴史・時代小説#28】
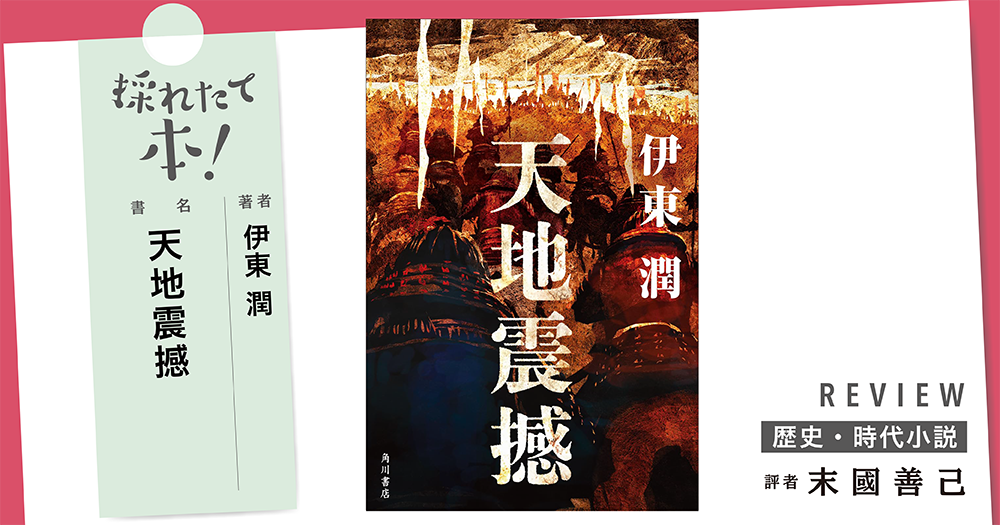
長篠の戦いを描いた『天地雷動』、北信濃の国衆の視点で第4次川中島合戦までを追った『吹けよ風 呼べよ嵐』、徳川家康と毛利輝元の対立として関ヶ原の合戦を再構築した『天下大乱』など、最新の歴史研究を使って戦国時代の有名な合戦を今までにない角度で切り取ってきた伊東潤の新作は、家康と武田信玄が激突した三方原の戦いを取り上げている。
体調不良が続き天から与えられた時間が短いと悟った信玄は、人生の仕上げとしてほぼ全軍を率いて西上を開始した。一方、三河・遠江二国の大名に成長したが兵力では信玄に及ばない家康は、同盟者の織田信長に援軍を要請する。
信玄の軍略を恐れ、兵は少なく、信長の意向も無視できない家康は、服部半蔵らの報告を聞き、信玄はどのルートを通るのか、この城を囲んだ意味は何かなどを予測して対策を練る。信玄は家康の思考を読んで、それを上回る一手を繰り出すが、西上戦の目的を達成するため兵をできるだけ温存する必要があり戦略の幅が限られるなどの制約があった。
それぞれに制限がある信玄と家康が、好手を増やし悪手を減らそうと知恵を絞るだけに、戦いの火ぶたが切られる前から名棋士が盤を挟んで長考しているようなサスペンスがあり引き込まれる。
三方原の戦いには、謎が多い。その最大のものは、なぜ寡兵の家康が浜松城に籠城せず信玄の大軍に野戦を仕掛けたかだろう。これまでは、家康が浜松城を無視して進む信玄に怒って出陣した、またはこのバリエーションで、家康を怒らせる信玄の策略に吊り出されたというのが通説だった。これに対し著者は、徳川の偵察隊が武田軍との遭遇戦になった一言坂の戦い、兵を損ないたくない信玄が天然の要害に守られた二俣城を攻めた二俣城の戦いの勝敗などによって家康の状況が刻々と変わり、主君に意見する家臣団、いつ離反するか分からない国衆、同盟者ではあるが国力の差が大きく実質的に逆らえない信長といった諸勢力の動向によって城を出ざるを得なくなったとしている。その解釈には説得力があり、戦国史に詳しい人ほど驚きが大きいのではないか。また中間管理職的な家康の悲哀には、共感する読者も少なくないように思えた。
信玄が西上を行った理由にも諸説あるが、著者はその理由を伏せたまま物語を進めていく。これが先を読ませる圧倒的な駆動力を生み出し、戦国武将の業を浮かび上がらせる真相も興味深かった。
卓越した軍略で家臣からも国衆からも高い支持を得ている信玄だが、母方の諏訪家に入れていた勝頼を後継者にしなければならなくなっていた。信玄の軍略を知らない勝頼に、短期間で必要な知識と経験を教えなければならない信玄の苦労と不安は、どのようにベテランの知識、人脈、技術などを若手に継承させるかが議論されている現代日本と重なるだけに生々しく感じられるはずだ。
評者=末國善己