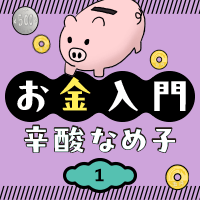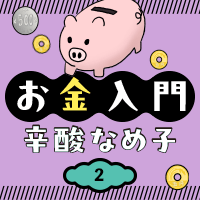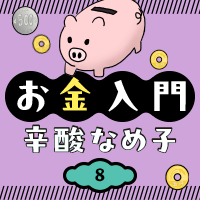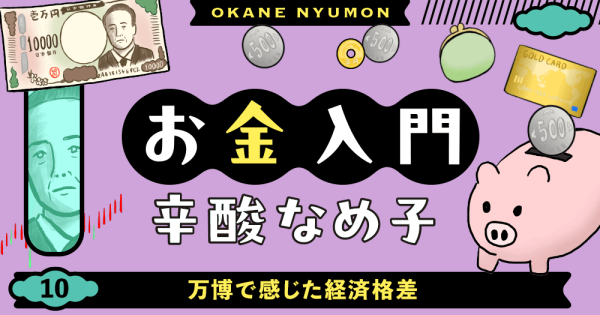辛酸なめ子「お金入門」 10.万博で感じた経済格差
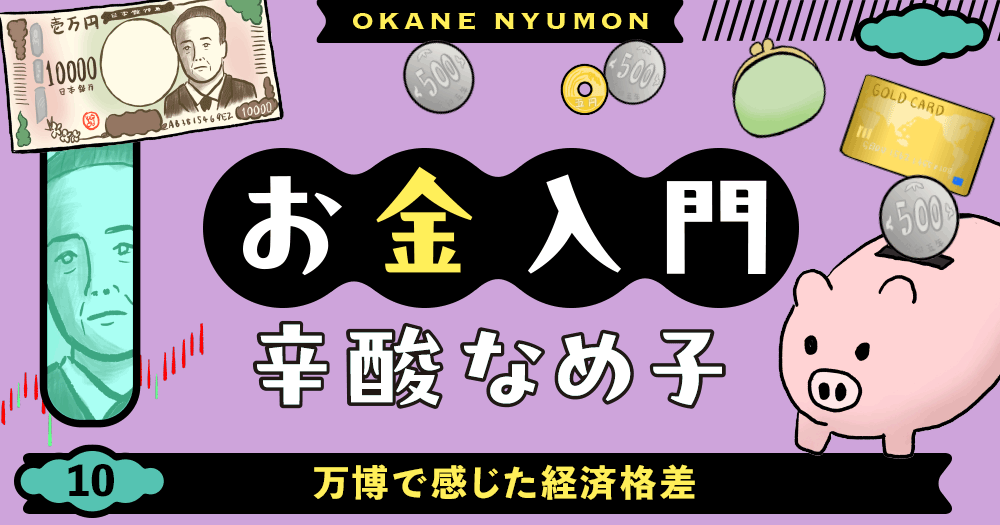
「予約システムが複雑」「大屋根がゆがんでいる」「雨と強風の中、入場に何時間もかかった」「パビリオンはどこも長蛇の列」「食事が高額」「2億円トイレが使用禁止」「パビリオンが工事の遅れでオープンできていない」……行く前からネガティブ情報が報じられていた大阪・関西万博。予算に関しては諸説ありますが、総額7600億円もの巨額の費用がかけられたとか、関連費を含めると10兆円という説もあります。行かないでただ批判するよりも、実際行ってみて、それだけお金がかかっている一大イベントを体感した方が、得られるものがありそうです。世界中の国々が多額の予算をかけて趣向をこらしたパビリオンを建設するので、並んでいて入れなくても建築を鑑賞するだけで楽しめます。新幹線の交通費も、億や兆単位のお金が飛び交っているイベントに行くと思えば微々たるもの……。ということでプライベートで大阪・関西万博に行って参りました。そこで感じたお金にまつわるエピソードを綴ります。
大阪・関西万博は、通常の一日券が7500円、平日券が6000円ですが、開幕後の4月13日から26日の間に入場可能な前売りチケットは4000円から。4月13日から7月18日までの期間に一回入場できる前期券は5000円からです(すべて大人料金)。時期や買い方によって値段が変わるので要注意です。でも、大阪在住の友人は「結構チケット配ってるらしいし、いつかもらえる気がするので、タダで入れるなら行こうかな」と言っていて羨ましかったです。そのぶん、税金を払っているのだと思いますが……。東京から行くのには、新幹線やバスなどの交通費、泊まりの場合は宿泊費も必要なので、5万円前後はかかります。チケットをオンラインで買ったり、バスを予約するのにもアプリが必要だったりと、デジタル系に弱かったら大阪・関西万博には行けません。愛・地球博はもっと気軽に行けたような記憶が……。
桜島駅からシャトルバスに乗って、人工島「夢洲」の会場へ。時間指定の人だけ集まっている感じで意外と空いています。入場時間を待っている間、どこからともなく民族音楽が聞こえて来て癒されました。ただ、バスは西口発着なのに間違って東口の入場券を買ってしまっていました。入り口の係員に「次からは気をつけてください」と言われましたが、なんとか西口から入場。荷物検査や金属探知機など空港並みの厳しさで、後ろの高齢女性はユンケルの瓶を持っていたのが「瓶、缶類は持ち込み禁止です」と言われ、その場で飲み干していました。歩いて疲れたら飲もうと思っていたと思われますが……その後大丈夫だったか心配です。
パビリオンの事前予約や抽選に関しては、2か月前抽選、7日前抽選は予約に失敗したので、3日前までの予約でオーストラリアパビリオン、当日入場してからの予約で日本館を予約できました。公式アプリは使いづらく、すぐタイムアウトしてしまうので毎回ログインしなおし、そのたびにワンタイムパスワードも入力。スマホの電池がどんどん消耗していきます。無料Wi-Fiもありますが、会場内では通信データ容量も消費。
西口から入ってまず並んだのは評判のイタリアパビリオン。レオナルド・ダ・ヴィンチのドローイング、日本初公開のファルネーゼのアトラス像、 カラヴァッジョ「キリストの埋葬」などの本物が展示されているという豪華すぎるパビリオンです。午前中だったので40分ほど並んで入れて、間近で至宝を拝見できました。プライスレスな体験で、イタリアへの好感度が高まりました。ちなみに他の国のパビリオンは、古代の貴重な遺物を展示していると思ったら複製だった、というケースも。万博ではその国の日本への思いを測れます。素晴らしい体験はそのまま国の好感度につながるので、経費は宣伝費用といっても良さそうです。
シンガポールパビリオンは、赤い球体をした外観で目立っていました。中に入ると天井から紙でできた動植物や自然のモチーフが吊るされていて、SDGsや環境保護、より良い未来に向けたロードマップに関する展示が添えられていました。願い事を書いて空に届けるインタラクティブなデジタルアートなどセンス良くまとまっています。ショップに立ち寄ったら、そんなに大きくないクッキー缶が8800円もしてシンガポールの物価の高さを実感。カフェのドリンクもアルコールは1500円以上していました。
モナコパビリオンは、シルバーの円筒形の建物に入ったら、そこは別館で、海の環境保護などについての展示が行なわれていました。「アルベール2世公殿下は環境保護の第一人者」だそうです。王族の写真や動画が流れると説得力が増します。
スペインパビリオンは、前面はグリーンからブルーの階段状の建物で、おしゃれな色彩センスがさすがです。階段を登りきった上の階が死角になっており、一見、行列がないように思えました。階段をかなり登ってたどり着いたら実は行列があったという……でももう登り降りしたくなくてそのまま並ぶしかない感じです。展示の内容は、また海洋や自然などの環境保護。そして自国自賛のメッセージが流れる部屋でしめくくられました。「スペインは美しい」「スペインは素敵」「スペインは光」など清々しいほどです。陽キャ感にあふれていました。
万博なので、地球環境に取り組んでいる、というテーマのパビリオンが多いですが、歩いて疲れている上に、意識高い系の展示ばかりで正直脳が疲れます。それぞれの国の真剣な取り組みはわかったので、もう小難しい展示はあまり見たくない、という心境に。
サウジアラビアのパビリオンも、自国の芸術、持続可能な環境保護、といった内容がメインでしたが、建物のゴージャス感に感動して気分転換になりました。ハリボテではない、本物の石造りの高い建物が複数建ち並び、庭にはヤシの木、そして暑さ対策のミストも出ていました。やはりオイルマネーで潤っているのでしょうか。テイクアウトのコーナーではサンドイッチ1600円、バナナケーキ1000円、スパイスをきかせたサウジコーヒーがエスプレッソくらいの量で700円、と、まあまあ高いですがゴージャス感漂う建物の余韻に浸りたくてサウジコーヒーをテイクアウト。お土産では小さめのピューマのぬいぐるみが8800円でした。
パビリオン間を移動中、目に入った食べ物屋さんの看板。「神戸牛すき焼き丼 冷やし豆乳担々セット4730円」「究極の神戸牛すき焼きえきそば3850円」「プレミアムツリーパフェ4200円」など……。インバウンドの人には安く感じられるのでしょうか。でも、フードトラックや、普通に安い飲食店もたくさんありました。予約して入ったのは、くら寿司で、そこでは世界各国の料理が、小さいながら一皿320円でオーダーできました。ただ説明が少なくて、写真と名前を見てもメニューの詳細が不明です。「ウムアリ(サウジアラビア)」、「ロパビエハ(キューバ)」、「マケロ(カメルーン)」、「アホ(パラオ)」など、気になったけれど頼む勇気がありませんでした。結局なんとなくわかる「セビーチェ(ペルー)」、「コーヒーゼリー(グアテマラ)」をオーダー。
午後になると会場は混雑を増していき、中国やアメリカ、オーストリア、フランスなど人気のパビリオンは長蛇の列で予約なしではとても入れません。ショップだけチェックしたパビリオンもありました。真っ赤な低層の建物が並ぶオマーンのパビリオンのショップに入ったら、フランキンセンスキャンディが一袋6300円もしました。
そんな中、すぐ入れたのはアラブ首長国連邦パビリオン。全面ガラス張りの建物で、かなり広いのですが、中にはナツメヤシの木でできたオブジェが多数林立しています。アラブ首長国連邦にとって重要な資源であるナツメヤシがテーマ。アラブ首長国連邦は、ドバイやアブダビが有名ですが、全部で7つの首長国で構成されていることを学びました。それぞれの国の砂漠の砂が展示されていました。海に近くてカルシウムが多い、山に近い、といった地理的な要因で砂の色が変わるとのこと。ドバイのリッチなイメージを裏切らないゴージャスなパビリオンでした。中東のパビリオンは経済力を感じさせるところが多いです。
ショップだけ行ったマレーシアのパビリオンでは、おそらくこの会場で最も安い土産を発見。やおきんの駄菓子「焼たら」15円です。実はマレーシアで生産されているそうです。これを万博土産として友人に渡したら……説明が難しいです。
オーストラリアパビリオンは、オーストラリアの自然の樹々と動物の映像、星空のプロジェクションマッピング、宇宙や深海の映像など没入感が得られる演出でした。何よりSDGsがどうこうという文字の展示がなくて、ただ大自然の素晴らしさを疑似体験できるのが良かったです。お勉強系の展示が多い中、脳が休まりました。
ウクライナパビリオンは、複数の国を集めた建物の一角にありました。「NOT FOR SALE」(非売品)の看板をかかげ、黄色い壁と床、天井の室内には青く塗られた商品が並んでいます。来場者が品物のバーコードを読み取ると、現地の様子の映像が映し出され、自由や平和などウクライナが守ろうとしている大切な価値観が伝わってきます。「ほぼ全ての物に値段がつく現代世界でもウクライナ人の価値観を買うことはできない」というメッセージが込められているそうで、考えさせられました。
日本館は、総合デザイナーの佐藤オオキ氏による木でできた建物がおしゃれで開催国のプライドを感じさせます。展示は「プラントエリア」「ファームエリア」「ファクトリーエリア」にわかれていて、「プラントエリア」に話題の火星の石が展示。このコーナーは、ゴミを微生物によってタンクで発酵させ水などのエネルギーを発生させる、という流れを説明していて、「火星にも水があった」ということで半ば強引に火星の石をこじつけています。スライス状の火星の石は、皆がさわれるようになっていました。まだコロナが完全に終息していなくて、百日咳も流行っているので、皆がさわりまくる石コーナーに若干リスクを感じました。メインの火星の石は、係員が「一枚だけ撮影したらすぐ移動してください」と、せかすように案内していて、ろくに見ないで撮影だけして進む流れに。ガラス面の反射が激しく、肝心の石がちゃんと撮れずにただ疲れた自分の顔が写り込んでいました。
これまで数々の国のパビリオンで、豊かな大自然や資源、名産品、観光などのPRを見せられましたが、日本館ファームエリアがフィーチャーしていたのはなんと「藻」でした。日本のわびさびの精神を表現しているのでしょうか。日本館のテーマは「循環」で、ゴミを微生物が発酵させてCO2が発生。それを藻が吸収して増殖。藻が原料になって様々なプロダクトが作られる、という藻の可能性を大々的にアピールしていました。珪藻土に水滴を落とし、水のあとがはかなく消えていくというアート作品は、地味すぎるのと水滴がすぐ乾いてしまうので、ほとんど誰も撮影していませんでした。GDPや国力が下がっている日本の希望、そして最終兵器は、「藻」だったのでしょうか……。日本の未来が心配なのか安泰なのかわからなくなってきました。万博開催国の日本人として、おごらず謙虚になれる精神的作用があるパビリオンでした。歩き続け、並び続けた疲労感の余韻とともに、日常に戻ってまた粛々と働きます。
ゴージャスで趣向をこらした建築や素晴らしい展示物など、パビリオンでの体験はその国の好感度につながります。
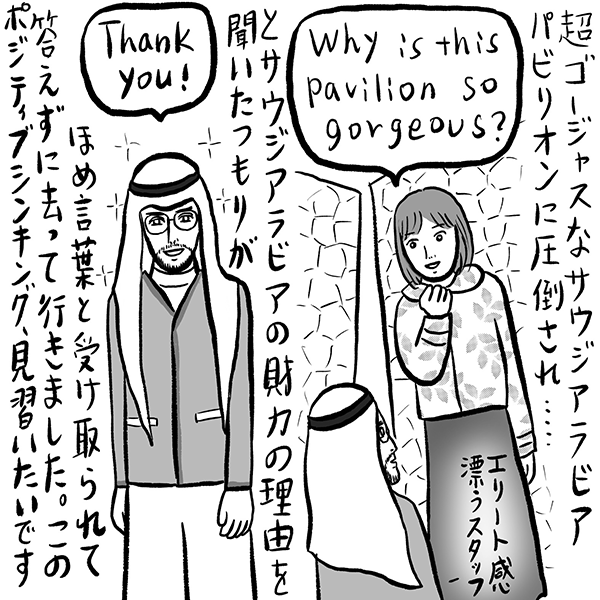
1974年東京都千代田区生まれ、埼玉県育ち。武蔵野美術大学短期大学部卒業。漫画家、コラムニスト、小説家。著書に『辛酸なめ子の世界恋愛文学全集』『女子校礼讃』『電車のおじさん』『新・人間関係のルール』『大人のマナー術』『煩悩ディスタンス』などがある。
Xアカウント@godblessnameko