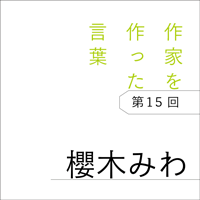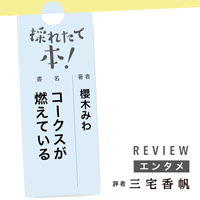櫻木みわ『アカシアの朝』◆熱血新刊インタビュー◆
アイドルが及ぼす作用

東ティモールやラオス、南インドなどアジア圏で暮らす女性たちの人生を綴った、文学の香り漂う短編集『うつくしい繭』でデビューした櫻木みわが、最新長編『アカシアの朝』で韓国を舞台に選んだ。しかも、題材は K-POP。とびきりポップで、エンターテインメント性もグッと高まっている。
「編集者さんから〝海外を舞台にした小説を〟というご依頼をいただいたんです。タイや東ティモールなど自分が昔住んでいたり行ったことがある国は、前に付き合っていた元カレみたいな感じで、今から新たに向き合う気持ちにはなれなくて。気になっていたけれど未知の国がいいなと思い、韓国が書きたいですとお伝えしました」
韓国は、幼い頃から身近に感じる国ではあったという。
「福岡の炭鉱町で生まれたので、戦時中に韓国の方がこの街に連れてこられた、という強制連行の話を大人から聞くことがありました。ラジオを聞いていると、たまに韓国語が流れてきたことも覚えています。韓国のラジオ番組の電波が入ってくるんです」
この機会に……とアンテナを張り巡らせてみると、韓国に関する二つの意見が目に留まった。
「若い子たちと話していると、K-POP に夢中な人が本当に多いんですよね。韓国のカルチャーの素晴らしさを熱く語ってくれるんです。でも、上の世代には嫌韓、反韓とも言われるヘイト感情を隠さない人たちがいる。同じ国なのに、世代によって抱いているイメージのギャップがものすごく大きいんです。上の世代の人のことはわりと想像がつくというか、差別主義的な人の話は書いてもあまりウキウキしなさそうですよね(苦笑)。それよりは、異文化に憧れる若者たちのことが知りたいし、想像したい。当時、K-POP のことは全く詳しくなかったんですが、私も主人公と一緒にこの世界に飛び込んでみたいと思ったんです」
私が本を読んで助けられてきたように、今の子たちは K-POP に助けられている
中学を卒業して間もない15歳の陽奈が、単身で渡韓する場面から物語は始まる。K-POP が大好きでダンスに情熱を注いできた陽奈は、故郷の大阪で行われたオーディションに合格し、ソウルの大手芸能事務所の「練習生」に選ばれた。これから会社の合宿所で他の練習生たちと共同生活をしながら、デビューを目指す──。序盤で記述される K-POP 独自の育成システムは、驚かされるものかもしれない。〈食費も家賃もレッスン代もすべて会社が持ってくれるが、それはいわば前借りで、デビューを果たしたら、それらの費用は給与から差し引かれ、会社に返済しなくてはならない。デビューができるかどうかはわからないし、たとえできたとしても苛酷な道〉。それでもこの道を突き進む、と決めたヒロインの情熱がまぶしくてたまらない。
「私も大学卒業後、海外旅行で短期間滞在した時に居心地が良かったという理由だけで、タイに移住したんです。作家になりたい、という夢を追っていた頃の自分の気持ちも、主人公に投影されていると思います」
陽奈の造形には、取材を通して出会った若者たちの情熱も息づいている。
「大阪のダンススクールに何度かお邪魔して、K-POP でデビューすることを目指している生徒さんたちにお話を伺いました。日本のアイドルではなく K-POP のアイドルになりたいんだ、という熱量がみんなものすごくて。特に印象に残っているのは、自分はそれまで孤独だったけど、K-POP を好きになったおかげで仲間ができたし前向きになれたという人が何人もいたことでした。私は本が好きだったから、本を読んでたくさん助けられていたんですが、この子たちは K-POP に助けられている。K-POP のアイドルが及ぼしている作用に驚きましたし、その作用への実感も湧きました」
陽奈の先輩となる4人の練習生は、ブラジルやタイ、韓国をルーツに持つ。のちに命名されるグループ名は、「SALT」。〈媚びず、動じず、自分らしさを追求している、女の子が恰好いいと思う女の子〉という属性を持つ、ガールズクラッシュと呼ばれる K-POP の流れを汲んだ5人組多国籍グループだ。このグループがとにかく魅力的で、応援したくなる。実質的な人気投票が行われるなどデビューまでの道のりには過酷なエピソードも待ち構えているが、5人の間にはギスギスした雰囲気がない。
「女の敵は女、とよく言われますけど、本当にそうなのかなと昔から疑問でした。特にみんなで真剣に何かに取り組んでいる時って、たとえライバル同士であっても励まし合う心境になるんじゃないかな、と思うんですよね」
5人の共同生活と切磋琢磨の日々は、もう一人の視点からも描かれていく。17歳の韓国人練習生・ソユンだ。38度線に接する故郷・坡州市で生まれ育った少女は、なぜアイドルになることを目指したのか? ソユンの視点を取り入れたことで、アイドルと恋愛というテーマに焦点が当たるとともに、韓国の歴史を紐解いていくことへと繫がっていった。
「ざっくりと〝日本の少女と韓国の少女が出会う〟という設定は最初に考えていましたが、韓国の少女を坡州出身にしたのは偶然でした。ソユンは田舎町出身がいいなとは思っていたんですが、なかなか取材できる場所が見つからなかったんです。そんな時に編集さんから、坡州はどうですかと提案していただいたんですよね。取材で足を運んでみたら、現地のタクシーの運転手さんが〝親戚のおばあちゃんがすごい田舎に住んでいるよ〟とおっしゃって、その方の家に連れて行ってくださった。そこが、北朝鮮近くの村でした。おばあちゃんの話も興味深かったですし、畑の中にあるおうちもすごく風情があって、ここを舞台の一つにしようと決めたんです」
韓国のアイドルを題材にしたからこそ、かの国の歴史と共に、共同生活の中でお互いの国について学び合うティーンたちの姿が描き出された。その姿は、過去の「アイドル小説」では決して見られなかったものだ。
「日本のアイドルは基本的に日本のことだけを気にしていればいいんですが、K-POP のアイドルは世界に出ていくのが当たり前ですから、韓国や日本のファン、アメリカなど諸外国のファンのことも考えなければいけない。そのためには自分たちで勉強して、いろいろな国の歴史や価値観に配慮をする必要があるんです」
違う意見を持った者同士って、現実だとなかなか出会えない
「SALT のプレデビュー曲のコンセプトをシェイクスピアから取ったのは、通訳の方が韓国のミュージカルが好きで、そちらのお仕事をされていたから。ソウル大学の女子学生もハマっていると言っていたし、韓国ではミュージカルが盛んなんだと知ったんです。そこから、ミュージカルの事務所が K-POP を始めるという設定にしたらどうかな、だったら楽曲はシェイクスピアを下敷きにするかもなと着想が膨らんでいきました。取材でお会いした方から、たくさんのヒントをもらってできあがっていったお話なんです」
SALT の5人が厳しいレッスンを重ね、プレデビューし……というキラキラした快感に満ちた物語は、後半でガラッと転調する。
「そこに関しては、お話の流れとしてああいう出来事が起こるということは、書き出す前に決めていました。韓国に住んでいる友達に話を聞いた時、〝韓国社会の若い人たちを見ていると、ものすごく閉塞感を感じる。そのことは心にとどめて書いてほしい〟と言われたことも頭に残っていたんです」
実は本作はアイドル小説であって、アイドル小説ではない。この世界のままならなさや人生の取り返しのつかなさ、それでも希望を持って生きていくにはどうしたらいいかについての物語だ。
「現実世界には K-POP のアイドルを目指す子がいれば、韓国をヘイトする人たちもいる。大阪の鶴橋のコリアンタウンで在日コリアンの大学生の方にお会いして、〝在日〟や〝同胞〟についての複雑な心情も伺いました。それぞれが考えていることは、全然違う。全然違う意見を持った者同士って、現実だとなかなか出会えないんですよね。でも、小説の中なら出会わせることができる。韓国についていろいろな意見があるし考えがある、という現実そのものを小説で表現したかったんです」
その結果、読めば隣人たちへの想像力に作用する一作となったのだ。本作は見た目こそ華やかだが、小説を書く際の感覚は、市井の隣人たちを書いてきた過去の作品と一緒だったという。
「スポットライトが当たっている人よりは、道端のお年寄りとか、すぐ隣りにいるような普通の人たちに興味があります。そういう人たちこそが、心にものすごい財宝を隠し持っている気がするんです」
K-POP デビューを夢見る陽奈と、大学進学する幼なじみに思いを寄せるソユン。日韓のふたりの少女は、それぞれの理由から芸能事務所の練習生としてソウルで暮らし始めた。ブラジル、タイなど各国出身の練習生とのつながりは深まる一方、韓国芸能界の荒波に心と体をすり減らしていく──。現代女性の抱える悲哀を題材とした中編『コークスが燃えている』で熱狂的な支持を得た著者による、初の長編小説!
櫻木みわ(さくらき・みわ)
1978年福岡県生まれ。タイ、東ティモール、フランス滞在などを経て、2018年に作品集『うつくしい繭』で単行本デビュー。現在は琵琶湖で唯一の有人の島、沖島に住む。