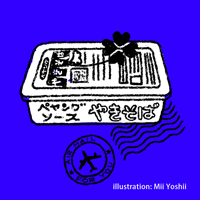思い出の味 ◈ 増島拓哉

中学生の頃、僕は近所の個人塾に通っていた。五教科を全て一人で教える先生は、これまでの人生で出会った人の中で最も頭が良く、最も怖い人だった。数学の問題を間違えると、「こんなもんは猿でも解ける」と罵られたが、教科書に掲載された小説ではなく、宮本輝や森絵都や重松清の小説で授業をしてくれたり、歴史上の合戦や戦争の模様を臨場感たっぷりに、講談師のような口調で語ってくれたりした。
高校進学が決まり、挨拶に伺うと、「京大行けよ」と言われた。僕は力強く返事をしたが、高校に馴染めないまま三年間を過ごし、受験勉強を半ば放棄していたため、当然のことながら京大には進めなかった。気まずさから年賀状にも返事を出さず、連絡を絶ってしまった。
大学二年生のとき、僕が小説の公募新人賞を受賞したと知った先生がお祝いの電話をくれたことから、五年ぶりにお会いすることとなった。先生は僕の不義理を笑って許し、マリオ・バルガス・リョサの『緑の家』という奇天烈なラテン・アメリカ文学の文庫本をくれた。肝心の僕の小説は「大したことない。車谷長吉の方がオモロい」と斬り捨てられたが、書店で五冊以上購入してくれたそうだ。
先生は祝いのために、中華料理屋に連れて行ってくれた。絶品の料理に舌鼓を打ったあと、二軒目に訪れた喫茶店で、僕は人生初のブラックコーヒーを飲んだ。
「この土臭さ、雑味。これや。この中に、本物の旨味がある。癖のない飲みやすい珈琲なんか、アホタレや。人間も一緒やぞ。癖のある奴になれ」
先生の声を隣で聞きながら、猫舌の僕は恐る恐る珈琲に口を付けた。芳醇で濃厚なコクのある香りが鼻腔に抜け、野性的な苦味が口内に広がる──ことはなかった。僕にはただ、ひたすら苦くて黒い汁にしか感じられなかった。旨えだろ? と問われ、小さく頷くと、噓吐け、と見透かされたように笑われた。ちょっとずつで構へん、と先生は続けて言った。
マンデリンは苦かったが、先生の隣で苦い珈琲を飲んだあの日の思い出は、僕の中で甘美な味として記憶されている。