【著者インタビュー】阿川佐和子『ことことこーこ』
フードコーディネーターとして働くアラフォーの出戻り娘・香子(こうこ)と、物忘れが多くなった母・琴子(ことこ)の、介護と料理をめぐる物語。自身も現在、認知症の母を介護しているという著者に、作品についてお話を伺いました。
【ポスト・ブック・レビュー 著者に訊け!】
仕事と母の介護の両立にアラフォー長女が翻弄される! 美味と人情あふれる奮闘記
『ことことこーこ』
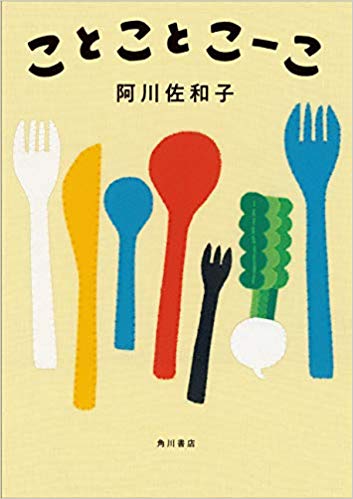
KADOKAWA
1500円+税
装丁/大久保伸子 装画/木野聡子
阿川佐和子

●あがわ・さわこ 1953年東京生まれ。慶應義塾大学文学部卒。報道キャスターを経て渡米後、作家、インタビュアーとして活躍。99年『ああ言えばこう食う』(檀ふみ氏との共著)で講談社エッセイ賞、00年『ウメ子』で坪田譲治文学賞、08年『婚約のあとで』で島清恋愛文学賞、14年菊池寛賞。12年のベストセラー『聞く力』や小説『スープ・オペラ』『正義のセ』等著書多数。昨年はTBS日曜劇場『陸王』に出演し、東京ドラマアウォード2018で助演女優賞を受賞。
徘徊も当人には当人なりの理屈や考えがあったはず。そこへの理解って全然ない
阿川佐和子氏の最新作は、結婚10年目に離婚し、フードコーディネーターとして働き始めた38歳の出戻り娘〈
自身、3年前に父・弘之氏を看取り、認知症の母を現在も介護中。先日は大塚宣夫氏との共著『看る力』も上梓し、本作では介護する側や
それは弟夫婦や甥も交え、家族水入らずで迎えた正月のこと。母が台所に立つのを見て、父は突然こう言い放つ。〈母さんは呆けた、呆けた、呆けた!〉――。
*
「これは父が本当に言った台詞です。いいか、お前たち、気づいてるかどうか知らんが、母さんは呆けた、呆けた、呆けた〜って(笑い)。元々父は何事も合理的に考える性格でしたけど、今思えば自分に覚悟させる意味もあったんでしょうね。
その父が家の中で転んで入院したり、介護って一気に起きるんですね。幸い、私は家族や友人のおかげで抱え込まずに済んだけれど、香子みたいに1人で頑張っちゃう人も大勢いると思う。
だから今ある介護小説や映画って、ほとんどは悲壮感に満ちている。でもケアされる側は意外とあっけらかんとしていたり、よく観察していると、笑えることも結構あるので、明るい介護小説があってもいいんじゃないかなって」
香子の場合は離婚後まもなく母に異変が生じ、〈もの忘れ外来〉で認知症の初期と診断された当日、今度は父が心臓発作で急死。母は葬儀でも頓珍漢な応対を繰り返し、冷蔵庫に入れたあれがない、銀行で下ろしたお金がない等々、特に母親が呆けることで生じる
「冷蔵庫は異変に気付きやすい場所かもしれませんね。なんでこんなところにバナナが? とか(笑い)。
整理整頓ができなくなるのも認知症の典型的症状で、私も最初は相当イライラしたけど、母の部屋で〈もう私、ダメだ〉と書いたメモを見つけてからは、そうか、母も苦しかったんだなって。
ただ最近の母は悩むこと自体なくなって、見事に明るく呆けています。症状の進行が比較的遅いことにも家族は助けられている。やはり対処の仕方がわからないと精神的に余計つらくなるので、今できることを一つ一つやっていこうと思えるのも、母の性格のおかげです」
介護は10年、20年と続くだけに喫緊の問題から解決し、〈あらゆる親切な人〉を巻き込むことも大事。そう友人に教えられ、母の妄言にも明るく応じる事務所の後輩〈麻有〉や〈タモ社長〉など、仕事仲間にも恵まれた香子は、やがて母の味をアレンジすることに公私を超えた
介護は素人だけでは限界がある
母の部屋で見つけた古いノートには、鶏肉と玉ねぎをホワイトソースで煮込み、レモンを絞った〈レモンライス〉など、いかにも昭和の家庭の味が並ぶ。ある時、〈白ワインに合うレシピ〉300種の開発を依頼された香子は麻有と共に試作に励むが、結局好評だったのも母のレシピ絡みだった。
「レモンライスは母がよく作ってくれた私の大好物で、トマト缶を牛乳で伸ばして冷やすだけの〈簡単トマトスープ〉とか、母の世代の料理ってどこか懐かしくて、簡単でモダンなんですよね。
実は主人公をフードコーディネーターにはしたものの、何を得意分野にするかは全然考えてなくて、母の味云々は書いていくうちにそうなったんです。あと、『TVタックル』で介護の専門家から『徘徊する人には徘徊する理由がある』という話を聞いた時に、あ、そこへの理解って全然ないなと思ったことが大きくて、介護する側だけじゃなく、される側の気持ちも、想像でいいから書いてみようと。
例えば本人は晩のおかずを買いに出ただけなのに、気づくと全然違う町にいたりする。それを『とうとう警察のご厄介になるほど壊れちゃった』と思うのは家族側で、当人には当人なりの理屈や考えがあったはずなんです」
香子もまた、自分の中の母親像が失われていくことに傷つき、家を売って母を施設に入れようと言う弟や常に遠慮がちな義妹の態度が冷たく思えてしまうのだ。
「客観的に見ればこの弟の言うことは正論で、介護はプロの仕事で、素人だけでは限界があると、大塚先生もおっしゃっていました。それでなくてもたとえば、遠方に住む姉より在宅で看ている妹の方が親に恨まれたり。兄弟間で必ず揉めるんです。
あ、うちの話じゃないですよ。こないだも弟に言ったんです、今度こんな小説を書くけど、別にアンタたちのことじゃないからねって(笑い)。彼らには、もっと頼りなよと言ってもらってます。それでも意見のすれ違いは生じますからね」
母が母でなくなるというのも香子側の問題で、どんなに老いようと母は母だった。その事実を受け入れ、母の味の
「ウチの母も、どんどん子供返りしていくんですけど、ときどき、母親らしくなる瞬間があるんですよ。そこが不思議。面白いですよ」
ところで阿川作品はなぜこれほど笑いに満ちながら、どこか物悲しいのだろう。
「うーん。笑っているのに心は泣いてる話が好みなのかもしれませんね(笑い)」
●構成/橋本紀子
●撮影/国府田利光
(週刊ポスト 2018年12.14号より)
初出:P+D MAGAZINE(2019/01/29)

