高校球児の汗が光る、「甲子園」を描いた小説3選

8月の名物と言えば、高校球児たちが熱戦を繰り広げる「甲子園」。中継を見るたびに、思わず目頭を熱くしている方も多いのではないでしょうか。今回は、そんな甲子園を舞台とした傑作小説を3作品ご紹介します。
8月といえば、高校球児たちが活躍する「甲子園」(夏の全国高等学校野球選手権大会)を真っ先に思い浮かべる方も多いのではないでしょうか。全国から集った野球少年たちが一生に一度の晴れ舞台に立ち、太陽のもとで熱戦を繰り広げる様子には、思わず目頭が熱くなってしまうものです。
今回は、夏の甲子園を夢見る野球少年たちや、かつてその舞台に立った大人たちの姿を描く、「甲子園小説」の傑作を3作品ご紹介します。
延長15回、あの夏の決勝戦を振り返る──『大延長』(堂場瞬一)
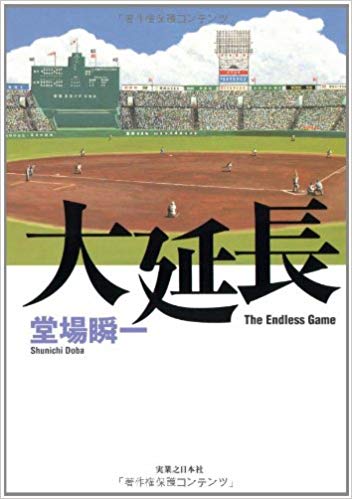
出典:https://www.amazon.co.jp/dp/4408535087/
堂場瞬一による長編小説『大延長』は、その名の通り15回の“大延長”となった甲子園決勝戦での激闘を描く物語です。
15年前、甲子園でライバル校の恒正学園と死闘を繰り広げた
15年前のその日、甲子園決勝の常連である恒生学園とは対象的に、牛木の通う新潟海浜高校は、初めての決勝出場に沸き立っていました。しかし、エース級のピッチャーであった牛木は膝を壊しており、長時間の試合を投げきれるようなコンディションではありません。一方の恒生学園にも、野球部員の喫煙というスキャンダルが持ち上がり、メンバーの結束力は弱まってしまっていました。
どちらの高校にとっても最大のピンチと言える局面の中、牛木と久保を中心に繰り広げられる試合は思わぬ熱を帯び、“大延長”へと向かっていきます。
規律を重んじる恒生学園と、選手の自主性や積極性を重んじる新潟海浜高校。そして、カリスマ性のあるエースの久保と、頭脳派で負けず嫌いな牛木──。まったくカラーの違う両校・両選手の個性がぶつかる決勝戦の描写は、思わず手に汗を握ってしまうほど熱くドラマティック。
こんな試合実際にあるはずがない、と思うほど怒涛の展開が続いても、「いや、甲子園ならばありえるかもしれない」とつい考えてしまいます。甲子園には魔物がいる、という言葉を思い起こさせてくれるような、興奮の詰まった1作です。
勝者と敗者、それぞれにとっての甲子園──『晩夏のプレイボール』(あさのあつこ)
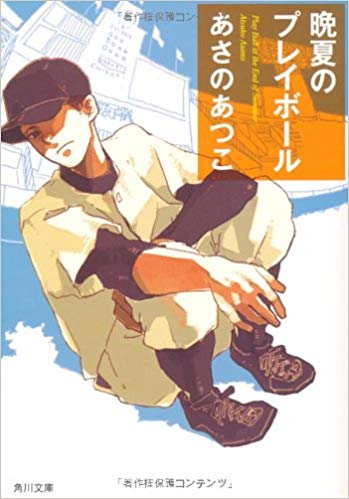
出典:https://www.amazon.co.jp/dp/4043721099/
『晩夏のプレイボール』は、あさのあつこによる「夏の甲子園」をテーマにした10篇の短編集です。かつて甲子園の舞台に立ったことがある大人やいままさに県大会に挑もうとしている少年、女性であるが故に甲子園出場の夢を諦めなければならなかった少女──といったさまざまな人物が、それぞれの立場から甲子園にまつわる思いを綴ります。
その中の1篇である『練習球』では、甲子園の地区予選準決勝を舞台に、高校野球部の元エース・
肩を壊したことをきっかけにベンチ入りが多くなり、野球への情熱を捨てかけていた真郷と、たしかな才能を持ちながらも、控えめな性格ゆえに目立たない存在だった律。激情家の真郷と柔和な律はタイプこそ正反対ではあるものの、互いに「律と野球をやれるなら」、「真郷と野球をやれるなら」と野球の強豪校への進学を決めたほど、強い信頼で結ばれていました。
準決勝の舞台、9回で律の球は相手チームに打たれてしまい、真郷たちの高校は最大のピンチを迎えます。代打でバッターボックスに立った真郷は、「まだ終わらせはしない」という思いでバットを握っていました。
この一打席、これはおれのものだ。おれだけのものだ。
インコースに真っ直ぐな球が入ってきた。白く発光したように見えた。身体は動き、バットは球に食らいついていく。手のひらに衝撃がきた。それはそのまま、真郷の奥深い場所を貫いて過ぎた。
「真郷!」
律の叫びが聞こえた気がした。
真郷と律、それぞれが野球に抱いている情熱はもちろん、切磋琢磨しながらも常に互いを思い合うふたりの友情が本作の最大の魅力です。
『晩夏のプレイボール』には、同じくあさのあつこによる名作シリーズ『バッテリー』のような天才球児やカリスマ性のある選手は、ほとんど登場しません。しかし、『バッテリー』の選手同士の関係性に心を掴まれた方には、ぜひおすすめしたい1冊です。
箕島vs星稜、「神さまが創った試合」のドキュメント──『スローカーブを、もう一球』(山際淳司)
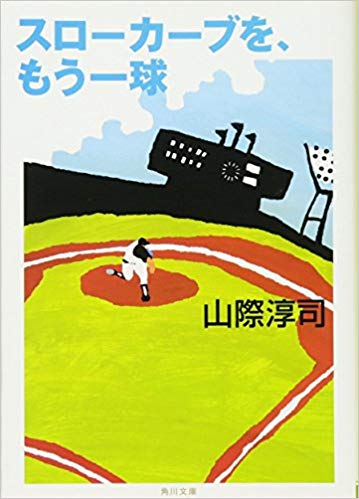
出典:https://www.amazon.co.jp/dp/404100327X/
ノンフィクション作家の山際淳司による『スローカーブを、もう一球』は、1979年から1981年にかけて実際に山際が取材をしたアスリートたちの姿を描く、8篇のスポーツドキュメンタリーです。中でも、79年の日本シリーズの一試合、9回裏で伝説的なプロ野球選手・江夏豊が投げた“21球”だけに着目したドキュメント『江夏の21球』は大きな話題を呼び、作家としての山際の地位を確固たるものにしました。
本書に収録されたドキュメントの中の1篇である『八月のカクテル光線』では、甲子園ファンの間で「神さまが創った試合」とも呼ばれる名勝負・1979年の箕島高校対星稜高校の試合の様子が描かれます。
試合が始まる前、箕島高校のエースである石井毅投手は、まったく緊張はしていなかったと語っています。
苦戦するんじゃないかっていう予感なんてなかったよ。自分のピッチングをすれば勝てると思っていた。いつもそうだった。負けるときはたいてい自分のピッチングができないときさ。落ち着いて投げれば勝てる。それだけだね。
……このように、試合の当事者である選手たちや当時の監督のリアルな言葉を挟みながら進む本作。石井投手の予想に反して試合はもつれにもつれ、延長線からのナイターに突入してゆくのです。
エース選手の信じられないようなエラー、隠し玉の登場、2本の同点ホームラン。まるでフィクションのようにめまぐるしい展開を見せながら、試合はなんと18回まで続きます。
人は誰でも、自分の人生の中から最低一つの小説をつむぎ出すことができるように、どんなゲームにも語りつがれてやまないシーンがある。それは人生がゲームのようなものだからだろうか、それともゲームが人生の縮図だからだろうか。
山際のそんな言葉に思わずうなずいてしまうほど、箕島対星稜戦は“語りつがれてやまないシーン”に満ちています。伝説の試合をリアルタイムで見ていた世代の方にとってはもちろん、そうでない読者にとっても、ページをめくるたびに胸の高鳴りが増していくような傑作です。
おわりに
普段はあまり野球の試合を見なくても、夏の甲子園にだけは特別な魅力を感じてしまう──という方はきっと少なくないはず。選手のひたむきさや情熱、同級生たちの熱い声援、OBたちの思いといったさまざまな要素はあれど、甲子園に私たちの目がくぎづけになってしまう最大の理由は、まるで小説のようにドラマティックな試合が展開する場所だからではないでしょうか。
甲子園を描いた作品は、そんなひと夏の感動を何度でも追体験させてくれます。試合の中継が終わってもまだあの感動を味わい足りないという気分のとき、今回ご紹介した3作品のページを開けば、ふたたび球児たちの世界に飛び込んでいけるはずです。
初出:P+D MAGAZINE(2019/08/13)

