【働けど働けど】借金、豪遊、有名税……文豪たちの知られざる“お金”事情

文豪と呼ばれた作家たちの中には、「お金」にまつわるトラブルを抱えていた人も多いようです。今回は、坂口安吾や小川未明、永井荷風といった文豪たちの「お金」にまつわるさまざまなエピソードを紹介します。
はたらけどはたらけど猶わが生活楽にならざりぢっと手を見る
……あまりにも有名なこの歌は、歌人・石川啄木が貧しさの中で自らの生活を嘆き詠んだ短歌です。啄木の貧困は娼妓と遊ぶための借金が原因だったとも言われていますが、文豪と呼ばれる人々には、印税暮らしという言葉の華やかなイメージとは反対に、“お金”で苦労した人物も少なくないようです。
今回は、そんな文豪たちのキャラクターが垣間見られるような、彼らの“お金”や“借金”にまつわる知られざるエピソードを紹介します。
「みんな呑んでしまひ、今月お返しできなくなりました」──借金しても謝らない坂口安吾
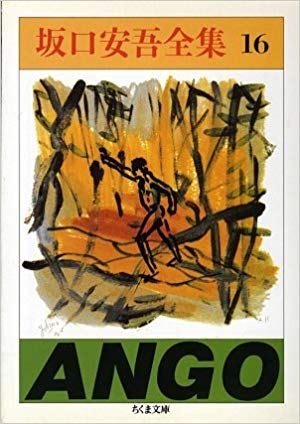
出典:https://www.amazon.co.jp/dp/448002476X/
『堕落論』や『白痴』などの代表作で知られる小説家・坂口安吾。安吾は10代のときから石川啄木やボードレールなどの作品を愛読し、反抗的で型破りな“落伍者”への憧れを抱いていました。
やがて20代になるとフランス文学に傾倒し、フランス語教室の仲間たちとともに同人誌『言葉』を創刊した安吾は、同人仲間たちと東京中を飲み歩くようになります。1930年代には新進気鋭の作家として活躍するようになりますが、原稿料が入ってもすぐにお酒を飲むのに使ってしまい、人からお金を借りることもたびたびあったようです。
特に、飲み仲間であった小説家・編集者の隠岐和一には原稿用紙の手配をしてもらったりお金を借りたりと、事あるごとに世話になっていました。1936年には、借金を返せないということをストレートに伝える手紙を隠岐に書いています。
拝啓
貴兄から借りたお金返さねばならないと思つて要心してゐたのですが、ゆうべ原稿料を受取ると友達と会ひみんな呑んでしまひ、今月お返しできなくなりました。たいへん悲しくなりましたが、どうぞかんべんして下さい。
小生こんど競馬をやらうかと思つてゐますよ。近況御知らせまで。 安吾
──隠岐和一への手紙『坂口安吾全集 16』より
盗っ人猛々しい、という言葉が真っ先に思い浮かぶような文章ですが、お金を貸している相手からこんな手紙が届いたら、怒りを忘れて笑ってしまうかもしれない──とも思わされます。“たいへん悲しくなりました”と一方的な気持ちを述べるだけで、お金を返せないことに関してはまったく謝っていないのも妙におかしく、憎めないポイントです。
安吾は戦後、大宰治や織田作之助らとともに「無頼派」として人気作家の仲間入りを果たしますが、酒や遊びでお金を使い果たしてしまうという性格は変わりませんでした。1951年には、税金を滞納し家財道具と蔵書を差し押さえられた経験をもとに『負ケラレマセン勝ツマデハ』という随筆を書き、国税庁を相手に税金不払い闘争をおこなうなど、生涯にわたって破天荒なエピソードに事欠かない人物でした。
(合わせて読みたい:【堕落したっていいじゃない】無頼派、坂口安吾の破天荒エピソードとその作品。)
「貧民を相手とする商売は吸血漢だ」──貧しさを極めた小川未明

出典:https://www.amazon.co.jp/dp/B009NJM3T0/
「日本のアンデルセン」と呼ばれた児童文学・童話作家の小川未明。未明は1909年、27歳のときに、雑誌記者や編集者などのすべての勤めを辞め、小説一本だけで生きていこうと決心をしました。
当時の未明は、東京専門学校(現・早稲田大学)在学中に発表した小説『
その当時、売るに着物もなく、書物もなく、妻が指にはめていた指輪を抜き取らせて、私が売りに行ったことを覚えています。こうした、数々の場合に際会するたびに、深く頭に印象されたものは、貧民を相手とする商売の多くは、弱い者苛めをする吸血漢の寄り集りということでした。第一質屋がそれであります。合法的に店を張っているには相違ないけれど、苦しい中から、利子を収めて、さらに品物を受出すということが、すでにそうした境遇に於かれている者には、殆んど不可能のことでした。
もう一つ、貧困の時代に、苦しめられたものは、病気の場合であります。手許に、いくらかの金がなくては、医者を迎えることもできない。どんなに近い処でも、医者は俥に乗って来る。その俥代を払はなければならず、そして、薬をもらいに行けば薬代は払って来なければならぬ。
──『貧乏線に終始して』より
どんなに近いところでも医者は車に乗ってくる、そしてその車代を払わないわけにはいかない──。貧乏だった時代の悲痛な暮らしがストレートに伝わってくるような文章です。未明のふたりの子どもは栄養失調になり、どちらも幼いうちに亡くなってしまいます。未明は後年、童話作家としての地位を確立しましたが、子どもを亡くしたことを長いあいだ悔いており、“親として、悔恨の深いものがあります”と同じ随筆の中でも綴っています。
『金の輪』や『赤い蝋燭と人魚』といった未明の代表作には、不在の父親や、幼くして亡くなってしまう子どもといったモチーフが登場します。これらの作品には、貧しさゆえ、父親として我が子を守ることができなかった未明の罪悪感が影を落としているようにも感じられます。
“有名税”を税務署で本当に払わされた永井荷風
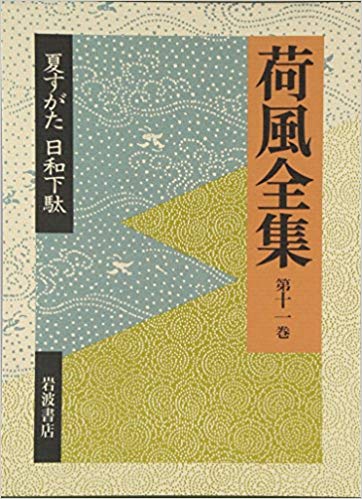
『文士の生活』収録/出典:https://www.amazon.co.jp/dp/4000917315/

出典:https://www.amazon.co.jp/dp/400310420X/
抑 も文学に依つて生活すると云ふ事が無理ではないかと思はれる。(中略)一版千部か千五百部で、それも売出した当時きり寿命がない日本で、印税から得る所の報酬のみで生活すると云ふ事は頗る不安である。
──『文士の生活』より
『文士の生活』と題されたこんな赤裸々な随筆を1914年に発表したのは、文豪・永井荷風です。印税のみで生活するのは日本では無理、と主張する荷風は当時、慶應義塾大学文学部の主任教授を務めており、こちらの月給が主な収入源であったと同じ随筆の中で綴っています。
……この情報だけを聞くと、荷風は教授としての職を頼りにさぞかし慎ましい生活を送っていたのでは、と想像する方もいるかもしれません。しかし実際には、荷風は非常に裕福な家庭の生まれだったため、父親のコネでアメリカ、フランスの外遊をしたり芸姑との交流を続けるなど、金銭面での苦痛は特に感じていなかったようです。
幸か不幸か、私は今親の脛噛りで、別に生活の上の苦痛を知らずに居るが、若し破産をするなり、何かの事情が持上つて、自分で自分の汗に依つて生きて行かなければならぬやうになつたら、私は今の様に文学を弄つて行く少しも考へはない。もつと別な方面でもつと金の儲かる仕事をして行く。
──『文士の生活』より
文学はまったく儲からない、万一のことがあればもっと儲かる仕事をする──と主張していた荷風ですが、彼はそれでも、当時の文士の中では高収入であったと推定されています。そんな荷風は『濹東綺譚』などの代表作を発表後、60代を迎えた1941年に、税務署に“有名税”をとられたという驚くべき日記を書き残しています。
幸橋税務署より出向かれたき趣昨日
端書 到着したれば、朝早く風邪涼しきを幸に赴き見たり。けだし本年の所得税去年の倍額に近きものになりたれば去五、六月中抗議のため届出を送り置きしなり。係の役人余を別室に招ぎ仔細らしく書類帳簿等持ち出し貴下の申しさるる所一々尤もなれども世に有名の文士なれば、実際の収入よりも多額の認定をなすは是非なき次第なり。有名税とも言ふべきものなれば本年は我慢されたし。
──『断腸亭日乗』より
この日記によると、荷風はこの年に前年の倍の額の所得税を通知され、「有名税とも言うべきものだから今年は我慢しろ」と言われた──というのです。仕方ないと思って特に抗議をしなかった、と日記は続きます。なんとも理不尽な話ですが、当時の荷風の裕福さや、文壇での存在感の強さを思わせるエピソードです。
偏屈な人物として知られていた荷風は、現金はもちろん、株券や土地の権利書など、すべての財産をボストンバックに詰め込み、片時も離さず持ち歩いていました。79歳で心臓麻痺で亡くなった際には、自室に置かれていたボストンバッグの中に、約2300万円(現在の価値で約3億円)の記帳がされた通帳が入っていたといいます。
おわりに
小説家・村上春樹はエッセイの中で、とても貧乏だったという若い頃をこんな風に振り返っています。
夏の糞暑い午後に頭がボオっとして喫茶店に入って冷房の中でアイスコーヒーが飲みたくても、女房と二人で「我慢しようぜ」と励ましあってやっとの思いで家にたどりついて麦茶をごくごくと飲む……それはそれですごく楽しかったのだ。
それは金とは関係のないことなのだ。それはいわば想像力の問題なのだ。想像力というものがあれば、我々は大抵のものは乗り切っていけるのだ。たとえ金持ちであろうが貧乏であろうが。
──『お金本』より
想像力があれば貧乏も乗り切っていける──という言葉を、ちょっと楽天的すぎると感じる方も少なくないかもしれません。しかし今回ご紹介した文豪は実際にその“想像力”を武器にし、名作を生み出すことで世知辛い世の中と闘い続けた人物たちでした。
“お金”という切り口から文豪たちのことを眺めてみると、教科書でしか名前を見たことがなかった偉大な小説家たちが、少しだけ身近に感じられるようになるかもしれません。
初出:P+D MAGAZINE(2020/02/29)

