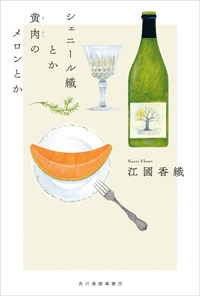江國香織さん『シェニール織とか黄肉のメロンとか』*PickUPインタビュー*

50代女性3人の友情と日常を描く
3人の女友達を中心にした群像劇
「ひたすら読んで楽しい、日常と地続きの話を書きたかったんです。それでなんとなく、女性たちの話にしたいなと思って」
そう語る江國香織さんの新作『シェニール織とか黄肉のメロンとか』は、久々に再会した50代後半の女性3人や周囲の人々の日常を、複数視点で語っていく群像長篇である。
2017年に本作と同じ版元から刊行した『なかなか暮れない夏の夕暮れ』は50代の男性、稔を中心とした群像劇で、それと対となっている印象も。
「たまたまなんです。この間指摘されて、前作と今作で男性版と女性版になっていると気づきました。『なかなか~』を書いた時も思っていたんですけれど、50代の人の日常ってあんまり小説になっていないんですよね。10代だったら学校生活、20~30代なら社会での軋轢や結婚問題、70~80代になると健康の不安や孫のことなど、イメージできる出来事がある。でも50代の人が日々何をしているのかって、ぱっと浮かびにくいんですよね。そのこと自体が面白いなと思っていて。それで、50代の彼女たちがどんな日常を送っているのか私自身が知りたくて、観察する気持ちで書きました。大きな事件中心に話が進む小説も、読むぶんには好きです。でも書く時は、大きい出来事がない時に人は日々何をしているのかに興味があります」
長いつきあいの友達の楽しさ、面白さ
大学の出席名簿で名前がならんでいたことから親しくなり、教授から「三人娘」と呼ばれていた民子、理枝、早希。その後、民子は作家となり、理枝はイギリスの金融会社で働き、早希は専業主婦となった。そしてこのたび理枝が仕事を辞めて帰国。住む家を見つけるまでの間、民子が母の薫と二人で暮らす家に居候することとなる。早希との再会も果たし、3人は昔のようにお喋りに花を咲かせるのだった。
「いくら仲がいい友達でも、大人になるとしょっちゅう会うわけではないんですよね。彼女たちはラインやフェイスタイムといったツールで繋がっていたとは思いますが、早希のように結婚した女の人は、どうしても子育てや家のことで忙しくて外に出掛けにくくなりますし。でも50代になると子供も手を離れて、また友達とも出会い直せる感じがありますよね」
3人は生活も性格もばらばら。理枝はアクティブな自由人、民子は決して社交的なタイプではなさそうで、早希は二人に比べると穏やかな印象。個性の異なる者同士が親しくなることは、現実でもよくあるだろう。
「友達の面白いところってそこですよね。すごく気が合うからとか、すごく素敵な人だから友達になるというわけじゃない。彼女たちも出席名簿の順番という偶然から親しくなっている。仲良くしているうちに、この人しょうもないなと思ったり、こういうところは苦手だなと思ったりするけれど、恋人と違って友達ってだから別れるということにはならない。そうしてつきあっていくうちに唯一無二の、取り替えられない存在になっていくんですよね」
3人に特にモデルはいないそうだが、
「実際出会ってきた女たちのストックがいっぱいあるので、ソースには事欠かなかったです(笑)。一人の登場人物にいろんな人が投影されていますね」
という。3人のなかでも、理枝の自由人っぷりがインパクト大。帰国してほどなく、急に思い立って連絡もせずに早希の家に遊びに行くなど、かなりの自由っぷりだ。が、突然の訪問に驚きながらも喜びを隠せない早希の姿に、この3人の親しさがはっきりと感じられる。
「私にも電話もせずに急に来る友達がいるんです(笑)。自分では絶対にできないし、来られると困るんですよ、掃除してないし締切があったりするし。なんで急に来るの? と文句を言いながらも、でも、すごく嬉しいんです。あの困るのに嬉しい感じって独特だなって思います」
他にも、理枝は帰国してすぐに車を購入したり、精力的に新居探しを始めたりするなど、かなりパワフル。
「理枝にはちょっと憧れます。この歳になって、一人で暮らすための家を買ってリフォームしようとするエネルギーはすごいですよね。自分は年々エネルギーが減ってきていると感じるので、理枝を書きながら〝私も頑張ろう〟と思っていました(笑)」
ちなみに、作家の民子がどんな小説を書いているのかというと、さりげなくSF恋愛小説という言及があり、意外な気も。
「自分では絶対に書けないんですけれど、そういうものが書けたらいいなってふと思ったんです。イメージしていたのは、人類がほとんどいなくなって、南の島で20、30人だけサバイバルしている世界です。彼らは子孫を残すために生殖しなくちゃいけないけれど、そういう時って恋愛するという感じではなくなるだろうし、それが可能な人もそうでない人もいるだろうし……。そういう小説があったら面白いかなという、思いつきです(笑)」
役に立たない言葉を記憶に刻みたい
学生時代、民子と早希は読書サークルに所属し、そこに時折理枝も顔を出していた。その頃に3人の間で〈正体がわからないが故に想像と憧れをかき立てられる、特別な言葉〉だったのが、「シェニール織」だ。
「自分も昔は、学校や家族や、妹と二人の間にそうした特別な言葉がたくさんあったんです。それに本を読んでいると、ストーリーは忘れても、単語だけ憶えていることってありますよね。子供の頃にレモンの学名がシトラスリモンバームFだと知ったんですが、今でも忘れていないんですよ。何も役には立たないけれど、それがちょっと嬉しくて。以前『パンプルムース!』という子供向けの詩集を出したんですが、パンプルムースってフランス語でグレープフルーツのことなんです。フランスに行ってレストランでグレープフルーツを頼む時はパンプルムースって言えばいい、という詩なんですけれど、でもたぶんそんな機会なんて来ませんよね。役に立たない、無駄な言葉を、読んでくれた人の記憶に残したいと思って書きました。無駄なことをいっぱい読んでもらいたい」

シェニール織だけでなく、本作の中には、ちょっとした言葉、ちょっとしたエピソード、さらに日常的な料理やワインも含め、ささやかで素敵で愛おしいものが詰まっている。
いろんな関係性があったほうが豊か
視点人物は他に、民子の母の薫、民子の元恋人で今は友人の百地、民子の亡くなった友人の娘で、よく訪ねてくるまどかとその恋人、理枝が可愛がっている甥っ子の高校生、朔ら。10代から80代までさまざまな人物が登場する。
「50代の女性たちを書いていても面白かったんですけれど、薫さんのように80歳くらいになってお元気な方も、また一段階はじけた面白さがあるなと書きながら思っていました。薫さんはすごくきちんとしているので自分では良識的な人間だと思っていますけれど、わりと自由ですよね(笑)」
また、百地は最近になって離婚、そこから家事に目覚め、民子に料理を振る舞ったりしてなんだか楽しそう。
「離婚後に家事にのめり込んでいる男性を何人か知っています。その人たちが言うには、結婚していた頃は自分は毎日会社に行くから家事は妻の領分で、口出しするとケンカになるので何もできなかったそうです。ただ、百地については、この先ずっと一人で自分のために家事をしていたら孤独じゃないのかなと他人事ながら心配になります(笑)。彼は自分の丁寧な暮らしの観客がほしいんですよね。だから民子に料理を振る舞ったり、自分が撮った写真でカレンダーを作って配ったりしている」
ちなみに百地と民子は、今のところ恋愛感情が再燃することはなさそう。
「異性の友達って長く知っていると、異性だと意識しなくなるところがありますよね。それに、同性同士でも異性同士でも、いろんな関係があるほうが健全だと思うんです。男女だからといってドキドキするとは限らないし、同性同士だからフランクな関係になるとも限らない。でもそんなふうに、いろんな関係性を持てるほうが豊かな感じがします」
一方、まだ若いまどかや朔それぞれの恋模様は、意外な展開に。さらには理枝にも新たな恋が待ち受けている。彼女は遊び慣れていそうな男にもころっといくところがあるのだ。
「彼女の気持ちも分かります。友達に急に遊びに来られた時の困るけど嬉しい気持ちと同じで、急に露骨なアプローチをされると困るけれど嬉しいんじゃないかな、って(笑)。理枝が新たに恋に落ちた相手と手をつなぐ場面は、私も書きながらドキドキして〝やだ、もう〟みたいな気持ちになりました(笑)」
同じ50代でも、理枝のように恋愛体質の人もいれば、民子のように恋愛から遠ざかった人もいるわけだ。
「民子と百地のような友達づきあいも楽しそうだけど、理枝みたいに男の人をあくまでも恋愛対象として見るエネルギーにも羨ましさを感じます。私はこの歳になって、自分はこの先恋愛しないのかなって思うとちょっと驚くというか。若い時って、結婚しても離婚するかもしれないし浮気するかもしれないし、浮気されるかもしれないし、先のことは分からないという感覚が普通でした。でも今は、この先なにもないかもしれないと思うんですよね。他にも、昔は映画やテレビで海外の素敵な場所を見たらいつか行こうと思ったし、いつでも行けると思っていたけれど、今はそういう映像を見ても、自分は生涯ここに行くことはないのかなって思うんです。もしかしたらこの先何もないかもしれないと思う時の驚きと恐怖ってある。そういうことが増えていく年齢ではありますね」
とはいえ、3人や薫さんを見ていても分かるように、50代以降は変化のない日常が続くというわけでもない。
「日々変わっていくものはありますよね。たとえば理枝が来る前の民子と薫の暮らしと、理枝が去った後の二人の暮らしは、表面的に変わらないように見えて、何かが違うはず。民子のなかで、自分はもう結婚はしないだろうと思うようになるという心の変化もあるだろうし、薫さんの亡くなる時も近づく、という変化もある。日々失われていくものって物語的には面白かったり美しかったりするけれど、実際にはちょっと切なくもありますね」
この3人や周囲の関係についても、変わらないでほしい、ずっとこのまま読んでいたいと思わずにはいられない。この物語の終え方は、どのようにイメージしていたのだろう。
「いつ終わりにしてもよかったんです。彼女たちはこんなふうに暮らしていて、明日も来週も来年もいろんなことが続いていくと感じられる終わり方にしようと思っていました」
本を閉じた後も、登場人物たちのその後を想像、あるいは予想して楽しませてくれる本作。前述の『なかなか暮れない夏の夕暮れ』や、実に100人以上のキャラクターが登場する『去年の雪』など、最近の江國さん作品は群像劇の印象も強い。
「昔は一人称だったり、せいぜい二人の視点を交互に書いていたのに、なぜか群像劇が多くなりましたよね。ここ最近は現実の時間と地続きっぽい小説を書きたいと思うことが増えたんですが、地続きを書こうとすると人が増えてしまうんですよね。たとえば、夫婦が出てくるとしても、二人がお互いのことだけを喋っているだけなんてことはありえない。他の誰かのことを話すだろうし、誰かに電話したり、誰かから連絡があったりするだろうし、人との繫がりが果てしなく広がっていく。小説にするならそれを上手にトリミングして分かりやすい形にしなくてはいけないんでしょうけれど、私はわりと茂り放題のものを書きたくなるというか。人工的な手を加えないまま、天然のままの姿を見ていたいのかもしれないです」
江國香織(えくに・かおり)
1964年東京都生まれ。2002年『泳ぐのに、安全でも適切でもありません』で山本周五郎賞、04年『号泣する準備はできていた』で直木三十五賞、07年『がらくた』で島清恋愛文学賞、10年『真昼なのに昏い部屋』で中央公論文芸賞、12年「犬とハモニカ」で川端康成文学賞、15年『ヤモリ、カエル、シジミチョウ』で谷崎潤一郎賞を受賞。小説のほか童話、詩、エッセイ、翻訳など幅広い分野で活躍。