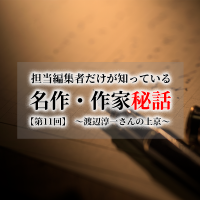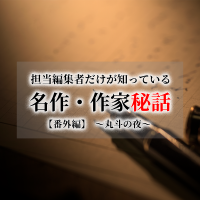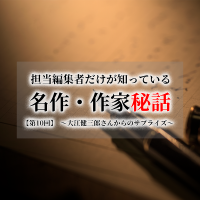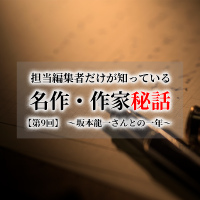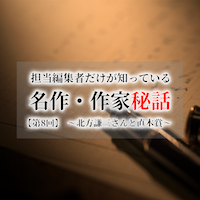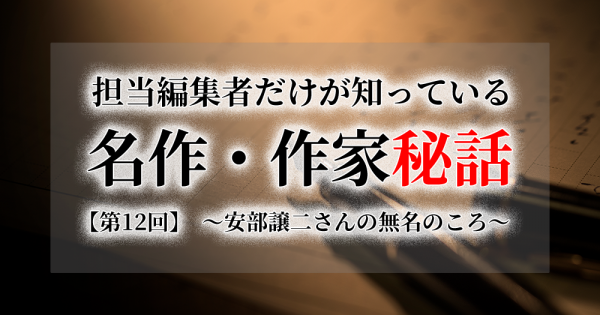連載[担当編集者だけが知っている名作・作家秘話] 第12話 安部譲二さんの無名のころ
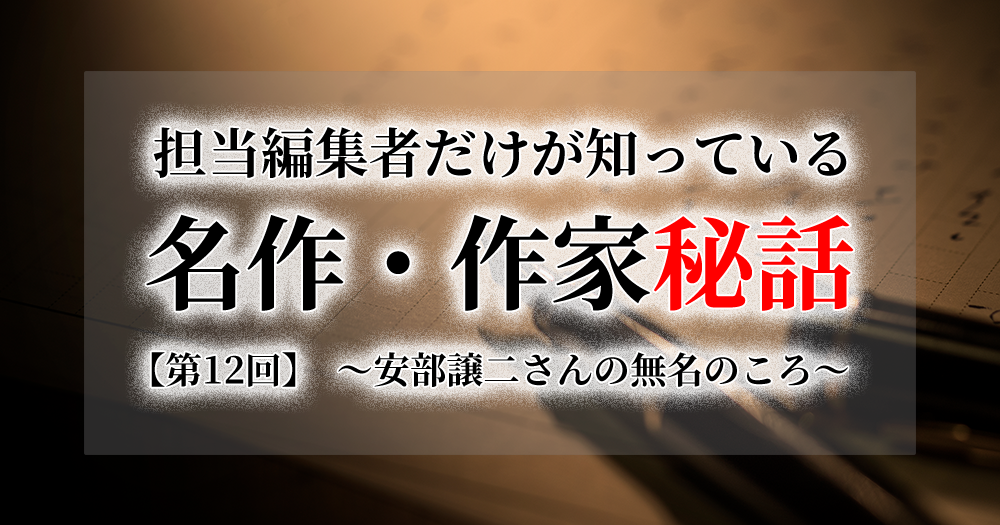
名作誕生の裏には秘話あり。担当編集と作家の間には、作品誕生まで実に様々なドラマがあります。一般読者には知られていない、作家の素顔が垣間見える裏話などをお伝えする連載の第12回目です。「安部譲二」といえば、ベストセラー『塀の中の懲りない面々』を生んだ作家であり、その波乱万丈な生き方やエピソードでも広く知られています。どんな経緯で執筆を始めることとなったのか、担当編集者が振り返ります。
安部譲二さんの無名のころ
安部譲二さんに初めて会ったのは、私が「イン・ポケット」という文庫サイズの、文庫本の宣伝雑誌を創刊した頃だから、1983年のことだと思う。もう四十年も前のことになる。
『コメディアン犬舎の友情』という短篇集で、1975年に直木賞候補になった作家の沼田陽一さんから紹介された佐藤実さんと仲良くしていたが、その佐藤さんが、
「元やくざで、いまノミ屋をやっている男がいてね。小説を書きたがっているんだ。会ってやってくれないかな」
と、話を持ちかけてくれた。佐藤さんは、一人で編集プロダクションをやっていて、フリーランスの編集者でもあった。
「サドマゾ専門誌のタイトルを思いつきましたなんて電話してきて、それが、『無理矢理マガジン』って言うようなおかしな男なんだけどね」
正直、いまは競馬のノミ屋をやっているという、元ヤクザと会うのは億劫だった。小説を書くことは地道な作業で、多くの場合、その努力が報われることの少ない、厳しい職業だ。私には、ヤクザを、職業と言っていいのか分からないけれど、世間の人から甘い汁を吸うというようなイメージがあった。小説家になるということと真逆に過ごしてきたような元ヤクザがそんな苦労に耐えられるとは思えなかったのである。
だが、佐藤さんは、自分には一文の得になる話でもないのに、ぜひ会ってほしいと言って、神楽坂の小料理屋の二階の小部屋を予約までしてくれた。これでは、佐藤さんの顔を立てないわけにはいかない。私は、佐藤さんのつきそいを条件にその男に会うことにした。

約束の日の夕方、神楽坂の小料理に行くと、佐藤さんと大柄な男がもう部屋で待っていた。
その大柄な男が、のちの安部譲二さんだった。
安部さんは、これまでの半生を清算して、堅気になるために小説を書きたいと言った。変わった経験をたくさんしてきたので、書く材料には事欠かないとも言った。
少し掠れた声でそんなことを話しながら、ときに愛嬌のある笑い顔を見せることがあった。それは、のちに安倍さんが、「ゴロツキのマスクを崩してしまい、少年の頃の顔に一瞬戻った」と表現している顔の変化だと思う。
だが、その笑顔が、急に真面目な顔に変わるとき、ヤクザ独特の怖い表情になった。この落差のオソロシサを、そのむかし安部さんが恐喝などをしたときに効果的に使ったのだなとも思った。
私が高校生のとき、同じ高校生からカツアゲを食らったことがあったが、そのとき、笑顔から怖い表情に変わったときの落差がオソロシくて、オズオズと財布を差し出したことを思い出していた。
つまり、私にとって、そのときの安部さんは、ベストセラー作家・安部譲二になる前の、ゴロツキで、いまは、ノミ屋で食べている安部さんだったのだ。
私は、安部さんに、「小説を書くというのは、一字一字マス目を埋めていく、愚直な作業を強いられます。これまで安部さんが歩いてこられた道とはまったく逆の作業なんです。それに耐えられますか?」
と、訊いた。このことだけはしっかり確認しておきたかった。
安部さんは、急に座り直して、姿勢を整えた。そして、
「もちろん、小説を書くことは大変なことだと承知しています。頑張りますから、よろしくお願いします」
と、言って畳に手を着き、深くお辞儀をした。
この人の決意は本物だ。
私はそう思って、「それじゃあ、一緒にやって行きましょう。まず、いま一番書きたいものを、好きな枚数で書いて来てください。それを拝見するところから始めましょう」
「よろしくお願いします」
「こちらこそよろしくお願いします」
それからしばらくして、20数枚の、コクヨの原稿用紙に躍るような字で書かれた短篇小説を持って安部さんが来社して来た。まだタイトルもついていない、荒削りの原稿で、その段階では、とても小説とは言えないようなものだった。
しかし、随所にほかの人には書けない独特のユーモアとペーソスに溢れた一言一句があった。
たとえば、いまでも覚えているのは、塀の中でのソフト・ボール大会で、賭けに勝ちそうになった男が、大口を開けて笑う姿を、「ノドチンコに春風を当てた」と描写してあったことだ。こんな表現は安部さん独特の表現で、安部さん以外誰にもできないことだ。
「懲役」という単語も、安部さんの小説の中では、独特の人間臭さを持つ言葉になっていた。「ウカンムリ」と言えば、窃盗犯の前科のことだ。
また懲役人へのあだ名の付け方やソフト・ボール・チームの名前の付け方にもセンスを感じさせた。凄い腋臭のニオイの男は「オイニ」、甲府の痴漢が「甲州」、新橋のルンペンが「オトウ」、背中に鯉の入れ墨の男が、「抱き鯉」。頭と首が左肩に傾きっ放しの看守には「ハテナ」という仇名を奉っている。対戦するふたつのチームの名は「バレモト・ギャングズ」と「グレイ・ジャイアンツ」という塩梅で、そのほかに、詐欺横領の知能犯チーム、「トリッキーズ」や、彫物をアンダーシャツがわりのゴロツキが集っている「タトゥメン」が控えている。
まだ小説以前だが、随所にきらめく表現がある原稿が、私を魅了した。新しい才能を見たときの、全身に電気が走るような感じを持った。
そして、原稿を全てコピーして、それに赤字を入れて行った。そのとき、自分に戒めたのは、「角を矯めて牛を殺す」ようなことをしないということだった。文法に適っていなくても、奇抜で面白い表現ならそれでヨシ! だ。
そして、そのコピーを渡しながら、安部さんに、「この赤字を取り込みながら、全部書き直してください。赤字が気に入らないところは、自分で工夫して新しい表現にしてもらっても構いません」
というようなことを言った。
安部さんは、喜んで帰っていった。そして、それからあまり日が経たないうちに、安部さんが書き直した原稿を持ってやってきた。その原稿はずっと良くなっていた。コピーにとって、また赤字を入れて、安部さんに返しながら、同じことを言った。
こういう過程を4度ほど繰り返して、一本の原稿が完成した。安部さんの言葉では、「文章の書き方も、原稿用紙の使い方も全て、面倒臭がりもせず、とうの立った新米に教えて下さったのです」ということになる。
発表するにあたり、ペンネームをどうするか話し合った。堅気になるんだから、本名の安部直也ではなく行きたいという希望だった。元ヤクザが堅気になるのはそれなりの苦労があるのだろう。
安部さんは、
「三島由紀夫さんが、『楯の会』の制服を作ったりする資金稼ぎに、『週刊女性セブン』に、ぼくのことをモデルに小説を連載しているんです」
と、言った。
へえと私は思ったが、三島さんが、日航のパーサーだった安部さんをモデルにして『複雑な彼』という小説を、1966年に、『週刊女性セブン』に連載していたのは本当のことだった。ちなみに、「楯の会」は1968年10月5日に正式に結成されている。
「その小説の主人公が、『宮城譲二』って言うんですが、それをペンネームにいただきましょうか」
安部さんは言った。
「『譲二』はいいけれど、『宮城』ってのが、ピンとこないなあ」
私は答えた。
「じゃあ、橘丈二ってのは?」
「演歌歌手じゃないんだから」
そんな会話のあと、私は、
「堅気になるんだと決心したんだから、姓の『安部』は残して、『安部譲二』ってしましょうよ」
と、言った。
安部さんは何度か、「安部譲二」「安部譲二」と呟いてから、「いいなあ。『安部譲二』で行きましょう」と言った。こうして、作家・安部譲二が誕生した。
安部さんは、「ここ(講談社)の売店で本が2割引で買えるのがとてもうれしい」と言って、「今日も寄って行きます」と続けた。本当に本好きな人なのだ。
おまけに安部さんは何度か来社するうちに、受付のご婦人たちの人気者になった。たぶん「少年の頃の顔」で、話しかけていたのだろう。
私は原稿の書き方などは教えたことになるが、安部さんからはいろいろなことを教わった。安部さんはジャズでも、映画でも、野球でも、酒でも、バーでも、着る物でもなんでも本物を知っていた。実は、安部さんは、ヤクザな生活をしながらも、その複雑な半生で、一流の人と出会い、一流のジャズを聴き、一流の酒を飲み、しかも本をたくさん読んできた、本物の知識人だった。
ところで、Wikipediaなどを読むと、安部さんは「1983年から小説を書き始めた。著書を出してくれる出版社が見つからなかったが、1984年山本夏彦に文才を見出され、雑誌『室内』に刑務所服役中の体験記『府中木工場の面々』の連載を開始した」と書かれている。続けて、「1986年に、その連載がまとめられ、『塀の中の懲りない面々』として出版された」とある。
このあたり、いくつかの誤解があるようなので、補足しておきたい。まず、『塀の中の懲りない面々』は、『室内』に連載されたものをまとめたのであるが、本にするには原稿が少し足りなくて、9篇は書き下ろされて収録されているというのが本当だ。
もうひとつ、「1983年から小説を書き始めた。著書を出してくれる出版社が見つからなかった」とあるが、安部さんがはじめて書いた小説「塀の中のプレイ・ボール」は、1983年10月号が創刊の「イン・ポケット」の翌1984年の1月号に、「今月の短篇」として、掲載されているのだ。
安部さんは、「最初に『塀の中のプレイ・ボール』が『イン・ポケット』で活字になった日のことを、今でも決して忘れません」と書いているくらいだ。
『塀の中のプレイ・ボール』の文庫版に「無名のころ」と題した解説で、山本夏彦さんが、
「安部譲二を最初に発見したのは私ではない。『イン・ポケット』(講談社)の宮田昭宏氏で、それを見て、『室内』にながい連載を頼んだのが私だというだけのことである」
と、書いて下さっている。ありがたいことだ。
ただ、私が、安部さんに申し訳なく思っているのは、次のようなことがあって、書籍化するまではずいぶんと時間がかかってしまったことだ。
小説やエッセイを掲載する雑誌を編集していると、その間、新人作家などの掲載を待機している「組み置き」という原稿がいくらかたまっているものである。作家に不慮の出来事が起きたり、大いに多忙の作家の原稿が土壇場の土壇場でオチたときに、代わりの作品として使えるようにしておくわけだ。
私が「イン・ポケット」誌を出したときには、その「組み置き」原稿が一作もない状態だった。
それなのに、私は、「遅筆堂」なんて自分専用に原稿に印刷しているくらい、自他ともに認める遅筆作家・井上ひさしさんの連作「ナイン」をはじめてもらっていた。そんなことがないに越したことはないが、この連作が、いずれ落ちるだろうと覚悟していた。だから、「ナイン」と同じ枚数の「組み置き」を何篇が持っていたかったのである。
私の心配は杞憂に終わらなかった。井上ひさしさんの連作は何度か落ちた。そしてその代わりに、「組み置き」の安部さんの原稿が掲載されたのである。安部さんは、「イン・ポケット」では、そんな扱いだった。誠に申し訳ないことだといまでも思っている。
その一方で、安部さんは山本夏彦さんの「室内」に毎月の連載をはじめていた。しばらくして、安部さんは、自分の作品だけが載っている本が欲しいと思うようになった。当然である。
そして、安部さんの希望通り、1986年に、文藝春秋から、はじめての本が出版された。ミリオン・セラーになり、安部さんを人気作家にした『塀の中の懲りない面々』である。この本が出た背景にも人と人の繋がりが作るドラマがあるので、それを書いておきたい。
山本夏彦さんの担当だった文藝春秋の新井信さんは、同時に丸谷才一さんの担当でもあった。当時、丸谷さんはいくつかの小説のプランを進めていて、そのために、喧嘩に強い人に喧嘩の仕方を教授してほしいと思っていた。それを新井さんに漏らしたところ、山本さんの薦めで、安部さんの本も進めていた新井さんは、元ヤクザだった安部さんが適任だと、丸谷さんが安部さんに喧嘩殺法を教わる場を設けた。その席で、丸谷さんは、安部さんの人柄にすっかり魅了された。結局、そのときに聞いた喧嘩のことは、丸谷さんの小説には活かされることはなかったが、その縁で、丸谷さんは、安部さんの『塀の中の懲りない面々』の帯を書くことになった。
当時、丸谷さんは帯の推薦文の名人の名をほしいままにしていて、丸谷さんが書いた帯を巻いた本はほとんどベスト・セラーになったものだ。
丸谷さんが『塀の中の懲りない面々』に書いた帯文はこうだ。
「安部譲二さんは喧嘩がむやみに強かった。強すぎて、刑務所にはいつた。それがキッカケで原稿用紙に字を書くといふ道楽を覚え、とうとう物騒な渡世をよして、わたしの同業者になった。向うの業界のために惜しむべし、こっちの業界のために喜ぶべし」
しばらくして、「安部譲二を励ます会」が催されたが、そのときに、山本夏彦さんは、「私は盗みも殺しもしない。けれども盗むひと殺すひとの心持が書けるのは、心中ひそかに盗みまた殺しているからだ。私と安部はこと同根の兄弟だ」と、とてもいい挨拶した。
その会の終わりに、安部さんの兄弟分という人が締めの挨拶に立った。
「私はひとつのシマを守っています。死んで守る、死守と書きます。よく死にます」
と、笑いをとったあと、
「安部をそちらの世界に送りますので、もうこちらに帰ってこないようによろしくお願いします」
と、言ったあと、
「では、一本締め。ご唱和、願います」
と、音頭を取ったが、このときの一本締めほど、一同、気合が入って、素晴らしくキマった一本締めは後にも先にもない。
こうして、安部譲二さんが人気作家になっていったのは、どなたもご承知の通りである。
『塀の中のプレイ・ボール』は、少し遅れて1987年に単行本になった。
「スーパーで、財布と相談しながら買い物をしなくていい身分になりましたよ」
と、本当に嬉しそうに言った安部さんの言葉が、スーパーの中で、ときおり聞こえてくるときがある。
【執筆者プロフィール】
宮田 昭宏
Akihiro Miyata
国際基督教大学卒業後、1968年、講談社入社。小説誌「小説現代」編集部に配属。池波正太郎、山口瞳、野坂昭如、長部日出雄、田中小実昌などを担当。1974年に純文学誌「群像」編集部に異動。林京子『ギアマン・ビードロ』、吉行淳之介『夕暮れまで』、開高健『黄昏の力』、三浦哲郎『おろおろ草子』などに関わる。1979年「群像」新人賞に応募した村上春樹に出会う。1983年、文庫PR誌「イン☆ポケット」を創刊。安部譲二の処女小説「塀の中のプレイボール」を掲載。1985年、編集長として「小説現代」に戻り、常盤新平『遠いアメリカ』、阿部牧郎『それぞれの終楽章』の直木賞受賞に関わる。2016年から配信開始した『山口瞳 電子全集』では監修者を務める。