江國香織『彼女たちの場合は』で迎えたひとつの終着点 「自由であること」への覚悟と潔さ

2年ぶりの長編小説となる『彼女たちの場合は』を2019年5月に上梓した江國香織さん。翻訳、詩作でも高く評価され多方面で活躍をつづける彼女は、児童文学の書き手としてキャリアをスタートし、恋愛小説の旗手となって多くの読者の心を掴んできました。自身が年齢を重ねるとともにその作品世界も深みと広さを増していき、さまざまな年代の男女の愛のかたちを描いてきた作者が、いまふたたび、10代の少女の物語を描くことで伝えたかったこととは何なのでしょうか。
1.がんじがらめの10代が「自由」を求める旅へ/『彼女たちの場合は』
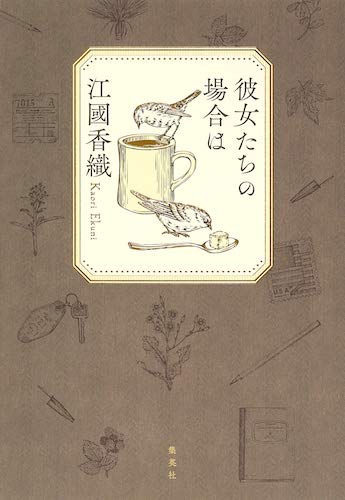
https://www.amazon.co.jp/dp/4087711838
「礼那(れいな)」と「逸佳(いつか)」。2年ぶりの長編『彼女たちの場合は』に登場する2人の少女は、いとこ同士。物語は、ニューヨーク近郊の家で礼那の母・理生那が書き置きのメッセージを発見するところから始まります。突然の、少女二人の出奔――。サスペンスフルなそんな状況とは裏腹に、感情を抑えた硬質な語り口で、物語は徐々に展開していきます。
本書に登場する14歳の礼那は、まだ存在のすべてがその純粋さに満ちている「少女」。見守る逸佳は、礼那とは反対に、おそらく少女のころから「純粋さ」を手放しに表現することができなかった不器用な性格で、日本の学校になじめずアメリカへと渡ってきます。17歳と14歳のいとこ同士の関係は、逸佳が礼那の保護者代わりであるかと思えばそうでもなく、甘えあい、ときには争い、まるで完全には分離していない一卵性双生児のように、二人は10代の多感なセンサーそのものとなって見るもの、体験するものすべてをこころとからだに刻みつけていくのです。
「来たね」
チェックインを済ませ、部屋に入って荷物を置くと、いつかちゃんが言った。
「来た」
こたえると、じわじわと喜びが湧いた。『ホテル・ニューハンプシャー』のパパとママがほんとうに出会った場所。静かな海辺、電車もバスも走っていない土地、しかも太陽はまだほとんど真上に輝いている!
江國香織作品には、しばしば、「旅」が重要な要素として登場します。ロード・ムービーを思わせる『彼女たちの場合は』や『神様のボート』のように、実際の移動を伴うこともあれば、日常の中で、自分だけのルールに従い、心と体を解き放つような精神的な意味での「旅」もあります(『ホリー・ガーデン』や『薔薇の木 琵琶の木 檸檬の木』など)。
10代のふたりの少女、礼那と逸佳が体験する、人生はじめての旅。思わぬトラブルや悪意にさらされながらも、それでも進むことを止めないふたり。それらを補って余りある旅の醍醐味とは、「自由」です。どこへいくのも、何をするのも自由。自分がどこへ行き、何をすべきかの決定権が自分にあること――。それこそ、幼い体で内外のストレスに耐えてきたふたりが、10代の今、求めずにはいられないものだったのかもしれません。
また、ふたりの旅のサイド・ストーリーとして語られるそれぞれの両親の物語の中で、礼那の母は夫との離婚を決意し、新たな人生への一歩を踏み出します。年代やとりまく環境は違えど、これも、ひとつの「自由」を得るための戦いだったと言えるでしょう。
作者にとって、自分の人生の決定権が「自分にある」こと、そしていつでも「自由」でいることが、どれほど大切なことであるかが、物語を通して幾重にも語られていくのです。
2.素直に、のびやかに、自身の過去と今の想いに向き合う/『旅ドロップ』

https://www.amazon.co.jp/dp/4093886997/
2019年7月に上梓された『旅ドロップ』は、タイトルにあるように「旅」をモチーフにしたエッセイ集です。巻頭にはやはり旅に関する詩が3編収められており、読み進めるたびに心を躍らせてくれる、不思議な軽さと温かさに満ちた一冊です。
ひとつひとつ独立した短いエッセイにしばしば登場するのが、作者の10代のころの親友とのエピソードです。
私とその友人は、十三歳のときに女子校で出会った。どちらも本が好きで外国に憧れていて、ドラマティックなことが好きでおいしいものが好きで、すぐに意気投合した。
トーマス・クックの時刻表は、私たちの宝物だった。ひろげて部屋の壁に貼り、「壁のその部分だけ外国みたいだ」と思っていた。
いつか二人で世界を見よう。シベリア鉄道にも乗ろう。パリの地下鉄にも乗ろう。(中略)
たくさんの約束をした。
『旅ドロップ』と『彼女たちの場合は』を比べて読むと、礼那と逸佳の旅は、著者自身とかつての親友との、若き日の経験をもとに着想されていることが感じられます。作者は親友とふたりで、20歳のときに初めてのパリ旅行に出かけており、思いがけぬ多くのトラブルに見舞われています。しかし、くじけそうになりながらも、大人に守られることなく自分たちの手ではじめて広い世界に触れた鮮やかな感動と衝撃が、『彼女たちの場合は』の主人公2人の描写に重ねられていることは想像に難くありません。そして作者の、「旅が好き」というより「旅をせずにはいられない」性分を知ると、江國作品に登場する人物たちが老若男女を問わずなぜあれほど「自由」を求めてやまないのかが、少しだけわかるような気がします。
いつも、現実のようでいて現実ではないような「ここではないどこか、いまではないいつか」を描き、私小説的な物語とは断固として距離を置いてきたような作者が、とてものびやかにそして素直に、自身の過去と今に向き合っているかのような『彼女たちの場合は』と『旅ドロップ』を続けて上梓したことにも驚かされるのです。
3.“自分に正直であること”の難しさを教えてくれる/『流しのしたの骨』

https://www.amazon.co.jp/dp/4838707967/
ここで初期から中期の江國作品を改めて紐解いてみましょう。まず最初は、ドキリとするタイトルが印象的な、風変わりな6人家族の日々を描いた作品である『流しのしたの骨』です。
大学にいかない主人公のこと子、学校で問題をかかえる末弟の律、詩人でこだわりの強い母……。宮坂家の個性的な面々に読者は最初、とまどい、世間のルールを無視したような自由奔放なあり方に眉をひそめるかもしれません。物語がすすむにつれ、家族の内外で起きる様々な出来事に、ひとりひとりが向き合い、何かを失ったり得たりしながら成長していく姿に、いつしか自分自身のあり方を重ね合わせてしまう、ふしぎな温かさに満ちた物語です。
そよちゃんは堂々としていた。
「おどろかせてごめんなさい」
気の毒な両親にそう言って頭を下げたけれど、ちっともすまなそうじゃない。
(中略)
「いま四カ月で、お医者様の診断ではすべて順調だそうです。そろそろ安定期に入ります」
「四カ月ってあなた、それじゃわかってて別れたの?四カ月って」
(中略)
母がため息をつき、部屋のなかがしんとした。
プツンと小さな音がして、一瞬のちにテレビがついた。みると父がリモコンを持っている。
「あなた」
母が厳しい声をだした。テレビは騒々しいクイズ番組だ。
「仕方ないじゃないか」
ソファにすわってテレビをじっとみたままで、父は小さな声で言った。
「仕方ないじゃないか」
私は律と顔をみあわせた。苦々しい口調をとり繕っていても、父の口元がすでにゆるんでいたからだ。
妊娠していながら、とつぜん離婚を宣言した長女そよのように、彼らの起こす騒動は、「世間」からみれば「インモラル」であったり「常識外れ」であったり、子どもっぽくさえ見えるかもしれません。しかし主人公のこと子や両親は、驚きはしても、そうしたことをひるむことなく受け入れてしまうのです。きちんと進学する、結婚をして独立する、経済的に安定する……、「大人として」推奨される形は、あくまで結果であって「目的」ではないことを、作者はこのちょっぴりおかしな家族のすがたを通して、私たちに提示しているのかもしれません。
正しいとか間違っているとか、おかしいとかおかしくないとか、そうしたことを他人に決めさせるのではなく、自分たちで決める。それは一見簡単なことのようで、じつはなかなか出来ないことのようにも思えます。「こうありたい」という心に正直で居続けることは、大人になればなるほど難しい。それがわかっているからこそ、主人公のこと子が少女から大人へと脱皮してゆくひとときの季節を描いた物語が、胸をゆさぶるように美しく、そしていとおしく思える気がします。
4.“瞬間”を切り取るように生きる潔さ/「泳ぐのに、安全でも適切でもありません」
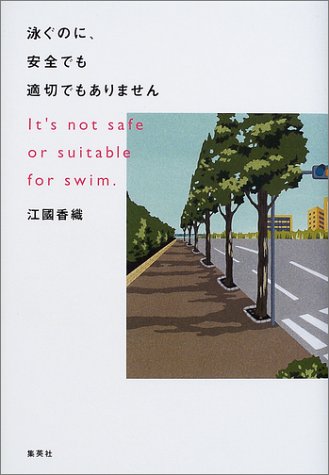
https://www.amazon.co.jp/dp/483425061X/
第15回山本周五郎賞を受賞した本作は、10編の物語からなる短編集です。詩人としても評価の高い作者の言葉選びは、短編という形によってより発揮され、殺風景な部屋や散らかったカップめんの容器といったものさえ、凜とした情景のある佇まいに変えてしまうようです。ほぼ一人称で、暴力的にさえ思えるほど次々くりだされる主人公達のモノローグは、行き場のない恋情や、あきらめ、性への渇望を、おもむくままに語ります。そこには、「常識」や「世間」といったものからどう見られるか、といった遠慮はひとかけらもありません。やりたいからする、食べたいから食べる。体と心で存分に感じる、生きることと愛することの喜び。いつも他者との比較ではなく、いかに自分の心に誠実であるかに意味を求める作者のしなやかさと強さが、行間からあふれでてくるほどです。
「こんなふうにしてどこまでいかれるかしら」
あたしは裕也に訊いてみることがある。(中略)
「死ぬまでこんなふうに暮らせるかしら」
きょうのワインは濃く、口の中のあちこちにしっかりと触れ、かがやかしい干しぶどうの味がする。
「こんなふうに、食べることと寝ることだけをくり返して」
あたしの言葉を、裕也がクレソンでふさぐ。
「食べて」
(中略)
「つまらないことを考えてないで、食べて」
裕也がくりかえす。あんまりやさしい声なので、あたしは泣き出しそうになる。
(中略)
あたしはもう裕也が欲しくてたまらなくなる。食事どころではなくなる。でも同時に、うんとたくさん食べられそうな気がする。うんとたくさん、もう超人的に。
(「うんとお腹をすかせてきてね」)
2編目の「うんとお腹をすかせてきてね」に登場する裕也と美代のカップルは、怖いものなしのように見えながらも、物語の終盤、美代はふたりの将来についてふいに不安を感じてしまいます。それを打ち消すように、ふたりはまた、ふたりだけの世界に没入していきます。どれほど体を重ねても、所詮は別々のいきものであること、流れる時をとどめることはできないこと、そうした諦念をのみこんだ上で、だからこそ、ともに過ごす時間を思い切り味わいつくす。「安定」や「約束」にこだわるよりも、それがどんなに贅沢で、そして得がたい「自由」であるかが、短編とは思えないほどの質量で胸に迫ります。
恋愛も結婚も、打算的なものであふれている世にあって、作者は純粋な愛のかたちを映画のシーンのように切り取りながら、自分らしくしなやかに生ききることの大切さを、伝えてくれているかのようです。
日々の中で、誰もがしがらみや、摩擦、他者の視線や世間の評価を気にしないでは生きられません。「そういうものなんだ」と割り切ってしまおうとすればするほど、心の中にあるのびやかな「自由」、それを求めるほんとうの「自分」の声さえ聞こえなくなってしまうのかもしれません。江國作品に登場する主人公達は、一見すれば世の中にうまく適応できなかったり独自の価値観で生きているように見えながら、その実とても「まっとうな」純粋さを身につけており、それはそのまま、「自由であることから逃げない、自分自身であることから逃げない」作者からの変わらないメッセージのようにも受け取れます。
バスは予定より十五分早くポート・オーソリティに到着した。地下停車場は螢光灯に照らされ、何台ものバスの排気ガスや、乗客たちの眠気や疲労、乗車を待つ人々の列が発する落ち着かない空気が充満していたが、逸佳が感じているのは思いがけない高揚感だった。この場所からバスに乗って旅を始めた。あのときの自分たちは、そのあとに起きたたくさんの出来事の、どれ一つ知らなかったのだ。自分たちがどこに行くことになるのかも、何を見ることになるのかも。
「帰ってきたね」
うさぎを抱いた礼那が言い、このうさぎもあのときにはいなかった、と逸佳は思った。
「うん、帰ってきた」(『彼女たちの場合は』)
礼那と逸佳の長い長い旅は、出発地点へ戻ることでこうして終わりを迎えます。そして終わりは、新しい始まりでもあります。失われていくものや変わっていくもの。愛情という、うつろうもの。児童文学の書き手から恋愛小説家へ、そして男女のかたち、家族のかたちをさまざまに描きながら、「自分であること」そして「自由であること」から目をそらさない作者の強い想いは、儚く美しい文体ながら、読むものの心の確かな拠り所となる強さを持っています。新作に登場したふたりのティーンエイジャーの旅を通して作者が私たちに見せてくれたのは、「自分の人生の決定権は自分にある。そして自由であることの代わりに、すべての責任も自分にある。」という、まっとうだけれど世間ではどこか軽んじられている「真実」です。初期の作品から形を変えながらも、繰り返し強く伝えられる自由へのメッセージは、作者自身を思わせる少女たちの「旅」を通して、まるでひとつの終着点を迎えたようです。
そして物語と同じように、この「終着点」は新たな始まりでもあるのでしょう。これからも私たちは、江國作品を手に取ることで、自由な精神とともに「ほんとうの人生」や「ほんとうの恋愛」に踏み出すための勇気を、行間からあふれだす、ひそやかな情熱をまるごと咀嚼してからだに取り込むように、手に入れることができるのかもしれません。
初出:P+D MAGAZINE(2020/03/04)

