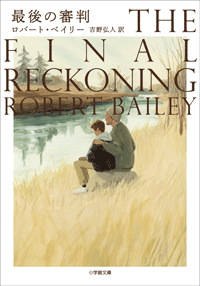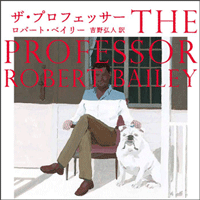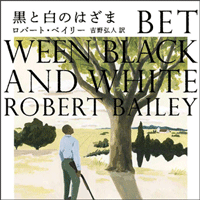◎編集者コラム◎ 『最後の審判』ロバート・ベイリー 訳/吉野弘人
◎編集者コラム◎
『最後の審判』ロバート・ベイリー 訳/吉野弘人

「ありがとう、教授」
原稿を読み終えて、思わず呟いてしまった言葉です(作中にも、主人公トムの担当医の言葉として登場します)。
二〇一九年三月に刊行した第一作『ザ・プロフェッサー』にはじまり、『黒と白のはざま』『ラスト・トライアル』と巻を重ねてきたアメリカ発胸アツ法廷エンタメシリーズも、いよいよ最終作となりました。あらゆる困難に対しても常に全力で立ち向かい、仲間や教え子の危機には命を掛けて救おうとする――元教授で弁護士のトムは小説の登場人物にすぎないにもかかわらず、一読者の私に多くのことを教えてくれ、気づけば私にとっての本当の「先生」となっていました。今では、自分自身が「チーム・トム」の一員のような気すらしていています。
それは、本シリーズをこれ以上無いほど力強く応援し続けてくれた TSUTAYA 中万々店の山中由貴さんも同じだったようです。今回、最終作『最後の審判』に愛溢れる激アツ解説原稿を寄せてくださいました。読者の皆さまにもこの熱い思いをご共有頂きたく、山中さんの解説全文を掲載致します。ぜひお読みください! そしてとにかくべらぼうにおもしろい、この四部作を手に取って頂ければ幸いです。
──『最後の審判』担当者より
解 説山中由貴
大好きなシリーズの本の最後の一冊を読み終わるとき、ああおもしろかった、だけではない、さびしさとほっとした気持ちがごちゃまぜになったような、好きな人が乗った電車が動きだしてもう二度と帰ってこないことを噛みしめるような、たっぷりした放心が身体にゆき渡る。そこから少しずつ感情がほどけていって、最後に、シリーズを書き通した作者と、読み通した自分とが、肩をくんで「やあ、おつかれ、おつかれ」なんていい合いながら夜道を去っていくところを夢想してやっと、心が落ち着く。
だけどいま、そんな比喩では足りないほどの深い喪失感を味わっているのは、わたしばかりではないはずだ。
もっともっと読んでいたかった。
トム・マクマートリー、あなたがあまりにも最高だから。
シリーズ一作目、『ザ・プロフェッサー』をまだ序盤しか読んでいないうちから、「やべーーーーー!」なんていう、語彙力をどこかに置き忘れてきた叫びをツイッターに吐露してしまったのは、そのおもしろさをひとりで抱えきれなくなったからだった。
最初の百十ページで、わたしはこのトム・マクマートリー・シリーズにぎゅっと腕を摑まれてしまった。
アメフトの学生王者として活躍したのち法律家になり、大学の教授に転身して堅実に生徒を育て、社会に数百人と法律家を送り出してきたトムが、癌で妻を喪ったあと、友人に裏切られて職を失い、さらには自分自身まで癌に冒されていると判明する。人生に絶望しきってしまうまでを、ものすごくスピーディに書いてひと息で読ませ、あとは逆転するしか道はない。そうなったらもう誰だって、続きが読みたくてたまらなくなるものだ。
やばいぞ、これはおもしろいぞ……!
興奮でとにかく誰かになにかをぶつけたかった。ツイッターに吐きだしたあとも、次の日が仕事なのも関係なく、枕もとの狭い電球の明りのなかで、何時間でも読んでいられた。
そしてそこからまたさらに、数倍の握力で物語に引きずり込まれるのがすごい。
こんな展開は想像もしてなかったぞ、寝かせない気か! と文句をいいながら一気に読んで、二作目、三作目を買いに走るはめになるんだから、もしまだシリーズ全作を買い揃えていない方は、すぐにでもまとめてレジへ持っていってほしい。
『ザ・プロフェッサー』、『黒と白のはざま』、『ラスト・トライアル』。
ロバート・ベイリーが書き上げたこれまでの三つの物語のなかで、弁護士であるトムはつねに戦ってきた。従業員を酷使し、暴利をむさぼる巨大企業を相手に、不可能とおもえる裁判に挑み、容疑者として逮捕された親友の冤罪を晴らすべく、さまざまな妨害をかいくぐって法廷に立ち、ひとりの少女のために、ともに励んできた仲間と対決する。重要な鍵を握る証人を粘り強く探しだし、依頼人のためなら身の危険を顧みずどこへでも駆けつける。そしていざ裁判がはじまれば、陪審員の心を摑む、静かで熱い弁論を繰り広げる。けしてあきらめずに、守るべきもののために戦う。
わたしはいつでも、トムのかっこいい背中を物語のなかに追い求めてきた。
シリーズを通して登場する、トムの仲間たちだってきっとわたしと同じだ。
トムの元教え子で現相棒の弁護士リック、トムを実務的にも精神的にも支える親友ボー、リックの親友の検事パウエル、捜査官のウェイド、そして検事長であり妻を亡くしたトムの晩年のよき理解者でもあるヘレン。彼らが年齢も職業上の利害関係も気にせず、事件のたび物語に姿を現すのは、作者の都合によるものなんかではなく、トムという人についていきたいと彼らが思っているからだ。そうわたしは信じている。
そしてもうひとり、トムに異様なほど執着する人物がいる。
このシリーズをずっと追いかけてきた人ならもうおなじみの、ジムボーン・ウィーラーだ。
はじめは悪徳経営者に雇われた始末屋(殺し屋ともいう)にすぎなかったボーン(ジムボーン)は、作品を重ねるごとにだんだん凄みを増してゆく。トム側に有利な証言を提供しかねない人物を追い詰め、トムとその仲間たちの家族をも攻撃の対象に巻き込んで、彼らに精神的・肉体的苦痛を与えることを心底愉しむような、ヒール中のヒール。
いや、それにしても……。
殺し屋って存在するのかよ!?(みなさんも思いましたよね?)
日本の法廷サスペンスで、証人を消しまくる殺し屋なんていうキャラがでてきたら、まずリアリティがないとけちょんけちょんに貶されそうだ。
それがそうはならないのが、映画をはじめとするフィクション大国アメリカというか、リアルに存在していてもおかしくないだけの〝なじみ〟があるから不気味だ。
こういう日本の作品では荒唐無稽になってしまうようなスリラー要素が、違和感なく大胆に盛り込まれて物語を揺さぶり、読む人を震え上がらせるおもしろさを生み出すのだから、見事というほかない。
そのジムボーン・ウィーラーが、前作『ラスト・トライアル』ではついに死刑囚となり、もうなにもトムたちに手出しはできないと思ったのも束の間、ボーンの息がかかった新たな女刺客、マニーが登場したのも驚きだった。
そして満を持してのシリーズ完結編が、今作『最後の審判』である。
いやもうね……、読みましたか、みなさん!?
ジムボーン・ウィーラーですよ。彼が、最凶最悪のヒールとして、トムとの最後の決着をつけるために戻ってきたんだから、おもしろくないはずがないってことですよ。
正直に告白してほしい。『ラスト・トライアル』でボーンの出番がめっきり減ってしまったとき、がっかりした人も少なからずいるのではないだろうか。わたしもそのひとりだ。それほど、ボーンの悪役としての印象は強烈で、代替のきかない人物だった。
そのボーンが、マニーの手を借りて脱獄するところから、『最後の審判』は、はじまるのだ。
しかし、わくわくしながら読みはじめて衝撃をうけるのは、そればかりではない。
トムの病状は、なんとなく覚悟していたこととはいえ、胸を衝かれるものだった。
これは、ジムボーンとの戦いでもあると同時に、癌との闘いの物語でもある。
それをことあるごとに思い知らされて、ひゅんっと心臓が縮むのを感じる。彼が末期癌と宣告されて十四カ月。体重は十五キロも減り、一九〇センチの身長で体重は七十五キロしかない。歩くことさえ容易ではない。ボーンが、トムや彼の家族を殺すべくひたひたと迫るなか、こんな状態でどうやって対決するというのか。
トムはもう戦えない。
ロバート・ベイリーは『ラスト・トライアル』の「著者あとがき」で、ほかに類を見ないほど想いのこもった文章を書いている。そこで、彼の父親が癌で他界したこと、彼の妻もまた、長らく癌と闘病したことが明かされている。それはまさに、作者がこのシリーズを執筆している真っ最中だったことも。
じつはわたしも、癌で父親を亡くしたひとりだ。
もう十数年も前のことだが、体格のよかった父が余命宣告を受けたあとみるみる痩せていき、別人のようになってひとりで歩くこともままならず、ときには息がうまくできなくなって苦しげに喘ぐようすは、いまでも忘れられずにいる。
だからこそトムの痩せ衰えた姿が、父と重なってのしかかってきた。
トムはもう戦えない。
なぜなら、トムはもう、じぶんの生命を維持するだけでたいへんな体力を消耗しているのだから。
そしてそれは、病と闘う家族とともに過ごしながら、作者もずっと見つめてきたことであり、トムの身体がいまどれほどの状態なのか、物語はつねに、実感とリアリティをもって書かれている。
ジムボーンの執念深さを、シリーズを通してわたしたちは嫌というほど知っている。これまでに骨の髄まで植えつけられてきた彼を恐れる気持ちが、今作では、過去にありえないほどの緊張感を生んで、ひとときも息をつかせない。彼が標的にするのは、トムの大切な仲間たち、そしてなんの関係もないその家族たちだ。それを予想して、トムらは最大級の厳戒態勢を敷くけれど、ものものしくなればなるほど、ボーンの威圧感が高まっていくだけだ。読んでいてだんだん腹が立ってくる。もっとトムの晩年を心安らかに読みたかったぞ! なんでここまでトムを痛めつける。トムの命をつなぐように、必死になって本に齧りつく。祈りながら読む。
そしてわたしたちは再び、思い出すのだ。
トムがどんな人だったかを。
彼が、どんな苦境にあっても、けしてあきらめることなく、誰かを守り抜いてきたことを。
トムはもう戦えない。
けれど彼には、いっしょに最悪の状況を乗り越えてきたチームがいる。
リック、ボー、パウエル、ウェイド、ヘレン。動けないトムのぶんまで、彼らは大切な人を守るために戦う。助けられなかった人のために、もういちど立ち上がって戦う。
そしてトムもまた、チームに支えられ、愛する家族を守るため、孫のジャクソンを取り戻すため、弱った身体で最後の対決に一歩を踏み出す。
どうか、日々完全燃焼できないままくすぶっている人に、この物語のなかで結末まで生きてみてほしい。なにをやればいいのかすぐには答えがでなくても、うおおおお! なにか成し遂げたい、最後まで力を尽くしきりたい、という無限のパワーが湧いてくる。
全力を出しきらないままでいいのか? ここで終わっていいのか?
トムは毎ターン叱咤激励してくれる。わたしたちは弱小チームで、トムはそれでもあきらめない最強の監督だ。
物語の最後に、トムが孫のジャクソンとふたりで語りあう場面がたまらなくすきだ。
ジャクソンの素直で悲痛な叫びこそ、わたしたち読者のトムへの想いだ。わたしが父にいえなかった言葉だ。作者自身が、彼の愛する父親にぶつけたかった感情だ。
泣きじゃくるジャクソンに、トムはこんな言葉を返す。
「けどわたしが生きているあいだに、お前とわたしとで何かしようじゃないか、どうだ?」
ちいさなちいさなチームを組んで、ふたりがそのあとの日々をどんなふうに過ごしたか、想像してはまた力をもらう。
トムの物語はおしまいを迎えたけれど、どうやらまだ、解き明かされない謎がひとつ、残ったようだ。
新たなリックの物語がはじまるのか、そこではまた、トムの言葉が聞けるのか、楽しみに待ちたいと思う。リックはきっと、トムとおなじくらいわたしたちを勇気づけてくれるはずだ。