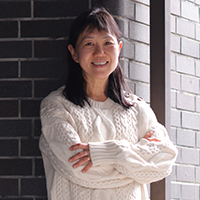角田光代『希望という名のアナログ日記』

私はきちんとそこにいた
忙しいと言う大人にはなるまいと決めていたのに、三十代の半ばすぎから、忙しいと言うことも思いつかないほど忙しくなってしまった。もっとも忙しかった時期、一か月に締め切りは小説とエッセイを含め二十八個あり、毎日のように仕事がらみの人たちと酒を飲み、それでも翌日は午前五時には仕事場の机に座った。
あんまり忙しいと、日々はかたまりになって過ぎていき、記憶もまだらになる。私はそのころのことをあんまりよく覚えていない。じつは数年前、仕事場から原稿の束が出てきて、どうやら小説のゲラ刷りらしいのだが、それがなんの小説なのか思い出せない、ということがあった。だれの書いた小説なのか、まさか私の書いた小説? それにしてもタイトルが記憶にない。その後、あるきっかけでその小説の正体がわかった。もっとも忙しい時期に雑誌で一年間連載していた、私の小説だった。単行本にするにあたってゲラ刷りにしたものの、書きなおしをしようとしたままになっていたのだ。自分が書いた小説すらも記憶にないとは、なんたること。
四十歳も近づいて、さすがにこんな日々は何かおかしい、もっと自分のペースで暮らすべきだと思い、以後、なんとか締め切りも仕事がらみの会食も減らし続けて今に至る。それから十年以上がたって、ようやく朝の暗いうちに仕事机に向かわなくてもよくなった。それでもまだまだ、自分のペースとは言いがたいのだが。
ところで私は家計簿というたいへんアナログな記録を、二十年以上、つけ続けている。その日使ったお金と、その日の夜に食べたものを毎日毎日書きこんでいる。驚いたことに、記憶のほとんどない時期も、この家計簿を見返すと、その一日一日がありありと、生々しく浮かび上がるのである。そうだそうだ、友人の個展にいって、そのあとみんなで中華を食べた、とか、そういえば牛すじのカレーに凝って、牛すじをよく煮ていた、とか、どれほどつまらない一日でも、何かしらくっきり思い出す。覚えていないことで、あとかたもなく消えたような一日、私はきちんといたんだなあ、と感動すら覚える。
私のパソコンにも、外付けハードディスクにも、スマートフォンで撮った写真が、十数年前からすべておさまっている。けれどこれらの写真を見返しても、家計簿ほどには生々しく、くっきりと過去は起き上がってこない。私がアナログな人間だから、アナログな記録のほうが実際の記憶に近く思えるのだろうか。
この十年ほどのあいだに、あちらこちらの新聞雑誌に掲載してもらったエッセイと、小説ひとつをまとめたこの一冊も、私にとってはアナログな記録なのである。書きつけたあんなこともこんなことも、読み返すまで忘れていて、ああ、私はきちんといたんだなあとまたしても思った。