2019年本屋大賞受賞! 瀬尾まいこ『そして、バトンは渡された』はここがスゴイ!

2019年本屋大賞は、瀬尾まいこさんの『そして、バトンは渡された』が受賞しました! 大賞受賞作の読みどころはもちろん、惜しくも大賞を逃した候補作を含むノミネート作全10作品のあらすじとレビューをお届けします。
2019年4月9日に「2019年本屋大賞」が発表され、瀬尾まいこさんの『そして、バトンは渡された』が見事受賞しました。
『そして、バトンは渡された』は、血の繋がらない親の間を“リレー”されて生きてきた高校生の優子を主人公とする物語。さまざまな親や友人たちとの出会いと別れを繰り返し、少しずつ成長してゆく優子の姿に励まされる感動作です。
『そして、バトンは渡された』のほかにも、魅力的な作品が数多く揃った2019年本屋大賞の候補作。P+D MAGAZINE編集部では、受賞作の発表前に、ノミネート作全10作品の徹底レビュー&受賞予想を行いました。
果たして、受賞予想は当たっていたのでしょうか? そして、惜しくも大賞受賞を逃した作品の魅力とは?
1. 三浦しをん『愛なき世界』
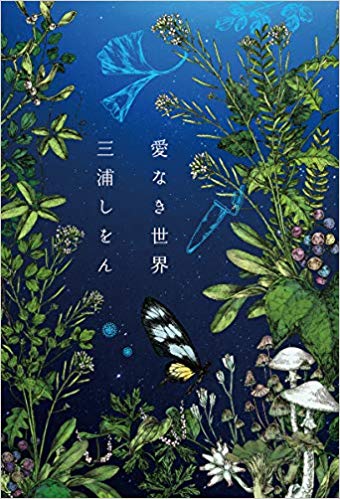
出典:https://www.amazon.co.jp/dp/4120051129/
三浦しをんの『愛なき世界』は、生粋の植物好きである本村紗英に恋をした洋食屋の見習い、藤丸陽太を主人公とする物語です。
藤丸は、勤めている洋食屋が宅配サービスを始めたことをきっかけに、洋食屋の近所にある国立大学・T大に出入りするようになります。T大の理学研究室で知り合ったのが、シロイヌナズナという植物の研究を専門にしている大学生、本村でした。
本村は今日もTシャツにジーンズという、飾り気のない恰好だ。Tシャツには、唇を大写しにしたような妙な白黒写真が、ドカーンとプリントされていた。
「それ、なんの柄すか?」
「気孔です」
「へ?」
「葉っぱの表皮にある穴です。それを顕微鏡写真で撮ったもの。かわいいのでプリントしてみました」
本村は一見、控えめな女性ですが、植物の気孔をプリントしたTシャツを着てしまうほど生粋の植物オタク。藤丸はそんな本村に圧倒されつつも、彼女の研究への熱心さを目にするうち、本村に強く惹かれていきます。
本村さんたちが研究してるのは、つまりは生き物がどうして生まれ、どうやって生き、なぜ死ぬのかってことについてなのかもしれない。俺も含めて多くのひとが、一度は抱いたことのある疑問。でも、俺も含めて多くのひとが、「そんなこと考えたってしょうがないや」と投げだしてしまった疑問。本村さんたちは投げだすことなく、しつこくしつこく考えつづけてるんだ。
本作の魅力は、一生懸命にコックの夢を追いつつも本村を振り向かせようと努力する藤丸と、とにかく植物に一途な本村、そして彼らの周囲にいる植物研究者や洋食屋の店長……、といったさまざまなキャラクターが、皆くせ者でありながらも非常に魅力的なところ。恋愛小説として楽しむのはもちろん、読み終えたあと、目を向けたことのなかった植物にも少し詳しくなれるような作品です。
2. 平野啓一郎『ある男』

出典:https://www.amazon.co.jp/dp/4163909028/
平野啓一郎の『ある男』は、平野啓一郎自身と思しき小説家が、ある晩、たまたま入ったバーで城戸という弁護士の男に出会うところから始まります。語り手である小説家は、城戸と親しくなるにつれて知った、かつて城戸が経験したという非常に奇妙な物語について書き始めます。
城戸はある日、かつての依頼主である谷口里枝から、「ある男」についての相談を受けました。林業を営んでいた里枝の夫・大祐が、仕事中に伐採した木の下敷きになって命を落とし1年が過ぎた、と彼女は言います。
生前の大祐の「自分の実家に関わらないでほしい」という言葉を守り、しばらくは彼の実家に訃報を伝えなかった里枝ですが、1周忌をきっかけに大祐の実家に手紙を書いたことで、彼の兄である恭一が里枝の家へやってきます。すると、大祐の写真を見た恭一は、驚くべきことを言い出すのです。
「これは大祐じゃないですよ。」
「……え?」
恭一は、腹を立てているような眼で、里枝と母を交互に見た。そして、頬を引き攣らせながら笑った。
「……いや、全然わかんない。……ハ? この人が、弟の名を名乗ってたんですか? えっ、谷口大祐、ですよね?」
なんと恭一は、写真の男は自分の弟ではなく、おそらく誰かが大祐になりすましてこの家で暮らしていたのだ──と里枝に告げるのです。
いったい、大祐になりすましていたのは誰なのか? そして、本物の大祐はいまどこにいるのか? その謎を調査してほしいという依頼を受けた城戸はやがて、過去の自分を捨て、新しい戸籍で生きようとした男たちの存在に行き当たるのです。
愛する人が自分に語った過去がすべて嘘だったとして、それでもその相手を愛し続けることができるか。本作は、そんな難題を読者に投げかけてきます。「ある男」の正体をめぐるミステリ仕立てのストーリーにハラハラさせられるのはもちろん、人間のアイデンティティや自分らしさのありかについて深く考えさせられる傑作です。
3. 木皿泉『さざなみのよる』

出典:https://www.amazon.co.jp/dp/4309025250/
木皿泉の『さざなみのよる』は、43歳の女性、ナスミが癌で亡くなる静かなシーンから始まります。その後、ナスミを失った彼女の姉や妹、友人、夫の日出男の視点を通して、ナスミが彼らにとってどのような存在で、自分たちの未来になにを残してくれたのか、ということが語られていきます。
日出男は、ナスミの喪失をこんな風に表現します。
もう一度ナスミに何かして欲しいとか、声を聞きたいとか、そういうことは少しずつあきらめてきたつもりで、それなりの覚悟はできているつもりだった。でも、コトバにできない、自分だけが持っているナスミのイメージを、どうすればよいのか。そんなことが自分の中でこんなにも困ったことになるとは思いもしなかった。というか、人が死ぬとそんなことが起こると誰も教えてくれなかった。もしかしたらイメージの集積は炭酸水のようなもので、放っておくと、泡だけが空中に抜けゆき、ただの水みたいになってしまうのではないか。
この物語には、ナスミの死を除けば、特別なことはなにも起こりません。ただ、あとに残された人たちが、ナスミのいない世界でそれぞれどのように生きてゆくかという姿が描かれるだけです。
しかし、大切な人を亡くした経験がある人はもちろん、いま失いたくない大切な存在がひとりでもいる人ならば、涙なくしては読めない作品のはず。『すいか』や『Q10』など名作ドラマの脚本を多数手がけた木皿泉ならではのさりげない台詞のきらめきが、読み終えたあとも温かく心に残り続けるような1作です。
4. 瀬尾まいこ『そして、バトンは渡された』
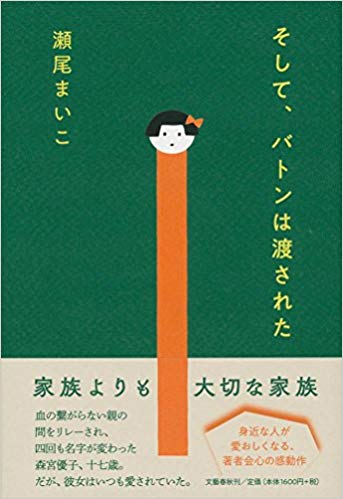
出典:https://www.amazon.co.jp/dp/4163907955/
瀬尾まいこの『そして、バトンは渡された』は、3人の父親と2人の母親を“リレー”され、現在は3人目の父親と暮らしている高校生の優子を主人公とする物語です。
優子は、家庭の事情で親が何度も変わっている子ども──と聞いてイメージするような陰のあるタイプではなく、非常にあっけらかんとした性格。担任の向井先生から「悩みがあるなら打ち明けてみなさい」と言われても、
私に必要なのは、悩みだ、悩み。これだけ手を広げて受け止めようとしてくれているのに、何もないのでは申し訳ない。こういうときのために、悲惨な出来事の一つくらい持ち合わせておかないといけないな。
と内心で感じてしまうほどでした。
そんな優子がいま生活をともにしているのが、血の繋がらない父親である森宮。森宮は東大出身、現在は一流企業に勤務する“頼れる大人”である反面、“父親”という役割を立派にまっとうしようと意識するあまり、朝から優子にボリューム満点のカツ丼を作って食べさせようとしたり、受験前に遊んでいた優子を義務感から無理やり叱ったせいで胃を痛めてしまったり……、と、どこか人とずれたところがあるタイプです。
本作は2章立てで、第1章では優子が森宮と毎日の食卓をともにしつつ、クラス内のいじめや合唱コンクールといった出来事を経験しながらも高校を卒業していくまでの日々が描かれます。第2章では、栄養士として町の食堂で働き始めた22歳の優子が、高校時代に出会ったある男の子と結婚することを決め、自分を育ててくれた何人もの父親や母親たちに挨拶に行くことになります。
どんな理不尽な目に遭ってもさほど悩まない優子の淡々とした性格に、始めはまったく感情移入ができない──と思う読者も少なくないかもしれません。しかし、本作の中では、優子がたくさんの親たちとの別れと出会いとを通し、少しずつ自分を強くしていく様子が回想のように時折描かれます。
それらのエピソードを知った上で第2章を読むと、優子と別れざるをえなかった親たちにもさまざまな事情や感情の動きがあったことがわかり、物語に厚みが感じられます。ラストは、思わず涙してしまうこと請け合いです。
5. 森見登美彦『熱帯』

出典:https://www.amazon.co.jp/dp/4163907572/
森見登美彦の『熱帯』は、誰も最後まで読んだことがない幻の本、その名も『熱帯』をめぐる物語です。そんなあらすじを聞いただけで、熱心な森見登美彦ファンならずとも胸が躍るのではないでしょうか。
物語は、最初の語り手である森見登美彦自身が、新作の小説が書き出せずに悩んでいる……、というシーンから始まります。なかなかいいアイデアが思い浮かばない森見は、先人たちが書いた名作文学を読みふけることで時間を潰していました。
そんな中、そのときたまたま読んでいた『千夜一夜物語』の話を妻にしたことをきっかけに、森見は学生時代に出会った『熱帯』という本の存在を思い出します。
彼は学生時代、当時住んでいた京都のアパートの近くにある古書店で、1982年に出版された『熱帯』という本を見つけたことがありました。作者は佐山尚一という聞き慣れない人物で、物語はこのように始まるのでした。
汝にかかわりなきことを語るなかれ
しからずんば汝は好まざることを聞くならん
森見はこの『熱帯』に興味を惹かれ、半分ほどまで本を読み進めます。しかしある朝、目を覚ますと、枕元に置いていたはずの『熱帯』が忽然と消えてしまっていたのです。
自分がかつて体験したそんな不可思議な出来事を思い出しつつ、東京でとある“読書会”に参加した森見。その会場で彼は、なんと自分がついぞ最後まで読めなかった『熱帯』を持っている女性、白石さんに出会います。その本をなんとか読ませてほしい、と頼み込む森見に、白石さんはこう言いました。
「この本を最後まで読んだ人間はいないんです」
本作の面白さは、森見や白石さんを始め、幻の本『熱帯』の続きを知りたがっている人たちの話を通じて語り手がリレーのように代わっていくところと、実際の『熱帯』はどんな結末だったのか、という謎がなかなか明かされないところにあります。
さまざまな語り手が語る『熱帯』にまつわる物語を読んでいると、読者である自分はいったいどこに連れて行かれるのだろう──とハラハラしてきます。森見登美彦らしい幻想的な世界観はもちろん、サスペンスのような張り詰めた緊張感を味わうこともできる傑作です。
6. 小野寺史宜『ひと』
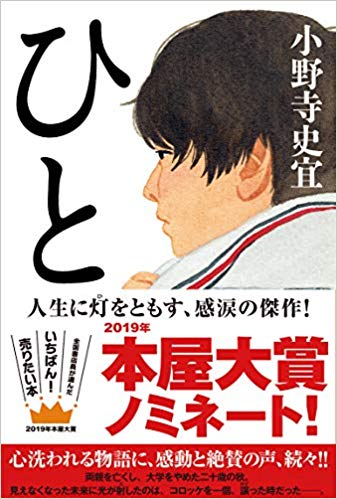
出典:https://www.amazon.co.jp/dp/4396635427/
小野寺史宜の『ひと』は、両親を亡くし、天涯孤独となった20歳の青年・聖輔を主人公とする物語です。
3年前に父親を亡くし、女手ひとつで育てられた聖輔。大学2年の秋に母親が急死してしまったことで、奨学金を返済できる目処が立たなくなり、大学を中退することを決めます。
職を探さなければいけない、と考えながら過ごしていたある日、聖輔はたまたま入った商店街の中の惣菜屋で、自分が買おうとしていた50円のコロッケの最後のひとつを、見知らぬお婆さんに譲ります。店主に「コロッケはもうないけど、120円のメンチがおすすめだよ」と言われた聖輔は、困ってしまいました。
「あの、下ろし忘れちゃって」
「何だ、そういうことか。百二十円もないの?」
「はい」
「いくらある?」
わかっているのに財布を開き、もう一度なかを見る。
「五十五円、です」
「五十五円かぁ。よし、負けてやるよ」
「え?」
「今のお客さんにコロッケを譲ってくれたから、メンチ、五十五円」
聖輔がコロッケを譲ったからという理由で、メンチの値段を負けてくれた店主。聖輔はその優しさと熱々のメンチの美味しさに感動し、ここでアルバイトをさせてほしい、と店主に頼み込みます。惣菜屋で働き始めた聖輔はやがて、調理師であった亡き父と同じ夢を叶えるべく、調理師免許をとるという大きな目標に向かって歩み始めるのでした。
聖輔は、他人にすぐ物を譲る優しさを持っている反面、なんでもひとりで抱え込んでしまう頑なさも持っています。そんな生き方を時に褒め、時に諭しもしてくれる周囲の人たちとの心のふれあいで、聖輔が少しずつ成長していくのが本作の最大の読みどころ。淡々としたストーリーではありますが、読後に胸がほんのりと温かくなるような1作です。
7. 知念実希人『ひとつむぎの手』

出典:https://www.amazon.co.jp/dp/4103343826/
知念実希人の『ひとつむぎの手』は、大学病院に勤務する外科医・平良祐介を主人公とするヒューマンドラマです。
徹夜明けで勤務をしていたある朝、祐介は医局の最高権力者である赤石教授に呼ばれます。赤石は祐介に3名の研修医の指導をするよう指示し、彼らを心臓外科に入局させることができれば、祐介に心臓外科医として安泰の道を用意してやる──と暗に告げます。しかし、失敗すれば心臓外科のない病院に彼を出向させる、と言うのです。
祐介は3名の研修医の指導を引き受け、研修医たちを他の科にとられないよう熱心な指導を始めますが、不器用な性格が災いし、研修医たちと険悪な雰囲気になってしまいます。
そんな中、病院にファックスで赤石を告発する怪文書が送られてきたことで、医局は騒然とします。怪文書の内容は、赤石が薬剤臨床試験の結果を改ざんし、その見返りに賄賂を受け取っている、というものでした。
怪文書を送ってきたのはいったい誰なのかという謎解きと、研修医たちの指導に奮闘する祐介をめぐるヒューマンドラマの2つの軸でストーリーは進みます。要領の悪さで時に研修医と衝突したり、自分よりも優遇されているように見える後輩・針谷に不満をぶつけたりと、決して冷静沈着な医師ではない祐介の不器用な人間らしさが本作をより魅力的なものにしています。
8. 芦沢央『火のないところに煙は』
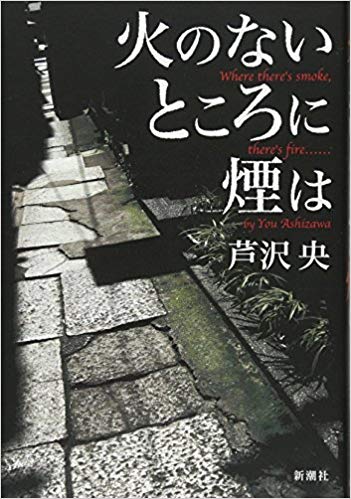
出典:https://www.amazon.co.jp/dp/4103500824/
芦沢央の『火のないところに煙は』は、作者である芦沢自身が、「新潮社のある神楽坂を舞台にした怪談を書きませんか」という依頼を受けるところから始まります。芦沢は、神楽坂という地名を見て“ある出来事”を思い出し、その依頼を受けることにしたのでした。
8年前、出版社の編集者として勤務していた芦沢のところに、学生時代の友人である早樹子から連絡がきました。早樹子は、尚子という友人の恋人が神楽坂で交通事故死してしまい、それ以来尚子の身に不可解なできごとが起こり続けているということを話し、お祓いができる人を紹介してもらえないか、と言うのです。
広告制作会社に勤務する尚子は、かつて早樹子の紹介で、“よく当たる”と評判の占い師に恋人との今後を占ってもらったことがありました。その占い師に「早く別れたほうがいい」と言われたのがきっかけで尚子の恋人は激怒し、その日から人が変わったように「別れるなら死ぬ」と尚子に迫るようになります。しばらくして、恋人は神楽坂で事故死してしまったのでした。
その事故以来、尚子が納品する交通広告のポスターに「染みがついている」というクレームが入るようになります。何度も入るクレームに、尚子が思わずそのポスターの染みをルーペで拡大してみると、そこには無数の
あやまれ あやまれ あやまれ
という文字がありました。尚子はその後、交通事故で死亡してしまい、同様に早樹子も死亡してしまいます。
この物語『染み』は、『火のないところに煙は』の中の第1話。本書には、この他にも5話の短編が収録されています。特に、最終話の『禁忌』では、これらすべての話に共通する点があると芦沢が気づき、ゾッとするような結末が訪れます。どの物語も、作者の身の回りで本当に起こった出来事なのではないかと考えてしまうほどリアルなので、夜寝る前に読むことはおすすめしません。
9. 伊坂幸太郎『フーガはユーガ』

出典:https://www.amazon.co.jp/dp/4408537322/
伊坂幸太郎の『フーガはユーガ』は、互いのいる位置を“入れ替える”ことができる特殊能力を持つ双子、風我と優我をめぐる物語です。
ストーリーは、優我が仙台にあるファミリーレストランの中で、テレビ制作会社に勤める高杉という男と話をしているシーンから始まります。優我は、5歳のときに自分と双子の弟・風我に起きた、ある不可解な出来事について高杉に語っているのでした。
5歳の優我は、家の中で気性の荒い父親に殴られ続けている風我を見ながら、「僕が代わってやりたい」と感じます。すると突如、ぷるぷると体がしびれるような感覚に襲われるのです。
何だろう、と思った直後、僕は床に寝そべっていた。身体の向きが分からないものだから、顔の横に床があるのも理解できなくて、あれ、あれ、とおろおろした。(中略)
彼は? さっきまで、この男にやられていた僕は?
あっちの僕と代わってあげたい。
自分が念じていたことを思い出す。
代わってあげられたんだ!
風我と優我はこのときの出来事をきっかけに、自分たちが年に一度、誕生日の日にだけ2時間ごとに瞬間移動をすることができる、ということに気づきました。
成長した風我と優我はこの能力を活かし、同級生のワタボコリが彼をいじめている同級生の広尾たちを驚かすのを手伝ってやったり、風我の恋人である小玉を壮絶な境遇から救い出そうと奮闘したりし始めます。
入れ替わりという特殊能力を活かしたエピソードの爽快感はもちろん、伊坂幸太郎らしい小気味よい会話も楽しむことができる本作。特に、優我が風我を人に紹介する際の
「俺の弟は、俺よりも結構、元気だよ」
という何気ないひと言が重要なシーンのキーとなる演出には、読んでいて必ず唸らされてしまうはず。散りばめられた小さな伏線がしだいに回収され、驚くべきラストへつながっていく伊坂作品の醍醐味を存分に楽しめる1作です。
10. 深緑野分『ベルリンは晴れているか』

出典:https://www.amazon.co.jp/dp/448080482X/
深緑野分の『ベルリンは晴れているか』は、第二次世界大戦直後のドイツ・ベルリンを舞台とする歴史ミステリです。
主人公のアウグステ・ニッケルは、アメリカ人の兵員食堂で働く少女。ある晩、突如アメリカ兵のジープに乗せられ連れて行かれた警察署で、ある男性の遺体との面会を命じられます。それは、彼女の恩人であるドイツ人、クリストフ・ローレンツの遺体でした。
アウグステは、警察署のドブリギン大尉にクリストフとの関係を尋ねられ、彼がかつて妻のフレデリカとともに、ナチスの迫害から潜伏者を匿っていた地下活動家であったこと、そして、アウグステにとって妹のような存在であった少女・イーダとアウグステ自らも、彼ら夫婦に匿ってもらっていた過去があることを話します。しかし、アウグステは生き延びることができましたが、幼いイーダは不幸なことに命を落としてしまいました。
淡々と過去を語るアウグステに、ドブリギン大尉はクリストフの死因を告げます。
「彼は歯磨き粉で亡くなったんですよ」(中略)
「歯磨き粉、ですか」
「驚くでしょう。歯磨き粉で人が死ぬなんて、私も聞いたことがありません。しかし笑いごとではないのですよ。現実にクリストフ・ローレンツは、歯ブラシに絞り出した歯磨き粉を口に含んだ瞬間に事切れたのですから。ブレンツラウアーベルクの自宅で、妻フレデリカ・ローレンツの目の前で。歯磨き粉には青酸カリが混ぜ込まれていました」
大尉は、クリストフの死は他殺の可能性が高い、と言います。いったいなぜ物不足の街で、クリストフは歯磨き粉を手に入れられたのか。そして、歯磨き粉に青酸カリを混ぜるという驚くべき手口で、彼を殺したのは誰なのか。アウグステは、亡くなってしまったイーダの恨みを晴らしたのではないかという理由で殺人の嫌疑をかけられつつも、クリストフの甥に彼の訃報を伝えるため、甥を探しに旅立ちます。
誰がクリストフを殺したのか? というミステリとしての面白さを最後まで楽しめるのはもちろん、戦時下のドイツの情勢や風景に関する詳細な描写が非常にリアルで、思わず物語に入り込んでしまうのが本作の魅力。重厚な歴史ミステリを読みたい方にはイチオシの作品です。
大賞はどの作品に!? 受賞予想
これまでの本屋大賞の傾向を振り返ると、村田沙耶香の『コンビニ人間』や又吉直樹の『火花』など、ノミネート前からベストセラーとなっていた作品にはあまり票が入らず、壮大なファンタジー小説や胸が熱くなるような青春小説、リアリティのある歴史小説などが人気のよう。また、全国の書店員さんが選ぶ大賞ということもあり、三浦しをんの『舟を編む』など本をテーマにした名作は多くの支持を集めるようです。
そういった傾向も踏まえ、今回の本屋大賞は、平成の日本で書かれたとは思えないほどのリアリティで戦時下のベルリンの空気を再現した、深緑野分の『ベルリンは晴れているか』が受賞すると予想します。次点を挙げるならば、“幻の本”をテーマにした傑作、森見登美彦の『熱帯』でしょうか。
果たして、大賞を掴むのはどの本なのか──? いまから、4月9日の発表が待ちきれません!
初出:P+D MAGAZINE(2019/04/03)

