【没後50年】討論映画公開、切腹写真集発売……、三島由紀夫の再ブームが到来。その素顔と、戯曲作品の魅力に迫る

2020年11月に、没後50年を迎える三島由紀夫。映画『三島由紀夫vs東大全共闘』の公開や“死”をテーマにした写真集の発売などをきっかけに、三島由紀夫の再ブームが到来しています。今回は、そんな三島の素顔と、彼が傾倒していた“戯曲”の魅力に迫ります。
戦後の日本文学界を代表する作家・三島由紀夫。2020年11月には没後50年を迎える三島に対する人気と関心が、いま再燃しつつあります。
そのきっかけのひとつにもなったのが、今年3月に公開された、三島と東大全共闘との伝説の討論会をテーマにした映画『三島由紀夫vs東大全共闘 50年目の真実』。また、撮影から50年の時を経て米国で出版された、写真家・篠山紀信による写真集『三島由紀夫 男の死(原題・YUKIO MISHIMA THE DEATH OF A MAN)』も大きな注目を集めています。
今回はそんな“三島ブーム”に迫るとともに、三島が小説と同じかそれ以上に心血を注いでいたと言われている、彼の戯曲の魅力を紹介します。
三島の死の数日前まで撮影が続いた、“伝説の写真集”の全貌
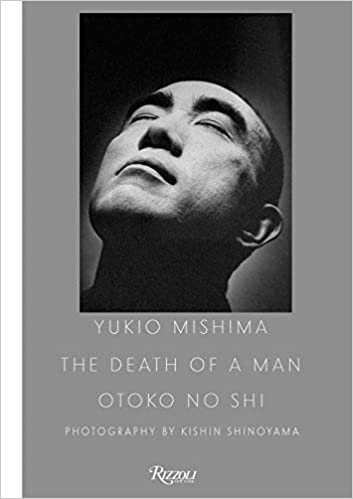
出典:https://www.amazon.co.jp/dp/0847868699/
いま、再びの三島由紀夫ブームで話題を集めているのが、米国で2020年9月に刊行されたばかりの写真集『三島由紀夫 男の死(原題・YUKIO MISHIMA THE DEATH OF A MAN)』(撮影・篠山紀信)です。進んでいた刊行の準備が三島の事件の余波によって見送られ、撮影から50年の時を経てようやく出版に至りました。
本作の撮影がおこなわれたのは、三島が自衛隊駐屯地で割腹自殺を遂げる直前の1970年。写真集のコンセプトと実際の撮影の顛末について、三島の“共演者”として本作の被写体になっている美術家の横尾忠則は、『男の死 始末記』と題された文章のなかでこのように語っています。
1970年、足の病で長期入院していた。ある日、某出版社の編集者が出版契約書を携えて病室に現れた。三島由紀夫が「男の死」と題する写真集を企画し、写真を篠山紀信、三島の共演者に横尾忠則。出版社を交えた四者による出版契約に署名しろ、というのだ。実に唐突な話だが、如何にも三島らしい強引さでもある。ぼくは直感的に面白い企画だと、特に理由も聞かないで引き受けることにした。
三島と私、横尾が対頁で「男の死」を演じるという。この段階で三島は自らの死を客体化させ、様々な死を演出するつもりだった。
この三島流の“演出”に付き合わされることとなった篠山と横尾は、まるで歌舞伎の「三島座」の一員のように撮影場所をあちこち指示され、死をモチーフにした写真を撮らされたと横尾は言います。写真集のなかで、三島は自らの死を予行演習するかのように、切腹する武士や決闘に敗れた闘士などに扮し、鍛え上げた肉体を披露しながらさまざまな“死”を演じています。
撮影者である篠山の写真について、三島は
──篠山氏の写真作品には、しかし、造型の的確さもさることながら、崩れる寸前の、熟れて落ちる寸前の、夕日のやうな「危機のロマンティシズム」がある。
と評していますが、本作は、まさにその「危機のロマンティシズム」を自身の体で体現したような作品です。三島流の芸術をどのように受け取るかは、鑑賞者の目にかかっています。
自らのことを小説家よりも“劇作家”だと称していた三島由紀夫
自らの写真集の総合プロデュースを務めるなど、いわば稀代の“演出家”であった三島由紀夫。『潮騒』や『金閣寺』といった長編小説を代表作に持つ三島には、戦後を代表する小説家というイメージを持っている方がほとんどだと思います。しかし三島自身は、自らのことを
一に評論家、二に劇作家、三に小説家
──『作家論』あとがきより
と評していました。三島の評論家としての手腕は『作家論』や『文章読本』といった著作のなかで遺憾なく発揮され、多くの作家や文芸評論家もその作品群を絶賛していましたが、実は三島自身はいち ファンとしても劇作家としても演劇に傾倒しており、小説よりもむしろ演劇で身を立てていきたかった、としばしば発言しています。
『肉体の学校』などエンタメ要素の強い作品も発表していた小説とは違い、三島の戯曲には難解で芸術的なものも多く、殘念ながら彼の生前、舞台で上演された三島の戯曲が興行的に大成功を収めることはあまりありませんでした。しかし三島は自らの戯曲が上演されることを非常に楽しみに感じていたようで、
小説は書いたところで完結して、それきり自分の手を離れてしまうが、芝居は書き了えたところからはじまるのであるから、あとのたのしみが大きく、しかも、そのたのしみにはもはや労苦も責任も伴わない。こんなに面白いことがあってよいものだろうか、というのが当時の私の正直な感想であった。
──『私の遍歴時代』より
と随筆のなかでも綴っています。東大全共闘との討論会やUFOを研究する「日本空飛ぶ円盤研究会」への参加など、生前、大胆かつ奇想天外な振る舞いで世間を賑わせ続けた三島は、生涯を通じて生粋の演劇人であったと言えるのかもしれません。
三島由紀夫のおすすめの戯曲3選
そんな三島が実際に著した戯曲には、名作が数多くあります。特におすすめの作品を、3作品ご紹介しましょう。
1.『近代能楽集』

出典:https://www.amazon.co.jp/dp/4101050147/
『近代能楽集』は、三島由紀夫の代表的な戯曲のひとつです。三島は芝居好きだった祖母の影響で幼年期から演劇に強い興味があり 、10代では歌舞伎の虜に、その後は能の世界にどっぷりと浸かるようになりました。本書は、三島が幼い頃から親しんできた謡曲を現代風に翻案した戯曲集です。
本作は、「卒塔婆小町」や「葵上」など有名な謡曲を大筋はそのままに扱い、登場人物が法律事務所で働く会社員やOL、政治家といった現代を生きるキャラクターに大胆にアレンジされているのが大きな特徴です。この脚色に対し、三島は
私の近代能楽集は、(中略)能楽の自由な空間と時間の処理や、露はな形而上学的主題などを、そのまま現代に生かすために、シテュエーションのはうを現代化したのである。そのためには、謡曲のうちから、「綾の鼓」「邯鄲」などの主題の明確なもの、観阿弥作のポレミックな面白味を持つた「卒塔婆小町」のやうなもの、情念の純粋度の高い「葵上」「班女」のやうなものが、選ばれねばならなかつた。
とあとがきで語っています。本作は日本はもちろん、海外圏での評価が非常に高く、能を世界に紹介した作品のひとつとしてさまざまな国で親しまれています。
2.『鹿鳴館』
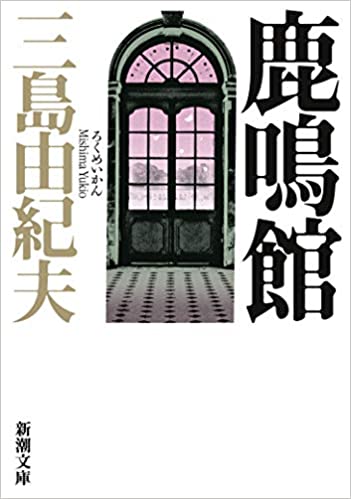
出典;https://www.amazon.co.jp/dp/410105035X/
『鹿鳴館』は、明治時代に欧化対策の一環として建築された社交場・鹿鳴館で、天長節に催された大夜会を舞台に、政治的な陰謀や恋に翻弄されていく華族たちの姿を描いた4幕ものの戯曲です。
中心となる登場人物は、影山伯爵、伯爵の夫人で元芸者の朝子、自由民権運動家の清原、清原の息子である久雄の4人。朝子は人づてに、久雄が何か危険な行動を企てていると聞きショックを受けます。実は、朝子は芸者時代に清原と愛を誓った過去があり、久雄は朝子の実の息子でした。朝子が久雄に話を聞くと、彼はなんと、父親である清原の暗殺計画を立てていると言います。清原の命を救うため画策する朝子と、実は清原の暗殺計画の陰の首謀者であった影山伯爵の思惑と愛憎が絡み合う──というのが本作の主なストーリーです。
圧巻なのは、物語の終幕で交わされる影山伯爵と朝子のやりとり。
影山:今あなたの心が喋っている。怒りと嘆きの満ち汐のなかで、あなたの心が喋っている。あなたは心というものが、自分一人にしか備わっていないと思っている。
朝子:結婚以来今はじめて、あなたは正直な私をごらんになっていらっしゃるのね。
影山:この結婚はあなたにとっては政治だったと云うわけだね。
朝子:そう申しましょう。お似合いの夫婦でございましたわ。実にお似合いの……。でも良いことは永く続きませんのね。今日限りおいとまをいただきます。
詩的かつ絢爛たる台詞まわしが独特の緊迫感を生み出し、物語は一気に悲劇へと突き進んでいきます。政府が一気に進めた西欧化の象徴でもあった鹿鳴館は批判にさらされることの多い存在でしたが、三島は当時を“日本近代史上まれに見る花やかなロマンチックな時代”と評し、現実よりも美しい舞踏会を戯曲を通じて描きたかったと解説しています。
3.『サド侯爵夫人』
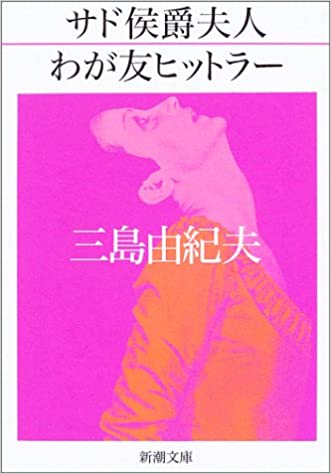
出典:https://www.amazon.co.jp/dp/4101050279/
『サド侯爵夫人』は、無垢でありながらも残虐で冷酷な面を持つ夫・サド侯爵(アルフォンス)の出獄を20年にわたって待ち続けた妻・ルネの生き様を描き、ルネが“離婚”という選択をするに至った経緯を紐解く戯曲です。
舞台は3幕から成り、サド侯爵が娼婦虐待事件を起こして当局から追われる身となっていた1772年、その6年後の1778年、サド侯爵が晴れて自由の身となった12年後の1790年の3つの時代を描きます。ルネは始め、母であるモントルイユ夫人から何度離婚を勧められてもその忠告を受け入れようとせず、サド侯爵をかばい続けようとします。やがてルネは、自らの母と父を“偽善としきたりの愛”にまみれた人々であり蔑んでいると告げ、
アルフォンスは、私だったのです
と宣言するまでに至ります。ところが、サド侯爵がいざ自由の身となると、あらゆる悪徳の限りを尽くした夫はもはや自分の手の届かない場所にいるとルネは言い、彼の帰りを待たずに修道院に入るという選択をするのです。
三島は実在の人物であるサド侯爵とその夫人を描いた作品を執筆しようとした背景を、
私がもつとも作家的興味をそそられたのは、サド侯爵夫人があれほど貞節を貫き、獄中の良人に終始一貫尽してゐながら、なぜサドが、老年に及んではじめて自由の身になると、とたんに別れてしまふのか、といふ謎であつた。この芝居はこの謎から出発し、その謎の論理的解明を試みたものである。
──『サド侯爵夫人』より
と述べています。本作の詩情あふれる美しい台詞まわしと理論的に構成された非の打ち所のないストーリーは、三島の戯曲の真骨頂と言えるでしょう。
おわりに
今年は没後50年を記念し、「MISHIMA2020」と題された複数の演劇作品の上演が東京・日生劇場でおこなわれるなど、三島由紀夫の演劇人としての側面にも再度光が当てられつつあります。これまで三島の戯曲を読んだことがなかった方は、ぜひこの機会に、彼の熱量のこもった作品群に手を伸ばしてみてください。
初出:P+D MAGAZINE(2020/10/28)

