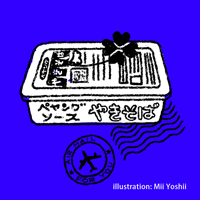思い出の味 ◈ 坂岡 真

十数年通った駅近の鮨屋が、ある日突然、壁になっていた。何の前触れもなく、見慣れていたはずの表口が白い壁でふさがれ、スイーツ店の甘ったるそうな看板が掛かっている。スイーツ店に衣替えしたわけでもなく、白壁に覆われてしまったことが悲しみをいっそう掻きたてた。心の底から泣きたくなったのだ。
花板のYさんは最初は取っつきにくい印象だったが、乗合船で鯊釣りにもおつきあいいただき、馴れてくると気さくに何でも喋ってくれるようになった。おまかせでお願いすると、たいていは鯛か平目からはじまって、産地のわかる鮪のトロと赤身、気が向けば炙りなども出される。「和歌山沖だよ」とか「LA沖だよ」と教えてくれ、正月過ぎに行くと「大間だよ」と、鼻の穴をひろげてみせた。こっちも嬉しくなって、今年もいっちょ頑張ろうなどと胸の裡に誓ったものだ。なれど、ほんとうの目当てが鮪でないことはYさんも先刻御承知なので、それを出すまでは焦らしながら、光り物の小鰭だの、蒸した車海老だの、春先ならば煮蛤だの、梅雨時ならば穴子だのを握ってくれ、珍しいところでは平貝や北寄貝、北海道は利尻島あたりで採れたウニなんぞも軍艦に巻かずに出してくれ、それはもう舌が蕩けるほど美味いのだが、肥えた秋鯖の昆布締めに勝るものはなかった。旬の鯖にありつけたときは、まさに幸福の絶頂で泳がされている気分になるのだ。
Yさんは数ヶ月後、わざわざ拙宅を訪ねてくれた。消息を案じていたので、おもわず、おたがいにハグをしあい、少しばかり涙ぐんでしまったが、元気にやっておられるとのことで安堵した。壁のことは言えなかった。後継者の問題やら何やら、閉店にいたるまでにはさまざまな事情があったのだろう。あそこで二十数年も鮨を握りつづけてきたYさんの来し方が白い壁で閉ざされてしまったことに、棍棒で撲られたような衝撃をおぼえずにはいられなかった。されど、それは偶さか通いつづけた客の身勝手な感傷なのだとおもう。鮨職人は腕一本さえあれば、何処でも美味い鮨を握ることができるのだ。あの世へ逝くまえに食べたいものはと聞かれたら、Yさんの握った鯖と躊躇なくこたえよう。いや、近いうちにかならず食べてみせる。白い壁の前に佇み、わたしはそんなことを誓っていた。