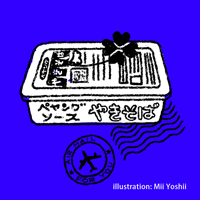思い出の味 ◈ 平野啓一郎

歯科医だった私の伯父は、腎臓が悪く、長らく人工透析を受けていた。もう随分と前に亡くなってしまったが、音楽好きで文学好きで、私は少年時代には、大きな影響を受けたように思う。
伯父は、透析の日は、よく病院近くのタコ焼き屋で、タコ焼きを買ってきてくれた。私は父を早くに亡くして、母方の実家で育ったのだが、祖父母を訪ねて、親類が遊びに来ることが多かった。
そのタコ焼きは、とにかくタコが大きく、伯父は、それが自慢だった。何かと食べ物に拘りのある人で、子供の頃に食べた「黄色いカレー」をどうしても食べたいと、カレー屋を訪ねてまわり、出されたカレーが「黄色くない」からと、一口も食べずに帰ってくるような、まあ、変わったオジサンだった。
小学生だった私は、いつも外で遊んで腹を空かせていたので、勿論、喜んでその手土産を食べた。透析は苦しいので、伯父はいつも憔悴していたが、それでも浮腫が引いて、傍目には毒が抜けたような感じもした。そして、タコ焼きを次々に口に放り込んでいく私を面白そうに眺めながら、まだ健康だった少年時代の思い出話を、色々と聞かせてくれた。
私にとって、タコ焼きは、そういう伯父との思い出と不可分に結びついていて、今でも食べると懐かしくなる。
だが、大学に入り、関西に住み始めて、ようやく本場のタコ焼きを食べた時には、少しガッカリした。というのも、私が少年時代に食べていたタコ焼きは、〝ウェルダン〟で、パックに入っているので表面もしっとりしていたのだが、関西では「外はカリッと、中はとろとろ」というのが主流だったからである。しかし、「とろとろ」というのは、薄力粉を溶いた汁が生焼けという意味であり、私はそれが苦手である。そういうと、大体、関西人の友人からは白い眼で見られるのだが。……
そんなわけで、私はいつも、ウェルダンの少しふやけたようなタコ焼きを探し求めているのだが、そうしてようやく「黄色いカレー」を食べたがっていた伯父の心情も理解するようになったのだった。