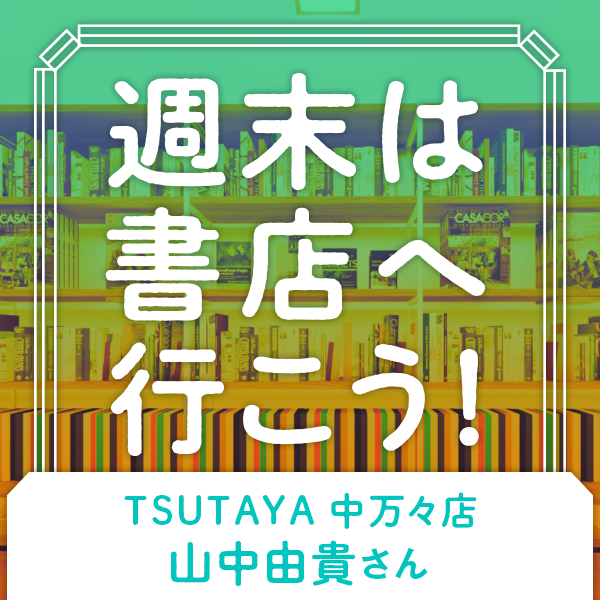藤谷 治さん『世界でいちばん美しい』
それでも生きていけるのかを考えたかった。
藤谷治さんには、10年近く前から思い描いていた小説があったという。当初「けむり」と題されたそれは、さまざまな試行錯誤をへて、ふたつの連載と書き下ろしを組み合わせ、数奇な人生模様を描き出す長編となった。それが『世界でいちばん美しい』。ある天才音楽家の人生を親友の作家が振り返る物語だ。
天真爛漫な一人の天才とその親友
島崎哲には親友がいる。雪踏文彦、通称せった君。小学生の頃、勉強ができなくて周囲から馬鹿にされていたせった君だが、島崎がピアノを弾く姿を見ただけで同じ曲を弾いてみせて周囲を驚かせる。そう、彼はとてつもない才能の持ち主だったのだ。
大人になり小説家になった島崎がつづる形でせった君との交流が語られる本書は、やがてもう一人の重要人物の登場により、複雑なうねりを見せていく。序章で不穏な光景が描かれるものの、なぜそこに辿りつくのかがなかなかわからず、ページをめくらせる。
「2004年に『おがたQ、という女』を出版した時、担当編集者に"これと同じような勢いのある濃い小説を1000枚くらい読みたいです"と言われ、僕も"それ面白いですね"と言っていて。そこから折に触れてその担当者と話しているうちに、ちょっとずつイメージが湧いてきました」
しかし当初は現在完成した小説とはまったく異なるものを思い浮かべていたという。
「作中にも同じ場面を書きましたが、もうもうと煙が立ち上っているイメージだけがあって、『けむり』というタイトルの小説を考えていたんです。そこからいろんな話を考え、その都度相当煮詰めたんですが、なかなか形にならなかった。そうこうしているうちに『きらら』で『津々見勘太郎』という話の連載が始まったんです。これはバブルとその崩壊を背景にした青年のビルドゥングスロマンにするつもりで、その連載が終わったら『けむり』に取り掛かる予定でした」
実は前述の"もう一人の重要人物"とは、この津々見勘太郎である。
「連載をはじめた頃に東日本大震災が起き、その余波のなかで小説を書いているうちに津々見の話では物足りないと思うようになったんです。震災後の世の中の動きを見て自分が直観したことを書きたい、今すぐ『けむり』を書きたい、と。それで、『津々見勘太郎』と『けむり』をつなげることはできないかと考えました」
その時心にあったのは「美しい人を書きたい」という気持ち。頭の中でせった君の物語がどんどん広がっていった。そこで、島崎とせった君の幼少期から高校を卒業するあたりまでが描かれる部分は「そびえ立つ大路の松」というタイトルで本誌に連載。その後島崎らの大人時代の部分を書き下ろし、津々見勘太郎の物語を挿入し再構成。こうした経緯によって、お決まりの起承転結という流れにおさまらない物語が誕生したというわけだ。
「僕は小説を書く時にいつもチャレンジをひとつしようと思っているんです。今回言えるのは、後付けになりますが、一人称のプリズムが書けたかな、ということ。主人公の視線だけでなく、いってみれば敵役となる津々見の言い分もたっぷり入れ込んであるんです。ストーリーテリングの基本からは逸脱するくらいのものが書けたことは非常に満足しています」
本作には今自分が持っている小説技術を使えるだけ使ったという。
「視点の転換の部分も構成の部分もそう。読みやすくてのどごし爽やかなものにしたかった。僕は難解なものを難解なまま書くことはしたくないんです。わかりやすくリーダブルなものにしても小説の持つ力は失われないという自信もありました」
自分を投影した主要人物たち
語り手の島崎は音楽家を目指して挫折するが、この境遇は藤谷さん自身の経歴と重なる。つまりは著者自身が投影されているとすぐわかる。では天真爛漫だが社会性に欠けるせった君、少しずつ反社会的な価値観にとらわれていく津々見にも、誰かが投影されているのだろうか。
「それが一人称のプリズムが意味するところなんです。島崎も僕、せった君も僕、津々見も僕。三人が似ているんだという要素を細かくちりばめていきました。それも今回の技術的な自信のひとつ」
せった君は自分の才能を磨くことや、それを世の中にアピールしていくことに関しては非常に不器用な人物だが、
「知能指数が足りないように見えるけれども、決してそうではない。天使のような純真な存在にもしたくなかった。彼はただ音楽に対する集中力が異常にあるんです。僕も学校では本当に勉強ができなかったんです。学校のカリキュラムや受験勉強とは関係ない、自分の好きなものに集中力を注いでいましたから。子供心に自分は馬鹿ではないと思っていたけれど、それを証明する手立てがなかった。その気持ちがせった君にこめられているのかもしれませんね」
津々見勘太郎に関しては、
「自分を表現したいけれどどうしたらいいかわからなくて苛々している人間。でもその気持ちは誰もが持っていると思う。津々見はひどい行動をとりますが、島崎もせった君も一歩間違えたら津々見になりうるんです。それは読者も同じ。その暗示になればいいと思いました」
彼の場合、男女関係がこじれたことから転落が始まるが、
「へんな女や男につかまったって人生を踏み外さない人だっている。どちらに転ぶかは本当に紙一重なんです。津々見の場合は判断力が欠けていたんでしょうね」
後半には津々見の手紙も登場し、行動の裏にあった心理が綿々とつづられる。彼はすべてが"けむり"のようなもので虚しいという境地に至ったというのだ。だからどんな行動を起こしてもよいというのは未成熟で短絡的だが、著者はその心理をねっとりと語らせる。
「人生は虚妄であるという主張をなるべく濃く書いておきました。神様や来世を信じられたら宗教的な希望も持てるんでしょうけれど、それが馬鹿馬鹿しいと思う人、すべては無意味だからどんな行動を起こしてもいいんだという人に対して、どんな反論ができるのか考えてみたかったんです」
津々見にもせった君にも著者が投影されているわけだが、その生き方はかなり対照的。
「せった君や島崎が津々見のようにならずにすんだのは、楽しいことがあったからだと思うんです。生きて働いて生命を維持していくという本来必要なこと以外に、楽しいことがあるかどうか。猫やカラスだって生命活動とは別に楽しいことを探して遊んでいますよね。では人間にとって楽しいこととは何かというと、それは芸術のことだと思う」
一流の芸術家とは?
そこで考えさせられるのは、芸術とは、そして芸術家と何かということだ。せった君は音楽に没頭するが、才能はなかなか世に認められない。彼は野心が希薄で、世間に認められるために行動を起こすことはしない。行動しても、どこかずれている。せった君の人生はわかりやすいサクセスストーリーのようには展開しない。
「彼なりの論理はあるんでしょうね。作者である僕から見ても、せった君の芸術観はずれていると思う。それでは通用しないんじゃないかとは思いますね」
それでも、そうした自己顕示欲にとらわれていないからこそ、せった君は美しいものを創り出せたのではないかと思えてしまう。
「そこから先は読者自身にも考えてほしいところなんです。僕は最近『こうして書いていく』というエッセイ集を出したんですが、そこに後世に残る偉大な芸術家は必ず生前に大ヒット作を持っている、ということを書きました。例外はカフカや宮沢賢治、メルヴィルなどごくわずか。ほかはドストエフスキーにしろディケンズにしろナボコフにしろ、必ず生きているうちにヒット作を出している。それは通俗的な成功かもしれません。でもその下衆な成功をクリアしないと超一流にはなれないんです。すごくシビアな話です。だからせった君のように通俗性に堪えうるものを創ろうとしない人は、ちょっとズレていると思ってしまう。ただ、そう言った先から、僕のお腹の中がちくちく痛くなるんです。何かに対して"ごめんなさい"という気持ちになってしまう」
生前に広まったかそうでないかによって作品の質が変わるわけではない。変わるのは作者の生活だろう。
「ものを創って生活している人たちのヒリヒリするような厳しさってありますよね。僕も毎月ローンの支払いのたびにその厳しさと向き合っている。樋口一葉だってあと5年長生きしていたら自分の原稿料で暮らせていただろうに……と考えたりしてしまいますね」
芸術を鑑賞する側にとっては、創作活動は金銭欲とは関係のない高尚なものであってほしい、という身勝手な願望がある。ただし、クリエイターにとって創造活動が生活手段のひとつであるのは事実。では、メジャーを目指すわけではないせった君にとっての創作活動は何だったのだろうか。
「彼はただ創ったんです。難しいことはわかっていなかった。彼が作った曲のなかには、商業ベースにのろうとしなかったがために幻の傑作になってしまったものもあるかもしれない。でも僕にとってそれは2番目の興味にすぎないんです。いちばん興味があるのは、彼が一緒にいて本当に気持ちのよい、美しい人だったということなんです」
その美しさとは何か。
「世界でいちばん美しい人というのは、何も残さずきれいさっぱりいなくなる人なんじゃないかという気がするんです。作品も子孫も残さず名前すら残さず、存在したかもわからなくなる人。その潔さみたいなものを持っている人なのかもしれません。でもそれは寂しい。僕みたいな自己顕示欲が強い人間には耐えられない」
それでも人生に価値はあるのか
序章で暗示されているように、物語では大人になったせった君は理不尽な目にあってしまう。
「目論見としては、せった君を美しく可愛らしく描いて、それをぶっつぶすつもりでした。よくそんな残酷なことが自分に書けたと思う。でもそれを書かないと、それでも人は生きる値打ちがあるのか、じゃあその値打ちとは何なのかを考えることができませんでした。生きることは素晴らしいとか、明日に希望はあるとかいったきれいごとで終わらせたくなかった。人はみんな"けむり"のような存在であり、ゲーテだって例外ではない。それでもなお生きていけるのかを考えたかった」
書き終えた今、"それでもなお"と思えたのだろうか。
「わからないです。物語の最後に書いたことが精いっぱいの結果です。自分が生きたことが何かの種になって芽が出ていずれ森になるなんてやはり思えません。でも、雨の一滴くらいにはなっていると思いたい。僕がこう書いたことを誰かが読んで、その人が何かを誰かに伝えていく。その程度の価値はあると思う……と考えないと、自分が書いていることに対して無責任になってしまいますね」
今できることを詰め込んだという本書は、藤谷さんにとって新たな代表作となることは間違いない。それでも著者は言う。
「自分が書いたものが芸術だったらどんなにいいか、と思う。でも僕は芸術に対する憧れが生半可なものじゃない自信があるので、自分が書いたものが芸術だと思えないんです」
それでも藤谷さんは書くことはやめない。やめられない。
「世俗的ではない方向に行きたいですね。家のローンを払いきってしまって、お金のことを考えず創作できたら(笑)。……これだけいろいろ言っておきながら、本当の芸術というものはお金のために売るようなものじゃないという気持ちがあるんでしょうね」
創作、芸術への焦げ付くような情熱を抱きながら、著者の挑戦は続く。