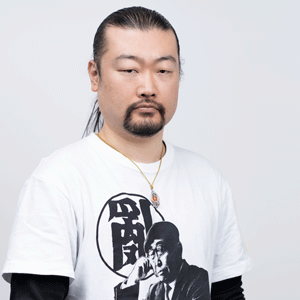佐藤 究『幽玄F』◆熱血新刊インタビュー◆
幽玄に心をとめよ

美とは形の中にたわめられた力
2000年に東京の四谷で生まれた、通訳の父と数学教師の母を持つ寡黙な少年・易永透は、幼少期から飛行機が大好きだった。将来の夢はパイロットになることだ。夢を追う姿に滑稽さも漂う少年の言動に、やがて不穏さが混じり始める。高校二年生のある日、羽田空港でフェンス越しに航空機見物をしていた時の感覚が決定的だ。〈なぜ俺は、向こう側にいないのか。/その思いは、あこがれよりも、悲しさと呼んだほうがふさわしかった。悲しさはやがて焦燥に変わり、それから説明のつかない激しい感情の奔流となって、透の内側であばれ回った〉。夢よりも呪いと呼んだ方がふさわしいかもしれない空に対する思いは、航空宇宙自衛隊に入隊し超音速で飛ぶ戦闘機のパイロットになることで、一旦は落ち着かせることができた。ところが、不慮の出来事で自衛隊を辞めることになり、無味乾燥の余生が幕を開け……。
人類史を掘り返す血と暴力の群像劇となった前作『テスカトリポカ』から一転、佐藤究は『幽玄F』で、易永透という一人の飛行機乗りの人生にフォーカスを当てた。
「主人公以外の視点を入れたり、時間軸を前後させたりといった構造は基本的に排除して、できるだけシンプルに易永透の人生を追っていこうと思いました。普通に考えると一人称で書くのが正解なんですが、そうなると三島由紀夫さんの『金閣寺』に似通ってしまう。あの小説で主人公が取り憑かれた金閣寺の美を、F-35B(戦闘機)に置き換えてもらえば分かりやすいと思います。文体の絢爛豪華さという面では到底敵わないので(笑)、『金閣寺』のスタイルである一人称は回避しました」
作中では、戦闘機の「美」ではなく「力」への憧憬が、主人公のモノローグを通して語られていたが。
「三島さんは最晩年のインタビューで、〝美とは何か〟と質問され、〝形の中にたわめられた力〟と答えています。三島さんの話し振りからして、そこではおそらく、核分裂までいくような危険なイメージがなされていると思います。核分裂では原子核という構造、その〝形の中にたわめられた力〟を引き裂くことで、爆発的なエネルギーがもたらされるわけじゃないですか。そういう意味では、流線型で美しいとされる戦闘機のデザインも、形の中に力がたわめられたものと言えます。超音速で飛ぶ、敵と戦闘する、そうした目的を叶えるための形ですから。ただし、今回の作品で透が見出す相手は、いわゆる政治的なものや、人間的なものではないんです。そこに自分は惹かれたんだ、それらに刃向かう力が欲しかったんだ、と透が気付く場面は、この物語にとって大きな分岐になっているかなと思います」
やがて透は、「力」を手に入れるための行動に打って出る。
「太陽のせいで人を撃った……というカミュの『異邦人』が分かりやすい例ですけれども、文学がずっと読者を魅了してきた描写の一つに〝夏のめまい〟ってあると思うんです。本人にも説明できないんだけれども、それまでの人生とは全く違う方向にクラッと進んでいってしまう瞬間は、たぶん誰にでもある。三島さんの小説の多くにはそういうめまいがあると思いますし、それらは『八月十五日前後』というエッセイで書かれた、夏空の下での不思議な感覚に繋がっているはず。そういう足もとの地面が急になくなってしまうような夏のめまい感を、『幽玄F』では出したかった」
鋼の刀のかわりが戦闘機になり得る
本作の構想は、のちに第20回大藪春彦賞&第39回吉川英治文学新人賞をW受賞することになる長編第二作『Ank: a mirroring ape』の刊行直後、2018年から始まった。編集者から、「三島由紀夫をモチーフにした小説を書いて欲しい」と依頼されたのだ。打ち合わせの時にこぼした、三島作品が好きだ、という自身の言葉が出発点だった。最初に手掛かりとしたのは、三島の死生観や行動原理が赤裸々に披露された自伝的随筆「太陽と鉄」と、三島が航空自衛隊の戦闘機F-104に搭乗した経験を綴ったルポルタージュ「F104」だ。
「この作品を書くために何度も相談に乗ってもらった詩人の河村悟さんは、三島さんがスターだった時代をリアルタイムの読者としてすごしていたんですが、〝地球を取り巻く巨きな蛇の環を戦闘機に乗って見たあたりから、三島は変わったね〟と言っていました。これは『太陽と鉄』のエピローグとして知られる『F104』に書かれた内容を指しているんですが、『幽玄F』の執筆依頼よりもっと前、僕がデビューする以前に聞いていた言葉なんです。執筆依頼を受けたのち、この言葉の意味をあらためて考えました。空の上にいる時、三島さんはもちろんパイロットではなく複座の席に体験搭乗者として座っていたわけですよね。もしもパイロットのコックピットに座って自分で戦闘機を操縦できたのなら、あの時が最期の日になった可能性はあり得るんじゃないか、と。三島さんが市ヶ谷の陸上自衛隊駐屯地で手にした鋼の刀は、戦闘機に置き換えられるんじゃないかと思ったんです。そこから、主人公を飛行機乗りにするイメージが固まっていきました」
三島をモチーフにする以上は、人生に自ら終止符を打った「自決」のエピソードは避けて通れない。そのエピソードを、自分なりにどう描くか? ラストシーン──もちろん、季節は真夏だ──からの逆算で、物語の全体像を導き出していった。
「基本的に、戦闘機ものってドッグファイト(空中戦)の連続なんです。みんなが好きな『トップガン』の魅力もそこにある。それはそれで痛快なんですが、最初から最後まで飛ぶのが当たり前だったら、空を飛ぶこと自体の喜びとかありがたみというのは、なかなか描きにくい。だから、この作品ではドッグファイトの強度に頼らず、それはせいぜい仮想空間での訓練くらいにとどめていますし、全体としては透が飛ぶ時間よりも飛べなくなった時間のほうが長い。同時に『Ank』や『テスカトリポカ』で積み重ねてきた暴力的な描写を抑制しながら、三島さんのことを考えつつ、読者の望む佐藤究らしさも出しつつ、ラストシーンにカタルシスを持ってくるというのは、かなり難しい作業でもありました」
武士道と「太陽と鉄」に対抗できる思想と価値観
もしかしたら、本作は自殺やテロリズムを肯定するような小説では決してない、ということは伝えておいたほうがいいかもしれない。むしろ、そこからの回避が書き手にとって一番の勝負どころだった。
「結果としてああするしかないんだけれども、易永透は片時も死への憧れを持ったりはしないんですよね。テロリズムへの共感もない。つまり、三島さんとは違うわけです。だとしたら、その違いをどのようにして描くのか。ここは考え抜きました。違うといっても、まったく正反対の人物を書けばいいというものではない。それをやったら、執筆依頼を引き受けた意味がなくなってしまうので。三島さんの中には〝武士道といふは死ぬことと見つけたり〟という『葉隠』の一節がありましたが、易永透の内に刻まれるのは、室町時代の心敬という歌人が残した〝ふるまひをやさしく。幽玄に心をとめよ〟という言葉なんです。幽玄が具体的に何を指しているかは謎のヴェールに包まれているとしても、感覚としてなんとなく伝わってくるものがあると思うんですよね。つまりこの作品では、いわゆる夏のめまいに襲われた時に、三島さんの行動のようにアクセルを踏むのではなくて、透がブレーキを踏むように仕掛けたんです。説明しようとすると難しいところなんですが、実際にはブレーキは踏まないんですよ(笑)。ただ、そこに幽玄の奥深さがある。ブレーキを踏んだように見えて速度は落とさないというか、たとえば覚醒して疾走する速度ではなくて、眠りのような穏やかな静止のなかに最高の速度が秘められているというか」
果たしてブレーキは、うまく作用したのか否か。初稿を読んだ編集者からの指摘を受け、二段ブレーキにしたことが奏功している。
「初稿にはなかったエピローグを付け加えたんです。もともと構想にはあって、けれども『文藝』掲載の入稿リミットの時間を使い果たしていたので、たぶん誌面には載せられない、とあきらめていました。せめて単行本化のさいに追加しようと。ところが担当編集者さんから〝まだ時間はあります!〟と、ありがたくも恐ろしい言葉をもらって(笑)。全速力で『文藝』用の原稿に書き足したんですが、それをもって本当のブレーキというか、三島さんのいた時空と紙一重ですれちがって、かつそこに漂っていた荒御魂を鎮める試みもできたのかな、と。そうだといいんですが。三島さんはバーベルで肉体を鍛えて、お気に入りの軍刀も持っていましたよね。その根源にあるのが『太陽と鉄』であって、それを相殺する力として〝紙と風〟を当ててみたんです。太陽のような苛烈さや、鋼鉄の属性である重さにこだわらなくても、何かもっと軽いものに自分自身の存在を完全に乗せてしまって、そうやって空を飛ぶこともできるのではないか。こういうのは三島さんの盟友だった舞踏家の土方巽さんや、それこそ詩人の河村悟さんのような考えなんですけど。エピローグまで書き終えたところでそう実感した時は、自分自身もすっかり戦闘機ファンになっていた身としては、目から鱗が落ちる思いでした」
取材の最後に、三島の「小説とは何か」というエッセイについて教えてくれた。『幻想小説とは何か 三島由紀夫怪異小品集』(編・東雅夫、平凡社ライブラリー)に収録されているものだ。
「三島さんはそのエッセイで、『遠野物語』の〝炭取の廻る話〟を取り上げています。二十二話、佐々木鏡石氏の曽祖母が亡くなった時の話なんですが、遠野では喪に服す間は家の炭の火を絶やしてはいけない慣習があって、遺族が夜通し炭火を見守っている。そうしたら、死んだはずのおばあさんが突然現れて目の前を横切っていった。着物の端が炭取という、炭を入れておくカゴに当たって、そのカゴがクルッと回る。おばあさんは幽霊であるはずなのに、当たると回る、そこにゾクっとくる。三島さんはこのディテールを取り上げて〝ここに小説があった〟と絶賛しているんですね。重要なのは、超常現象であるおばあさんの幽霊よりもむしろ、炭取という物質の回転が、あたかも僕らの現実で起こったように感じられることです。言葉が幽霊を連れてきて、幽霊が物質を音もなく回転させて、その回転が僕らにとっての虚実の境界をあいまいにする。そこに幽玄の秘密がちらと垣間見える気がしますね。確かに、『金閣寺』でも炭取は回っているんですよ。『豊饒の海』でも。〝この小説では炭取は回っているだろうか?〟と考えるだけで、書き手も読み手も、小説の捉え方が変化するんじゃないかと思います。少なくとも現代にそういう批評や分析は見かけないですし、三島さんからの深みのある問いかけではないでしょうか」
丸5年近く三島と向き合ってきた日々はひとまず終わりを迎えた。しかし、三島が残した数々の謎について、「小説とは何か?」についての佐藤究の旅は、これからも続いていく。
少年は、空を夢見、空へ羽ばたく──空を支配するG(重力)に取り憑かれ、Fを操る航空宇宙自衛隊員・易永透。日本・タイ・バングラデシュを舞台に「護国」を問う、直木賞受賞第一作。
佐藤 究(さとう・きわむ)
1977年福岡県生まれ。2016年『QJKJQ』で江戸川乱歩賞を受賞。『Ank: a mirroring ape』で大藪春彦賞、吉川英治文学新人賞を、『テスカトリポカ』で山本周五郎賞、直木賞を受賞。