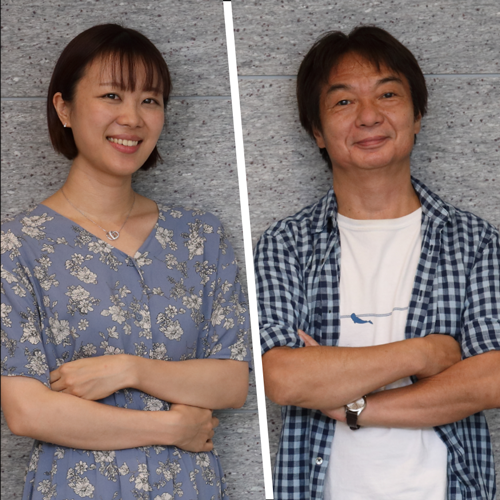著者の窓 第31回 ◈ 辻堂ゆめ『山ぎは少し明かりて』

3世代の女性が織りなす、故郷をめぐるドラマ
──『山ぎは少し明かりて』はダムに沈んだ瑞ノ瀬という集落を軸に、女性3代の人生を描いた壮大なスケールの物語です。時代と人の関わりを描くという点で、『十の輪をくぐる』と共通する部分があるように感じました。
まさにおっしゃるとおりで、『十の輪をくぐる』を書いたことで、昭和という時代にあらためて興味が湧いたんですね。あの作品は1960年代のごく短い期間しか描いていませんが、当時生きていた人たちが子供だった頃のことや、その親世代が生きていた時代も描いてみたくなりました。それで今回は3世代の女性たちを主人公にして、戦前から令和までの長い時間を扱うことにしたんです。
──ダムに沈んだ瑞ノ瀬という集落には、具体的なモデルがあるのでしょうか。
神奈川県の宮ヶ瀬ダムなどいくつかイメージした場所はありますが、はっきりここがモデルという村はありません。ダムに沈んだ村のさまざまな記録を読み、それらを組み合わせることで瑞ノ瀬を作り出しました。実は作中には瑞ノ瀬という名前以外、県名などの固有名詞がほとんど出てこないんです。読んだ方それぞれが、自分の故郷などを自由に思い浮かべていただけたらと思います。
忙しい現代に翻弄される都の葛藤
──物語は3部構成で、世代の異なる女性たちが順に主人公を務めます。第一章「雨など降るも」は、大学生・都の物語。留学先のイタリアで適応障害を発症した彼女は、帰国したことを友人にも恋人にも隠したまま、失意の日々を送っています。
わたしも経験がありますが、就職活動している大学生はみんなエントリーシートに書ける〝光る一行〟が欲しいんですよね。バイトリーダーだったとか、サークルの代表だったとか。でもそんな特別な経験は誰もができることではない。それで都は海外留学という経験に飛びついたのですが、海外で何をしたいか、将来どうなりたいかという具体的なビジョンを持っていなかった。それで留学先で挫折を味わうことになる。多くの若い人が直面する高い壁に、都はぶつかっているんです。
──都のような葛藤は辻堂さんにも覚えがありますか?
ありますね。思い返してみると、学生時代はすごく世間が狭かったと思います。社会のことをよく知らないのに、文字情報だけで志望する企業を決めないといけなくて、途方に暮れるような気持ちになることもありました。ただ上の世代と都が違うのは、今の若い人たちは日々触れている情報の量が膨大ですよね。作中に未読の LINE が何百件もあるという描写がありますが、常にインプットとアウトプットを求められて、ぼんやり心を休める暇がない。そういう苦しさもあるだろうなと思います。

──そんな都の心を変えたのは恋人・竜太の存在でした。台風で被害を受けた竜太の実家のリンゴ農園を手伝ううちに、都は少しずつ自分の存在意義を発見していきます。
2019年の台風19号に関する報道で、長野県のリンゴ農園が大変な被害を受けたことを知ったんです。もとの状態に戻すまでに何年もかかると農園の娘さんが話していたのがずっと心に残っていて。故郷という作品のテーマと響き合うこともあり、都にリンゴ農園の手伝いをしてもらうことにしました。就職活動などのために災害ボランティアをすることについて、偽善だという批判がよくなされますが、たとえ偽善であっても手を動かさないよりずっといい。その経験によって前に進む勇気が持てるなら、それはそれで悪いことではないですよね。
LINE、メール、手紙。思いを伝える手段の変化を描いて
──第二章「夕日のさして山の端」は都の母・雅枝の物語です。地元の企業で営業部長として働く彼女は、42年にわたって仕事に打ち込んできましたが、一方で家族との関係はぎくしゃくしています。
雅枝の世代の女性は、男性社会で認められることが社会進出とほぼイコールだった時代を生きています。男性に負けるな追い越せという思いで懸命に働いてきましたが、そのせいでいろいろなものを背負い過ぎている。雅枝の場合は特に、故郷の瑞ノ瀬を捨てたという経緯もありますし、いっそう仕事に打ち込むことになったんじゃないでしょうか。
──夫の弘との短いメールのやり取りが、夫婦の微妙な距離感を表していますね。
これは作品の中心的テーマというわけではないんですが、男女の思いを伝えるツールがどのように変化してきた、それがどれだけ思いを伝えられるものだったかを3章通して描いているんです。都と竜太は LINE を日常的に使いこなしていますが、雅枝と弘の世代になるとメールもどこかぎこちない。そして佳代の時代には、手紙が思いを伝える手段でした。弘は雅枝の気持ちを先回りして考えてしまうせいで、極端にシンプルな文章になってしまうんですよね。そのすれ違いが解けていく過程を、この章では描いています。

──雅枝にとって瑞ノ瀬は捨て去りたかった場所。先祖代々の土地を売り、補償金で都会に家を建てたことで、彼女と両親の関係は悪化します。なぜ雅枝はそこまで故郷を嫌っていたのでしょうか。
雅枝にとっても瑞ノ瀬は生まれ育った場所で、子供時代からの思い出がたくさんある。多少不便を感じたとしても、積極的に嫌いにはならないと思います。その気持ちが変化したのは、ダム建設が決まって、あなたたちの村は価値がないと宣言されたから。故郷が否定されるのは辛いことだろうと思います。しかも雅枝の両親はダムの反対運動の中心で、そのために学校で孤独を感じることもあった。そうした経験から瑞ノ瀬を否定することになった、ある意味気の毒な人なんですね。
子供時代の経験が、故郷を愛する気持ちの原点
──そして第三章「山ぎは少し明かりて」は都の祖母・佳代が主人公。三人姉妹の長女として瑞ノ瀬で成長した佳代の子供時代が、郷愁をそそる山村の生活とともに描かれていきます。
故郷を好きになる原体験は、子供の頃の経験から来ているはずです。そこを描かずには、佳代がなぜここまで瑞ノ瀬を愛するのかが読者に伝わらないだろうと思いました。といってもわたしは都と同じ都会暮らしで、山村の生活にはほとんど馴染みがありません。自分の選ばなかった人生を選んだ人々のことを深く理解するためにも、山での生活に関する資料をたくさん読みました。そのうえで佳代のキャラクターや生活環境を作り上げていったんです。
──戦後、幼馴染みの孝光と結婚。穏やかな日々を送っていた佳代に、村にダムが建設されるという知らせがもたらされます。佳代たちは反対運動を続けますが、保障金をもらって都会に出たいという人もいる。ダム計画は村を二分してしまいます。
ダム建設に反対した人も賛成した人も、どちらにも納得できる動機があります。一方が正しくて、もう一方が間違っているということはありません。取材の一環で宮ヶ瀬ダムの反対運動についての資料を読んだのですが、ダムに沈んだ旧宮ヶ瀬村の人たちは、わたしが想像していたよりダム建設に賛成だったんですよ。都会に出て、新生活を始めようという意見が多かった。それを知ってすごく意外だったんですね。旧宮ヶ瀬村の人たちにももちろん故郷への思いはあったと思いますが、そうはいっても生計を立てないといけない。その思いを想像しながら、賛成派にも反対派にも等しく視線を注いで、偏りのない描き方をするように心がけました。

──反対派がひとり減り、ふたり減りする中で、夫婦をある不可解な事件が襲います。それでも佳代は瑞ノ瀬で暮らすことにこだわり続ける。彼女はなぜそこまでして、瑞ノ瀬を守ろうとしたのでしょうか。
それはわたし自身も疑問に思っていたんです。ダムに限らず、空港や道路の建設計画でも、反対運動を続けている人たちがいます。それはなぜなのだろうかと。佳代の人生を描いていて思ったのは、彼女が愛していたのは子供時代からの記憶や、そこで育まれた人間関係だったんじゃないでしょうか。それが突如として否定され、一定の補償金と引き換えに取り上げられてしまうことは、佳代にとってあまりに理不尽な出来事だった。それが故郷に固執する理由になっているんじゃないでしょうか。とはいえ、それは一言で言い表せるような単純なものではありません。だからこそ、こんなに長い小説を書くことになったんですけどもね(笑)。
幸せに生きた祖母の姿を思い出しながら
──辻堂さんらしいミステリー的な展開を交えながら、佳代の後半生が鮮やかに描き出されていきます。時代に翻弄されながらも変わることがない、孝光との夫婦愛にも心打たれました。
周囲の環境がどうであっても、夫婦という単位で幸せに暮らすことができたら、とても羨ましいことだと思うんです。わたしの祖父母がまさにそうだったんですよね。祖父は7年前、祖母は2年前に亡くなっているんですが、祖父を亡くした後の祖母は気落ちして、「ここから先はおまけの人生だから、いつ死んでも構わない」と口にしていました。孫からしたら「おばあちゃん、もっと長生きしてよ」という気持ちでしたが、祖母はそれだけ幸せな人生を生きたということ。佳代と孝光もそういう夫婦だったんです。
──『山ぎは少し明かりて』というタイトルは、清少納言の『枕草子』の「春はあけぼの」の一節から取られていますね。
小学生の時に国語の授業で『枕草子』の冒頭を暗唱させられて、山と日の光の描写がとても美しいなと思ったんです。とりわけ春の「やうやう白くなりゆく山ぎは少し明かりて、紫だちたる雲のほそくたなびきたる」というのと、秋の「夕日のさして山の端いと近うなりたるに」というのが印象的で。今回、山に囲まれた集落をイメージした時に、光に照らされた山の情景がふっと浮かんできたんです。

──昭和から令和へといたるこの物語を書き終えたことで、辻堂さんの故郷観に変化はありましたか。
親の仕事の関係で引っ越しが多かったので、わたしにはここが故郷だと呼べる土地がないんです。プロフィールには神奈川出身と書いていますし、実際親戚もたくさん暮らしているのですが、生まれ育ったのは別の県なんですね。ここが地元だと思えるようになるまで、長い時間がかかりました。
この物語の3人の主人公は、それぞれ故郷に対して異なる思いを抱いています。瑞ノ瀬とともに生きた佳代、瑞ノ瀬を捨て去りたい雅枝、都会育ちで特に思い入れのない都。彼女たちの人生を描いたことで、ただ漠然と故郷に憧れるのではなく、あらためて自分の住んでいる土地を見つめ直してみようという気になった。そこにどんな歴史があり、どんな人たちが住んでいたのか、時々思いを馳せてみるのは大切なことのように思うんです。これからも折に触れて、親の世代、祖父母の世代の物語を紡いでいきたいと考えています。
辻堂ゆめ(つじどう・ゆめ)
1992年神奈川県生まれ。東京大学卒業。第13回『このミステリーがすごい!』大賞優秀賞を受賞し、『いなくなった私へ』でデビュー。2021年『十の輪をくぐる』で第42回吉川英治新人賞候補、22年『トリカゴ』で第24回大藪春彦賞を受賞した。他の著書に『コーイチは、高く飛んだ』『悪女の品格』『卒業タイムリミット』『あの日の交換日記』など多数。12月6日に『十の輪をくぐる』(小学館文庫)が発売。