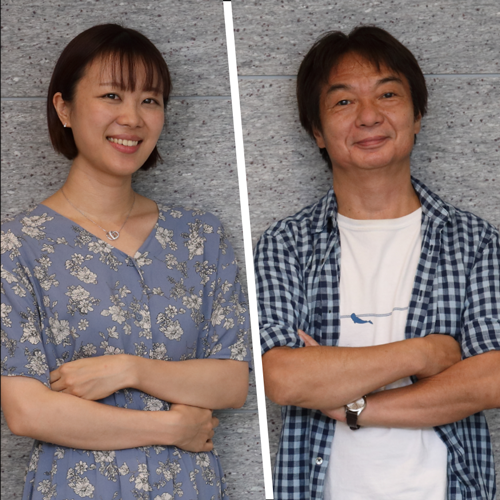「推してけ! 推してけ!」第40回 ◆『山ぎは少し明かりて』(辻堂ゆめ・著)

評者=藤田香織
(書評家)
不便で何もない「ふるさと」への思い
「故郷」というものが、自分にはない。
父が転勤族だったので、物心がついた頃から三年に一度は見知らぬ土地へ移り住みながら大人になった。幼馴染もいない。祭で沸き立つこともない。なんなら現在、母がひとりで暮らす実家を「地元」という意識もない。
テレビのニュースなどで、地震や水害に遭い、めちゃくちゃになった家の前で呆然としながら、それでも「生まれ育った場所だからここを離れられない」と話す人を見ると、いつも疑問だった。危険な場所だと判ったのに? 辛い記憶が残るのに? ほんとに? そんなに? なんでそこまで? と。
本書の第三章の主人公となる佳代は、まさしくその生まれ育った「故郷」を失くす。
祖母と両親、妹ふたりと共に佳代が暮らしていた瑞ノ瀬村は、山間の小さな村でありながら、土地が肥沃で作物がよく穫れた。四季折々の景色が美しく、動植物が常に命を息吹かせ、湧き水も随所にあり、ゆったりとした時間が流れる村で、つつましいながらも生き生きと過ごす子ども時代の佳代の様子が、まずとても読ませる。妹を背負い山の斜面を駆け上がり、草花を摘み、沢に駆け込み、手づかみで魚を捕る。蚊帳に放った蛍の光を見ながら眠りにつく。各学年一学級しかない村の子どもたちは男女かまわず兄妹のように仲が良く、小学五年生の佳代は同い年の孝光を少し意識している。遊んでいて足をねん挫し、孝光に背負われて家まで帰る場面など、憎まれ口しかきいていないのに、互いに想いあっていることが伝わってきて、甘酸っぱさがこみあげてくる。
十七になり、ひと冬だけ県境の町にある織物工場へ出稼ぎに行った佳代のもとへ届く、意外にも真摯な孝光からの手紙。色濃くなっていく戦争の影。二十歳になり赤紙が届いた孝光を見送ったのは、かつて一緒に学んだ小学校の校庭だった。肺を病んだ妹の千代を家で看取った。戦争が終わっても音沙汰がなかった孝光が帰ってきた日も、二十三でついに嫁いだ日も、佳代は瑞ノ瀬の山に、風に、見守られてきた。
その村に、ダムを造ると国が発表したのは、三十五歳でようやく授かった娘が十になる年だった。約三百戸が水の底に沈む。なぜ突然。どうして瑞ノ瀬が。
到底納得などできない計画に、反対派の代表として孝光は立つ。けれど、当初は怒り心頭だった住民たちも、立ち退きに好条件を提示され、長い歳月が経つうちに便利な町へ移り住むことを受け入れていく。そのなかで闘い続ける孝光と佳代の姿から、「故郷」というものの意味が立ちあがってくる。
この三章だけでも一冊にまとめられるほどの迫力があるが、二章では佳代の娘で、保証金で建てた〈分不相応に広い家〉のローンを払うため事務用品販売会社で勤めあげた雅枝が、六十歳の定年を迎えるまでの日々が。第一章では、適応障害になり留学先のイタリアから帰国したことを友人や恋人に打ち明けることもできぬまま、ほぼ自宅に引きこもり続けている雅枝の娘・都の失意と足掻きが描かれる。
雅枝は両親と同じく瑞ノ瀬で生まれ育ったものの、孝光や佳代ほど思い入れはない。田舎を出たい、便利で綺麗な町のほうが良い、という彼女の思考はとてもよく分かるし、間違っているわけでもない。都にとっては、瑞ノ瀬は故郷でさえない。しかし、恋人・竜太の、長野でリンゴ農園を営んでいる実家が台風で浸水し、片付けを手伝ううちに「故郷」というもののあり様に気付き、再び前を向き歩き始めるのだ。
ミステリーを核としているわけではないが、そうくるか! と感嘆する大きな謎もあり、三世代にわたる家族の関係性小説でもある。
遠くにあってもなくても、故郷を思う。そうか、そうだったのかと、思うことを知る。
見たことのないものが、見えていなかったものごとが、目の前に浮かびあがってくる。
藤田香織(ふじた・かおり)
1968年三重県生まれ。音楽出版社勤務を経て、フリーライターに。著書に「だらしな日記」シリーズ、『ホンのお楽しみ』など。