髙山文彦著『生き抜け、その日のために 長崎の被差別部落とキリシタン』著者にその執筆の背景を訊く!
長崎を舞台とするこの物語の創作の背景を、著者・髙山文彦にインタビュー!差別と闘い続けた3人の男の生涯を鮮烈に描くノンフィクションは読み応えあり!
【ポスト・ブック・レビュー 著者に訊け!】
差別と闘い続けた
3人の男の生涯を描く
ノンフィクション小説
『生き抜け、その日のために 長崎の被差別部落とキリシタン』
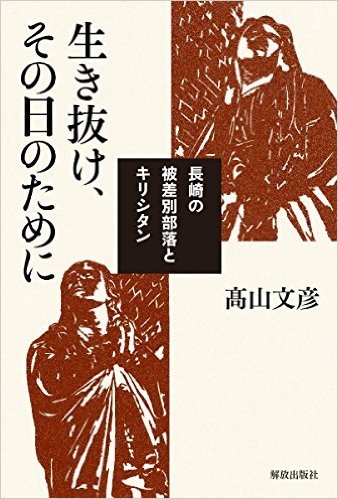
解放出版社 2200円+税
装丁/上野かおる 装画/菊池弦
不都合な過去に蓋をした今の明るすぎる
長崎は日本の戦後復興の縮図なんです
髙山文彦

●たかやま・ふみひこ 1958年宮崎県高千穂生まれ。法政大学文学部哲学科中退。2000年『火花―北条民雄の生涯』で大宅壮一ノンフィクション賞と講談社ノンフィクション賞をW受賞。著書に『「少年A」14歳の肖像』『エレクトラ―中上健次の生涯』『どん底―部落差別自作自演事件』『宿命の子―笹川一族の神話』『ふたり―皇后美智子と石牟礼道子』等。執筆の傍ら「高千穂あまてらす鉄道」代表取締役を務め、再建に尽力。178㌢、68㌔、A型。
国際平和都市長崎を語るには、欠くことのできない3つの要素があったという。「原爆」、「キリシタン迫害」、そして「部落差別」である。
特に後者2つは慶応3年の〈浦上四番崩れ〉など、隠れキリシタン摘発の先兵に部落民が使われた史実が禍根を残し、両者の関係は抉れたまま現代に残された。ある人が言う。〈浦上部落とキリシタン部落は、差別される者どうしやった。それを時の権力は一方を捕り手に仕立て、両者をいがみあわせて、下層民どうしでぶつかりあわせて支配構造を組み立ててきたわけだ〉。
髙山文彦著『生き抜け、その日のために』は、この歴史的確執を和解へと導くべく奔走した3人の人物を軸に、長崎の近現代史からキリスト教の伝来と迫害の実相までを追った力作だ。
実はこの「作られた対立」の裏には、語られてこなかったある事実が潜んでいた。〈歴史をありのままに見る目〉を何が曇らせるのか。ことは長崎に限らない。
*
このタイトルには見覚えがある。髙山氏は全国水平社議長・松本治一郎の評伝『水平記』(05年)の中で、松本が長崎で被爆したある青年に送った手紙に触れ、そこには〈生き抜け、その日のために。松本〉と認められていた。「その日」とは人種や宗教など、あらゆる差別から人類が解放される日を意味するが、この青年こそが本書の主人公の1人、部落解放同盟長崎県連初代委員長・磯本恒信なのだ。
「僕はその青年がどう戦後を生き抜いたのか、ずっと気になっていたんですね。
まず長崎県連に協力を仰ぎ、その時『例の和解の件はどうなりました?』という話になった。以前、月刊『部落解放』が長崎のキリシタンと被差別部落の特集を組んでいて、非常に感銘を受けたからです」
その記事に登場するのが、日本二十六聖人記念館初代館長・結城了悟ことディエゴ・バチェコ神父と磯本の従兄で盟友・中尾貫だった。
「それこそかつては殺し合いまでした間柄でしょう? それがなぜ歩み寄れたのか、その和解の行程に俄然興味が移っていったんです」
残念ながら磯本も結城も既にこの世になかったが、著者が同地で集めた証言は、「僕自身、全く知らなかった長崎」を伝えて余りある。
長崎では原爆は〈浦上に落ちた〉という見方が今でも根強いといい、浦上川を望む丘の麓で主に履物業を営んだ旧・浦上町は、長崎にあって長崎ではなかった。原爆投下直後、市街にいた知事は被害程度を〈極メテ軽微〉と報告したが、爆心地に近い浦上は壊滅状態にあり、磯本家でも母と姉が死亡。戦後は開発や町名変更が進み、被差別部落自体、なかったことにされてゆく。
実は長崎に原爆が落とされた時、磯本は中国青島にいた。奨学金を得て同地の国立商業学校に進み、〈決して浦上で生まれたと言うちゃならんとばい〉という母の戒めを胸に刻んだ彼はしかし、組合や反原水爆運動で頭角を現わす中、その戒めを破ることになる。
悲劇性が高いほど
聖地は聖地になる
「彼が出自を公言したのは、開港記念土産として市販された古地図に部落を特定する町名があると抗議に行った際、市長室にあった同じ地図ではその町名が伏せられていたことが発端でした。新聞はこの一件を記事にし、出自を明かす格好になった彼は長崎初の県連を興す。
一方、中尾も復員後は上野で靴磨きをしたり、さんざん苦労して、隠れキリシタンの末裔も多い五島の中学教師になる。そして子供たちの前で島崎藤村『破戒』さながらの告白をした彼は、磯本共々、信者側との和解に目的を見出していきます」
その磯本が〈原爆のときは長崎におったとさ〉と、致命的な嘘をついていたことを、氏は「事実を知った者の責任として書かなければならなかった」という。それでもその功績が色褪せることはなく、本書は後半、彼らが〈私怨〉の壁を克服する姿を、一層丹念に追う。
転機は両者の〈連帯〉を裏付ける史実の発見だった。長崎奉行は彼らを隣住させ、監視や処刑すら命じたが、元々信者も多かった部落民の中には命をしてこれを拒み、匿う者もいたのだ。
「そうした材料が発掘できたのは確かに幸いでしたが、むしろ結城神父は自分たちの愛の世界がいかに狭隘で排他的か、〈真実を見よ〉と、厳しく諭したといいます。そもそもキリスト教では殉教は至上の行為とされ、秀吉が二十六聖人を磔にした西坂は中世の頃から世界的に知られた聖地でした。神父はそこに記念館を作るべく派遣されながら、より広い心で解放運動に携わる。僕はそこにあらゆる宗教が主題とすべき許しを感じる。実は〈クロシュウ〉と虐げられた信者側も相当部落側を差別していて、許しと狭隘という視点なくして和解はなく、神父が自著に引く一茶の〈喧嘩すな あひみたがひの 渡り鳥〉は彼の心そのものだと思います」
一方で悲劇性が高いほど、聖地が聖地たるのも事実で、長崎の殉教の歴史は戦後、観光の目玉にもされてゆく。
「世界遺産の登録も、僕は見送られてよかったと思う。不都合な過去に蓋をした今の明るすぎる長崎は、日本の戦後復興の縮図ですから。生き抜くためとはいえ、人間嘘もつけば差別された側が酷い差別もする。悲劇が多ければ多いほど、虚ろな英雄が生まれてくるんです」
一時国政を志した磯本も、英雄になる日を夢見たのか。今となってはわからないが、愚かすぎるの向こうに、今まで見たこともない生身の長崎が、透けて見えるのは確かだ。
□●構成/橋本紀子
●撮影/国府田利光
(週刊ポスト2016年5.20号より)
初出:P+D MAGAZINE(2016/05/15)

