多和田葉子『百年の散歩』が彩り豊かに描く幻想的な町の景色
ドイツでも評価を受けるベルリン在住の作家、多和田葉子による、多彩で幻想的な連作長編。創作の背景をインタビュー。
【ポスト・ブック・レビュー 著者に訊け!】
ドイツでも評価を受けるベルリン在住の著者による幻想的な連作長編
『百年の散歩』
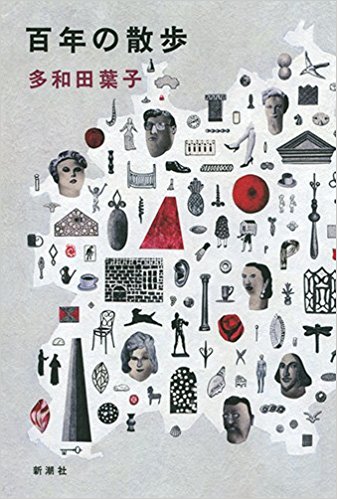
新潮社 1700円+税
装丁/新潮社装幀室
装画/村橋貴博
多和田葉子

●たわだ・ようこ 1960年東京生まれ。早稲田大学文学部卒。ハンブルク大学大学院修士課程、チューリッヒ大学大学院博士課程修了。91年『かかとを失くして』で群像新人文学賞、93年『犬婿入り』で芥川賞、2000年『ヒナギクのお茶の場合』で泉鏡花文学賞、03年『容疑者の夜行列車』で伊藤整文学賞と谷崎潤一郎賞、11年『雪の練習生』で野間文芸賞、13年『雲をつかむ話』で読売文学賞と芸術選奨文部科学大臣賞等の他、ドイツでの受賞も多数。158㌢。
常に揺らぎ移ろう〝町〟という運動体全体を小説ともつかない形でとらえようとした
世間には国や言語や文化風習等々、一つ所に留まる人と、そうでない人がいる。
多和田葉子氏は明らかに後者だろう。創作には日本語とドイツ語を用い、82年からはハンブルク、現在はベルリンに在住。世界中を表現の場とし、散歩する、物心両面の越境者でもある。
最新刊『百年の散歩』はベルリン市内の10の通りを舞台に、主人公・わたしの脳裏に去来する10の夢想を綴った連作集。カント通り、カール・マルクス通りなど、古の哲学者や芸術家の名を冠した通りはどれも実在し、この町に住む日本人という以外、属性を明かされない彼女は、ただ〈あの人〉を待ちながら町を彷徨うのだ。
以前、「なぜエッセイストの日常は豊かなのか?」と本稿に書いた記憶があるが、何気ない町の景色や、言葉が宿命的に孕む揺れなどが、作家にかかるとアラ不思議。書くに値する物語へと魅力的な変化を遂げるのである。
*
「今回は私が元々好きな、特に人の名前が付いている通りを選んで、本人の作品を見たり読んだりしながら歩いてみようかなと思って。例えば普通は20秒も見れば見た気になる美術館の絵が3分後にはまた違って見え、さらに15分粘ると全然違うものが見えたりするでしょ。そんな風に自分が空っぽになるまで粘りに粘り、住み慣れた町で目にしたものを全て小説化したらどうなるかという、一つの実験です」
〈わたしは、黒い奇異茶店で、喫茶店でその人を待っていた〉〈店の中は暗いけれども、その暗さは暗さと明るさを対比して暗いのではなく、泣く、泣く泣く、暗さを追い出そうという糸など紡がれぬままに、たとえ照明はごく控えめであっても、どこかから明るさがにじみ出てくる〉……。
「カント通り」の書き出しである。「なく」「いと」など、音たちは文字に定着するまでに自由な浮遊を許され、また、目の前の事物を言葉に置き換えると、そこには当然、
「周囲の音を完璧に記述することはほぼ不可能ですよね。でもそれを書いた瞬間、それは自分の世界になるし、どこまでが頭の中でどこからが外界かわからなくなる感じも含めて、私はものを書く行為だと思うのです」
さて、その喫茶店であの人を待つわたしは、壁際に座る女性客を勝手に〈ナタリー〉と名付け、注文したグリーンピースのスープを眺めては、同名の自然保護団体から指弾される日本の捕鯨について考えたりする。そんな時、耳に飛び込んできたのが、〈しぇるしぇ〉というフランス語だ。〈脳の正面にいるゴールキーパーの手をすり抜けて、入ってきたこの「しぇるしぇ」をどうしていいのかわからないまま、わたしはスープを食べた〉
「ベルリンにいると、東京より多くの言葉が耳に入ってくる気がします。まず店で大声を出すのを恥じる日本人と何でもタブーなく話すベルリン人では声量が違う(笑い)。ほかにもベルリンが東京と違う点として、町なかには大戦が昨日終わったのかと思うほど歴史の跡が残され、人名の付く通りが多い。それは、銅像よりは日常的に名前を口にするとか、さりげない想い方がよしとされるから。
そもそもベルリン自体が歴史に翻弄された町なので、移民排斥的な空気も比較的薄い。人に何か言われる前に口を噤むようになったら、町も人もお終いです」
国同士が線を引くことに意味はない
マルティン・ルター通りやローザ・ルクセンブルク通りで夢想はなおも続き、彼女と違って山や森の生活に憧れるあの人が、結局、姿を現わすことはなかった。
〈森の中を散策していても、言葉が浮かんで来ない〉〈町はわたしの脳味噌の中そっくりで、店の看板に書かれた言葉が連想の波をたえず引き起こし、おしゃべり好きの通行人のぺらぺらがオペラになり〉〈言葉は本当は世界とは何の関係もないんだというしらじらとした妙に寂しい気持ち〉〈傷つく必要なんてない。何度ふられても町には次の幸せがそこら中にころがっているのだ〉
そんな彼女のやせ我慢が、多くのモノや言葉に囲まれながら何一つ手に入らない都会人の孤独を浮かび上がらせて胸に迫り、秀逸だ。
「作物を育てている実感の中を生きている農村の真っ当さから切り離された都会人は、給料はここからもらう、トマトはあそこで買う、と生産の実感すらない。その何でもあって何もない虚しさの一方には町特有の楽しさもあって、常に揺らぎ、移ろう、町という運動体全体を小説ともつかない形でとらえようとした私は、線を引くことに何の意味があるのかと思うわけです。そもそもフランスやドイツという国以前にパリやベルリンといった町が屹立し、
私自身、82年の渡独当時は日本とドイツという国に囚われていましたが89年にベルリンの壁が崩壊。EUへと動く中、21世紀は町や村の時代だと確信するに至った。日本も韓国や中国や台湾や、北朝鮮とだって連携するに越したことはなく、お隣同士が線を引き、喧嘩することほど、危険でつまらないことはないんです」
だから多和田氏はあえて住み慣れたベルリンを歩き、過去と現在と未来の地層に思いを巡らせた。今は亡き革命家とわたしの境界線はいつしか消え、時を超えた連携も散歩は可能にしたが、それも孤独であればこそ。個が個を求め、点が点を求める時、その彼方には豊潤な言葉の地平が広がるという、本書は証左でもあるのだ。
□●構成/橋本紀子
●撮影/三島正
(週刊ポスト2017年5.19号より)
初出:P+D MAGAZINE(2017/09/07)

