【著者インタビュー】藤岡陽子『満天のゴール』
医療過疎地で、医師が往診の度に貼ってくれる、星の形をしたシール。痛みに耐えたら1枚、採血したら1枚と星は増え、そのゴールは死を意味していた――。生と死に向き合う、感動の医療長編小説。
【ポスト・ブック・レビュー 著者に訊け!】
現役看護師の著者が医療過疎地の生と死に誠実に向き合った感動長編
『満天のゴール』
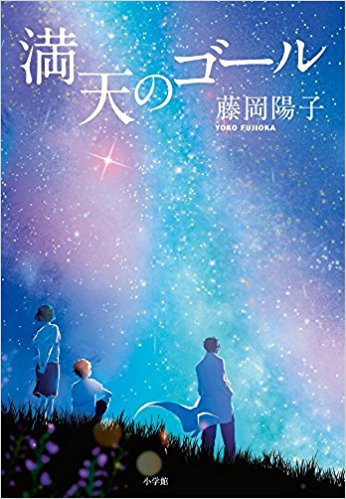
小学館 1400円+税
装丁/山下知子(GRACE.inc)
装画/alma
藤岡陽子

●ふじおか・ようこ 1971年京都生まれ。同志社大学文学部卒。報知新聞社に入社し、高校野球等を担当。97年退社、タンザニア・ダルエスサラーム大に留学。帰国後に小説を書き始め、01年慈恵看護専門学校に入学。現在は京都市の脳外科兼ペインクリニックに勤務。06年「結い言」で北日本文学賞選奨を受賞、09年『いつまでも白い羽根』でデビュー。他に『トライアウト』『手のひらの音符』『テミスの休息』等。自身小4の息子を含む2児の母。156㌢、O型。
誰もが抱える過去や傷が〝おもり〟となってその人を生に繋ぎとめることもあると思う
「うちの子もそうですけど、子供ってシールやスタンプ集めが大好きでしょう?
あれって何かを頑張った証拠というか、
藤岡陽子著『満天のゴール』には、医師が往診の度に貼ってくれる〈星の形をしたシール〉が登場する。
舞台は京都・丹後半島。宮津駅から更にバスで2時間かかる限界集落では唯一の診療所も閉鎖され、近隣の総合病院に勤務する若手医師〈三上〉の往診に頼るしかない状況にあった。
わけあって実家で暮らし始めた主婦〈奈緒〉と4年生の息子〈涼介〉は、在宅で最期を迎えたい患者のために最低限の治療と看取りを担ってきた彼と出会い、村の老人が集めるその星の意味を知る。痛みに耐えたら1枚、採血したら1枚と星は増えてゆき、ゴールはすなわち死を意味していた。
尊厳ある穏やかな死―それはたった一人の医師の努力によっても、叶えられる場合はあると著者は言う。
*
元新聞記者で、現役看護師でもある藤岡氏にとって、実際に丹後で僻地医療に従事する石野秀岳医師は、以前から注目する人物だったという。
「私は京都市内に勤めていて、僻地経験はないんですが、石野先生の新聞連載は毎回切り抜いたり、個人的に尊敬していたんです。
でも、お忙しい方だし、取材は無理だろうと諦めていたら、たまたま仲のいいママ友が医大で同期だったらしく、いいよ、紹介してあげると言ってくれて。それからです、先生の活動に密着させてもらったのは。
彼は地元伊根町で病院勤務の傍ら診療所長を兼ね、ワークショップまで開いていた。要するに人はいつか死ぬ、貴方はどんな死に方がしたいですかって、人が死ぬまでのプロセスを寸劇で見せて、意識改革を図ってるんです。例えばいざって時には、119より僕を呼んでくださいとか、家で死にたい人は最期までサポートするから、わがまま言っていいんですよとか。それを見る地元のおじいさんたちもゲラゲラ笑っていて、死に方は自分で選べるということを面白おかしく学べる場なんです。
先生は元々故郷のために医者を志した方なんですが、そこまでなさる情熱に私は興味があって、この三上を造形してきました」
一方主人公の境遇もなかなかに過酷だ。夫がよそに女を作り、妊娠までさせたことを、奈緒は愛人のブログ〈ソムリエ響子のワインEYE〉で知り、一方的に離婚を迫られる。ひとまず涼介を連れて帰省したが、この10年、育児に専念してきた〈ペーパーナース〉の彼女には到底納得できない。
「ずっと夫に尽くしてきた専業主婦にすれば、それこそ天災級の衝撃ですよね。私としては彼女がそのマイナスをどうプラスに変えるかを描きたかったし、夫と愛人はとことん悪者にした方がいいと思って、響子をこのイヤ〜な感じのブログの主にしてみました(笑い)。
最近はペーパーナースも話題になっていて、どこも人手不足に喘ぐ中、潜在的な有資格者が何万といる。奈緒は母親の死因や病院に不審を抱き、看護師にならずに結婚した人なのですが、涼介を育てていくには自分が働くしかないし、何とか壁を乗り越えてほしくて」
それこそ帰省直後、父が骨折して運ばれたのが因縁の〈海生病院〉で、奈緒が母の死に疑念を抱いたのも、そこでの看護師の一言が原因だった。看護師は〈手術をやめなさい〉と転院を勧めたが、院に要望は通らず、母は合併症で死亡。そのまま看護師は退職し、名前もわからずじまいだが、奈緒は三上の勧めもあって同院に就職。涼介と新生活をスタートさせるのだ。
不幸を嘆くより自分から動く
海と山に囲まれた丹後に育った奈緒が、蝶を追って山中に迷い込んだ幼い日の反省を回想する場面がある。〈欲張ってはいけない。求めすぎてはいけない〉〈それからはもう必要以上に欲しがることなどしなかった〉
そうした大自然の教えと、夫に従順なだけの謙虚さは、似ているようで全く違い、彼女は粛々と死に向き合う〈トクさん〉や〈早川さん〉との交流を通じて、人生や生死に関する程よい態度を学んでいくようでもある。
また涼介と昆虫博士・三上の関係も微笑ましく、本書は医療小説でありながら、死より
「今のペインクリニックでも、
その三上もここに来るにはそれなりのワケがある。彼や早川さんらが抱える過去や傷が、〈おもり〉としてその人を生に繋ぎとめることもあると私は思うのです」
やがて明らかになる三上のおもりの正体はさておき、涼介の存在が老人の頑なな心を和らげるなど、ほんの通りすがり程度であっても、人は人に支えられて生きていた。例えばある人がある人に言う。〈誰にも救ってもらえないのなら、あなたが救う人になればいい。救われないなら救いなさい〉
「強い言葉ですよねえ……。
確かに不幸を嘆くくらいなら、自分から動くことで景色は変わるかもしれない。そういう支え合いのドラマを、私はジャンルを問わず、書いていきたいんです」
その星を集め終えた時、人はみな穏やかに逝き、満天のゴールとは何者にも冒しえない〈満点のゴオル〉でもあった。そのまるで自然に帰るような死は、決して悲しいだけのものではないはずだ。
□●構成/橋本紀子
●撮影/国府田利光
(週刊ポスト 2017年11.10号より)
初出:P+D MAGAZINE(2018/06/08)

