【著者インタビュー】星野智幸『のこった もう、相撲ファンを引退しない』
19年ぶりの日本人横綱誕生に沸いた16~17年のブログやエッセイに加え、対談や相撲小説なども収めた、相撲ファンならぜひ手に取りたい一冊。大相撲を取り巻く環境と、その未来が見えてきます。
【ポスト・ブック・レビュー 著者に訊け!】
「相撲と愛国」のテーマにがっぷり四つで取り組んだ! 今だから読みたいエッセイ集
『のこった もう、相撲ファンを引退しない』

ころから 1600円+税
装丁/安藤 順
星野智幸
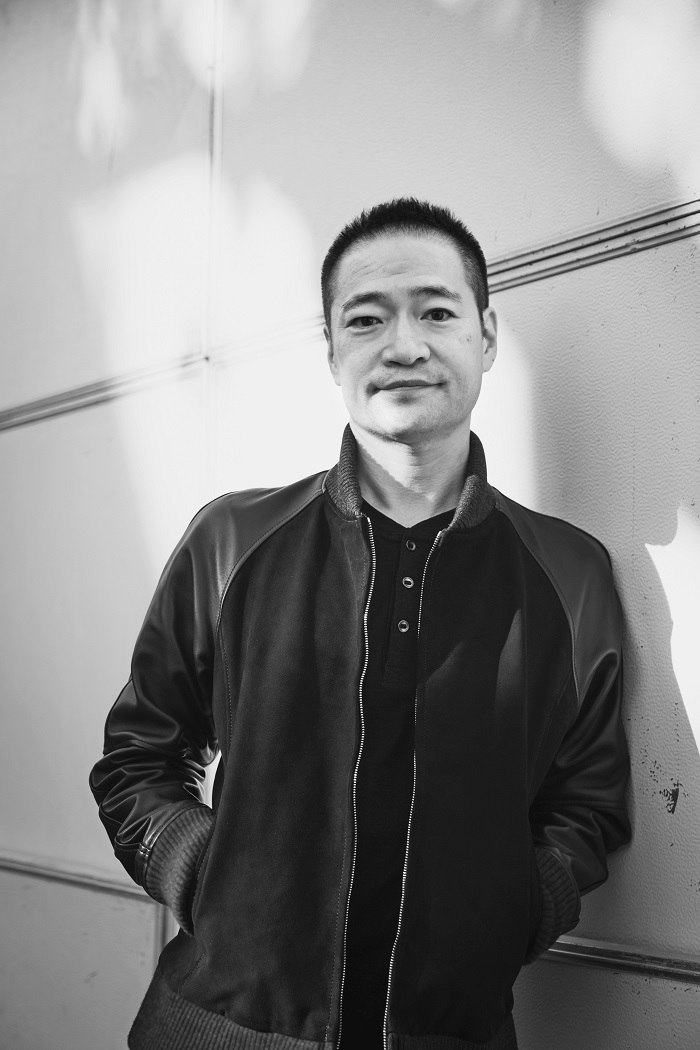
●ほしの・ともゆき 1965年アメリカ生まれ。早稲田大学第一文学部卒。新聞記者を経て、メキシコへ留学。帰国後は翻訳業の傍ら新人賞に応募、97年『最後の吐息』で文藝賞を受賞しデビュー。2000年『目覚めよと人魚は歌う』で三島由紀夫賞、03年『ファンタジスタ』で野間文芸新人賞、11年『俺俺』で大江健三郎賞、15年『夜は終わらない』で読売文学賞。ちなみに本書の帯は「嘉風色」。「特殊な緑らしく、お金がかかってます!」。170㌢、60㌔、B型。
スポーツこそが国籍や人種による差別をギリギリ食い止められる砦だと思います
目の前の事象に目を凝らすことで、世の中の構造や行く末さえ看破してしまう能力者がごく稀に存在する。例えば作家・星野智幸氏だ。〈スポーツとは、社会の深層で起こっていることを、社会よりも少し早く先取りする場〉と書く彼にとって、大相撲もその一つ。中でも観客らが必要以上に日本人力士に肩入れする、〈日本人ファースト〉を問題視する。
確かにヘイトスピーチやネトウヨの存在も問題だが、〈問題は、そのような人たちの暴力的な言葉に対して、一般社会が多少眉をひそめつつも無関心な態度を取り続け〉〈差別が大手を振ってまかり通るようになってしまったこと〉。特にスポーツなどの非日常的局面では〈不作為的差別から積極的差別への転換〉が起きやすく、日本人が日本人を応援しても誰も疑問を抱かない。
表題はその名も、『のこった』――。土俵際寸前まで追いつめられているのは、果たして力士か私たちか?
*
子供の頃から力士に憧れ、初めて投稿した作品も相撲小説だった(!)という純文学作家に会おうとした矢先、とんでもない事件が起きた。当時の現役横綱・日馬富士による貴ノ岩暴行事件とその後の引退劇である。
「まだ全容が解明されていませんが、僕は両力士のファンなので、寝込みそうなぐらいショックです。横綱時代に僕の人生まで託した貴乃花親方には今は不信感が募るばかりだし、相撲協会は、ちゃんとファンや力士のことを考えた明快な対応ができていないし、苦しくて仕方ないです」
本書では19年ぶりの日本人横綱誕生に沸いた16〜17年のブログやエッセイの他、著書『スー女のみかた』もある和田靜香氏との対談や、相撲小説「智の国」を収め、自身愛してやまない相撲の魅力やファンの変化についても、その筆は冴える。
例えば「豪・栄・道!」などと、力士を
「僕は
結局、彼は03年に引退し、僕は白鵬の優勝記録更新が話題になった14年9月まで、相撲を見なくなるんです」
そして15年1月。久々の観戦に訪れた氏は、大鵬の大記録に挑む白鵬をよそに、〈日本人力士がんばれ〉と声援が飛ぶ光景に目を疑う。
「あの時は思わず〈白鵬! 白鵬!〉と叫んだくらいです。その空気は翌16年の琴奨菊の優勝を経て、稀勢の里の横綱待望論に繋がっていく。僕には〈日本出身力士〉の優勝と日本国籍を持つ旭天鵬の優勝を区別する理由がわからないし、稀勢の里の早すぎる横綱昇進には当人が最も苦しんでいると思う。ところがファンやメディアにも差別の自覚は一切なく、無意識だから、怖いんです」
国技という概念もフィクション
その点、スー女は違った。一般には美形力士・遠藤や12年創刊のフリーペーパー『TSUNA』が火付け役とされるが、鶴竜や千代丸をアイコン化し、稀勢の里を〈魔性の男〉と呼ぶ独創性には、なるほど舌を巻く。
「あの朝青龍が〈朝さま〉として尊敬されていたり、意外と顔じゃないんですよね(笑い)。国籍も単にキャラの一つで、高安や御嶽海のフィリピン人のお母さんは『若くてカワイ〜』で、それ以上でも以下でもない。
かくいう僕も理屈を語りたがる分析オヤジの一人で、そうか、好きに理屈は要らないんだと気づかされたし、純粋に好きなものを守ろうとするスー女の存在は相撲界の希望だと思います」
彼はそこに韓流ファンにも通じる〈フィクションをさらにフィクション化して、自分の物語に変える〉ミーハー力を見、全てのスポーツは〈フィクションであることを意識に留めながらのめり込むべき〉だと書く。
「僕は大のサッカー好きでもあって、僕ら観客の熱狂が所有意識や排他性に転じる危うさと向き合ってきた。考えてみれば僕は
その虚構が時に途轍もない真実を孕むから私たちは胸打たれるのだが、昨今はトランプ政権の言う〈代替的事実〉やフェイクニュースが幅を利かせ、フィクションの取り扱いに関するリテラシーも低下しつつある。
「確かに。今は何事も声の大きい方の意見が
一方で現実がつらい時ほどフィクションはワンクッションになるし、目の前の事実が孕むフィクション性を自覚する訓練にもなる。今はみんなが孤独でつらいんだとは思う。だからって日本第一主義みたいな捏造的虚構にしがみついても、かえって自分たちの現実を息苦しくするだけです」
そんなフィクションとの幸福で成熟した関係を築くためにも、相撲は有効だと星野氏は言う。
「2歳までロスにいた僕は出身地の話が嫌い。文学とサッカーが目的で訪れた南米の、国籍も人種も全てが溶け合う空気に、未来への希望を確信したものです。
なのに日本では最盛期で30万人いたブラジル人労働者も
僕は相撲が差別の温床になることだけは避けたいし、むしろスポーツこそがそれをギリギリ食い止められる砦だと思っている。そして白鵬のスゴさとか、嘉風や安美錦の巧さの話だけを、本当はしていたいんです」
〈相撲ファンを引退することは、もうありません〉という彼の『のこった』宣言は、流れに流されそうになっても徳俵で踏みとどまり、あくまで私的で自由な「好き」をやめないことを、おそらくは意味する。
□●構成/橋本紀子
●撮影/国府田利光
(週刊ポスト 2017年12.22号より)
初出:P+D MAGAZINE(2018/07/04)

