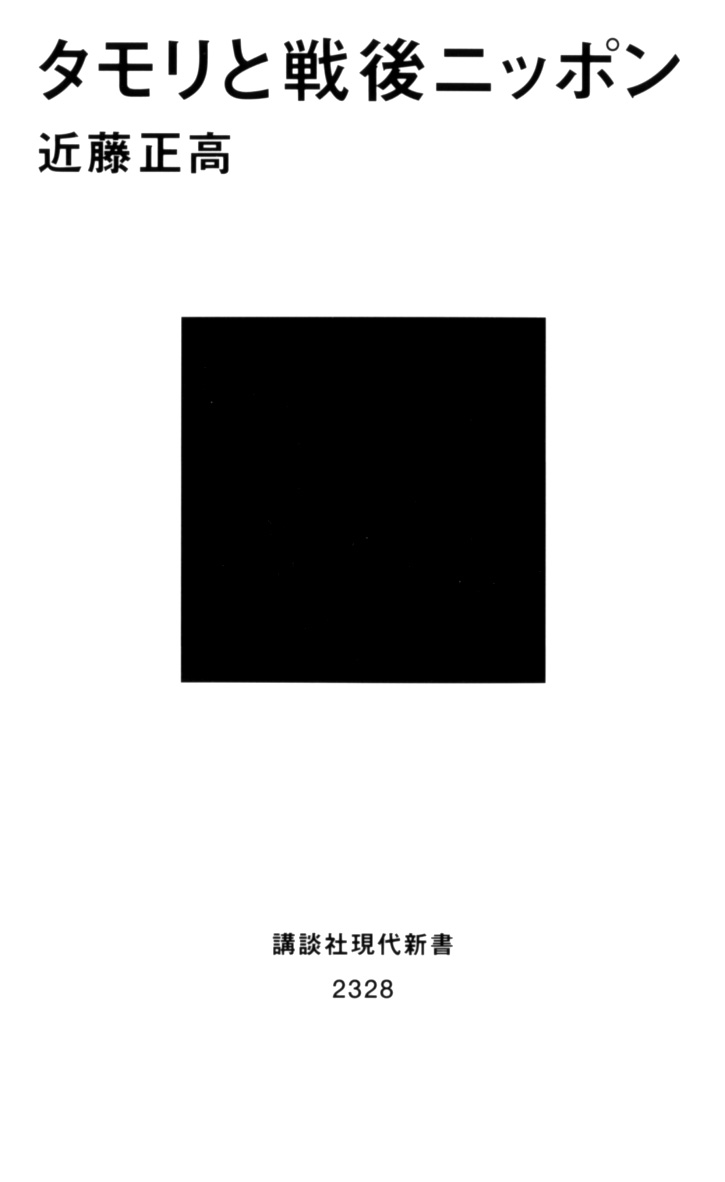『タモリと戦後ニッポン』
「時代」の肖像
評者/鈴木洋史(ノンフィクションライター)
「国民のオモチャ」を自覚し、時代を映す鏡に徹した凄み
『タモリと戦後ニッポン』
近藤正高著
講談社現代新書
本体920円+税
近藤正高(こんどう・まさたか)1976年愛知県生まれ。サブカルチャー誌『クイック・ジャパン』編集部を経てフリーに。著書に『私鉄探検』(ソフトバンク新書)、『新幹線と日本の半世紀』(交通新聞社新書)。ウェブサイト「cakes」でコラム「一故人」を連載中。
本書は、敗戦の年の8月22日に生まれたタモリを通し、戦後日本の「国民史」を描こうという野心作で、直接タモリに関係しないものも含めて膨大な資料を渉猟し、読み込み、考察した労作である。
〝タモリ本〟をあまり読んだことのない読者にとっては興味深い事実が数多く記されている。たとえば、森田家は代々筑前藩の家老を務めた名門であり、祖父は戦前満州鉄道の駅長を務め、父も母も満州育ちだった。戦後、そんな家族から日本とはまったく異なる世界が広がっていた満州の話を聞かされることで、タモリには日本の風土や生活を相対化する習慣が植えつけられた、と著者は想像する。
実は幼い頃に両親が離婚し、タモリは祖父母に育てられた。ルサンチマン(弱者の怨み)的情念を抱いてもおかしくないが、タモリは「バカバカしくてグレたりする気も起こらなかった」という。
著者は、この〈あらゆるものを相対化する視線〉をタモリの根本的な資質と見ている。タモリは全共闘世代で、騒々しい時代の早稲田大学に在学していたが、ノンポリだった。ジャズが大好きでモダンジャズ研究会に所属していたが、当時のジャズがまとっていたカウンターカルチャーの雰囲気に酔ってはいなかった。だからこそ、後に、当時のアングラの旗手のひとりだった寺山修司などのモノマネで笑いを取ることができたのだ。
タモリは大学を除籍になって故郷の福岡に帰り、生命保険の勧誘員、ボウリング場の支配人、フルーツパーラーのバーテンダーと職を転々とし、その間、保険会社の同僚だった女性と結婚した。そして、福岡に公演に来ていた山下洋輔と半ば偶然、半ば必然に出会い、その勧めで上京すると赤塚不二夫に可愛がられ、お笑い芸人としてデビューした。
タモリの芸は当初、ブラックな要素のある「密室芸」だったが、1982年10月から『笑っていいとも!』の司会を始めるようになると、自分は一歩身を引き、周囲の面白さを引き出す「受け身の芸」へと転換した。やがてマンネリ化し、文化人などからは「小役人のよう」「お笑いの区役所」などと批判されたが、タモリ自身は自分を「国民のオモチャ」だと自覚した。
〈それ(注・カウンターカルチャーなど)も消費社会の成熟にともない資本に取り込まれ、CMやテレビ、ラジオ番組などを通じて消費されていく。どちらかといえばカウンターカルチャー、サブカルチャー寄りの芸人だったタモリが(中略)「国民のオモチャ」を自称するまでにブレイクを果たした理由には、そうした時代背景も見逃せない〉
1988年の新語・流行語大賞の特別賞部門
人語一体傑作賞を受賞したときのタモリ。
タモリは、あらゆるものを商品として消費する資本主義の最前線を泳ぎ続けたのである。著者によれば、30歳のときに笑いの道に入ったことと、『笑っていいとも!』を終了させたことだけが、タモリが自らの意思で行ったことだというまるで昭和天皇の聖断だと思ったら、直後の文章でそう書かれており、思わず膝を打ったが、自らの意思でその2度目の決断を下せたことは、タモリが消費という荒波に溺れなかったことを物語っているのではないか。
本書はタモリの内面に迫ることを目指してはいないが、タモリが自覚的に「国民のオモチャ」を続け、時代を映す鏡に徹したことがよくわかる。そして、どれだけ売れても自分を相対化し続けられたことにタモリの本当の凄みを感じさせられるのである。
(SAPIO 2015年11月号より)
初出:P+D MAGAZINE(2015/12/22)